








19世紀半ばのNY。医師で財産持ちの男オースティン・スローパー(ラルフ・リチャードソン)と、適齢期(死語?)を過ぎた一人娘キャサリン(オリヴィア・デ・ハヴィランド)が高級住宅街の豪邸に2人で暮らしている。そんな地味で晩稲な娘が、イケメンだが文無し無職の男モリス・タウンゼンド(モンゴメリー・クリフト)と恋に落ち、、、。
ま、トーゼン、お父さんはモリスが財産狙いのだめんずだと考えて娘の恋路を阻み、キャサリンは相続権を失ってでもモリスと結婚しようとすると、モリスは駆け落ちの約束をすっぽかすわけですが、、、。
この映画はそんなストーリーからは想像もつかない衝撃的な映画です。見終わって、もの凄い余韻。ワイラー監督、恐るべし。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
ちょっと、今回の感想は長くなります。
またまた、何でこのDVDをリストに入れたのかまったく記憶になく、送られてきたので見てみたのですが、、、、これは、衝撃大です。
◆ウィリアム・ワイラー監督作品と言えば、、、
ウィリアム・ワイラー監督の映画というと、私には『ローマの休日』でも『ベン・ハー』でもなく、圧倒的に『コレクター』なんですよねぇ。そもそも、名画の誉れ高い前者2作は、恥ずかしながらちゃんと見たことないもので、、、。『嵐ケ丘』は見たはずなんだけれども、記憶にない、、、がーん。
というわけで、どうして本作を見ようと思ったのかは思い出せませんが、よくぞリストに入れたものだと自分を褒めたいですね。
もとは戯曲だそうで。なるほど、、、という気がします。印象的なセリフが多かったので、紹介がてら、、、。
◆最悪な父親
ま、本作をそこまで秀逸なものにした最大の要素は、父娘の関係の描き方でしょう。一見、仲の良い父娘。人格者の医師で、一人娘を慈しみ、使用人からも慕われるジェントルマンな父。そして、そんな父を尊敬し、逆らうことを知らずにひたすら従順な娘。
でも実は、この父親は心の中では娘をまったく認めていない。蔑んですらいるのです。娘と共に出席したパーティ会場で、父親はキャサリンがダンスをしている最中、親類の女性にこんなことを言っています。
「娘は名門の学校を出た。音楽や踊りの習い事も、寝る前には社会の常識も教えてきた。のびのびと育てたがご覧のとおりだ。平凡で世間知らずの娘になってしまった」
我が娘に対する言葉として、これだけでも怒髪天なんですが、親類の女性の「彼女に失礼だわ。期待し過ぎよ」という諫言に対し、さらに侮辱の上塗りをします。
父「あの娘の母親を(知ってるだろう)? 気品があり、しかも明るかった。彼女の娘なのに、、、」
女性「母親と娘を比べてはいけないわ。亡くなった奥さんを美化しすぎているわ」
父「それは言わんでくれ。死んで初めて分かった。彼女の大切さが、、、」
……どーです、この会話。この父親のキャサリンを語る言葉の数々。これだけでもう、父親は地獄行きです。ま、実際、彼はこの後、地獄を見るのですが。
恐らくこの男は、生前の妻も、心から愛して大切にしてはいなかったと思いますね。死んで初めて分かった、なんて、亡き妻からすれば噴飯ものなセリフなわけで。私が亡き妻だったら、呆れてモノが言えないと思うなぁ。そんなふうに勝手に美化して思い出してばかりいるより、現実に我が娘を全力で愛して、娘の幸せのために犠牲になってくれる夫の姿を空の上から眺めたいものです。
それに、いくら表面的に良い父親を装っていても、いざとなると本性が牙を剥くのです。モリスとの結婚を貫こうとするキャサリンに対し、こんな暴言を吐きます。
「今まで黙っていたが真実を教えてやろう。(モリスの目的はキャサリン自身ではなく)財産だ、それしかない。信じたくないだろうが、お前は昔から取り柄のない娘だった。唯一の例外は、刺繍ができることだ」
つまり、
モリスのようなモテ男が、お前なんかに惚れるわけねーだろ、このブス!! と言ったも同然な訳です。……この暴言により、キャサリンの父親への信頼は見るも無残に砕け散りました。
このセリフは、その表面的な意味ではソフトに聞こえるかも知れませんが、その核心は、
「初めて言うが、今までずっと親の私はそういうふうに娘であるお前のことを認定してきた。それだけの人間でしかなく、だからお前の考えも判断も到底信用も出来なければ尊重する意味がない」というものであり、まさに、娘への死刑宣告なのです。
大げさな、、、とお思いのあなた。あなたは人の親ですか? であれば、大げさだと思わない方が良い。
こういう人格を根こそぎ否定するような侮辱の言葉を、赤の他人ではなく、実の親に言われるということが、子どもの心にどれほどの衝撃を与えるか、世界中の親という存在は覚悟した方がよい。
この父親のさらに悪質なところは3点あります。
1つ目は、今までは理解あるよき父親を演じて来たこと。腹の中では亡き妻と比較しては蔑んでいたのに、表面を取り繕って25年もキャサリンを欺いてきたのです。
2つ目は、結局自分が一番大事な人であること。なんだかんだ言っても、結婚に反対したのはモリスに自分が築いた財産を食いつぶされるのがイヤだからです。娘が相続した遺産は娘のものだと思えない。もの凄く自己チューな上に、強欲です。
3つ目は、自覚がないこと。亡き妻が素晴らしかったのに、こんな娘で、、、と彼は思っている。しかし、キャサリンは、その亡き妻と自分の間に出来た子であり、亡き妻の良い所に似ても似つかぬのであれば、そのダメダメ要素は自分が授けたものであるはずだ、ということに思いが至らない。自分がどんだけ素晴らしい男だと思っているのか。傲慢甚だしい。
こんな父親が側にいては、キャサリンに訪れようとする幸せも逃げて行ってしまうのは、むしろ自明の理であります。なんと罪深い父親。
しかし、この父親の一番の罪は、今まで書いてきたものではありません。一番の罪、それは、キャサリンを“完全な人間不信”にしてしまったことです。
山岸凉子の作品に『
天人唐草』というのがありますが、あれと話はちょっと違いますが、似ていると思いました。あの主人公、岡村響子の行き着いた先よりは、キャサリンの方がまだマシかも知れません。キャサリンはどこの誰とも分からない男にレイプされてもいないし、少なくとも一生喰うに困らない財産と、心は凍りついても正気な頭はありますので、、、。
◆キャサリンの変貌ぶりが見もの
本作の見どころは中盤以降。もちろん、そのための序盤なのですが、序盤~中盤にかけてのキャサリンのダサさ、従順さ、素直さ、そういうものが後半、モノの見事に、それこそオセロの白を一気に黒に裏返すがごとく反転していきます。美しく垢抜けたキャサリン、しかし、性格は冷たく、頑なに、、、。
終盤、モリスが、5年ぶりにキャサリンを訪ねてくるシーン。叔母のラヴィニアが何とかキャサリンに女性としての幸せを味わってほしいと、2人をとりもとうとします。言い訳がましい上に、白々しいセリフを吐くモリスですが、キャサリンはその夜、結婚しようと約束し、彼の気持ちを受け入れるかに見せて、一旦、モリスを帰します。が、しかし、キャサリンはその後、ラヴィニアにこんなことを言うのです。
「彼はまた現れた。同じ嘘を並べながら、さらに強欲になって。初めは財産だけだったのに、今は、愛まで欲しがっている。来るべきでない家に2度も訪れるとは。3度目は許さない」
ショックを受けるラヴィニアをよそに、おめおめと再び現れたモリスを完全に拒絶するキャサリン。外で戸を激しく叩くモリスの横顔に被るエンドマーク。
でも、思うに、キャサリンはまだモリスのこと、好きなのです。それは、キャサリンの微妙な表情に現れている気がします。私がキャサリンなら、たとえ嘘だと分かっていても、モリスと結婚しちゃうなぁ。だって好きなんだもん。好きな男があそこまで言ってくれるのです、嘘でも。
灯りを手に、玄関の戸をモリスが打ち鳴らす音を聞きながら、決然と階段を上がって行くキャサリンは、なにかこう、、、荘厳でさえありました。そして、哀しい。とても。復讐は果たしたかも知れないが、キャサリンの心はこれでもう、一生閉ざされたままの可能性が高いのですから。
この一連の終盤のシーンについて、ネットの感想など見ると、“女はコワい”みたいのがチラホラありました。コワいと書いているのは大抵男性の様でしたけれど、コワいってどこが? 本当に怖いのは、何度も言うけど、父親ですよ、本作では。
娘が生まれてこの方、ずーーーっと、腹の底ではバカにし続けてきた、娘を欺き続けてきた父親。ああ、やっぱり『天人唐草』の父親と同じに思えます、私には。
◆モリスは本当に財産“だけ”が目的だったのか。
さて、本作のもう一つの主眼は、果たしてモリスは本当にキャサリンを愛していたのか、ですが、、、。まあ、これは本作の中では意図的に曖昧にされています。見る人によって受けとめも違う、、、というか、まあ、大抵は財産目当てに軍配ですよね。
でも、父親があそこまで決め付けなかったら、、、? 見る人の見方も変わるのでは。私は、ロミジュリの変型版という解釈もアリだと思うのです。
親に反対される結婚だけれど、当人たちの気持ちだけは確かである。少なくとも今は。1点の曇りもない(つまり財産度外視ではない)、、、わけじゃないけれど、でも愛していることは間違いない。そういうのだってアリでしょう。純粋に、無一文でも愛さえあれば、ってのじゃなければ愛ではない、なんて決め付けすぎない方が、案外幸せなんじゃないでしょうか。
同じ山岸凉子の作品に『ブルー・ロージズ』というのがありますが、これはキャサリンのように引っ込み思案で晩稲な女性がある男性と恋愛関係になるんだけれど、相手は元カノと復縁してしまい、、、。結果は別れとなるけれど、でも、女性は、恋愛経験を通して、一人の男性に愛されたことで自信を得ます。「自信とは愛情だった。……自分を愛せるということは、ひとをも愛せるということなのだ」という女性の心の声のセリフが印象的です。
キャサリンがどこか自信なさげで、凡庸に見えたのは、父親に愛されていなかったから。ルックスが人並みでも、キラキラしている人って、普通にいるじゃないですか。キャサリンも、序盤でパーティの支度をしながらラヴィニアと交わす会話はユーモアもあり、決して気の利かない凡庸な娘ではありません。そしてもし、モリスの愛を知ったら、、、。キャサリンは、その後モリスと破綻しても、人間不信などにはならず、また誰かを愛することが出来る人間になれたはず。
◆その他もろもろ
オリヴィア・デ・ハヴィランドは本作でオスカーを受賞しているそうですが、なるほどの演技です。前半と後半の明暗の素晴らしさ。前半の野暮ったさと言ったら、、、もう、娘というより“オバサン”に近い。モリスに恋してからは、オバサンぽいままだけれど、恋の悦びを全身にまとって素晴らしい。可愛く見えるんですもん。モリスにすっぽかされた後、ガックリと、自室への階段を上がるときの、あの暗い階段が聳え立つシーンが、何ともいえず切なく哀しいです。
モリスを演じたモンゴメリー・クリフトは、私的には好みじゃないけど、なるほどイケメンです。リズの恋人でもあったとか。モンティ自身はバイセクシャルだったそうですが、確かに、これは男にも女にもモテそう、、、。
そして、悪し様に罵って来た父親を演じたラルフ・リチャードソンは名演ですね。最期、娘にも看取られない憐れな父親役ですけれど、顔には知性も品性もあって、ちょっと意地悪そうで、ぴったりのハマリ役。
原作(ヘンリー・ジェイムズ著『ワシントン広場』)を読んでみたくなりました。
★★ランキング参加中★★
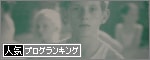















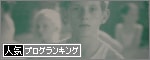


 なタイプ。
なタイプ。 、な話だったんですけど、、、。だってそうでしょう? “友達”に限らず、職場の同僚or上司、好きな男、近所のおばさん、親戚のおじちゃん、誰にだってぜ~んぶ同じ顔なわけないじゃんか。好きな男の前で見せてしまう顔を、親に見せるはずなかろうが。ちょっと考えれば分かることなのに、母親は、当たり前すぎることを言語化して真正面から娘に言われて、気持ちの持って行き場がなかったんでしょうなぁ。それは分かるけど、あの激昂振りはちょっと酷かった、、、。
、な話だったんですけど、、、。だってそうでしょう? “友達”に限らず、職場の同僚or上司、好きな男、近所のおばさん、親戚のおじちゃん、誰にだってぜ~んぶ同じ顔なわけないじゃんか。好きな男の前で見せてしまう顔を、親に見せるはずなかろうが。ちょっと考えれば分かることなのに、母親は、当たり前すぎることを言語化して真正面から娘に言われて、気持ちの持って行き場がなかったんでしょうなぁ。それは分かるけど、あの激昂振りはちょっと酷かった、、、。




