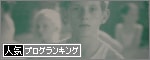1920年代のパリ。男爵家で大資産家の夫人、マルグリット・デュモン(カトリーヌ・フロ)は、音楽を、中でもオペラをこよなく愛する女性。彼女は、その資力にモノを言わせて、自宅で本格的なサロンコンサートを頻繁に開いていた。コンサートのトリは決まってマルグリット。ゲストに招いたプロ歌手に激励の言葉を掛けながら悠然と舞台に立つ彼女。
……が、彼女は、、、なんと、絶望的な音痴さんなのでした。しかも、そのことに本人だけが気付いていないという悲劇。音楽を理解する耳を持っているのに、自分の声を聞き分けることが出来ないという皮肉。
夫は彼女の資産で爵位を維持しているようなものだから、本当のことを彼女に言えず……。周囲も、彼女の資産目当てで付き合っている貴族ばかり。誰も彼女に真実を教えられないし、教えようとしない。でもそれは、彼女の資力だけでなく、彼女の人としての魅力も作用していたからなのだけど。
そんな状況で、マルグリットは、辛口評の新聞記者にも絶賛され、ますますオペラへの情熱は高まり、高名な歌手を家庭教師として、遂には、一流ホールでリサイタルを開催することを決意する。夫は何とか止めさせようとするが、彼女はリサイタルを決行する。
果たして、彼女の運命は、、、。
☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜☆゜'・:*:.。。.:*:・'☆゜'・:*:.。。.:*:・'゜
ちょっと考えさせられました、、、。何を考えたかは後述するとして、まずは鑑賞しての感想を(ネタバレしていますのであしからず)。
本作は、オペラ仕立てで構成されていて、第1幕から5くらいまであったんじゃないでしょうか。正直なところ、第2幕くらいまではいささか退屈でした。マルグリットが初めて歌うシーンは度肝を抜かれましたけれども。そして、最終幕のタイトルは、「真実」。これで大体ラストは想像できると思うのですが、、、。そう、蓄音機に録音された自分の歌声を聞いて、彼女は真実を知り、ショックのあまり床に倒れます。
彼女があそこまで歌にのめり込んでしまったのは、ひとえに、「夫の愛情不足」によるものです。
そして、その夫がね、、、。ヤなヤツなんですよ。というか、少なくとも私は嫌いな男です。マルグリットがサロンコンサートを開く日は、必ず車で出かけて、途中で車を止め、コンサートが終わるころを見計らって帰ってくる。つまり、車が故障して間に合わなかった、ということにしている。でも、妻はお見通しで、帰って来た夫に「また車が故障したのね?」とカマす。、、、セコいおっさんだ。
しかも、この夫、妻の友人と不倫までしているのです。不倫はともかく、相手が悪い。でもって、その不倫相手に「妻はモンスターだ」とかって愚痴る。うー、サイテーな男だ。せめて、妻の友人じゃない女にしなさいよ、不倫相手は。当時の上流階級じゃ、まあ、何でもアリだったんだろうとは想像しますが、、、。
妻の資力が頼りの夫は、妻が絶望的な音痴であることを告げられない。それは、妻への思いやりなんかじゃなく、そんなことを言ったら、妻との関係が破綻しかねないことを恐れているから。、、、まあこの辺は、後半で微妙に変わってくるんですけれども。
本作は良い映画だと思うのですが、今一つグッと来なかったのは、この夫の描写が理由だと思います。ヤなヤツだから、ではありません。それはいいのです、そういうキャラ設定なのですから。何が気に入らないかというと、終盤、この夫が妻への愛情を見せるようになるところです。妻への愛情を見せること自体は良いのですが、いかんせん、夫の心境が変化した理由が見ている方には伝わってこないのです。
ラスト、倒れたマルグリットに駆け寄る夫。そして夫はマルグリットを抱き起そうとしたカットで、ジ・エンド。この後の彼女はどうなったのか、、、。オペラ的に言えば、まあ、ヒロインの死で終わる、ってことで、マルグリットは真実を知ってショックのあまり死んでしまった、、、。解釈は色々あり得ますけど。
本作に通底していたのは、マルグリットの“孤独”じゃないかな。人としては魅力的なので、関わる人は皆、最初こそ奇異の目で彼女を見ますが、次第に彼女に好意的になって行きます。だからこそ、真実を誰も彼女に言えなかった、という側面もあるのですが。、、、でも、彼女が欲しかったのは、夫の愛情だったのだよねぇ。あんな男でも、彼女には愛しい夫だったのですよ。
なんか、見ていて、マルグリットが可哀想になってしまいました。あんまり、誰かを可哀想と言うのは好きじゃないのですが、本作のマルグリットに対しては他に言葉が見当たらない。それは、自分が音痴であるという真実を知らずにいるからではありません。この世で大好きなたった2つのもの~夫と音楽~に、死ぬまで片思いを続け、しかも、夫に裏切られただけじゃなく、最後は頼みの綱の音楽にまで裏切られてしまった、、、。
で、何を考えさせられたかと言いますと、、、。
本作中でのマルグリットの歌は、確かに下手だけれども、別に不快ではない。むしろ、私は楽しく聴きました。……そして、彼女は何と言ってもアマチュアで、趣味で歌っているのです。オペラのヒロインになり切って。この、“アマチュア”ってのがクセモノなんですよねぇ。私も学生時代にオケにいたので、アマの音楽がどういうものかは一応知っています。アマは実に幅が広い。もの凄く上手なアマもいますし、もの凄く下手なアマもいますが、所詮はアマであり、もの凄く上手なアマも、どう頑張ってもプロにはなれない程度でしかないのです。
なので、私は、社会人2年目での演奏会を最後に、“音楽とは私にとっては聴くものである”とハッキリ認識し、音楽をプレイすることからは一切足を洗いました。そして、聴くのは、必ず“プロ”の音楽で、“それなりの対価を払って”と決めています。アマの音楽は(ほぼ)絶対に聴きません。アマの音楽とは、プレイする人が楽しむためのものであり、聴衆を喜ばせるものではないからです。私も一時期はどっぷりハマっていたアマの世界でしたが、ある時ふと、そういう“所詮アマの世界”であるにもかかわらず上手いだ下手だと批評し合う仲間の奏者たちに辟易しましたし、自分たちの奏でる音楽のド下手ぶりにもウンザリしてしまったのです。自分たちさえ楽しきゃいいのか、ということを突き詰めて考えてしまったのです。
もちろん、これは私の定義であり、人によってはアマの演奏会に好んで行く人もいますし、アマの音楽で感動する人もいます。そういう楽しみ方を否定するのではありません。ただし、アマの音楽を敢えて聴くからには厳然とした約束事があって、それは「絶対に彼らの演奏を批判しない」ということです。
だから、本作でもマルグリットには罪はなく、聴衆が悪いと思うわけです。きちんとアマの音楽であることを弁えて聴けば良いのです。そして、夫も、マルグリットに真実をきちんと早い段階で伝えるべきなのです。本当に愛情があるのならば。ま、なかったんですけどね、マルグリットの夫には。
とはいっても、演奏経験のない全くの素人の聴衆というのは、もの凄く下手なのは聴き分けられちゃうのですよ。上手いについては、どの程度上手いかは聴き分けられなくても。そこが、マルグリットの悲劇を生んだ要因の一つでもあると思います。
カトリーヌ・フロは、割と好きな女優さんの一人ですが、さすがに彼女も歳をとりましたね。大分ふくよかになられたような、、、。もちろんお美しいですが。マルグリットを実に魅力的に演じておられました。序盤に出てくるプロを目指す歌手アゼル役のクリスタ・テレがとっても美しくて素敵でした。彼女が狂言回しかと思っていたら、中盤以降ほとんど出て来なくて拍子抜けでしたが、、、。男性陣の出演者にイマイチ魅力がなかったのが残念。強いて言えば、マルグリットの歌の家庭教師役を務めたミシェル・フォーがイイ味出していたかな。
カトリーヌ・フロが、本作でセザール賞を受賞されたそうで。見れば納得の受賞です。
衣装・美術が圧巻です 

★★ランキング参加中★★