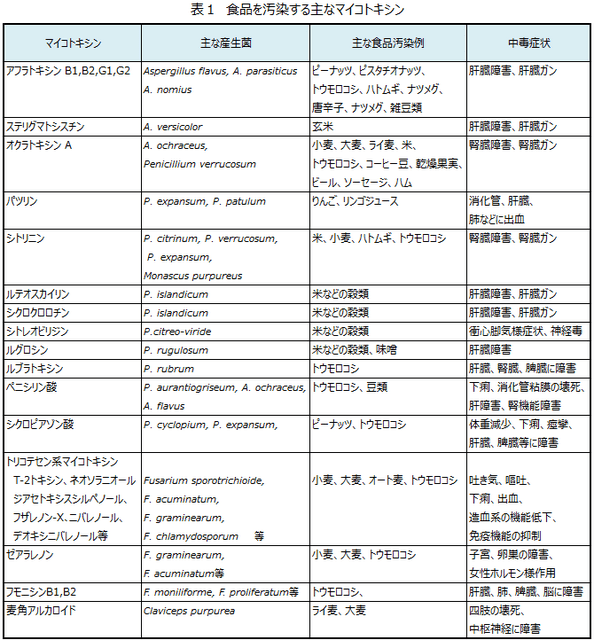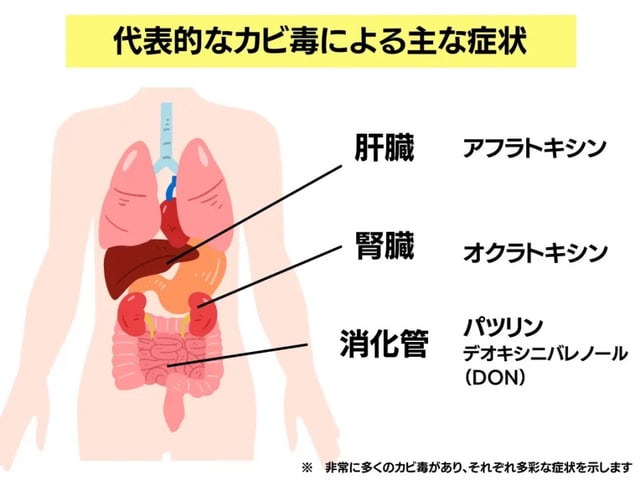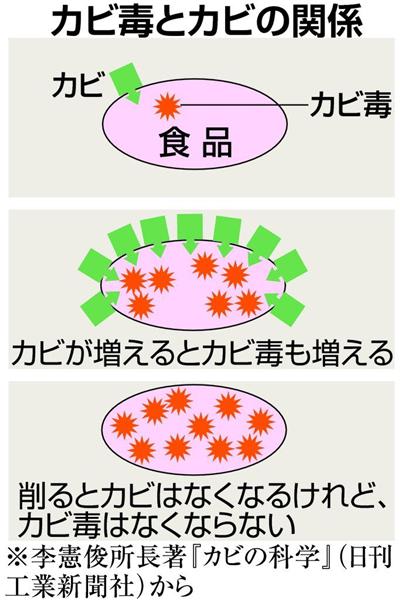2024 3月28日 (木曜日) ② 曇り日
上毛新聞の三山春秋
地域や季節の話題をひもときながら、心あたたまるコラムをお届け。
▼和菓子屋の前に「草餅」と書かれたのぼりがはためいていた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
野の香りとかすかな苦みが浮かんでくる。
平安時代の歌人和泉式部の「和泉式部集」に、
手箱に入れて子に贈ったとの記述があるほど歴史は古い
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼もっともその頃は砂糖を使った甘い小豆餡(あん)などなかったはずだから、
今のような味わいだったとは考えにくい。
違いは他にもあり、練り込んでいたのはハハコグサである。
後に、母と子を一緒につくのは縁起が悪いとしてヨモギが主流になった。
へえ~!知らなかった。
メモ 母子草「ハハコグサ」季節の花より借用
母子草「ハハコグサ」季節の花より借用

・菊(きく)科。
・開花時期は、 4/ 1 ~ 5/末頃。3月以前に咲きだすものもときどき見かける)
・春の七草のひとつ。(春の七草では「御形(ごぎょう、または、おぎょう)」と呼ぶ。)
・柔らかいうす緑色の葉の先に、黄色の花がつぶつぶになってかたまって咲く。
・名前は「母」と「子」の 人形(ひとがた)に由来する、との説がある。
・薬効 せきどめ ・薬用部位 全草
・昔は草餅の材料だったが、明治の頃から次第に「蓬(よもぎ)」が
材料にされるようになった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
蓬「ヨモギ」
・春の若葉は「ヨモギ摘み」でお馴染み。
・古くから邪気を払うと信じられ、
端午の節句に 菖蒲(しょうぶ)とともに浴湯にこれを入れる。

・秋、9~10月頃に茶色っぽい小さな花が咲く。
・夏から秋にかけて、1m以上に背を伸ばすが、
夏の草刈りでほとんど刈られてしまうので、秋に背が伸びたのを見られるのは
植物園で見かけるときぐらいです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・「善萌(よもき)草」の意で、よく萌え出でることから。
または、「善燃(よもき)草」の意で、お灸に使うと、よく燃えることから。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼邪気払いの願いを込めて3月の節句に欠かせなかった菓子は、
現代でも春の甘味の代表格だ。
一つ二つと携えて花見に出かけたいところだが、桜の便りはまだ届かない
~~~~~~~~~~~~~~
▼今年は暖冬で、春が駆け足でやって来るとみられていた。
県内は先月下旬、春を飛び越えて初夏の陽気になった日があったほど。
ここに来て平野部でも雪が積もったり、冷たい雨が続いたり、
真冬に逆戻りしたかのようである
~~~~~~~~~~~~~~~~
▼気をもむ人々を横目に、桜前線は高知、宮崎、広島と北上中である。
前橋は今週後半の開花予想となった。
咲いてしまえばあっという間に満開となり、
散ってしまう。
今日か明日かと待っているうちが楽しいのかもしれない
~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼〈花のさと心も知らず春の野にいろいろつめるははこもちひぞ〉和泉式部。
筆者も昔、祖母とヨモギを摘んで草餅を作ったことがある。
花見まで間があるのなら手作りもいい。
========================
◆小さいころ、ヨモギ摘みをさせられたなあ~!
香りが強かった!
今は畑にはびこる草でほっておけない。
上毛新聞の三山春秋

地域や季節の話題をひもときながら、心あたたまるコラムをお届け。
▼和菓子屋の前に「草餅」と書かれたのぼりがはためいていた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
野の香りとかすかな苦みが浮かんでくる。
平安時代の歌人和泉式部の「和泉式部集」に、
手箱に入れて子に贈ったとの記述があるほど歴史は古い
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼もっともその頃は砂糖を使った甘い小豆餡(あん)などなかったはずだから、
今のような味わいだったとは考えにくい。
違いは他にもあり、練り込んでいたのはハハコグサである。
後に、母と子を一緒につくのは縁起が悪いとしてヨモギが主流になった。
へえ~!知らなかった。
メモ
 母子草「ハハコグサ」季節の花より借用
母子草「ハハコグサ」季節の花より借用
・菊(きく)科。
・開花時期は、 4/ 1 ~ 5/末頃。3月以前に咲きだすものもときどき見かける)
・春の七草のひとつ。(春の七草では「御形(ごぎょう、または、おぎょう)」と呼ぶ。)
・柔らかいうす緑色の葉の先に、黄色の花がつぶつぶになってかたまって咲く。
・名前は「母」と「子」の 人形(ひとがた)に由来する、との説がある。
・薬効 せきどめ ・薬用部位 全草
・昔は草餅の材料だったが、明治の頃から次第に「蓬(よもぎ)」が
材料にされるようになった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
蓬「ヨモギ」
・春の若葉は「ヨモギ摘み」でお馴染み。
・古くから邪気を払うと信じられ、
端午の節句に 菖蒲(しょうぶ)とともに浴湯にこれを入れる。

・秋、9~10月頃に茶色っぽい小さな花が咲く。
・夏から秋にかけて、1m以上に背を伸ばすが、
夏の草刈りでほとんど刈られてしまうので、秋に背が伸びたのを見られるのは
植物園で見かけるときぐらいです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・「善萌(よもき)草」の意で、よく萌え出でることから。
または、「善燃(よもき)草」の意で、お灸に使うと、よく燃えることから。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼邪気払いの願いを込めて3月の節句に欠かせなかった菓子は、
現代でも春の甘味の代表格だ。
一つ二つと携えて花見に出かけたいところだが、桜の便りはまだ届かない
~~~~~~~~~~~~~~
▼今年は暖冬で、春が駆け足でやって来るとみられていた。
県内は先月下旬、春を飛び越えて初夏の陽気になった日があったほど。
ここに来て平野部でも雪が積もったり、冷たい雨が続いたり、
真冬に逆戻りしたかのようである
~~~~~~~~~~~~~~~~
▼気をもむ人々を横目に、桜前線は高知、宮崎、広島と北上中である。
前橋は今週後半の開花予想となった。
咲いてしまえばあっという間に満開となり、
散ってしまう。
今日か明日かと待っているうちが楽しいのかもしれない
~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼〈花のさと心も知らず春の野にいろいろつめるははこもちひぞ〉和泉式部。
筆者も昔、祖母とヨモギを摘んで草餅を作ったことがある。
花見まで間があるのなら手作りもいい。
========================
◆小さいころ、ヨモギ摘みをさせられたなあ~!
香りが強かった!

今は畑にはびこる草でほっておけない。











 ⇒雨
⇒雨