【東福寺:方丈庭園】
日帰り京都の旅でもう一箇所訪れたのは東福寺でした。
ここ数年毎年参拝している伏見稲荷へ向かう途中、隣にある東福寺を横目で見ながら
来年は・・・この次は・・・と思いながら素通りしていました。
やっと、見に行くことができました。

東福寺と言えば、禅寺としては最大で最古の三門
紅葉の名所として名高いな通天橋、そして方丈の市松模様の庭が知られています。
東福寺は臨済宗重複はの大本山であり、京都五山の第四位でもある位の高いお寺です。
鎌倉時代:嘉禎2年(1236)摂政・九条道家によって建立されました。
聖一国師を開山として、19年もの歳月を費やし造営されました。
東福寺の名は、「洪基を東大に亜(つ)ぎ、盛業を興福に取る」と、
奈良の二大寺である東大寺と興福寺にちなんで名付けられたのだそうです。



【三門】詳しくは 「こちら」 【本堂】詳しくは 「こちら」

【経蔵】詳しくは 「こちら」

方丈庭園(ほうじょう ていえん)にも立ち寄りました。
昭和13年に作庭家である重森三玲(しげもり みれい)によって作庭されました。
四方(東西南北)に4つの美しい庭園を配しています。
釈迦成道を表現し、八相の庭と命名され、近代禅宗庭園の代表として広く世界各国に紹介されています。
方丈とは宇宙を意味し、住職の生活の場でもあったそうです。


【南庭】
西方に京の五山にみたてた築山。 蓬莢・方丈・瀛洲(えいじゅう)・壺梁(こうりょう)の四島に見立てた巨石と
砂紋による荒海を大和絵風に表されています。

そして、今回一番見てみたかったのがここ!

北庭です。
東福寺の紹介されているものには必ずといっていいほど写真のが載せられている庭です。
市松の庭は、作庭以前に南の御下賜門内に敷かれていた石を市松模様に配したもので
通天紅葉の錦織りなす景観を借り、サツキの丸刈り、苔地の妙が調和するという
南庭とは逆に色彩感あふれる空間となっています。
昭和初期のモダンデザインを具現化しているとして、外国からの見学者の多い庭でもあります。
フランスの幾何学模様に刈り込まれた庭園を、思い浮かべ
斬新で素晴らしいと評価の高い庭に暫し見入っていました。
市松模様になぜ市松と言う名がついているのかというと
江戸時代の歌舞伎役者、初代佐野川市松が舞台「心中万年草」で小姓・粂之助に扮した際
白と紺の正方形を交互に配した袴を履いたことから人気を博し
着物の柄として流行したことから「市松模様」・「市松格子」などと
呼ばれるようになったのだそうです。
そのため、家紋や名物裂など江戸時代以前から存在するものは石畳模様と呼ばれます。

家紋と言えば、ルイ・ヴィトンが日本の家紋を見て「モノグラム」をデザインしたことは有名な話です。

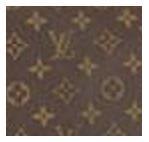

ルイ・ヴィトンが最初に有名になったのは、「ダミエ」と言う黒と茶のチェッカー(チェス盤模様)
日本語で言う市松模様です。
その後発売された白とグレー「ダミエ」は


この襖のデザインにとてもよく似ていると思いませんか?

【桂離宮:松琴亭】
東福寺の方丈の庭を作庭した重森三玲(みれい)の名は、フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーにちなみ
本人が改名したものなのだそうです。
そして、彼の自邸は庭園美術館として公開されており
その中には、桂離宮を髣髴とさせるデザインがあるのだそうです。
彼の目指した「永遠のモダン」・・・
いつの時代にも、新しいと感じられるデザインは
ずっと昔から日本の美意識の中にあったのだということなのでしょう。


今日も長々とお付き合いくらはって、おおきに。ほなさいなら~♪

日帰り京都の旅でもう一箇所訪れたのは東福寺でした。
ここ数年毎年参拝している伏見稲荷へ向かう途中、隣にある東福寺を横目で見ながら
来年は・・・この次は・・・と思いながら素通りしていました。
やっと、見に行くことができました。

東福寺と言えば、禅寺としては最大で最古の三門
紅葉の名所として名高いな通天橋、そして方丈の市松模様の庭が知られています。
東福寺は臨済宗重複はの大本山であり、京都五山の第四位でもある位の高いお寺です。
鎌倉時代:嘉禎2年(1236)摂政・九条道家によって建立されました。
聖一国師を開山として、19年もの歳月を費やし造営されました。
東福寺の名は、「洪基を東大に亜(つ)ぎ、盛業を興福に取る」と、
奈良の二大寺である東大寺と興福寺にちなんで名付けられたのだそうです。
 【通天橋】 このあたりは、紅葉の季節には人で 溢れかえるのだそうです。 かつてこの寺ににあった桜は 花見に浮かれる人々の姿を嫌った 室町時代の僧(明兆)が将軍へ 伐採を請願したのだそうです。 |  紅葉の時期ではありませんでしたが 野鳥が出迎えてくれました。 ~調べてみましたが残念ながら名前が わかりません。 どなたかご存じないですか?~ |



【三門】詳しくは 「こちら」 【本堂】詳しくは 「こちら」

【経蔵】詳しくは 「こちら」

方丈庭園(ほうじょう ていえん)にも立ち寄りました。
昭和13年に作庭家である重森三玲(しげもり みれい)によって作庭されました。
四方(東西南北)に4つの美しい庭園を配しています。
釈迦成道を表現し、八相の庭と命名され、近代禅宗庭園の代表として広く世界各国に紹介されています。
方丈とは宇宙を意味し、住職の生活の場でもあったそうです。


【南庭】
西方に京の五山にみたてた築山。 蓬莢・方丈・瀛洲(えいじゅう)・壺梁(こうりょう)の四島に見立てた巨石と
砂紋による荒海を大和絵風に表されています。
 【北斗七星の庭】 ◇西庭 さつきの刈り込みによる大きな市松模様を表現しています。 花の咲く季節に来てみたいものですね。 | ◇東庭 東司(とんす・トイレのこと)に使われていた柱石を 北斗七星に並べ、雲文様地割に配し小宇宙空間を表現。  |

そして、今回一番見てみたかったのがここ!

北庭です。
東福寺の紹介されているものには必ずといっていいほど写真のが載せられている庭です。
市松の庭は、作庭以前に南の御下賜門内に敷かれていた石を市松模様に配したもので
通天紅葉の錦織りなす景観を借り、サツキの丸刈り、苔地の妙が調和するという
南庭とは逆に色彩感あふれる空間となっています。
昭和初期のモダンデザインを具現化しているとして、外国からの見学者の多い庭でもあります。
フランスの幾何学模様に刈り込まれた庭園を、思い浮かべ
斬新で素晴らしいと評価の高い庭に暫し見入っていました。
市松模様になぜ市松と言う名がついているのかというと
江戸時代の歌舞伎役者、初代佐野川市松が舞台「心中万年草」で小姓・粂之助に扮した際
白と紺の正方形を交互に配した袴を履いたことから人気を博し
着物の柄として流行したことから「市松模様」・「市松格子」などと
呼ばれるようになったのだそうです。
そのため、家紋や名物裂など江戸時代以前から存在するものは石畳模様と呼ばれます。

家紋と言えば、ルイ・ヴィトンが日本の家紋を見て「モノグラム」をデザインしたことは有名な話です。

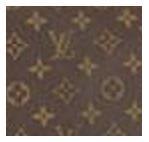

ルイ・ヴィトンが最初に有名になったのは、「ダミエ」と言う黒と茶のチェッカー(チェス盤模様)
日本語で言う市松模様です。
その後発売された白とグレー「ダミエ」は


この襖のデザインにとてもよく似ていると思いませんか?

【桂離宮:松琴亭】
東福寺の方丈の庭を作庭した重森三玲(みれい)の名は、フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーにちなみ
本人が改名したものなのだそうです。
そして、彼の自邸は庭園美術館として公開されており
その中には、桂離宮を髣髴とさせるデザインがあるのだそうです。
彼の目指した「永遠のモダン」・・・
いつの時代にも、新しいと感じられるデザインは
ずっと昔から日本の美意識の中にあったのだということなのでしょう。


 【京ばあむ】 | 京都の新しい和洋折衷スイーツ! ~抹茶豆乳バームクーヘン~「京・ばあむ」をお土産に買いました。 抹茶の大好きな姪は大喜び。  今、抹茶味は女子高生の間でも 大人気なのだとか。 http://www.otabe.co.jp/item/baum.html |
今日も長々とお付き合いくらはって、おおきに。ほなさいなら~♪



















