
【東福寺:方丈庭園】
日帰り京都の旅でもう一箇所訪れたのは東福寺でした。
ここ数年毎年参拝している伏見稲荷へ向かう途中、隣にある東福寺を横目で見ながら
来年は・・・この次は・・・と思いながら素通りしていました。
やっと、見に行くことができました。

東福寺と言えば、禅寺としては最大で最古の三門
紅葉の名所として名高いな通天橋、そして方丈の市松模様の庭が知られています。
東福寺は臨済宗重複はの大本山であり、京都五山の第四位でもある位の高いお寺です。
鎌倉時代:嘉禎2年(1236)摂政・九条道家によって建立されました。
聖一国師を開山として、19年もの歳月を費やし造営されました。
東福寺の名は、「洪基を東大に亜(つ)ぎ、盛業を興福に取る」と、
奈良の二大寺である東大寺と興福寺にちなんで名付けられたのだそうです。



【三門】詳しくは 「こちら」 【本堂】詳しくは 「こちら」

【経蔵】詳しくは 「こちら」

方丈庭園(ほうじょう ていえん)にも立ち寄りました。
昭和13年に作庭家である重森三玲(しげもり みれい)によって作庭されました。
四方(東西南北)に4つの美しい庭園を配しています。
釈迦成道を表現し、八相の庭と命名され、近代禅宗庭園の代表として広く世界各国に紹介されています。
方丈とは宇宙を意味し、住職の生活の場でもあったそうです。


【南庭】
西方に京の五山にみたてた築山。 蓬莢・方丈・瀛洲(えいじゅう)・壺梁(こうりょう)の四島に見立てた巨石と
砂紋による荒海を大和絵風に表されています。

そして、今回一番見てみたかったのがここ!

北庭です。
東福寺の紹介されているものには必ずといっていいほど写真のが載せられている庭です。
市松の庭は、作庭以前に南の御下賜門内に敷かれていた石を市松模様に配したもので
通天紅葉の錦織りなす景観を借り、サツキの丸刈り、苔地の妙が調和するという
南庭とは逆に色彩感あふれる空間となっています。
昭和初期のモダンデザインを具現化しているとして、外国からの見学者の多い庭でもあります。
フランスの幾何学模様に刈り込まれた庭園を、思い浮かべ
斬新で素晴らしいと評価の高い庭に暫し見入っていました。
市松模様になぜ市松と言う名がついているのかというと
江戸時代の歌舞伎役者、初代佐野川市松が舞台「心中万年草」で小姓・粂之助に扮した際
白と紺の正方形を交互に配した袴を履いたことから人気を博し
着物の柄として流行したことから「市松模様」・「市松格子」などと
呼ばれるようになったのだそうです。
そのため、家紋や名物裂など江戸時代以前から存在するものは石畳模様と呼ばれます。

家紋と言えば、ルイ・ヴィトンが日本の家紋を見て「モノグラム」をデザインしたことは有名な話です。

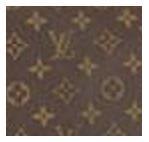

ルイ・ヴィトンが最初に有名になったのは、「ダミエ」と言う黒と茶のチェッカー(チェス盤模様)
日本語で言う市松模様です。
その後発売された白とグレー「ダミエ」は


この襖のデザインにとてもよく似ていると思いませんか?

【桂離宮:松琴亭】
東福寺の方丈の庭を作庭した重森三玲(みれい)の名は、フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーにちなみ
本人が改名したものなのだそうです。
そして、彼の自邸は庭園美術館として公開されており
その中には、桂離宮を髣髴とさせるデザインがあるのだそうです。
彼の目指した「永遠のモダン」・・・
いつの時代にも、新しいと感じられるデザインは
ずっと昔から日本の美意識の中にあったのだということなのでしょう。


今日も長々とお付き合いくらはって、おおきに。ほなさいなら~♪

日帰り京都の旅でもう一箇所訪れたのは東福寺でした。
ここ数年毎年参拝している伏見稲荷へ向かう途中、隣にある東福寺を横目で見ながら
来年は・・・この次は・・・と思いながら素通りしていました。
やっと、見に行くことができました。

東福寺と言えば、禅寺としては最大で最古の三門
紅葉の名所として名高いな通天橋、そして方丈の市松模様の庭が知られています。
東福寺は臨済宗重複はの大本山であり、京都五山の第四位でもある位の高いお寺です。
鎌倉時代:嘉禎2年(1236)摂政・九条道家によって建立されました。
聖一国師を開山として、19年もの歳月を費やし造営されました。
東福寺の名は、「洪基を東大に亜(つ)ぎ、盛業を興福に取る」と、
奈良の二大寺である東大寺と興福寺にちなんで名付けられたのだそうです。
 【通天橋】 このあたりは、紅葉の季節には人で 溢れかえるのだそうです。 かつてこの寺ににあった桜は 花見に浮かれる人々の姿を嫌った 室町時代の僧(明兆)が将軍へ 伐採を請願したのだそうです。 |  紅葉の時期ではありませんでしたが 野鳥が出迎えてくれました。 ~調べてみましたが残念ながら名前が わかりません。 どなたかご存じないですか?~ |



【三門】詳しくは 「こちら」 【本堂】詳しくは 「こちら」

【経蔵】詳しくは 「こちら」

方丈庭園(ほうじょう ていえん)にも立ち寄りました。
昭和13年に作庭家である重森三玲(しげもり みれい)によって作庭されました。
四方(東西南北)に4つの美しい庭園を配しています。
釈迦成道を表現し、八相の庭と命名され、近代禅宗庭園の代表として広く世界各国に紹介されています。
方丈とは宇宙を意味し、住職の生活の場でもあったそうです。


【南庭】
西方に京の五山にみたてた築山。 蓬莢・方丈・瀛洲(えいじゅう)・壺梁(こうりょう)の四島に見立てた巨石と
砂紋による荒海を大和絵風に表されています。
 【北斗七星の庭】 ◇西庭 さつきの刈り込みによる大きな市松模様を表現しています。 花の咲く季節に来てみたいものですね。 | ◇東庭 東司(とんす・トイレのこと)に使われていた柱石を 北斗七星に並べ、雲文様地割に配し小宇宙空間を表現。  |

そして、今回一番見てみたかったのがここ!

北庭です。
東福寺の紹介されているものには必ずといっていいほど写真のが載せられている庭です。
市松の庭は、作庭以前に南の御下賜門内に敷かれていた石を市松模様に配したもので
通天紅葉の錦織りなす景観を借り、サツキの丸刈り、苔地の妙が調和するという
南庭とは逆に色彩感あふれる空間となっています。
昭和初期のモダンデザインを具現化しているとして、外国からの見学者の多い庭でもあります。
フランスの幾何学模様に刈り込まれた庭園を、思い浮かべ
斬新で素晴らしいと評価の高い庭に暫し見入っていました。
市松模様になぜ市松と言う名がついているのかというと
江戸時代の歌舞伎役者、初代佐野川市松が舞台「心中万年草」で小姓・粂之助に扮した際
白と紺の正方形を交互に配した袴を履いたことから人気を博し
着物の柄として流行したことから「市松模様」・「市松格子」などと
呼ばれるようになったのだそうです。
そのため、家紋や名物裂など江戸時代以前から存在するものは石畳模様と呼ばれます。

家紋と言えば、ルイ・ヴィトンが日本の家紋を見て「モノグラム」をデザインしたことは有名な話です。

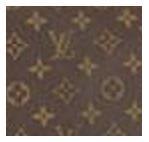

ルイ・ヴィトンが最初に有名になったのは、「ダミエ」と言う黒と茶のチェッカー(チェス盤模様)
日本語で言う市松模様です。
その後発売された白とグレー「ダミエ」は


この襖のデザインにとてもよく似ていると思いませんか?

【桂離宮:松琴亭】
東福寺の方丈の庭を作庭した重森三玲(みれい)の名は、フランスの画家ジャン・フランソワ・ミレーにちなみ
本人が改名したものなのだそうです。
そして、彼の自邸は庭園美術館として公開されており
その中には、桂離宮を髣髴とさせるデザインがあるのだそうです。
彼の目指した「永遠のモダン」・・・
いつの時代にも、新しいと感じられるデザインは
ずっと昔から日本の美意識の中にあったのだということなのでしょう。


 【京ばあむ】 | 京都の新しい和洋折衷スイーツ! ~抹茶豆乳バームクーヘン~「京・ばあむ」をお土産に買いました。 抹茶の大好きな姪は大喜び。  今、抹茶味は女子高生の間でも 大人気なのだとか。 http://www.otabe.co.jp/item/baum.html |
今日も長々とお付き合いくらはって、おおきに。ほなさいなら~♪




























むか~し昔に行った時の記憶が、ずい分薄くなってきてまして
でも、この市松模様の庭は、いろんな本や雑誌で見ていました。
pinkyさんの解説のおかげで、東福寺には他にも素晴らしい庭があり
その中で、一際目を引く庭だという事がわかりました。
それに、市松模様の語源も、知らなかったぁ!!!
今回も、いっぱい勉強になりました。
桂離宮は、9年前にヨーゼフが初めて日本へ来たときに行きました。
松琴亭の風景は、よく覚えています!
ただ・・8月初めの大変に暑い時期で、日本の(しかも京都の)暑さに驚いていたヨーゼフは
覚えていない場所も多いみたいなんです。
最後の抹茶バームクーヘンに、目を見開いてしまいました!!!
売られているのは、京都だけなんでしょうか?
抹茶のお菓子は、ヨーゼフはもちろん、こちらの友人に大変受けるのですが
このところ種類も数も減ってきてるんですよね・・・
出迎えの野鳥ですが、大きさが解らないので、もしかしたら違うかもしれませんが
ウグイス科のセッカとか、シマセンニュウとかじゃありませんか?
スイスに来て、いろんな鳥を見るようになり、時折使うサイトがあるので、良かったら見てください。
http://www.yachoo.org/?action=Book
永遠のモダン...........
新しいデザインが昔から有る日本の美意識にあると言う事。
日本人としては嬉しいですね。
有名なブランドの元は日本人が持っていると言う事ですね。
庭園のテーマが宇宙と言うのも気になります。
ゆっくりと京都巡り行きたくなります。
建築家のヨーゼフさんにとって、京都はそれは興味深い街でしょうね。
東福寺は、京都駅から南東にあって、伏見稲荷以外に歩いて回れる名所旧跡が少ないからでしょうか。
京都好きの方でも、行かれている方が少ないような気がします。
この市松模様の庭がずっと気になっていて、やっと見に行くことが出来たんです。
歌舞伎役者の佐野川市松は、まさに水も滴るいい男だったそうです。
そのイケメン歌舞伎役者は、お洒落のセンスもよかったのでしょうね。
一躍この市松模様が流行るようになったらしいです。
ところで、この抹茶バームクーヘンの白い部分は
豆乳味なんです。
全部抹茶味のものより、さっぱりしていて美味しい気がします。
今のところ京都駅でしか見たことがありませんが
「おたべ」の会社の製品
http://www.otabe.co.jp/item/baum.html
野鳥図鑑の紹介ありがとうございます。
似ているような?
スズメよりは大きくて、ムクドリくらいあったかな?
大きさは20cmくらいあったような気がします。
くちばしは肉色で、オールバックのようなヘアスタイル~!
眼光鋭い感じでした。
また何か気がついたら教えてくださいね~♪
そうなんです!
世界に誇るブランドが、古い日本のデザインに
ヒントを得たというのは誇らしい気持ちになりますよね。
日本人が、このブランドをとても好きな理由がわかったような気がしました。
冬の京都はお薦めです。
他の季節は観光客があまりに多くて、この壮大なイメージを持つ庭を
ゆっくり独り占めして鑑賞するなんてなかなか出来ません。
やはり、どこか素敵な宿で
せめて一泊したかったです。
和菓子製作の体験コースと言うのにも行ってみたいです~!
で、知らないことばっかりでした^^;;
写真も美しいし、内容も勉強になるし、
すごいよ!すごいよ!pinkyさん
こんな風に見られたら、わたしの人生もバラ色かしらん
……ナァンて思いつつ、今日もそれなりに楽しもうと決め込むわたし。
pinkyさん,今日も楽しい時間をつなぎあわせて下さいね☆
わたしも楽しもうっと!
上↑に紅葉東福寺の拙記事をリンク^^おお!はずかし
ブログが百科事典のようでもあり、学術書のようでもあります。
さわりだけ。
ルイ・ヴィトンと日本の家紋関係は妙に納得します。
あのデザインには不思議な感じを持っていました。
西洋人は東洋のものが神秘的に見えていろいろとひらめくんでしょうかね!
ビートルズもインド音楽にのめり込んだし、欧米にはたくさんの日本古来のコレクションがありますね。
ところで“抹茶豆乳バームクーヘン”のヒストリーはどうなっているんでしょう?
ふふふ・・・やはりこちらはRanchoさんの庭でしたか~!
素敵な場所ですね。
そして、そして紅葉の東福寺の様子をリンクしてくださってありがとうございま~~す!!
美しい写真の数々にうっとりです。
雪舟寺もいいですか!
実は前を通るときに、拝観しようか迷ったんです。
最近、記憶力の低下が著しく同じ日にふたつ以上のお寺を見学すると
後で記憶がごっちゃになってしまうんです。
それで、断念いたしました。
また次回の楽しみにとっておきます。
日々の平凡な暮らしの隙間を、こうした楽しいことでつなぎ合わせていけますように♪
また、お薦めの場所がありましたら教えてくださいね。
何か一つのことを、ず~っと辿って行くと
いつの間にかもとの場所に戻っていた・・・
そんな感じでした。
最初のパリ万博で、ヨーロッパの人々が驚嘆したジャポニズムは今も健在だと思いたいですね。
いつだったか、うちの祖父がルイヴィトンの模様を見て
信玄袋の柄のようだと行ったことを思い出しました。
「抹茶豆乳バームクーヘン」?
今、大ブームの抹茶味と豆乳とバームクーヘンを一緒にしてしまうなんて
大ヒットを狙ったんでしょうね。
今は、何でも抹茶味ってありますよね。
人気のバームクーヘンのお店は、行列しないと買えませんし・・・
生八橋のように、大ヒット商品になるでしょうか。
いつものことながら 今回は テレビや雑誌でも読んでるようでした
なかなか面白い
こういったモダンな庭園もいいですね
芝生の色もうまくできてますね
ヴィトン 息がながいですね
この古いデザインはしりませんでした
北斗七星~へえ~~~~
結構観光していたのですが・・・そうですか~
ヴィトンのモノグラムは好きです
花と星と、ルイ・ヴィトンのロゴ
究極ですよね~(笑)
あら~ダミエの方が先だったのですか?
ブランド品は、義姉のプレゼントがメインなので・・・