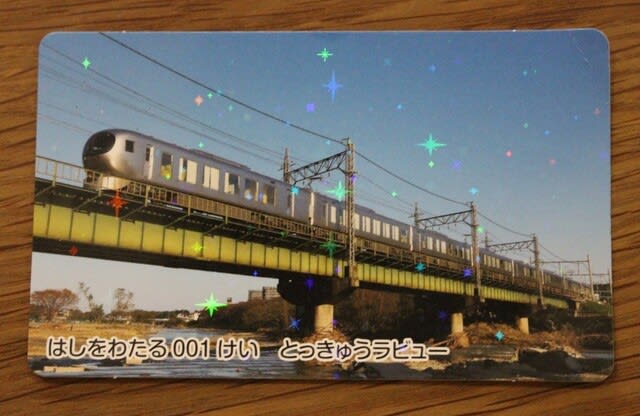エブロ1/24 シトロエンHバンのモバイルキッチン仕様については、随分前に製品化され、市場から消えるのも早かったと思います。今はバージョン違いでクレープ屋さん仕様が出ています。モバイルキッチンについては私も興味があり、発売直後に買ったのですが、どんな設定にするかで考え、さらにキットのパーツでは足りないものを自作したり、他社のパーツなどを使ったりで、構想2年、製作3年という感じになってしまいました(さっさと作れよ、ということですよね)。完成したのは今年の1月でしたが、今の時季にお見せしたく、ブログに掲載しました。

キットではフランスのパン屋さん仕様となっており、当然ですが全体にフレンチテイストです。クロワッサンやバゲットのサンドなどのパーツも入っています。厨房部分はガス台、レンジ、コーヒーマシンなどもあり、ちょっとした軽食も出せるパン屋さんの屋台が開業できるわけですが、私はあれこれ考えて、これをF1のサーキットで軽食を提供しているキッチンカー風、それもイタリアのキッチンカーとしてみました。
全体の説明となりますが、キットそのものはほぼストレートに組んでいます。車体はMr.カラーの「アルミナイズドシルバー」を吹き付け、アイボリー部分はGMカラー21番、アイボリーAです。

店の名前は「ポールポジション」にしました。こういう場所の軽食ですから速さが命、ということでこういう名前にした、という設定です。イタリア語と英語でパニーニやコーヒー、飲み物を扱っている、とあります。こちらは以前もご紹介した自作デカールです。
キットのオリジナルには無いものも適宜加えています。


ショーケース内側から見て右手にはパニーニをエポキシパテで作って入れました。焼き目がついていますので作り置きしているようです。本来なら焼きたてが美味しいのですが、たくさんのお客さんをさぱくために作り置きし、温めなおしているのでしょう。実際にイタリアの鉄道駅で似たような経験をしています。クロワッサンは白をペタペタ塗りつけ、粉砂糖を撒いた感じにしました。イタリアではクロワッサンというと中にジャムが入っていたり、甘めのものが出てくることが多いので、イタリア風としました。
また、右手前にはキットには無い流しもプラ板から作りました(完成後はほとんど見えませんが)。ガス台など調理器具が揃っている中で、流しが無いというのも変だなと思い、小さな流しをつけてみました。
カウンターの木部についてはタンを塗った後でクリアーイエローを塗り重ねてニス塗りっぽい質感を出しています。
さらに、ショーケースの隣にはグラニータ(イタリアのかき氷)メーカーも置きました。

夏のイタリアに行きますと、いろいろな味のグラニータの機械が屋台などに置かれています。四角いものが多いのですが、透明プラ板を四角く切り出し、そこにシリコンを入れるのもちょっと難しそうだったので、透明の丸いプラパイプにクリアーイエローで着色したシリコンを入れ、透明パーツのランナーをランダムに切ったものを散らして氷のように見せています。正面側にはレモンのマークが入っていますのでレモン味なのでしょう(100%レモンの場合は、黄色くならずに白っぽくなります。おそらく、このグラニータは着色料を使っているのでしょう)。
厨房側です。

ガス台、レンジ、コーヒーマシンなどは塗装後に注意表示のステッカーをキャラもののコーションデータデカールから貼りました。ガス台の周囲には防炎用のついたてを追加しました。こちらはキットにはありません。カーモデル用の断熱シートを再現するのりつきアルミ箔から切り出しています。ガス台の背後が樹脂か何かではやはり火災の心配もしないといけないかな、というわけです。背後の棚などの色はGMカラー27番・レッドAです。
ガス台の下などにも荷物や機器が入っています。ガス台の下の段ボールはイタリアの炭酸水のそれですが、マソモデル1/35のものを使っています。コーヒーマシンの下の「ラバッツァ」のコーヒーのカートンも同じです。レンジの下の銀色の箱状のものはキットには無いパーツですが、冷蔵庫に見立てています。これだけの設備があって冷蔵庫が無いのも、というわけで入れたかったのです。こちらはイタレリの「TRUCK SHOP ACCESORIES」という同社のトラックのキットなどのオプションパーツとして発売されているものからとりました。このキットのパーツはこの後も出てきます。
会計はショーケースのある側で行い、商品の渡し口はリアゲートの方にあるようです。

リアゲートの板ですが、キットではただわたしてあるだけで、少々心もとない感もしましたので、板の下にアングル材を入れて、リアゲートで挟み付ける構造にしています。プラ材を貼っただけですし、ほとんど見えないところではありますが、実際に自分がこの車のオーナーだったら、という目線で作りますと、いろいろ気になってしまうのです。

調理器具もいくつか入っています。

左の鍋はキットのオリジナルではありますが、蓋がなかったので、WAVEのHアイズから適当な大きさのものをもってきました。その上に丸モールドのパーツをつれています。中身はランプレドット(イタリア風もつ煮込み)をイメージしています。その次はフライパンで、こちらもキットのものです。エポキシパテで目玉焼きを作りました。
右側二つはキットにはないものです。パニーニがある以上、ホットサンドメーカーが必要となり、右端のものは自分で作ったものでしたが、ちょうど「ゆる△キャン」というアニメのキャラクターをキット化した製品の中にホットサンドメーカーがあるということでキットを購入、こちらにコンバートしてきました。
まだご紹介するものがいくつかありますが、長くなりましたので今日はここまで。次回はジオラマの設定のことなども含めてお話ししましょう。

キットではフランスのパン屋さん仕様となっており、当然ですが全体にフレンチテイストです。クロワッサンやバゲットのサンドなどのパーツも入っています。厨房部分はガス台、レンジ、コーヒーマシンなどもあり、ちょっとした軽食も出せるパン屋さんの屋台が開業できるわけですが、私はあれこれ考えて、これをF1のサーキットで軽食を提供しているキッチンカー風、それもイタリアのキッチンカーとしてみました。
全体の説明となりますが、キットそのものはほぼストレートに組んでいます。車体はMr.カラーの「アルミナイズドシルバー」を吹き付け、アイボリー部分はGMカラー21番、アイボリーAです。

店の名前は「ポールポジション」にしました。こういう場所の軽食ですから速さが命、ということでこういう名前にした、という設定です。イタリア語と英語でパニーニやコーヒー、飲み物を扱っている、とあります。こちらは以前もご紹介した自作デカールです。
キットのオリジナルには無いものも適宜加えています。


ショーケース内側から見て右手にはパニーニをエポキシパテで作って入れました。焼き目がついていますので作り置きしているようです。本来なら焼きたてが美味しいのですが、たくさんのお客さんをさぱくために作り置きし、温めなおしているのでしょう。実際にイタリアの鉄道駅で似たような経験をしています。クロワッサンは白をペタペタ塗りつけ、粉砂糖を撒いた感じにしました。イタリアではクロワッサンというと中にジャムが入っていたり、甘めのものが出てくることが多いので、イタリア風としました。
また、右手前にはキットには無い流しもプラ板から作りました(完成後はほとんど見えませんが)。ガス台など調理器具が揃っている中で、流しが無いというのも変だなと思い、小さな流しをつけてみました。
カウンターの木部についてはタンを塗った後でクリアーイエローを塗り重ねてニス塗りっぽい質感を出しています。
さらに、ショーケースの隣にはグラニータ(イタリアのかき氷)メーカーも置きました。

夏のイタリアに行きますと、いろいろな味のグラニータの機械が屋台などに置かれています。四角いものが多いのですが、透明プラ板を四角く切り出し、そこにシリコンを入れるのもちょっと難しそうだったので、透明の丸いプラパイプにクリアーイエローで着色したシリコンを入れ、透明パーツのランナーをランダムに切ったものを散らして氷のように見せています。正面側にはレモンのマークが入っていますのでレモン味なのでしょう(100%レモンの場合は、黄色くならずに白っぽくなります。おそらく、このグラニータは着色料を使っているのでしょう)。
厨房側です。

ガス台、レンジ、コーヒーマシンなどは塗装後に注意表示のステッカーをキャラもののコーションデータデカールから貼りました。ガス台の周囲には防炎用のついたてを追加しました。こちらはキットにはありません。カーモデル用の断熱シートを再現するのりつきアルミ箔から切り出しています。ガス台の背後が樹脂か何かではやはり火災の心配もしないといけないかな、というわけです。背後の棚などの色はGMカラー27番・レッドAです。
ガス台の下などにも荷物や機器が入っています。ガス台の下の段ボールはイタリアの炭酸水のそれですが、マソモデル1/35のものを使っています。コーヒーマシンの下の「ラバッツァ」のコーヒーのカートンも同じです。レンジの下の銀色の箱状のものはキットには無いパーツですが、冷蔵庫に見立てています。これだけの設備があって冷蔵庫が無いのも、というわけで入れたかったのです。こちらはイタレリの「TRUCK SHOP ACCESORIES」という同社のトラックのキットなどのオプションパーツとして発売されているものからとりました。このキットのパーツはこの後も出てきます。
会計はショーケースのある側で行い、商品の渡し口はリアゲートの方にあるようです。

リアゲートの板ですが、キットではただわたしてあるだけで、少々心もとない感もしましたので、板の下にアングル材を入れて、リアゲートで挟み付ける構造にしています。プラ材を貼っただけですし、ほとんど見えないところではありますが、実際に自分がこの車のオーナーだったら、という目線で作りますと、いろいろ気になってしまうのです。

調理器具もいくつか入っています。

左の鍋はキットのオリジナルではありますが、蓋がなかったので、WAVEのHアイズから適当な大きさのものをもってきました。その上に丸モールドのパーツをつれています。中身はランプレドット(イタリア風もつ煮込み)をイメージしています。その次はフライパンで、こちらもキットのものです。エポキシパテで目玉焼きを作りました。
右側二つはキットにはないものです。パニーニがある以上、ホットサンドメーカーが必要となり、右端のものは自分で作ったものでしたが、ちょうど「ゆる△キャン」というアニメのキャラクターをキット化した製品の中にホットサンドメーカーがあるということでキットを購入、こちらにコンバートしてきました。
まだご紹介するものがいくつかありますが、長くなりましたので今日はここまで。次回はジオラマの設定のことなども含めてお話ししましょう。