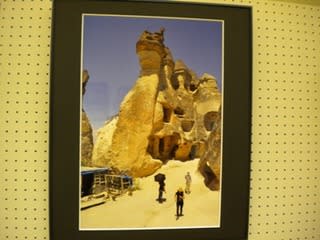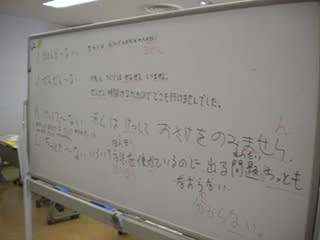「これはだれの手?」を、絵を見せてやったら、すぐ「カエル」とみんなそろって大きな声で応えてくれた。
この絵を使ったクイズは、すごく盛り上がった。
4歳になる子も参加して、「アヒル」と応えてくれた。

絵をノートに描いたりしていた子は、毎回パラグアイ人のお母さんとやって来る。
あきてきたので、ノートに「み ず き」と名前の練習をさせた。
書けるとすぐに、ぼくの所に持って見せに来た。
できると「上手だねえ」とほめるので、何度も見せに来た。
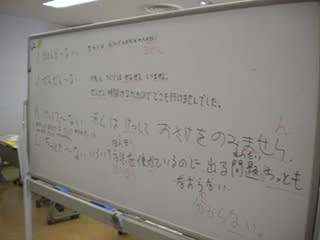
今日は、「ほとんど~ない」、「ぜんぜん~ない」、「けっして~ない」、「ちっとも~ない」の学習をした。
「わたしは、ほとんどさかなをたべません。」
「かれについてはぜんぜんしりません。」
「わたしは、あなたをけっしてわすれません。」など、自分たちの思いを自分の文として表現してくれた。
インドネシアのイスラム教の男性は、「わたしは、けっしておさけをのみません。」と書いた。
「本当かな?」と言っていた人がいた。

「ちっとも~ない」が難しいので、それだけもう一度全員に書いてもらった。
「ダイエットしたのに、ちっとも変わらない。」
「むすめのかんがえかたが、ちっともわからない。」
「にわに花のたねをまいたのに、ねがちっともでてこない。」などの文があった。
この最後の文について、他のボランティアの方から、「根」ではなく「芽」じゃないでhそうか?と言われた。
そうだよね。「ね」は土の中だからね。
そこで、「ね」を「根」、「め」を「芽」という漢字に直し、正しくは、・・・と説明した。
絵も描いて示したので、みんな納得していたみたい。
「ね」と「め」は間違いやすいですね。
でも、間違いもすごく勉強になる。
自分の文を使って勉強すると思いが入って楽しくなる。



授業が終わってから、「ぜんぜん日本語が話せません」をみんなで言う時、すごく大きな声だったね、という話をボランティアの人とした。
外国の人は、日本人に「ぜんぜんにほんごがはなせません」というと、日本人が、「ゆっくり、わかりやすく話してくれ」やさしく接してくれるのをよく知っている。処世術だね、と話していた。