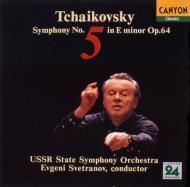
今週は、仕事も中休みって感じです。昼からは出張で出たり、金曜日はお休みをとることもできそうで、やっと仕事は一息ついた感じはしています。しかし、それも来週からはまた忙しくなりそうで、ふーっ。当然、週末は岡山にも行きます!。
つい一年ほど前になりますか、チャイコフスキーを熱心に聴いていましたが、その後も、この曲はまあ飽きもせずに聴くなあ、と思っている曲があります。これは交響曲第5番です。このブログでも過去6回も取り上げています。おそらく好きなんだろうと思います。チャイコフスキーの中では飛び抜けて好きなんですねえ。いろんな演奏があって、どれが一番いいか、というよりも、この演奏はこんなところが好きだ、といった風に色んな演奏を聴いています。
今回は、エフゲニ・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団です。スヴェトラーノフの演奏は、いったい何種類CDになっているのか、明確には知らないんですが、1993年のモスクワと1990年の東京の二種類のライブ録音があります。果たしてスタジオ録音のものはあるんでしょうか。今回は1990年6月4日サントリーホールでのライブです。全体的にテンポは速めです。特に第3楽章のワルツは、あっという間のワルツで、そっけなくあっさりと終わります。しかし、その前後がなんとまあひたすら濃厚であります。私は、特にこの曲の第2楽章が大好きなんですが、スヴェトラーノフ、じっくり聴かせてくれます。弦による序奏のあとのヴィブラートのかかったホルンの音色にに始まって、オーボエから弦へのうけつがれる曲は、なんと濃厚で、泣きの入った歌でしょうか。その後も延々と泣きが続き、クラリネット・ファゴットが登場して一層、盛り上がりを見せて、中間部クライマックスにつながり、激しい慟哭となります。しばらくしての再度の慟哭が一層激しく打ち出され、あとは余韻のように曲を閉じます。しかし、なんという濃厚な泣きでしょうか。そして、前述の第3楽章をへて、いよいよ終楽章へ、たたみ掛けるような第3楽章の終わりから、終楽章はいきなりの「運命の動機」ですが、抑え気味です。そして、次第に面目躍如の強烈な演奏が次第に見えだし、ティンパニの強打から慌ただしい諸楽器の登場から金管による「運命の動機」、少々テンポが速くなってどんどん盛り上がっていきます。そして、高らかに「運命の動機」の克服バージョンとも言えるテーマが歌われます.壮大なクライマックスへと突き進んでいきます。分厚い金管を前面に押し出しての盛り上がりは効果満点ですが、一方ではここまでやるか、と感心さえします。ここまでやられると、繰り返して聴きたくなる演奏であり、その迫力とパワーに屈服されてしまいますねえ。以前に同じ東京でのライブで交響曲第1番を取り上げたときにも触れましたが、この演奏でも重低音の充実ぶりには、やはりただものではない感銘をうけたのも事実でありました。
つい一年ほど前になりますか、チャイコフスキーを熱心に聴いていましたが、その後も、この曲はまあ飽きもせずに聴くなあ、と思っている曲があります。これは交響曲第5番です。このブログでも過去6回も取り上げています。おそらく好きなんだろうと思います。チャイコフスキーの中では飛び抜けて好きなんですねえ。いろんな演奏があって、どれが一番いいか、というよりも、この演奏はこんなところが好きだ、といった風に色んな演奏を聴いています。
今回は、エフゲニ・スヴェトラーノフ指揮ソ連国立交響楽団です。スヴェトラーノフの演奏は、いったい何種類CDになっているのか、明確には知らないんですが、1993年のモスクワと1990年の東京の二種類のライブ録音があります。果たしてスタジオ録音のものはあるんでしょうか。今回は1990年6月4日サントリーホールでのライブです。全体的にテンポは速めです。特に第3楽章のワルツは、あっという間のワルツで、そっけなくあっさりと終わります。しかし、その前後がなんとまあひたすら濃厚であります。私は、特にこの曲の第2楽章が大好きなんですが、スヴェトラーノフ、じっくり聴かせてくれます。弦による序奏のあとのヴィブラートのかかったホルンの音色にに始まって、オーボエから弦へのうけつがれる曲は、なんと濃厚で、泣きの入った歌でしょうか。その後も延々と泣きが続き、クラリネット・ファゴットが登場して一層、盛り上がりを見せて、中間部クライマックスにつながり、激しい慟哭となります。しばらくしての再度の慟哭が一層激しく打ち出され、あとは余韻のように曲を閉じます。しかし、なんという濃厚な泣きでしょうか。そして、前述の第3楽章をへて、いよいよ終楽章へ、たたみ掛けるような第3楽章の終わりから、終楽章はいきなりの「運命の動機」ですが、抑え気味です。そして、次第に面目躍如の強烈な演奏が次第に見えだし、ティンパニの強打から慌ただしい諸楽器の登場から金管による「運命の動機」、少々テンポが速くなってどんどん盛り上がっていきます。そして、高らかに「運命の動機」の克服バージョンとも言えるテーマが歌われます.壮大なクライマックスへと突き進んでいきます。分厚い金管を前面に押し出しての盛り上がりは効果満点ですが、一方ではここまでやるか、と感心さえします。ここまでやられると、繰り返して聴きたくなる演奏であり、その迫力とパワーに屈服されてしまいますねえ。以前に同じ東京でのライブで交響曲第1番を取り上げたときにも触れましたが、この演奏でも重低音の充実ぶりには、やはりただものではない感銘をうけたのも事実でありました。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます