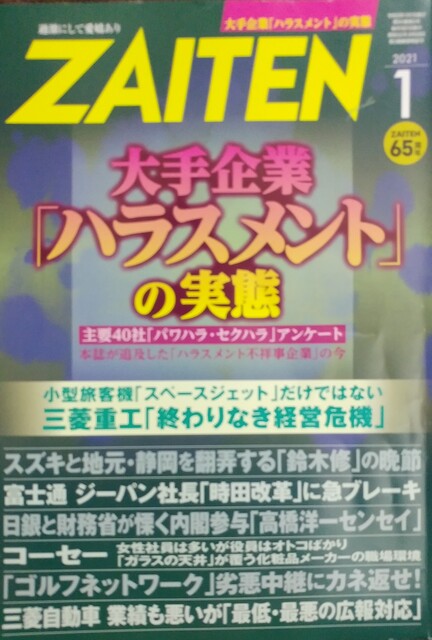内閣府政府広報室
もうすぐ勤労感謝の日。しかし、近年パワーハラスメントなど労働環境に関する問題が社会問題化しており、厚生労働省の労働局へ寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数も増加の一途をたどっています。そこで今回は、誰もが働きやすい労働環境を作っていくために知っておきたいトピックスとして「職場のパワーハラスメント」に加えて、今年4月から法定雇用率が引き上げられた「障害者雇用の促進」をテーマに取り上げます。
4人に1人が「過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある」との調査結果も
パワーハラスメントの概念と典型的な行為について知っておこう
職場における「いじめ」や「嫌がらせ」などのパワーハラスメント、いわゆる「パワハラ」は10年ほど前に登場した比較的新しい言葉にもかかわらず、今や多くの人がその言葉を認知しているなど社会問題化しています。厚生労働省の労働局に寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、平成14年度時点では約6,600件でしたが、10年後にはその7倍近い約46,000件にまで達しています。また、厚生労働省の調査結果によれば、従業員の4人に1人が「過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある」と答えており、回答内容には年齢や職種による大きな差もなかったことから、パワーハラスメントは決して上司から部下への行為に限らず、働く人の誰もが関わりうる可能性があると言えます。
では、どのような行為がパワーハラスメントに当たるのでしょうか。労使や有識者などの専門家で構成された厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が昨年3月に発表した提言によると、「職場のパワーハラスメント」は次のような概念となっています。
『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』
ポイントは次の2つです。
■職場内の優位性
上司から部下に対しての行為だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優位性を背景に行われるケースが含まれる。
■業務の適正な範囲
個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワーハラスメントに該当しない。
職場のパワーハラスメントは以下に示した6つの典型的な行為に分けられています。
---------------------------------------------------
※類型と被害の実例(性別、年齢)
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
→ 足で蹴られる(女性、50歳以上)
→ 胸ぐらを掴む、髪を引っ張る、火の着いたタバコを投げる(男性、40歳代)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
→ みんなの前で、大声で叱責。物をなげつけられる。ミスをみんなの前で、大声で言われる(女性、30歳代)
→ 人格を否定されるようなことを言われる。お前が辞めれば、改善効果が300万出るなど会議上で言われた(男性、20歳代)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
→ 挨拶をしても無視され、会話をしてくれなくなった(女性、30歳代)
→ 他の人に「私の手伝いをするな」と言われた(男性、50歳以上)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
→ 終業間際に過大な仕事を毎回押し付ける(女性、40歳代)
→ 休日出勤しても終わらない業務の強要(男性、30歳代)
(5)業務上の合理性なく、
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
→ 従業員全員に聞こえるように程度の低い仕事を名指しで命じられた。(女性、20歳代)
→ 営業なのに買い物、倉庫整理などを必要以上に強要される(男性、40歳代)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
→ 交際相手の有無について聞かれ、過度に結婚を推奨された(女性、30歳代)
→ 個人の宗教を、みんなの前で言われ、否定、悪口を言われた(女性、50歳以上)
※資料:厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」
---------------------------------------------------
上司が部下を厳しく指導することが必要な場面もありますが、(1)(2)(3)のように、暴力を振るう、相手の人格を否定するようなことを言う、無視する、ということは、「業務の適正な範囲」とは言えません。
また、(4)(5)(6)の場合は「業務上の適正な範囲」との線引きが難しいケースがあります。さらに、その行為が行われた状況や行為の継続性によっても、パワーハラスメントか否かの判断が左右される場合もあるため、各々の職場で、どこまでが「業務の適正な範囲」なのかを明確にすることが望まれます。
<パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組について、詳しく知りたい方はこちら>
URL: http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html
法定雇用率が引き上げられました
障害者とともに働く職場づくりのために
日本では「障害者の雇用の促進に関する法律」が制定されており、すべての事業主に一定の割合での障害者雇用を義務付けています。長年にわたる企業の積極的な取組などによって、働く障害者数は38万人を超えており(昨年6月1日時点)、急速に増えている障害者の雇用状況も踏まえ、今年4月1日から15年ぶりに法定雇用率(※1)が0.2%引き上げられました(※2)。これにより、雇用義務の対象となる事業主も、従来の従業員数56人以上から50人以上へと範囲が広がり、新たに制度の対象となる事業主は9千社ほど増加しています。
事業主の方に対しては、助成金も含め障害者雇用に関するさまざまな支援制度を用意しており、管轄のハローワークに相談窓口を設置しているほか、各都道府県にある地域障害者職業センターでも「障害者雇用に関する相談」や「雇用管理に関する助言」などを行なっています。
働きたい、自立したいと考えている障害者は、まだまだたくさんいます。その意欲と能力を積極的に活用していくことが、日本が目指す共生社会を実現することに繋がっていきます。
※1)法律の規定に基づき、「働いている」または「働きたい」と考えている障害者の割合を基準に、少なくとも5年ごとに見直し。
※2)民間企業は2.0%、国・地方公共団体などは2.3%、都道府県などの教育委員会は2.2%へと、それぞれ引き上げ。
<障害者とともに働く現場での取組について、詳しく知りたい方はこちら(動画 11分23秒)>
URL: http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg7267.html
もうすぐ勤労感謝の日。しかし、近年パワーハラスメントなど労働環境に関する問題が社会問題化しており、厚生労働省の労働局へ寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数も増加の一途をたどっています。そこで今回は、誰もが働きやすい労働環境を作っていくために知っておきたいトピックスとして「職場のパワーハラスメント」に加えて、今年4月から法定雇用率が引き上げられた「障害者雇用の促進」をテーマに取り上げます。
4人に1人が「過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある」との調査結果も
パワーハラスメントの概念と典型的な行為について知っておこう
職場における「いじめ」や「嫌がらせ」などのパワーハラスメント、いわゆる「パワハラ」は10年ほど前に登場した比較的新しい言葉にもかかわらず、今や多くの人がその言葉を認知しているなど社会問題化しています。厚生労働省の労働局に寄せられた「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、平成14年度時点では約6,600件でしたが、10年後にはその7倍近い約46,000件にまで達しています。また、厚生労働省の調査結果によれば、従業員の4人に1人が「過去3年間にパワーハラスメントを受けたことがある」と答えており、回答内容には年齢や職種による大きな差もなかったことから、パワーハラスメントは決して上司から部下への行為に限らず、働く人の誰もが関わりうる可能性があると言えます。
では、どのような行為がパワーハラスメントに当たるのでしょうか。労使や有識者などの専門家で構成された厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が昨年3月に発表した提言によると、「職場のパワーハラスメント」は次のような概念となっています。
『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』
ポイントは次の2つです。
■職場内の優位性
上司から部下に対しての行為だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるなどの様々な職務上の地位や人間関係の優位性を背景に行われるケースが含まれる。
■業務の適正な範囲
個人の受け止め方によって不満に感じる指示や注意・指導があっても「業務の適正な範囲」内であればパワーハラスメントに該当しない。
職場のパワーハラスメントは以下に示した6つの典型的な行為に分けられています。
---------------------------------------------------
※類型と被害の実例(性別、年齢)
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
→ 足で蹴られる(女性、50歳以上)
→ 胸ぐらを掴む、髪を引っ張る、火の着いたタバコを投げる(男性、40歳代)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
→ みんなの前で、大声で叱責。物をなげつけられる。ミスをみんなの前で、大声で言われる(女性、30歳代)
→ 人格を否定されるようなことを言われる。お前が辞めれば、改善効果が300万出るなど会議上で言われた(男性、20歳代)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
→ 挨拶をしても無視され、会話をしてくれなくなった(女性、30歳代)
→ 他の人に「私の手伝いをするな」と言われた(男性、50歳以上)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
→ 終業間際に過大な仕事を毎回押し付ける(女性、40歳代)
→ 休日出勤しても終わらない業務の強要(男性、30歳代)
(5)業務上の合理性なく、
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
→ 従業員全員に聞こえるように程度の低い仕事を名指しで命じられた。(女性、20歳代)
→ 営業なのに買い物、倉庫整理などを必要以上に強要される(男性、40歳代)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
→ 交際相手の有無について聞かれ、過度に結婚を推奨された(女性、30歳代)
→ 個人の宗教を、みんなの前で言われ、否定、悪口を言われた(女性、50歳以上)
※資料:厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」
---------------------------------------------------
上司が部下を厳しく指導することが必要な場面もありますが、(1)(2)(3)のように、暴力を振るう、相手の人格を否定するようなことを言う、無視する、ということは、「業務の適正な範囲」とは言えません。
また、(4)(5)(6)の場合は「業務上の適正な範囲」との線引きが難しいケースがあります。さらに、その行為が行われた状況や行為の継続性によっても、パワーハラスメントか否かの判断が左右される場合もあるため、各々の職場で、どこまでが「業務の適正な範囲」なのかを明確にすることが望まれます。
<パワーハラスメントの予防・解決に向けた取組について、詳しく知りたい方はこちら>
URL: http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201304/1.html
法定雇用率が引き上げられました
障害者とともに働く職場づくりのために
日本では「障害者の雇用の促進に関する法律」が制定されており、すべての事業主に一定の割合での障害者雇用を義務付けています。長年にわたる企業の積極的な取組などによって、働く障害者数は38万人を超えており(昨年6月1日時点)、急速に増えている障害者の雇用状況も踏まえ、今年4月1日から15年ぶりに法定雇用率(※1)が0.2%引き上げられました(※2)。これにより、雇用義務の対象となる事業主も、従来の従業員数56人以上から50人以上へと範囲が広がり、新たに制度の対象となる事業主は9千社ほど増加しています。
事業主の方に対しては、助成金も含め障害者雇用に関するさまざまな支援制度を用意しており、管轄のハローワークに相談窓口を設置しているほか、各都道府県にある地域障害者職業センターでも「障害者雇用に関する相談」や「雇用管理に関する助言」などを行なっています。
働きたい、自立したいと考えている障害者は、まだまだたくさんいます。その意欲と能力を積極的に活用していくことが、日本が目指す共生社会を実現することに繋がっていきます。
※1)法律の規定に基づき、「働いている」または「働きたい」と考えている障害者の割合を基準に、少なくとも5年ごとに見直し。
※2)民間企業は2.0%、国・地方公共団体などは2.3%、都道府県などの教育委員会は2.2%へと、それぞれ引き上げ。
<障害者とともに働く現場での取組について、詳しく知りたい方はこちら(動画 11分23秒)>
URL: http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg7267.html