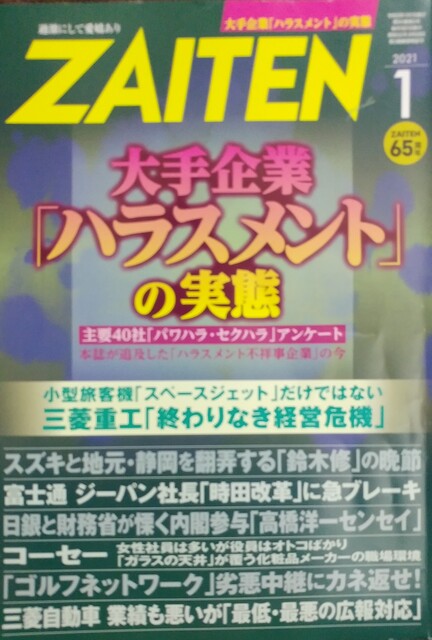何はなくとも「労働三法」
最低限、ぼんやりとでも頭に入れておきたいのは、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法です。
これらの法律は「労働三法」と呼ばれ、日本の労働法の基本となっています。
学習マンガで十分です。斜め読みして、いつでも手に取れるところに置いておきましょう。スマホやタブレットの中の電子書籍でも。
雇われて働く人なら、誰にでも必ず関係するのは、労働基準法です。
「勤務時間は、どの時点からどの時点をカウントするの?」「残業は何時から何時まで?」「有給はどういう時に取れるの?」、および現場仕事では時に大きな気がかりとなる「勤務時間中にトイレ行っていいの?」といった身近で切実な問題のほとんどすべてに対して、基本的な考え方は労働基準法に示されています(具体的には、各社に定められた就業規則)。
忘れてはいけないのは、労働組合法・労働関係調整法です。
就職する会社に労働組合がなくても、正規雇用でなくても、大いに関係あります。
会社に労働組合がなくても、貴方は労働組合法に関係あります
労働組合法は、労働者が連帯して組合を作る権利に関する法律です。労働関係調整法は、経営者と組合の関係調整の具体的あれこれに関する法律です。
経営者(雇用主)は、法的にはほとんど守られていない存在です。一方で、雇われて働く人は、法的に、まあまあ手厚く守られています。
この”不公平”の理由は、経営者が「雇用して仕事してもらって給料を払う」という形で、雇われて働く人の首根っこを押さえているからです。雇って給料を払っているからといって、したい放題されては困りますからね。
だから戦後、労働に関する法律が整備されたとき、労働組合に関する法律も同時に整備されました。
とはいえ、企業内の労働組合の力は、高度成長期以後、弱まっていくばかりです。70年台までは、経営陣を社屋内にカンヅメにして食事も摂らせないような強引な交渉を行う労働組合もありました。ホントです。
冨田勲さんのアルバム「展覧会の絵」には、経営陣と思われる人の哀れな懇願を一蹴する集団が描かれています。ムソルグスキーの原曲とは正反対のシンセサイザー演奏が当時(1970年代)大ウケしたのは、当時の「あるある!」だったからです。話がそれました。戻します。
今、労働組合にそこまでの力はありません。「こんど就職する会社は小さな会社で労働組合ないし」「自分は非正規雇用で組合員になれないし」という方もおられることでしょう。
そんな貴方のために、「独立系労組」「独立系ユニオン」があります。多くは勤務先や雇用形態を問わず、特定の企業や組織と独立した労働組合です。
独立系労組(ユニオン)が有効な活動を行える根拠は、労働組合法であり、労働関係調整法です。
というわけで、勤務先に組合があろうがなかろうが、貴方と労働組合法には関係があります。
いざ何か起こったときには、労働関係調整法も関係あります。「関係ない」と思わず、頭の片隅に入れておきましょう。
なお、もともと官公庁の一部だった組織を中心に、非正規雇用でも組合員になれる労働組合もあります。
そういう組合があるようなら、とりあえず加入しておきましょう。組合員費は若干イタいでしょうけれども。
どの程度、非正規雇用の問題に本気で取り組むかは、組合によって温度差があります。
でも、「ある」「加入している」と「ない」「加入してない」は、大変な違いです。
もちろん、「正規雇用で会社に労組があって入れる」というのなら、入っておくべきです。
さらに、会社がユニオン・ショップ制(組合員しか雇用しない)を採用しており、労働組合が一つだけ、しかしその組合はいわゆる「御用組合」、会社や上司との間に問題があったときに一社員を守ることはない……という場合もあります。この場合は、独立系労組(ユニオン)が有効です。
そういう企業では、「ウチはユニオン・ショップだから、独立系労組に相談したらクビ」というウソが喧伝されることもありますが、そんなことはありません。
労働法規の解説書・学習マンガの選び方
こだわるべきところを、優先順位の高い順に並べてみます。
1 新しさ。せめて1年以内に、新規出版または改訂されていること。
古本では、細かな法や通知の変更に対応できません。
2 著者または監修者が、雇われて働く立場での労働問題で定評ある人であること。
書籍のネット通販サイトのレビューではなく、著者名・監修者名をネット検索して、トップ20くらいまでの検索結果は確認しましょう。「労働法の専門家」といっても、いろいろです。世の中には、気に入らない社員を後腐れなく辞めさせる方法の専門家もいれば、パワハラを泣き寝入りさせる方法の専門家もいます。
3 新刊でなく改訂版の場合は、初版からの重版回数が3回を超えていること。
重版されて読まれ続けているかどうかは、ある程度、内容に信頼がおけるかどうかの指標になります。もちろん「新刊だからダメ」ということはありません。読んでみて、著者・監修者もチェックして「大丈夫そう」と思えるかどうかで判断を。
原理原則ではなく個別の問題、貴方自身に何か起こる可能性や対策については、最新の情報でないと役に立たないのです。
この記事を3年後に読まれる方が、古い情報を手にして「あれ?」と戸惑うことは避けたいので、ここに具体的な書籍名は挙げません。
数多くの労働法規、どれが関係ある?
この他にも、雇用形態や職種によって、数多くの労働法規が関係してきます。
たとえば、派遣労働だったら「労働者派遣法」が関係します。
「派遣なら派遣法」は明快ですけれども、自分にどの法律の何が関係あるのか判断に迷う場面もあるでしょう。
そんな時、どうすればよいでしょう?
答えは簡単。他人の頭脳に力を貸してもらえばいいんです。
専門家の力を借りよう
労働法規は身を守るための最低限の防具ですが、知っているだけでは、まず使えません。
物事によらず、「知っている」と「使える」の間には、高くて深い溝があるものです。
特に、労働法規の「知っている」と「使える」の間には、常人には絶対に超えられないほどの溝があります。
「よく分からないな」と思ったら、専門家の力を借りましょう。
恥ずかしいことではありません。もともと労働法規は、常人に扱える代物ではないんですから。
ふだんから労働相談の活用を
労働法規・労働問題の専門家の知恵を借りる機会は、至るところにあります。
無料電話ホットラインもあります。団体や公的機関が開設している相談窓口もあります。各地の「法テラス」もあります。
ふだんから、ちょっとしたことで、そういったところに相談をして知恵を借りることを習慣にしておくとよいと思います。
本当に”ちょっとした”こと
「給与明細のこの部分が意味しているのは何でしょうか?」
「上司・同僚との人間関係で、ちょっと悩ましいんですが」
といったことを相談していいんです。人間関係の悩みも、まずは労働相談へ。ゆめゆめ、「癒し」を求めてカルト宗教にのめり込みませんように。
どんな相談でも、働くことに関係していれば、それなりの知恵は借りられるはず。
もしかすると、貴方自身が「良くあることだ、大したことない」「もっと頑張らなきゃ」「このくらいガマンしなきゃ」と思っていることが、とんでもない労働問題かもしれません。大きな問題に巻き込まれていればいるほど、渦中の本人は気づきにくいものです。
似たような立場のお友達に愚痴るのも、あるいは何らかのストレス発散で解消した気になるのも悪くありません。
でも、それらに加えて、ぜひ、専門家の知恵を借りましょう。
さて、労働問題の相談窓口を提供している団体をネット検索すると、しばしば、左翼的政党との関係を噂されているのが判明します。そういった噂は、事実であることも、事実でないこともあります。
でも、そんなこと、どうでもいいじゃないですか? 貴方のお役に立てば。
少なくとも労働法規は、相談に応じる人の政治的立場によって歪められるものではありません。気になるなら、同じ問題を2ヶ所・3ヶ所に相談してみればいいんです。
極端に違う回答があったら「なんかヘンだ」と考えるべき場面ですが、似たような問題・似たような背景なら、たいていは似たような回答が得られることと思われます。
具体的な相談窓口を、少しだけ
労働相談・生活相談一般
Yahoo!ニュースのオーサーでもある今野晴貴さんが代表を務めておられる
NPO法人 POSSE
は、特に若い方にとって、非常に良い相談窓口です。
ネットには、さまざまな噂がありますけれども、気にする必要はありません。
出身大学
出身大学は、大学側にやる気と体制があれば、相談先として良い選択肢です。
せっかくの就職実績と卒業生が「すぐに退職させられてフリーター」「すぐにパワハラで精神を病んで再起不能に」は、大学としても望ましくない事態です。
卒業生が社会で活躍して在学生を牽引したり何らかのモデルになったりすることは、大学にとって極めて重要なことでもあります。
飛び抜けた一握りの卒業生だけが活躍していればいい、というわけではありません。普通の学生にも、おとなしめの学生にも、なんとか卒業だけはできそうな学生にも、それぞれの活躍が必要です。
この観点から、卒業生のさまざまな相談に乗る大学、卒業後早期に離職した卒業生の再就職支援をする大学も増えてきています。
なお、短大・専門学校・高校には、「そこまでは期待できない」というのが正直なところです。小規模すぎるからです。
在学生の人数が「万人」単位になる総合大学なら出来るけれども小規模な教育機関には無理、という事柄は多いです。
でも、規模が小さすぎて組織としての対応ができない教育機関にも、卒業生のその後を気にかけている教職員はいます。
何かあったら、ためらわずに相談してみましょう。
「ウチでは無理だけど」と、頼りになる大人や団体を紹介してくれるかもしれません。
「セーフティネット」の構造を知っておこう
個人的に相談に乗ってもらっても解決しない問題があっても、とりあえずの安全網=「セーフティネット」 があれば、生きていけます。
社会保障や社会福祉で「最後のセーフティネット」という言葉が出てくる時、たいていは生活保護のことを指しています。
生活保護は、そのセーフティネットから漏れたら生きていけない人を救う制度だから、「最後のセーフティネット」なのです。
でも、最後の1歩前や2歩前にも、セーフティネットは存在します。
日本のセーフティネットは、概ね
雇用
公的保険(失業給付、健康保険、年金保険)
公的扶助(生活困窮者自立支援制度、生活保護制度)
の3層構造です。
日本の大きな問題は、雇用からこぼれ落ちやすい上、雇用からこぼれ落ちた人を公的保険が受け止めきれず、簡単に ・・・・続きはこちら
最低限、ぼんやりとでも頭に入れておきたいのは、労働基準法・労働組合法・労働関係調整法です。
これらの法律は「労働三法」と呼ばれ、日本の労働法の基本となっています。
学習マンガで十分です。斜め読みして、いつでも手に取れるところに置いておきましょう。スマホやタブレットの中の電子書籍でも。
雇われて働く人なら、誰にでも必ず関係するのは、労働基準法です。
「勤務時間は、どの時点からどの時点をカウントするの?」「残業は何時から何時まで?」「有給はどういう時に取れるの?」、および現場仕事では時に大きな気がかりとなる「勤務時間中にトイレ行っていいの?」といった身近で切実な問題のほとんどすべてに対して、基本的な考え方は労働基準法に示されています(具体的には、各社に定められた就業規則)。
忘れてはいけないのは、労働組合法・労働関係調整法です。
就職する会社に労働組合がなくても、正規雇用でなくても、大いに関係あります。
会社に労働組合がなくても、貴方は労働組合法に関係あります
労働組合法は、労働者が連帯して組合を作る権利に関する法律です。労働関係調整法は、経営者と組合の関係調整の具体的あれこれに関する法律です。
経営者(雇用主)は、法的にはほとんど守られていない存在です。一方で、雇われて働く人は、法的に、まあまあ手厚く守られています。
この”不公平”の理由は、経営者が「雇用して仕事してもらって給料を払う」という形で、雇われて働く人の首根っこを押さえているからです。雇って給料を払っているからといって、したい放題されては困りますからね。
だから戦後、労働に関する法律が整備されたとき、労働組合に関する法律も同時に整備されました。
とはいえ、企業内の労働組合の力は、高度成長期以後、弱まっていくばかりです。70年台までは、経営陣を社屋内にカンヅメにして食事も摂らせないような強引な交渉を行う労働組合もありました。ホントです。
冨田勲さんのアルバム「展覧会の絵」には、経営陣と思われる人の哀れな懇願を一蹴する集団が描かれています。ムソルグスキーの原曲とは正反対のシンセサイザー演奏が当時(1970年代)大ウケしたのは、当時の「あるある!」だったからです。話がそれました。戻します。
今、労働組合にそこまでの力はありません。「こんど就職する会社は小さな会社で労働組合ないし」「自分は非正規雇用で組合員になれないし」という方もおられることでしょう。
そんな貴方のために、「独立系労組」「独立系ユニオン」があります。多くは勤務先や雇用形態を問わず、特定の企業や組織と独立した労働組合です。
独立系労組(ユニオン)が有効な活動を行える根拠は、労働組合法であり、労働関係調整法です。
というわけで、勤務先に組合があろうがなかろうが、貴方と労働組合法には関係があります。
いざ何か起こったときには、労働関係調整法も関係あります。「関係ない」と思わず、頭の片隅に入れておきましょう。
なお、もともと官公庁の一部だった組織を中心に、非正規雇用でも組合員になれる労働組合もあります。
そういう組合があるようなら、とりあえず加入しておきましょう。組合員費は若干イタいでしょうけれども。
どの程度、非正規雇用の問題に本気で取り組むかは、組合によって温度差があります。
でも、「ある」「加入している」と「ない」「加入してない」は、大変な違いです。
もちろん、「正規雇用で会社に労組があって入れる」というのなら、入っておくべきです。
さらに、会社がユニオン・ショップ制(組合員しか雇用しない)を採用しており、労働組合が一つだけ、しかしその組合はいわゆる「御用組合」、会社や上司との間に問題があったときに一社員を守ることはない……という場合もあります。この場合は、独立系労組(ユニオン)が有効です。
そういう企業では、「ウチはユニオン・ショップだから、独立系労組に相談したらクビ」というウソが喧伝されることもありますが、そんなことはありません。
労働法規の解説書・学習マンガの選び方
こだわるべきところを、優先順位の高い順に並べてみます。
1 新しさ。せめて1年以内に、新規出版または改訂されていること。
古本では、細かな法や通知の変更に対応できません。
2 著者または監修者が、雇われて働く立場での労働問題で定評ある人であること。
書籍のネット通販サイトのレビューではなく、著者名・監修者名をネット検索して、トップ20くらいまでの検索結果は確認しましょう。「労働法の専門家」といっても、いろいろです。世の中には、気に入らない社員を後腐れなく辞めさせる方法の専門家もいれば、パワハラを泣き寝入りさせる方法の専門家もいます。
3 新刊でなく改訂版の場合は、初版からの重版回数が3回を超えていること。
重版されて読まれ続けているかどうかは、ある程度、内容に信頼がおけるかどうかの指標になります。もちろん「新刊だからダメ」ということはありません。読んでみて、著者・監修者もチェックして「大丈夫そう」と思えるかどうかで判断を。
原理原則ではなく個別の問題、貴方自身に何か起こる可能性や対策については、最新の情報でないと役に立たないのです。
この記事を3年後に読まれる方が、古い情報を手にして「あれ?」と戸惑うことは避けたいので、ここに具体的な書籍名は挙げません。
数多くの労働法規、どれが関係ある?
この他にも、雇用形態や職種によって、数多くの労働法規が関係してきます。
たとえば、派遣労働だったら「労働者派遣法」が関係します。
「派遣なら派遣法」は明快ですけれども、自分にどの法律の何が関係あるのか判断に迷う場面もあるでしょう。
そんな時、どうすればよいでしょう?
答えは簡単。他人の頭脳に力を貸してもらえばいいんです。
専門家の力を借りよう
労働法規は身を守るための最低限の防具ですが、知っているだけでは、まず使えません。
物事によらず、「知っている」と「使える」の間には、高くて深い溝があるものです。
特に、労働法規の「知っている」と「使える」の間には、常人には絶対に超えられないほどの溝があります。
「よく分からないな」と思ったら、専門家の力を借りましょう。
恥ずかしいことではありません。もともと労働法規は、常人に扱える代物ではないんですから。
ふだんから労働相談の活用を
労働法規・労働問題の専門家の知恵を借りる機会は、至るところにあります。
無料電話ホットラインもあります。団体や公的機関が開設している相談窓口もあります。各地の「法テラス」もあります。
ふだんから、ちょっとしたことで、そういったところに相談をして知恵を借りることを習慣にしておくとよいと思います。
本当に”ちょっとした”こと
「給与明細のこの部分が意味しているのは何でしょうか?」
「上司・同僚との人間関係で、ちょっと悩ましいんですが」
といったことを相談していいんです。人間関係の悩みも、まずは労働相談へ。ゆめゆめ、「癒し」を求めてカルト宗教にのめり込みませんように。
どんな相談でも、働くことに関係していれば、それなりの知恵は借りられるはず。
もしかすると、貴方自身が「良くあることだ、大したことない」「もっと頑張らなきゃ」「このくらいガマンしなきゃ」と思っていることが、とんでもない労働問題かもしれません。大きな問題に巻き込まれていればいるほど、渦中の本人は気づきにくいものです。
似たような立場のお友達に愚痴るのも、あるいは何らかのストレス発散で解消した気になるのも悪くありません。
でも、それらに加えて、ぜひ、専門家の知恵を借りましょう。
さて、労働問題の相談窓口を提供している団体をネット検索すると、しばしば、左翼的政党との関係を噂されているのが判明します。そういった噂は、事実であることも、事実でないこともあります。
でも、そんなこと、どうでもいいじゃないですか? 貴方のお役に立てば。
少なくとも労働法規は、相談に応じる人の政治的立場によって歪められるものではありません。気になるなら、同じ問題を2ヶ所・3ヶ所に相談してみればいいんです。
極端に違う回答があったら「なんかヘンだ」と考えるべき場面ですが、似たような問題・似たような背景なら、たいていは似たような回答が得られることと思われます。
具体的な相談窓口を、少しだけ
労働相談・生活相談一般
Yahoo!ニュースのオーサーでもある今野晴貴さんが代表を務めておられる
NPO法人 POSSE
は、特に若い方にとって、非常に良い相談窓口です。
ネットには、さまざまな噂がありますけれども、気にする必要はありません。
出身大学
出身大学は、大学側にやる気と体制があれば、相談先として良い選択肢です。
せっかくの就職実績と卒業生が「すぐに退職させられてフリーター」「すぐにパワハラで精神を病んで再起不能に」は、大学としても望ましくない事態です。
卒業生が社会で活躍して在学生を牽引したり何らかのモデルになったりすることは、大学にとって極めて重要なことでもあります。
飛び抜けた一握りの卒業生だけが活躍していればいい、というわけではありません。普通の学生にも、おとなしめの学生にも、なんとか卒業だけはできそうな学生にも、それぞれの活躍が必要です。
この観点から、卒業生のさまざまな相談に乗る大学、卒業後早期に離職した卒業生の再就職支援をする大学も増えてきています。
なお、短大・専門学校・高校には、「そこまでは期待できない」というのが正直なところです。小規模すぎるからです。
在学生の人数が「万人」単位になる総合大学なら出来るけれども小規模な教育機関には無理、という事柄は多いです。
でも、規模が小さすぎて組織としての対応ができない教育機関にも、卒業生のその後を気にかけている教職員はいます。
何かあったら、ためらわずに相談してみましょう。
「ウチでは無理だけど」と、頼りになる大人や団体を紹介してくれるかもしれません。
「セーフティネット」の構造を知っておこう
個人的に相談に乗ってもらっても解決しない問題があっても、とりあえずの安全網=「セーフティネット」 があれば、生きていけます。
社会保障や社会福祉で「最後のセーフティネット」という言葉が出てくる時、たいていは生活保護のことを指しています。
生活保護は、そのセーフティネットから漏れたら生きていけない人を救う制度だから、「最後のセーフティネット」なのです。
でも、最後の1歩前や2歩前にも、セーフティネットは存在します。
日本のセーフティネットは、概ね
雇用
公的保険(失業給付、健康保険、年金保険)
公的扶助(生活困窮者自立支援制度、生活保護制度)
の3層構造です。
日本の大きな問題は、雇用からこぼれ落ちやすい上、雇用からこぼれ落ちた人を公的保険が受け止めきれず、簡単に ・・・・続きはこちら