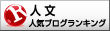宮脇 俊三(みやわき しゅんぞう、1926年12月9日 - 2003年2月26日)は、日本の編集者、紀行作家。元中央公論社常務取締役。鉄道での旅を中心とした作品を数多く発表した。父は陸軍大佐で、後に衆議院議員となった宮脇長吉。娘に作家の宮脇灯子。
人物
地理や歴史の深い教養に裏打ちされた簡潔かつ格調高い文章、軽妙なユーモアにあふれた文章を書くことで知られる。また熱心な鉄道ファンでありながら、一部のマニアに見られる特有の嫌味さ(専門用語や車両の形式名を自慢気に羅列したり、評論家ぶったりするなど)がほとんど無い飄々とした文体は多くの人々に受け入れられ、鉄道ファン以外にも多くのファンが存在する。
処女作『時刻表2万キロ』で、「鉄道に乗る」ということを趣味として確立させ、第2作の『最長片道切符の旅』では「最長片道切符」を世に知らしめることとなった。これらの作品によって「鉄道紀行」を文学の一ジャンルにまでした、と評されることもある(しかし、「鉄道紀行文学」で宮脇並みのレベルの作品を生んでいる人物はその後誰もいない、とも言われている)。
さらに晩年に刊行した『鉄道廃線跡を歩く』シリーズ(全10巻、1995年 - 2003年、JTB)では、これまでほとんど注目されていなかった鉄道趣味に「廃線跡探訪」という新たな1ページを築くなど、鉄道趣味の歴史において大きな役割を果たした事でも知られる。
年譜
1926年(大正15年)12月9日 埼玉県川越市で7人兄弟の末子(三男)として生まれる。宮脇家の男子の名は、「英雄俊傑」に「一二三四」を順に組み合わせた名前であった(長男英一、次男雄二は若くして病死。俊三が最後の子であり、「傑四」は誕生しなかった)。
宮脇家は元々香川県が本籍であり、父長吉も香川県から代議士に選出されている。俊三は幼い頃からの鉄道好きで、父が選挙区入りする際の一行の切符の手配なども、全て俊三少年が行っていたという。俊三の鉄道好きは戦中でも変わることがなく、1942年(昭和17年)に開通した関門トンネルを通ってみたいが故に、戦時下にも関わらず列車に乗って旅行に行ったほどである。
父長吉の陸軍予備役編入と共に、埼玉県川越町(現・川越市)から東京市渋谷町(現・東京都渋谷区)にあった皇族の梨本宮邸付近に一家で移住する。子供時代の遊び場は、梨本宮邸の裏に当たる山手線の線路沿いにあった空き地と、東京市電(現・東京都電)青山車庫だった。
旧制青山師範附属小学校、旧制成蹊高等学校卒業後の1945年、東京帝国大学理学部地質学科に入学。同年8月15日、米坂線今泉駅前で玉音放送を聞き敗戦を知る。戦後の混乱期に大学に戻ったものの、地質学科での現地調査で「ブヨ」に悩まされたこと、本来地図や時刻表が好きだったこと、ちょうどその頃文学の方面に興味が移っていたこと、などの理由から転部しようと決意。ところが当時は理科から文科へ転科できなかったので、東大の文学部西洋史学科を再受験し合格した。青年期の彼を知るには『私の途中下車人生』(話し手:宮脇俊三。講談社 1986年10月9日刊 なお同書は文庫化されていない)が最も詳しい。
1951年(昭和26年) 東京大学文学部西洋史学科卒業(途中で理学部から文学部へ転部)。中央公論社(現在の中央公論新社)に入社。以後編集者として活躍し、『中央公論』編集長、『婦人公論』編集長、開発室長、編集局長、常務取締役などを歴任。「世界の歴史」シリーズ、「日本の歴史」シリーズ、「中公新書」など出版史に残る企画にたずさわり、名編集者と謳われる。作家北杜夫を世に出したのも功績の一つである。
「世界の歴史」シリーズでは専門的過ぎて分かりづらい学者の文章は衝き返して再度執筆させた。東洋史学者宮崎市定に『科挙』『大唐帝国』執筆を依頼し、一般読書人に宮崎の名を知らしめてもいる。宮崎は名文で知られており、世界の歴史シリーズでも間然するところの無い文章を執筆したため、宮脇も衝き返さず、そのままとした。
1977年(昭和52年)5月28日 国鉄足尾線を最後に国鉄全線を完乗。
1978年(昭和53年)6月30日 常務取締役編集局長を最後に中央公論社を退社。
1978年(昭和53年)7月10日 国鉄全線完乗の旅をつづった『時刻表2万キロ』で作家デビュー。
1978年(昭和53年)12月12日 『時刻表2万キロ』で第5回日本ノンフィクション賞受賞。
1981年(昭和56年) 『時刻表昭和史』で第6回交通図書賞受賞。
1985年(昭和60年) 短編小説集『殺意の風景』で第13回泉鏡花文学賞受賞。この『殺意の風景』は同年上半期の直木賞候補にもなっている。このうち、第12話「石油コンビナートの巻」がのちに火曜サスペンス劇場「弁護士・高林鮎子 寝台特急あさかぜ4号殺人風景」」(1986年。主演、眞野あずさ)として、また第14話「砂丘の巻」がテレビ東京系月曜女のサスペンス傑作推理受賞作シリーズ「殺意の風景・砂色の迷宮」(1989年。主演、石野真子)としてドラマ化された。
1992年(平成4年) 『韓国・サハリン鉄道紀行』でJTB第1回紀行文学大賞受賞。
1999年(平成11年) 第47回菊池寛賞受賞。気力・体力に限界を感じ、休筆を宣言。この頃、家族には「宮脇俊三も、もう終わりだな」と漏らしていたという。
2003年(平成15年)2月26日 東京都内の病院で没する。享年76。戒名「鉄道院周遊俊妙居士」。
死去の報道は葬儀が済む3月になるまで差し控えられた。宮脇の死が発表されると世田谷区の自宅に多くのファンが詰め掛け、自宅周辺はちょっとした混乱状態になった。晩年は執筆の依頼はすべて断っていた。雑誌「高原文庫」から依頼された親友の北杜夫に関するエッセイだけは例外として引き受けたが、既に病床にあった宮脇は完成させることができず、それが遺稿となった。
エピソード
公私共に縁の深い北杜夫の『マンボウ交遊録』によれば、編集者時代の宮脇は本にした時の見栄えまで考え、改ページや字数を考慮した上で北に文章を直すよう求めたという。自分が作家になってからも文章を読めば分かるように、創作に関しては非常にストイックな姿勢を貫いていた。しかし素の宮脇本人は大酒豪で、しかも変わった冗談や言動の多い人物だったという(これは同じく北と親交の深かった星新一と共通する点である)。なお北が1966年に刊行したエッセイ集『どくとるマンボウ途中下車』の中に、「鉄道ファンの編集者に開通直後の東海道新幹線に乗ろうと誘われて付き合った」という趣旨のものがあるが、この編集者はもちろん宮脇のこと。このように宮脇は現役時、公私ともに「中公に宮脇あり」(宮脇灯子『父・宮脇俊三への旅』)として知られていた。
娘の宮脇灯子『父・宮脇俊三への旅』には、59歳の時に真夜中にファミコンの「スーパーマリオブラザーズ2」に熱中するなど、家族にしか見せなかった俊三の一面が描かれている。なお、灯子によれば俊三は子供の教育には一切口を出さなかったという。
宮脇は生涯渋谷育ちを自認し、編集者には著者紹介欄に「川越で生まれ、渋谷で育つ」という一文挿入を希望した。
小学生の頃(1933~5年ごろ)、渋谷駅に佇む生前の忠犬ハチ公の姿を見ており、『時刻表昭和史』や『昭和八年 澁谷驛』にもそのことが触れられている。この話は林順信の「玉電が走った街 今昔」での対談にも出ている。
一番遠くへ来たと感じたのは、小2の時に母と熱海へ行った時だとされた。
青年期の思い出で一番印象に残っていることは米坂線今泉駅で父と玉音放送を聴いたときで、旅行では昭和19年3月に関門トンネルへ向かった時であったとしている。
鉄道の次に好きな乗り物は路線バスであり、飛行機はその逆で乗るたびに早く着陸して欲しいという気になったという。ちなみに存命中に開通していたJRの路線のうち、乗らずに終わった唯一の路線が宮崎空港線だった。
お気に入りの路線は宗谷本線・根室本線・山陰本線で、車窓は利尻島が見える宗谷本線の抜海駅付近や余部橋梁であった。
旅情を感じる駅名として、音威子府駅・信濃追分駅・姨捨駅などを挙げていた。また観光客誘致などを目的とした安易な駅名改名を嘆いていた(沓掛駅、坊中駅など)。
思い入れがある自筆作品はデビュー作の『時刻表2万キロ』と『時刻表昭和史』であった。
時刻表以外でよく読んだ鉄道雑誌は、「鉄道ジャーナル」・「鉄道ダイヤ情報」だったとされる。
一番印象に残っている食べ物は、昭和17年に北海道へ向かった時に列車の食堂車で食べた鮭フライであった。駅弁では小淵沢駅の「元気甲斐」、駅そばでは音威子府駅のものだという。
自動車の運転免許は昭和29年に収得したが、後に更新をしなくて失効した。
女優では原節子、噺家では志ん生が好みであった。
プロ野球はヤクルト(旧、国鉄)スワローズ、力士では神風が好みであった。
東大文学部西洋史学科の後輩にあたる有名人には、歌手の加藤登紀子がいる。
かつての特技はテニスと駅名暗唱で、前者は旧制高等学校中等部の大会で優勝した事があり、後者では東海道本線の全駅名を小学生の時に48秒で言った事があった。
大のモーツァルト好きであった。東大の卒業論文は「モーツァルトよりみた十八世紀の音楽家の社会的地位」であったし、「年刊モーツァルト」という同人誌も編集・発行するほどだった。また、バッハの曲も「神に近い」として好んでいた。
鉄道の車両にあまり興味がなく、文体に嫌味がなく、論戦を好まなかったことから、鉄道ファンの間では「神様」のように親しまれている。一方で当の本人は前述の通り酒好きであり、酒にまつわるトラブルも多い。
酒の勢いで、青函連絡船の寝台船室に乗り合わせた学生に絡んだことがある。
「いい店の探し方」と称してスナックの扉を少し開けて覗いて回ったことがある。
どんなに忙しくても、作家などとの飲み会に出る時間は確保していた。
隣の北杜夫の家で飲んだときに、一緒に自宅の庭に空き缶を放り込んでいた。北家には常にボトルキープがしてあった。
原稿の推敲を徹底して行うときには酒が欠かせなかった。ただし仕事がはかどった訳ではない。
晩年、医者に酒を止められてからも、内緒で紹興酒を購入しては「度数が低いから」と言って飲んでいた。
末期、入院中に見舞いに来た家族に「酒を持って来い」と当り散らしていた。結核の後遺症で片側だけだった肺に転移して「もう助からない」と悟った夫人は、帰宅したときに医者に内緒で酒を与えた。
博学で鉄道だけではなく日本史などにも詳しく著書には鉄道以外の本もある。日本通史の旅は彼のライフワークとなった。
知識があっても知らないふりをして書いている、とされることもある。よって前述の「鉄道の車両にあまり興味がない」というのもはたして事実か、韜晦なのか定かではない。
国内では一人で旅行することを好み、同行者がいると気を使うからよくないとも書いている。ただし例外は沢山ある。特に旅行中でも夜に飲む時は相手が欲しくなるとしている。
車中の男子学生についてはその行動の粗暴さを文中で語り、女子学生については美点を語ることが多い。秋田を旅したときには女子学生の美人度の高さをメモし、「江戸時代の人買いの気分になった」などと書いている。
元重役らしく、タクシーを割と長い距離にわたって駆使するときもある。ただし計画の穴埋めをしようとして失敗することもあった。
国内だけでなく海外の鉄道にも相当乗りに行っている。
ただし前述のように飛行機嫌いのため、飛行機に乗るとすぐに睡眠薬を飲んで寝てしまう。
フィリピン旅行でポン引きをなだめすかして列車に乗りまわったことがある。最後に、乗った席に石を投げ込まれて、怪我をした。
インド旅行では水あたりによる下痢をこらえて列車を乗りまわった。
時刻表好きで国鉄の複雑なダイヤを愛好し、私鉄は国鉄に比べてダイヤが複雑ではないためあまり食指が動かないと言っていた。
巧みな乗り継ぎによる旅行案を考えるのが楽しみであり、うまい案ができたら旅行に出たという。
『線路のない時刻表』では未開通路線の仮想の時刻表を作成したりもしている。
実際は私鉄にも相当乗っている。特に後年は地方の中小私鉄に(創作活動のためでもあったが)好んで乗り、以前に廃止された地方私鉄に乗っておけばよかったと惜しんでいた。もちろん創作する上の発言である可能性もある。私鉄をテーマとした作品には「東京の私鉄七社乗りくらべ」(七社は当時。『終着駅は始発駅』所収)、『時刻表おくのほそ道』などがある。
犬が大の苦手で、時間つぶし等で街をぶらついている時によく犬に吠えかけられ「生きた心地がしなかった」と感想を述べたり、自分の長所を自身で診断し「自分は犬にも弱いし、強いのは酒ぐらいだ」と書いている。実際犬に吠えられた描写は数多い。
国鉄の分割民営化時に雑誌上で東北本線から東武日光線への直通列車の実現を提唱していたが、本人の生前には実現しなかった(2006年3月18日から開始)。
コレクターではないと自称し、初めは切符の収集もしていなかったが、国鉄完乗時の「証拠のために」乗った切符や入場券を集めるようになった。買った時刻表も途中から自宅に集めていた。
『鉄道廃線跡を歩く』最終巻の取材で狩勝峠の旧線を回る予定だったが、直前に病に倒れ、実現せずに終わった。同シリーズ編集担当の大野が遺志を継ぐ形で同所を回り、シリーズの巻頭記事を締めくくっている。同シリーズで最後に回ったのは碓氷峠の信越本線旧線跡である。
長女の宮脇灯子さんの著書を貪る様に読んで作家「宮脇俊三」が晩年、アルコールとの闘いで苦しんでいた事を知った。初めて「時刻表2万キロ」を読んだ時の「体が震える様な感動」は忘れられない。「鉄道ファン」がメジャーになる30年も前の事です。
宮脇俊三が以下の二つの紀行文学を娘さんがインドに行く時、推薦している事も頷けた。