年に一度の楽しみの行事、ラ・フォル・ジュルネ。有難いことに金沢でも行われているので今年も出かけました。
金沢駅前に到着。予想通りものすごく多くの人たちが集まっていました。今年は「ナチュール‐″自然と音楽″」というテーマで繰り広げられました。
最初に聴いたプログラムは、K112、カンマーアカデミー・ポツダムのアンサンブルでヘンデル作曲水上の音楽第2組曲、そしてカンマーアカデミー・ポツダムのアンサンブルとアンヌ・ケフェレックのピアノでモーツァルト作曲ピアノ協奏曲第27番KV595でした。
ヘンデルの水上の音楽といえば第2楽章が有名なアラ・ホーンパイプ。ヴァイオリンや木管楽器の方たちは立奏、そして顎当てのないバロックヴァイオリンや、ピストンのないトランペットやバルブのないホルン、そして鍵盤楽器はチェンバロというように、バロック時代当時のオリジナル楽器を使っていました。音の立ち上がりが強調されていて抑揚が感じられ、語っているような演奏でした。繊細ながらも凛としたハンサムな音楽。バロック当時の奏法を生かそうとしているのが感じられました。
晩年の貴重な作品、モーツァルトのピアノ協奏曲第27番ではカンマーアカデミー・ポツダムのメンバーも厳選され、ヴァイオリンは5本、チェロ2本、木管楽器のフルートやオーボエに至っては1本ずつと非常に少なかったのですが、まさに少数精鋭の状態、とことん突き詰めてきたというのが手に取るように伝わってくるアンサンブルを繰り広げていました。木管楽器の方たちの生き生きとした演奏、見事でした。楽しみにしていたアンヌ・ケフェレックのピアノ、隅々まで心が行き届いた温かく沁み入るモーツァルト、ピアノはカンマー・アカデミー・ポツダムの方を向きこちらからは背を向ける配置になっていたのですが、弾きふりをしているとは思えないのに、カンマー・アカデミー・ポツダムとの息もぴったり、見事な対話によるアンサンブルがなされていました。第3楽章の、短調に変わる部分で、ケフェレックさんのピアノ、はらりと表情を変え、たまらない気持ちを切々と訴えているような部分がありました。その部分のあまりの美しさに息をのむばかり。モーツァルトの生涯の中でまさに黄昏期に作られた第27番、もともと大好きな曲でしたが、今日は新たに、今まで気づいていなかった魅力を、演奏を通じて、発見させていただいた、そんな状態でした。ケフェレックさん、アンコールでは、ヘンデル作曲ケンプ編曲のメヌエットを演奏されたのですが、ホールいっぱいに、永遠の宇宙がまたたくまに広がり、優しくその宇宙に包み込まれるような演奏でした。
そして当日になって気になり出し、幸いチケットもあったので追加して聴いたプログラムは、K124、ベルリンフィルの首席奏者も務めたホルンの名手ラデク・バボラークが率いるバボラークアンサンブルによる、バッハ作曲「音楽の捧げもの」BWV1079より6声のリチェルカーレ、ベートーヴェン作曲ロンディーノ変ホ長調WoO.25、そして菊池洋子氏が加わって三名でブラームス作曲変ホ長調作品40でした。音楽の捧げものの6声のリチェルカーレでは、6声とはいえども楽器は7種類、バランスを取りながら、前面に出たり支えたり、お互いがお互いを尊重しながら演奏している印象を受けました。バボラークさんも、抑制するところで抑制し、とても考えて演奏している印象を受けました。プログラムでは最初に演奏されましたが、このような曲は、出だしから神経を使う必要のある、難しい曲なのだなということが感じられました。
ベートーヴェンのロンディーノは、がらりと雰囲気が変わり、かわいらしくほっとする音楽でした。各楽器が自分の持ち前を大切にしながらも相手の息遣いも細やかに感じ取り、親密なアンサンブルを繰り広げているところに、顔を覗かせていただいているような気分でした。最後あたりでの二本のホルンのアンサンブルの美しい響き合いも印象的でした。
プログラム最後のブラームス作曲ホルン三重奏曲がどんぴしゃり!最初から惹き込まれていたのですが、特に、第3楽章の、重苦しくありながらもたまらなく幻想的で美しく、依存性を聴き手からぐいぐい引き出す音楽に絡めとられました。菊池洋子さんのピアノも深遠な世界をたおやかに這い、ダリホール・カルヴァイ氏のヴァイオリンが音の絹織物を美しく編み上げ、バボラーク氏のホルンもまさに真骨頂、深いところから心を込めて歌っていました。この曲を作曲しているときにブラームスは母を亡くしたため、この第3楽章は母を追悼する気持ちを込めて書き上げているとWikipediaにありました。長い第3楽章の後の第4楽章は快速でインパクトの強い音楽。怒涛のように過ぎ去るものの、とても耳に残りやすいメロディーでした。これは演奏者たちもエネルギーを使い切っただろうと思えるような充実した内容の演奏にただただ酔いしれたまま会場を後にしました。
上記の二つのプログラムの間は、時間があいていたので、半券を使って入れるプログラムや券なしで聴けるプログラムを聴きました。
ピアノの日という企画で、ピアノオーディションに合格した小学生から一般の方たちによるピアノ演奏、昨日はモーツァルト、クレメンティ、スカルラッティの曲が演奏されました。さすがオーディションに合格するだけあって、指もしっかり回っているとともに音色も美しく情感があり、羨ましい限りでした。出演の子供たち、今後の成長や活躍が本当に楽しみ、これからもずっとピアノを続けてもらえたらいいな、と感じました。一般の方たちの演奏も素敵で、ここまで続けてこられ今も追求している姿勢に刺激を受けました。モーツァルト、譜読みはしやすいのに人前演奏が、、、と言われたり感じたりすることが多い作曲家なのですが、出演者の方たちはのびやかに演奏していました。(司会の青島広志さんは、モーツァルトは弾けるようになりやすい曲が多いので、どんどん弾いたらいいと話されていました。)スカルラッティはソナタだったのですがK.146、K.434、K.450、未知の曲が多くしかしとても丁寧に気持ちよく演奏していました。(司会の青島広志さんも、スカルラッティについてはふだんあまり聴かない曲が聴けて貴重だったと語っていました。)最後に弾いた大人の方たちはモーツァルトの4手のためのピアノソナタを連弾されたのですが、これが実に楽しそうなうえに素敵でただただ聴きほれる状態。見本にしたい方たちのように思えてきました。いつまでもこのように音楽を続けられたら素晴らしいと感じ入った次第です。
オーケストラの名曲集の演奏もありました。京都大学交響楽団による、親しみやすい名曲の演奏ということで、ワーグナーのニュルンベルクのマイスタージンガーより第一幕への前奏曲、ブラームスのハンガリー舞曲第5番、アンダーソンの舞踏会の美女、そりすべり、ワルツィング・キャットが演奏されたのですが、まるでプロのオーケストラなのではないかと思えるぐらい、見事な演奏でした。選曲もメジャーな曲ばかりとはいえ、この舞台には非常にふさわしく夢のある曲でした。音楽の世界にすっかり魅了されわくわくするひと時を過ごせたとともに、ただただ脱帽&感心してしまいました。なんとこの京都大学交響楽団、大学オケとはいえ、プロ活動を行っていたこともあるオーケストラで、朝比奈隆氏はこのオケのOBだったのですね。
その他音楽堂の前やホテルのロビーで子供たちの合唱を聴いたのですが、一生懸命に、そして楽しそうに歌っていた子供たち、みんな、輝いていました!音楽の教科書に載っている曲から、合唱コンクールに出てきそうな曲まで、聴けた曲の種類は、幅広かったのですが、聴いていて懐かしく嬉しい気持ちになりました。出演した子供たちにとって、このラフォルジュルネでの出演の機会がかけがえのない思い出、そして今後人生を送っていくうえでの自信のひとつになればいいなあと思った次第です。アーチストたちの公演とともに、子供たちや一般の方たちも舞台に乗って音楽を披露し、観客も一緒になって楽しんで、音楽体験を共有し、今後につなげていくきっかけになる、そのような場になっているような気がしました。
充実した半日を過ごすことができたひととき、余韻が残っています。。。とはいえラ・フォル・ジュルネ金沢は今も開催中なのですね!










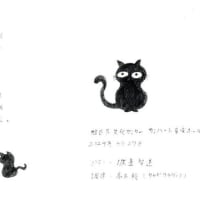
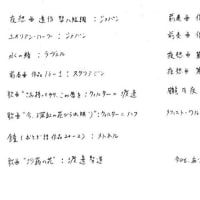




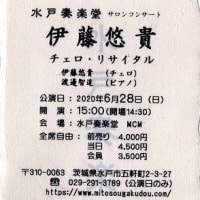


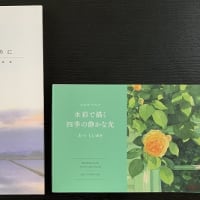

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます