伊予河野家家紋の変遷と分家の家紋は時代時代により変化していきます。
分かりづらいとの意見もあり少し整理してみます。
また、河野家家紋は色んな呼び方があり現物を見ないとよく分からない場合が多いのです。
同じ紋でも呼び方が違う事があります。
しかし、別紋の州浜紋(すはま)と一鱗紋(いちうろこ)を除けば二つの折敷と中の三の形の
組み合わせでしかありません。
今回できるだけビジュアルに説明していきます。
尚、過去提供を受けた河野家支族の方たちのマル秘資料もUPさせて頂きますので関係者の方々には
ご了承願いたいと存じます。
①折敷は原則二種類
イ)古来の折敷の形の角が取れていない□か◇の形

当方はこちらを◇を折敷(おりしき)と表現しています。
河野家の古い時代の物と思っています。
根拠としては、河野通有が元寇との戦いで使用したのはこちらの紋で現在「三島神紋流れ幡」として

大山積神社(三島社)宝物館に重要文化財として現存します。よって当時の大山祇神社神文は現在の
ものと違って古紋となります。この形が古い時代の河野家家紋であることは道後湯築城博物館も同じ

認識で復元の幟を立てていますので、現在の全国の河野関係者が湯築城を訪問した時、自家の紋と
違うので驚くことも多いのです。
また、ご案内の見聞諸家紋は日本最古の家紋帖で足利義政が東軍の見分けをつけるために編集させた
と伝えられます。こちらも河野家はこの◇三紋(折敷漢数字三文字紋)ですから間違いないです。
見聞諸家紋は1469年前後に作られたとされます。
「太平記」の河野通遠討死の描写に「傍折敷三文字」とあるのが不思議です。
「太平記」は1371年頃の編纂なので「折敷」◇でないと変なのですが、引用本の太平記がいつの転写か
が不明なのでなんとも言えません。印刷技術の無い時代ですので後世何度も何度転写されていますので
本来の原本に有ったか否かは不明です。
ロ)古来の折敷が進化し角(隅)がとれた変形八角形紋は

当方はこちらが「傍折敷」(そばおりしき)と表現しています。
別に角切(すみきり)とも隅切(すみきり)とも表現されます。
こちらが現在一番ポピュラーです。
折敷は「御食(おしき・をしき)の訛ったもので本来は神に供え物(食物)を捧げる為の盆が始まりとされ
これらは平安時代から見られますが、当時はまだ正四角形の折敷でした。後に技術が発達し、変形八角形の
形になったとされます。私は「傍」(そば)を角切ありの意味で解釈していますが、本来「傍」(すみ)
はかたわらの意味で「へり」の意味と思います。供え物が落ちないように「へり」につい立てを立てた
との意味と思います。
②折敷の中の三の文字は時代により変遷します。
イ)一番古いのは毛筆で書いた三文字で一番シンプルです。

わたしはこれを「漢数字三文字紋」(かんすうじさんもじもん)と表現します。
折敷が◇時代はすべてこれです。
ロ)次が三の字の真ん中の一が少し短めになってデザイン化されたものです。
【河野流岡田家系図冒頭】

ハ)他に三の字の一の長さがすべて同じものでこれを「算木(さんぎ)の三」と表現しています。

こちらは河野家関係の寺の瓦に使われている場合が多く見分ける為に「河野家寺紋」と呼ぶ場合が
あります。理由は簡単なのです。毛筆の三では手製で同じ瓦を沢山焼くのが難しかったのでしょう。
瓦が伊予に普及するのは室町後期とされます。現在、窯場で一番有名なのは伊予では菊間瓦です。
この瓦はいぶし銀色で最高級の瓦です。この菊間瓦が普及したのは上方から瓦の版型(親版)の
技法が伝わってからです。所謂、現在の「金型」です。この親型を作る時に作りやすい算木三を
採用したものと思われます。第二次大戦後に吹き替え工事ではどのようなデザインも作れますので
間違ったデザインを採用して河野関係寺は瓦の葺き替えをしている場合があります。
例として河野家最後の殿様、牛福通直の菩提寺、広島県竹原の長生寺は屋根の
葺き替えをして「縮三文字」(しゅくさんもじ)に変更してしまっています。
牛福通直が自害したのは天正15年7月12日ですの。翌年の
天正16年に牛福通直の弔いの為、母親が高野山に登り通直の慰霊塔を建てますがこちらは(折敷漢字の三
文字紋)で建立されていますから、竹原長生寺が間違えました。
長生寺寺紋

高野山奥の院の「牛福通直慰霊塔」を参照してください。違いますから。
ニ)三が揺れか縮か
揺れ(ゆれ)も縮(しゅく)も基本的には同じです。
この形は戦国期以降からの使用と思われます。
江戸期以降現在に至るまでこれを正紋と認識している河野家子孫が多いのはこの為です。
「揺れ」「縮」の論拠は後世の作であろう河野家「予章記」に
「白村江の戦いの時、舟の舳先に掲げた家紋の三の字が波に映り、揺らいで見えた為」と
語りますが、この時代に幕紋を押し立てていく戦はありませんし家紋の概念もありませんから
後世の作話ですが、子孫たちはそれを信じそれなりに家紋を作成していったのでしょう。
それ以前も州浜を使用していますので子孫は悩んだでしょうね。黒川家のように
「傍折敷三文字紋」を三つすはま紋としてしまいます。
そもそも河野家家紋は大山祇神社の神紋の借用です。
大山積神社の古い神紋は河野通有が戦勝祈願に大山積神社で祈ったのち、神紋を掲げて
出陣す、とありますので「折敷漢数字三文字紋」です。いまはもう無くなりましたが大山積神社
の古い紋は神社殿の一部に掲げられていました。現在は現代風に「傍折敷縮三文字紋」にされています。
河野家は神紋を家紋にする前は、「州浜紋」と思われます。
州浜紋は河野家支族によりイメージが違います。
三角一つを「一州浜」とし、これは別家では鱗(うろこ)紋とします。

三つを「みつすはま」とします。【河野鈴姫系図冒頭】

また「一鱗紋」(いちうろこ)(いちすはま)の併用は北条家から養子を貰ってからの使用紋と思われます。
三つ鱗紋は「「北条家」の家紋だから北条家から養子が河野家に入ったから引き継いだと思えます。
北条家家紋は

とされ、鱗が少しへしゃげているのが特徴です。
本来州浜とは

であり、河野家支族がつかう三つ州浜は【越智氏寺町三つ州浜紋】

の形です。これは州浜が三つ並んでいます。
河野家が折敷三文字紋にこだわるのは「予章記」や「予陽河野家譜」に書かれる、
「鎌倉で宴会の折、源頼朝から家来の中で三番に重要な人物であるとして、酒を折敷にのせ三番目に頂いた
とする」記述ですが、これは後世の挿入です。これ以前に大山祇神社神紋は「折敷三文字紋」です。
ちなみにこの鎌倉の宴会は材木座海岸でしたと河野文書は書きますが、ピクニック風ですが、実態は材木座にあった
河野通信邸での宴会と思われます。宴会はあったのでしょうが河野が鎌倉政権のNO3とは考えられません。
何故なら、総大将の源頼朝の屋敷は鶴岡八幡宮の左の山手にあり親族や譜代がその屋敷をぐるりと囲んで守って
います。毛利家の前姓大江氏は頼朝邸の左側に接し守護しています。現在も大江の墓がありますので山口県の
毛利家子孫は今も現地で法事をしています。
材木座は現在でも材木座海岸といわれる当時の浜辺で、頼朝邸から一番端になります。
この材木座の河野鎌倉屋敷を探していますがまだ見つかりません。だれが知りませんかね?
最期に河野家子孫が使用する家紋いろいろをUPしてみましょう。
これ以外も沢山あります。
越智姓山野井家家紋(広島県大原町)
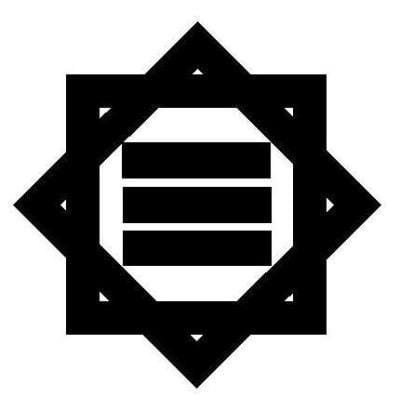
この家は「山野井本予章記」を保存する家です。
越智姓稲葉家家紋(東京・墓紋)

越智姓寺町氏家紋

越智姓難波氏家紋(丸に割菊に三文字紋)

河野流黒川家家紋(同家系図所収)

黒川系図は家標識(正紋)として「傍折敷三文字紋」を三つ𥻘(すはま)と表記します。
又、替え紋として「一鱗(いちうろこ)」紋を掲げます。
幕紋は黒川家は土佐長曾我部の系統を引き継ぎとして長曾我部家紋を引き継いでいます。
しかし、黒川系図は系図の途中に「三つ州浜紋」を別途挿入しています。

この家は河野流正岡家とも親族関係で、黒田藩に仕官した人は曾我部家として残ります。
また黒川桃女が生んだのが長福寺本予章記や長福寺本河野家譜を作成した南明禅師です。
この人が1650年前後に「予陽河野家譜」を作成したらしいので、一部時代が合わないこと
になったとともされます。
越智姓得能家家紋(三十万に鳥紋)

河野家支族一遍上人時宗寺紋

河野流鈴姫系図所収

この家は越智姓河野家家紋とする別紋も記載します。
越智流三つ鱗紋

河野家本城湯月城紋

河野通有元弘の役使用の流れ旗

河野家継承久留島家紋

河野家流一柳家紋

河野流岡田家紋(系図冒頭)

長福寺使用河野家紋

河野庵主家紋(系図所収)

黒田藩士河野流家家紋

黒田家にも多くの河野支族が仕官します。河野黒川家一族がそうですね。
東京上野鶯谷三島神社神紋

この三島神社の場所は伊豫河野家が源頼朝に仕官の折、鎌倉の材木座屋敷以外に江戸に構えた屋敷跡に
立てられたとされます。当時は今の上野駅までは海岸線で浜辺に河野邸を建てたとされます。
この時、荏原郷の江戸氏と婚姻関係を結んだとされ、現在の世田谷区の小田急沿線に多くの河野氏が
住んでいて「河野家譜」を継承しています。江戸氏は今もいますが、一部は伊豫へ移住し、伊豫江戸氏
として現存しますね。ただ、現在の鶯谷三島神社の神官や氏子はこの由緒はご存じないようです。
安芸高田へ移住の河野家家紋

この家は毛利家に従った家として有名です。{ひとへら河野」として慈善家の末裔と思われます。
和州越智氏家紋

この家は、いつの戦乱か分かりませんが、伊豫を追われる時、神仏を背中に負い奈良まで逃げてきたとします。
但し、子孫はこの由緒を昔否定しましたが、系図にはそう書かれています。
他にたくさん河野家家紋はあるとおもいますが、コメント欄に投稿して頂くと追加します。
屋代源三
分かりづらいとの意見もあり少し整理してみます。
また、河野家家紋は色んな呼び方があり現物を見ないとよく分からない場合が多いのです。
同じ紋でも呼び方が違う事があります。
しかし、別紋の州浜紋(すはま)と一鱗紋(いちうろこ)を除けば二つの折敷と中の三の形の
組み合わせでしかありません。
今回できるだけビジュアルに説明していきます。
尚、過去提供を受けた河野家支族の方たちのマル秘資料もUPさせて頂きますので関係者の方々には
ご了承願いたいと存じます。
①折敷は原則二種類
イ)古来の折敷の形の角が取れていない□か◇の形

当方はこちらを◇を折敷(おりしき)と表現しています。
河野家の古い時代の物と思っています。
根拠としては、河野通有が元寇との戦いで使用したのはこちらの紋で現在「三島神紋流れ幡」として

大山積神社(三島社)宝物館に重要文化財として現存します。よって当時の大山祇神社神文は現在の
ものと違って古紋となります。この形が古い時代の河野家家紋であることは道後湯築城博物館も同じ

認識で復元の幟を立てていますので、現在の全国の河野関係者が湯築城を訪問した時、自家の紋と
違うので驚くことも多いのです。
また、ご案内の見聞諸家紋は日本最古の家紋帖で足利義政が東軍の見分けをつけるために編集させた
と伝えられます。こちらも河野家はこの◇三紋(折敷漢数字三文字紋)ですから間違いないです。
見聞諸家紋は1469年前後に作られたとされます。
「太平記」の河野通遠討死の描写に「傍折敷三文字」とあるのが不思議です。
「太平記」は1371年頃の編纂なので「折敷」◇でないと変なのですが、引用本の太平記がいつの転写か
が不明なのでなんとも言えません。印刷技術の無い時代ですので後世何度も何度転写されていますので
本来の原本に有ったか否かは不明です。
ロ)古来の折敷が進化し角(隅)がとれた変形八角形紋は

当方はこちらが「傍折敷」(そばおりしき)と表現しています。
別に角切(すみきり)とも隅切(すみきり)とも表現されます。
こちらが現在一番ポピュラーです。
折敷は「御食(おしき・をしき)の訛ったもので本来は神に供え物(食物)を捧げる為の盆が始まりとされ
これらは平安時代から見られますが、当時はまだ正四角形の折敷でした。後に技術が発達し、変形八角形の
形になったとされます。私は「傍」(そば)を角切ありの意味で解釈していますが、本来「傍」(すみ)
はかたわらの意味で「へり」の意味と思います。供え物が落ちないように「へり」につい立てを立てた
との意味と思います。
②折敷の中の三の文字は時代により変遷します。
イ)一番古いのは毛筆で書いた三文字で一番シンプルです。

わたしはこれを「漢数字三文字紋」(かんすうじさんもじもん)と表現します。
折敷が◇時代はすべてこれです。
ロ)次が三の字の真ん中の一が少し短めになってデザイン化されたものです。
【河野流岡田家系図冒頭】

ハ)他に三の字の一の長さがすべて同じものでこれを「算木(さんぎ)の三」と表現しています。

こちらは河野家関係の寺の瓦に使われている場合が多く見分ける為に「河野家寺紋」と呼ぶ場合が
あります。理由は簡単なのです。毛筆の三では手製で同じ瓦を沢山焼くのが難しかったのでしょう。
瓦が伊予に普及するのは室町後期とされます。現在、窯場で一番有名なのは伊予では菊間瓦です。
この瓦はいぶし銀色で最高級の瓦です。この菊間瓦が普及したのは上方から瓦の版型(親版)の
技法が伝わってからです。所謂、現在の「金型」です。この親型を作る時に作りやすい算木三を
採用したものと思われます。第二次大戦後に吹き替え工事ではどのようなデザインも作れますので
間違ったデザインを採用して河野関係寺は瓦の葺き替えをしている場合があります。
例として河野家最後の殿様、牛福通直の菩提寺、広島県竹原の長生寺は屋根の
葺き替えをして「縮三文字」(しゅくさんもじ)に変更してしまっています。
牛福通直が自害したのは天正15年7月12日ですの。翌年の
天正16年に牛福通直の弔いの為、母親が高野山に登り通直の慰霊塔を建てますがこちらは(折敷漢字の三
文字紋)で建立されていますから、竹原長生寺が間違えました。
長生寺寺紋

高野山奥の院の「牛福通直慰霊塔」を参照してください。違いますから。
ニ)三が揺れか縮か
揺れ(ゆれ)も縮(しゅく)も基本的には同じです。
この形は戦国期以降からの使用と思われます。
江戸期以降現在に至るまでこれを正紋と認識している河野家子孫が多いのはこの為です。
「揺れ」「縮」の論拠は後世の作であろう河野家「予章記」に
「白村江の戦いの時、舟の舳先に掲げた家紋の三の字が波に映り、揺らいで見えた為」と
語りますが、この時代に幕紋を押し立てていく戦はありませんし家紋の概念もありませんから
後世の作話ですが、子孫たちはそれを信じそれなりに家紋を作成していったのでしょう。
それ以前も州浜を使用していますので子孫は悩んだでしょうね。黒川家のように
「傍折敷三文字紋」を三つすはま紋としてしまいます。
そもそも河野家家紋は大山祇神社の神紋の借用です。
大山積神社の古い神紋は河野通有が戦勝祈願に大山積神社で祈ったのち、神紋を掲げて
出陣す、とありますので「折敷漢数字三文字紋」です。いまはもう無くなりましたが大山積神社
の古い紋は神社殿の一部に掲げられていました。現在は現代風に「傍折敷縮三文字紋」にされています。
河野家は神紋を家紋にする前は、「州浜紋」と思われます。
州浜紋は河野家支族によりイメージが違います。
三角一つを「一州浜」とし、これは別家では鱗(うろこ)紋とします。

三つを「みつすはま」とします。【河野鈴姫系図冒頭】

また「一鱗紋」(いちうろこ)(いちすはま)の併用は北条家から養子を貰ってからの使用紋と思われます。
三つ鱗紋は「「北条家」の家紋だから北条家から養子が河野家に入ったから引き継いだと思えます。
北条家家紋は

とされ、鱗が少しへしゃげているのが特徴です。
本来州浜とは

であり、河野家支族がつかう三つ州浜は【越智氏寺町三つ州浜紋】

の形です。これは州浜が三つ並んでいます。
河野家が折敷三文字紋にこだわるのは「予章記」や「予陽河野家譜」に書かれる、
「鎌倉で宴会の折、源頼朝から家来の中で三番に重要な人物であるとして、酒を折敷にのせ三番目に頂いた
とする」記述ですが、これは後世の挿入です。これ以前に大山祇神社神紋は「折敷三文字紋」です。
ちなみにこの鎌倉の宴会は材木座海岸でしたと河野文書は書きますが、ピクニック風ですが、実態は材木座にあった
河野通信邸での宴会と思われます。宴会はあったのでしょうが河野が鎌倉政権のNO3とは考えられません。
何故なら、総大将の源頼朝の屋敷は鶴岡八幡宮の左の山手にあり親族や譜代がその屋敷をぐるりと囲んで守って
います。毛利家の前姓大江氏は頼朝邸の左側に接し守護しています。現在も大江の墓がありますので山口県の
毛利家子孫は今も現地で法事をしています。
材木座は現在でも材木座海岸といわれる当時の浜辺で、頼朝邸から一番端になります。
この材木座の河野鎌倉屋敷を探していますがまだ見つかりません。だれが知りませんかね?
最期に河野家子孫が使用する家紋いろいろをUPしてみましょう。
これ以外も沢山あります。
越智姓山野井家家紋(広島県大原町)
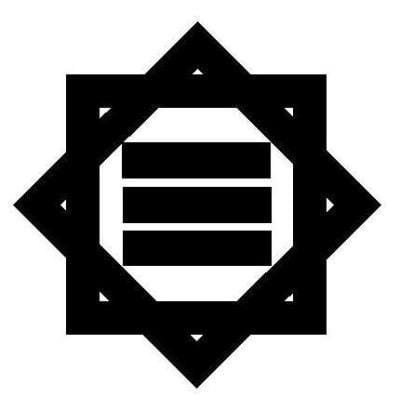
この家は「山野井本予章記」を保存する家です。
越智姓稲葉家家紋(東京・墓紋)

越智姓寺町氏家紋

越智姓難波氏家紋(丸に割菊に三文字紋)

河野流黒川家家紋(同家系図所収)

黒川系図は家標識(正紋)として「傍折敷三文字紋」を三つ𥻘(すはま)と表記します。
又、替え紋として「一鱗(いちうろこ)」紋を掲げます。
幕紋は黒川家は土佐長曾我部の系統を引き継ぎとして長曾我部家紋を引き継いでいます。
しかし、黒川系図は系図の途中に「三つ州浜紋」を別途挿入しています。

この家は河野流正岡家とも親族関係で、黒田藩に仕官した人は曾我部家として残ります。
また黒川桃女が生んだのが長福寺本予章記や長福寺本河野家譜を作成した南明禅師です。
この人が1650年前後に「予陽河野家譜」を作成したらしいので、一部時代が合わないこと
になったとともされます。
越智姓得能家家紋(三十万に鳥紋)

河野家支族一遍上人時宗寺紋

河野流鈴姫系図所収

この家は越智姓河野家家紋とする別紋も記載します。
越智流三つ鱗紋

河野家本城湯月城紋

河野通有元弘の役使用の流れ旗

河野家継承久留島家紋

河野家流一柳家紋

河野流岡田家紋(系図冒頭)

長福寺使用河野家紋

河野庵主家紋(系図所収)

黒田藩士河野流家家紋

黒田家にも多くの河野支族が仕官します。河野黒川家一族がそうですね。
東京上野鶯谷三島神社神紋

この三島神社の場所は伊豫河野家が源頼朝に仕官の折、鎌倉の材木座屋敷以外に江戸に構えた屋敷跡に
立てられたとされます。当時は今の上野駅までは海岸線で浜辺に河野邸を建てたとされます。
この時、荏原郷の江戸氏と婚姻関係を結んだとされ、現在の世田谷区の小田急沿線に多くの河野氏が
住んでいて「河野家譜」を継承しています。江戸氏は今もいますが、一部は伊豫へ移住し、伊豫江戸氏
として現存しますね。ただ、現在の鶯谷三島神社の神官や氏子はこの由緒はご存じないようです。
安芸高田へ移住の河野家家紋

この家は毛利家に従った家として有名です。{ひとへら河野」として慈善家の末裔と思われます。
和州越智氏家紋

この家は、いつの戦乱か分かりませんが、伊豫を追われる時、神仏を背中に負い奈良まで逃げてきたとします。
但し、子孫はこの由緒を昔否定しましたが、系図にはそう書かれています。
他にたくさん河野家家紋はあるとおもいますが、コメント欄に投稿して頂くと追加します。
屋代源三









