図書館で歴史書を漁っていて、”敗者の古代史”という本に巡り合った。勝てば官軍というように歴史は勝者を正として伝えられる。しかし、実際に起こったことはそんなに単純じゃない...ということを、いろんな事例を出して丁寧に解説た歴史書です。饒速日とナガスネヒコとか熊襲と日本武尊とか興味深い話しが生き生きとした語り口で述べられている。
この本の著者が森浩一で、調べてみると同志社の名物教授で数年前に亡くなっている。他にどんな本を出しているかと調べるとワンサカ出てくるじゃないか。そこでアマゾンンで片っ端から購入することにした。敗者の古代史は手元に置きたかったのでまず購入。あと、日本神話の考古学、倭人伝を読みなおす、記紀の考古学、古代史おさらい帳、巨大古墳 治水王と天皇陵、対論 銅鐸、倭人・熊襲・天皇をめぐって、以上8冊を注文して読み始めている。
この先生の面白いところは記紀に真正面から向き合っていることだ。戦前の皇国史観の反動で戦後は神武東征などの記紀の記述に関してコメントすることがタブー視されるなか、考古学の観点から堂々と論陣をはる姿には感銘を覚える。
たとえば、弥生後期に九州北部では漢鏡が大量に出土するが、畿内からは一枚も出土していず、古墳時代になって畿内からも大量に出てくる事実をどう捉えるか。素直に考えれば記紀の記述にある東遷があって、九州北部の連中が畿内にその風習を持ち込んだと考えられるじゃないか。
今読みかけているのが倭人伝を読みなおす、という本。魏志倭人伝の原文と当時の東アジアの政治状況を丁寧にわかりやすく且つ妥協抜きで解説してくれる。とても読み流すなんてことのできない内容で、一行一行味わいながら読んでいるので追々紹介したいとおもいます。
この先生、松本清張とも交友があり(というより師匠かな)じつに納得のいく論を展開しているのでいっぺんにファンになりました。これからしっかり勉強させていただきます。










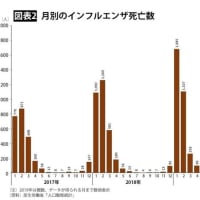
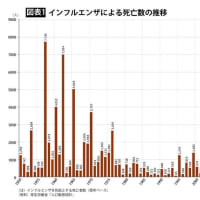
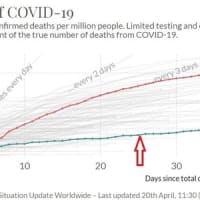
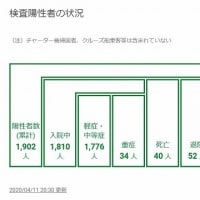
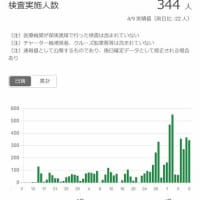
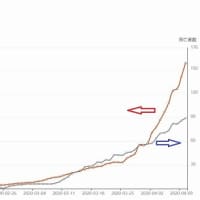
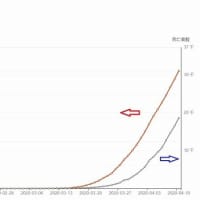

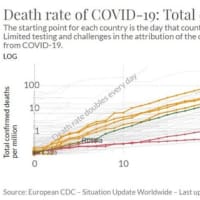
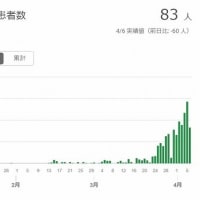
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます