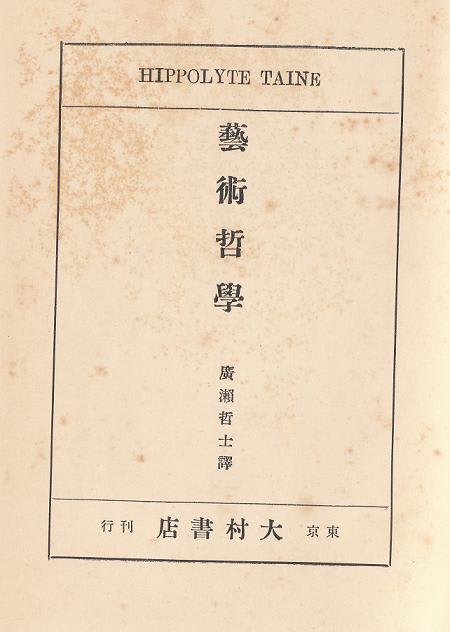賢治 「羅須地人協会時代」少し前の地図です。
(拡大してご覧下さい) 「複製禁止」
※ 地図拡大は、二段拡大になっております。
北上川の「渡し場」が見られます。
一部の桑畑は、関東のような桑の密集植えではなく、桑の木と大豆や麦等の間作栽培畑です。
丸小淵は尊菜の宝庫でした。
釜場に見える「文」は南城小学校で、立てに見える所は賢治等が使用した校舎を移築したもの、逆エルの黒く見える上の所は講堂です。この図で大体の時代が判明すると考えられます。
何時もカビ臭い話ばかりで我ながら歳だな~と嫌になる事が有る。今日は新しい話を書いていきたいと思う。大体このブログを見ている人はせいぜい五・六人であるから恥じ入る事もない。さて
「賢治研究」に入澤氏が河本緑石について115・116号に「研究漫筆」で書かれていた。河本と言えば小澤さん上の写真の本に「河本緑石考」(昭和四十六年出版)があるが、入澤氏そのうちに私などにも「ほとんど欠落のないものになった」こと等をどこかでかたられてほしい。入澤氏は「ツイッター」だけ?ではなく、「宮沢賢治と『アザリア』の友だち」などと同じように何処かで発信しているのかな~。「東京堂」での御講演には行きそびれた。「文教大学」にもだ。残念。
ところで「島根県立図書館」に河本緑石著「三徳山」が有る。図書館では貸出可能とある。小澤さんの書かれていたのとどの程度違いが有るかは見ていないので知らないが、何方か御調べになったら知りたいものだ。島根県立図書館が出たら、「所蔵資料 簡易検索覧」に 『河本緑石』と入れて検索されますと見られる。何方も御存知とは思いますが。
「宮澤賢治全集」や「江刺と宮澤賢治」等によると、菊池武雄の誕生日は明治二十七年十二月八日で亡くなられたのは昭和四十九年七月十一日である。
昭和十年四月から同十一年十二月までに出された宮澤賢治友の会 「宮澤賢治研究」は、賢治研究資料としては最初期のものである。発行者が菊池で連絡場所も自宅だった。
わたくしは菊池武雄に就いての知識は無い。しかし昆の「新聞人菊池武雄」は「宮澤賢治の友人」とは異なる人物ではないかと思う。記載されている生まれた日の違いもあるが、亡くなられた頃の年月日も異なるように思われる。「練馬新聞」の社長であった菊池は、昭和二十三年から同五十六年五月まで「練馬新聞」を続けていたとの事である。住まいは小竹町や桜台に住んでいたとの事、堀尾さんが知らないはずが無い。奥田氏も国会図書館で「岩手日報」等の新聞を良く調べられている(研究資料探索)。両者とも「新聞人菊池武雄」には一言も触れていない。
「注文の多い料理店」の挿絵や装丁そして賢治昭和六年東京八幡館での病臥に駆け付けた菊池武雄の晩年がわたしはあまり良く解らない。「全集」に「戦後は吉祥寺にデザインを生かした洋装店を経営」とある。「書簡」に「展示会云々」とあるが堀尾さんは「北斗会」について知って居られたと思うが何も書かなかった。「初期研究資料集成」の座談会でも菊池の事は「校本宮澤賢治全集」に出つくしているからか、何方も触れることはなかった。
些細のことだが「西巣鴨第二小学校」の名前は、昭和六年四月一日~昭和十年九月末日であった。
※ 訂正 文中奥田氏の「研究資料探索」ではなく「ホタル 増補版」でした。
「新校本宮澤賢治全集」によると、佐藤紅歌 明治31・1・13~昭和53・10・16とあります。昆は生年月日に付いては不明だった(間違った記述をしている)。紅歌と八木・金田一に付いては又の機会に記す事もあろう。だが此処では昆のこんな記事に気が魅かれた。菊池武雄にである。以下引用しよう。
「 岡山儀七によって世に送り出された新聞人が いる。菊池武雄(M30・7・13生)である。菊池武雄は、大正十年ころ花巻から『猫額私語』などを『岩手毎日新聞』に投稿していた。それを主筆岡山儀七が認めて『岩手毎日新聞』に入社させた。菊池は後に『東京日日 新聞』に移り、盛岡や青森の支局長をへて本社に入り編集部長に就く。敗戦後は『岩手新報』の副社長、編集局長となる。昭和四十年ころは、東京練馬区で『練馬新聞』を発行している。菊池は宮沢賢治(M29・8・27生)の友人であった。」
(岡山儀七に関してはPC検索でご覧下さい)
 先ずは入手した「練馬新聞」です。(練馬区光が丘図書館のご厚意による)
先ずは入手した「練馬新聞」です。(練馬区光が丘図書館のご厚意による)
どうゆうわけか菊池武雄に付いては、小生の知りたい経歴や賢治関連以外、例えば挿絵画家としての活躍がどのようであったのか、在京中の行動については堀尾氏は良く存じていたはずだと思うが触れていないようだ。博識の「校本全集」にもあまり良く載っていない。(「イーハトゥブの先人たち」を見ていない小生など解るはずもないが)。
つづく
「岩手タイムス」は「校本宮澤賢治全集 第十四巻 年譜」にも参考資料として出ていない(721頁 参考文献 新聞 )。昆も昭和11年以降しか見ていないとある。(以下写真を拡大して見て頂きたい)
「書簡 280 母木 光あて」に、「花巻町相生町 岩手タイムス 佐藤紅歌」が載っているが賢治解説に付き全てを網羅している上記本「年譜」に「岩手タイムス」の項目が見られない。残念。色々と推測も出来るが推測ではしょうがない。
清見が発行人名であるが、社長は平野で、副社長に「箱庄」(醤油屋&金融)の二代目社長箱崎圭助であった。箱崎は敗戦後に町長に立候補して北山愛郎に敗れた。紅歌家も箱崎家も孫の代になっているが、もしかしたなら「岩手タイムス」や他の新聞も有るやもしれない。
「稗貫郡の郷土紙」は、紅歌の生年月日等の誤記不明なところもあるが、色々と楽しく読める。
つづく
「岩手民報社」の編集印刷発行人は桜の伊藤謹吾になっているが、実質的には佐藤紅歌であつた。
昭和二十六年の暮れに「岩手民報社」を設立し、翌年に創刊した紅歌は、新興製作所の谷村(たにむらではなくヤムラと読む)や佐藤隆房等の宣伝マンとして資金を得て活躍した。八十二歳でこの世を去ったが、昆は紅歌を新聞人と記しているがわたくしはゴーストライターの一面も有ったと思う。
 昭和十年に八木英三が「花釜日の出新聞」(日刊)創刊。編集長は松田浩一であり、編集委員には 宮澤吉太郎がいたという。(旧姓は臼崎・花農ー師範ー教員)
昭和十年に八木英三が「花釜日の出新聞」(日刊)創刊。編集長は松田浩一であり、編集委員には 宮澤吉太郎がいたという。(旧姓は臼崎・花農ー師範ー教員)
≪あの戦争をしたがっているうちからは、「岩手中央新聞」と「「岩手タイムス」と「花釜日の出新聞」の合併を要請する。その結果として、「日刊いわて」が誕生する≫〈19頁)「第一次」と云う。≪社長佐藤忠治、副社長八木英三、編集長佐藤紅歌、営業清見浩平で、経営の実権は清見と八木であった≫と云う。≪終戦後八木英三は「週刊読む岩手」を創刊し、清見は「日刊いわて」を復刊している≫その後昭和十六年十二月二十八日に「新岩手日報」の買収される。
再々度復刊した「日刊いわて」は、一部では有りますがコピーを拡大してご覧戴きたい。ここではこのブログで以前にも記した事が有るが鶴田辰蔵に付いて触れたい。
社主鶴田は御田屋町で印刷会社を経営していた。花札の印刷は業界のトップであった。外国人までにも売り上げを伸ばしていたという。彼(大正五年六月十二日生まれ)当時は、若さと豪放磊落な面があってそれに人に頼まれる嫌と言えないタイプであったといえようか。清見が頼って行ったがこの新聞は前「日刊いわて」の4343号までとは違い長続きはしなかった。
つづく
佐藤紅歌についての覚書
≪佐藤紅歌氏・・・・本名佐藤源一(明30・1・13~ )は賢治とは小学校以来の友人。岩手毎日新聞・岩手日報・岩手タイムス・河北新報・岩手新報等の記者を次々に経て、現在は岩手民報社に勤務。書簡230を参照≫ 「校本 宮沢賢治全集 第13巻 596頁 昭和49年12月20日発行」より
 写真コピーは、昆 憲治「岩手県の郷土紙物語:敗戦後発行の県中南部の郷土紙 1994・3)より
写真コピーは、昆 憲治「岩手県の郷土紙物語:敗戦後発行の県中南部の郷土紙 1994・3)より
上記によると、昆氏は岩手民報社の発行所が花巻町桜町2丁目で、編集兼印刷発行人は伊藤謹吾であるが、佐藤紅歌と同一人物と思ったが、やはり佐藤と伊藤は別人であろうとされて、伊藤謹吾はなに者か。と記されている。(文 要約しています)
紅歌に付いては追々記するとしてここでは伊藤謹吾に触れたい。
謹吾については桜の人なら知らない人はいないと思うが、佐藤隆房の自宅の近くに住んでいて、獣医(?)で伊藤熊蔵(克己の父)と戦時中賢治詩碑等でよく馬の交配を行ったりしていた。(詩碑の南側の松の間隔がてごろであったからであろうか) また 魚屋をしたこともあり、良く言えばなかなかのやり手人であった。紅歌ではなく、謹吾は別人である。
つづく
十月のおしまい頃であった。杉並区立郷土博物館分館「野鳥の父・中西悟堂と善福寺池」展の会場でのことである。おそらくわたくしと同年輩の方と推察されるしとやかで気品に満ちた女性が、会場企画者の西村真一氏と中西悟堂についてかたらいあっていた。
「野鳥観察会での中西悟堂先生はいつも穏やかでニコニコと何方とでもお付き合いしてくれてそれは楽しかった。懐かしさのあまり今日やっとこの会場に来られて、先生の色々な資料を拝見できて嬉しい」と話されていた。
残念ながらわたくしは中西悟堂とは面識はない。鳥に関しても知識もない。唯一と言おうか中西の「講座 禅 第二巻」(筑摩書房発行)の「月報」(昭和四十二年九月)の「現代文明と禅」に魅かれたことがあることを思い出した。現代文明について騙られた後に、こんな事を記されている。
≪禅は思弁や観念の宗教ではない。行持を行動とする宗教である。論理ではなくて実践であり、外界や見てくれの幸福を相手にせぬ自己解放である。それは自我から解放されることによってあらゆる悩みの繋縛から自由にされ、死からも解放されることを教える。西洋のように自己の周囲に壮麗なものを組み立てるのではなくて、自己内観のギリギリの極限において「安心」を得る解脱の道であり、日常の一瞬一瞬に永遠を把握し、迷いの中に悟りを得ようとする迷悟不二、修証一如の生の実現である。≫と、 また ≪「摩訶止観」十巻こそは最古の禅書であり、且つ最も組織的な禅の思想と実践の解説書なのである。≫と。「法華経」の真髄おもかたっておられる。
わたくしは今年一年、何をして来たのか。相変わらず迷いの一年であった。悲しい事が多い一年でも有った。来年はもう少し増しな生き方をと反省の大晦日の今日である。
※ 校本宮沢賢治全集 第十四巻 1139頁 (資料) 「知己の詩人の便り四通」中の一人として、中西悟堂の文があります。

東陽堂 古書目録 70号 平成23年〇秋号より
寺の住職 M 氏から上記「古書目録」をもらってきました。廉価になった「宮澤賢治遺言の国訳妙法蓮華経」です。
余談。何年か前に「宮澤賢治イーハトーブセンター 掲示板」に、「鶴田辰蔵あての国訳妙法蓮華経を入手したが、鶴田とはどのようなお方か」と云うような書き込みが有りました。
わたくしは「御田屋町の鶴田印刷の社長である」むねを書き込んだ記憶が有りますが、彼の弟とは、晩年親しく旅行になど良く行きましが、今は彼等はあの世です。
上記の本はいちじはずいぶん高値でしたが、学校等の図書館等で如何かと思い、此処に書き込んでしまいました。
(この古書 お買い上げなされましたお方・そっとコメントを、内緒にしておきます。
おそらくあなたは本の中毒にかかっていられるでしょう。 いずれこの記事は消去しますが。)
 (写真は後日挿入・東陽堂書店外の物です)
(写真は後日挿入・東陽堂書店外の物です)
加藤完治は、大正四年(1915)年東大農学部の推薦で、大正天皇即位の御大典事業として山形県が自冶講習所をつくった、そこの初代所長になった。農本主義的青年幹部の養成のため全国に先駆けて開設したものである。
また、その後茨城県宍戸町に、「日本国民高等学校」を創設してその校長になり、さらに開拓移民の中心的人物となっていった。列強のアジア植民地化のなかで、日本の近代化と独立を守ることを名目として、第二次世界大戦への過程の中で、国内では解決できない土地所有のありかた、小作制による貧農問題の内部矛盾をかかえたままの農村の被幣や、農民の貧困を、満蒙開拓に、そして後には満蒙青少年義勇兵とその道に進める中心的人物となっていった。農村の次三男が対象であったのである。花巻にほど近い六原農場(道場)もそのひとつであった。
大戦中の桜にあった「兵舎」には、乙種工業国民学校(正式の名前は忘れたが)が創られた。にがい思い出である。
加藤完治の実践は、賢治の理想としたフォルケ・ホイスコーレとは程遠い学校であったと思う。
最新菊の作り方 石井勇義著 誠文堂 昭和四年十一月五日 発行
わが国のほまれと云へるこの花はとつくにまでもわたり行くらん
上記は賢治作の「東北菊花品評会」の一句です。
小沢俊郎氏の「新集 宮沢賢治全集」語註によると、『東北菊花品評会 昭和六年十一月、花城小学校(一部略)で開催。花巻の菊花同好会「秋香会」主催』と解説されております。
同じ「新集」本の解説によると「句作品中心をなしているのは、昭和七年十月に花巻で開かれた菊花品評会 に寄せるために作られたといわれる(入賞花に吊るす短冊の句をたのまれたのである由)一連の作品」との事(378頁)なそうです。まあ六年でも七年でも良いのですが、こちらは直接賢治とは関係が無い本ですが、気になる本があります。
 実験花卉園芸 発行所 裳華房 (写真は下巻724~725頁)
実験花卉園芸 発行所 裳華房 (写真は下巻724~725頁)
この本の「来歴」に、「日本に菊がはいってきたのは、三八五年(仁徳天皇七三)は、百済が菊種を貢納してからのことである」とされていますが、これは疑わしいのです。八世紀の万葉集には、多くの花がうたわれているが、キクについては一首もないそうです。四世紀に宮廷にキクが入ったのなら、万葉にうたわれていないはずはない。キクは奈良時代以後、平安期であろうということです。源氏物語になりますとキクはナデシコについで、多いとの事です。実験花卉園芸の書はおそらく賢治も使用されたであろうかと思われる本ですが、園芸実用書としては良書ですが、来歴については、いささか疑問な点がみられます。(この書は最近賢治研究者の論考にも引用されていました)
ところで、キクは天皇家のシンボルとなったのは、近代以後の事で、維新当時、菊は栄える葵は枯るとうたわれていた。天皇家の紋章になったのは後鳥羽上皇の1185年の事だそうですが、近代では明治二年(1869)の太政官布告でさだめられてからである。
このクリサンセマム(黄金色の花)も、昔から町民や農民に愛されてきた花ですが、わたくしは大輪の菊や菊人形のような人工的な菊ではなく、野におけるキクの花が好きです。また、農家の庭先には、どこの家にも植えられていたキクは、秋の日差しに映えて眩しいほどであった。
追記
昭和五年十月二十四日 花巻温泉主催「県下菊花品評会」審査員依頼状がきたが、病中を理由に断り、出品者として応じる。 堀尾青史 年譜 宮沢賢治伝より
※ 「校本 全集13巻」596~597頁の校異の解説参照されたい。