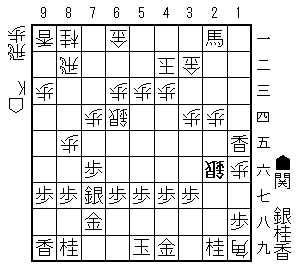戦いはこれからだ―人間的魅力の研究 (ノン・ポシェット)
1999年出版、米長先生と藤沢秀行(しゅうこう)先生の対談です。
この本が、というよりは秀行先生の生涯が面白すぎます。ぜひ読んでください。米長先生も遊び暮らした部分はありますが、秀行先生のほうが桁違いに破天荒です。
将棋は終盤になるほど複雑になるので(といっても収束してしまうのが不思議ですが)、読みの力がものをいいます。囲碁はだんだん手の可能性が少なくなっていく、序中盤の手の可能性が大きいので、感覚のほうがものを言います。というのは子供のころ囲碁のルールを覚えただけの私が言うので的がずれているかもしれません。でもそういうものでしょう。男女のレベルの差が少ないのと詰碁の世界が詰め将棋より狭いこと、年配になっても活躍できるのはそういうことかと。昔の棋士のほうがレベルが高かったという話も聞きます。
まあそれはともかく66歳で囲碁のタイトルを取った秀行先生に50歳名人の米長先生が話を聞き、まだまだ修行だというのですから、楽しいのです。
筋とは関係ないのですが、米長先生の名人を取ったころ、NTT株を安値と思って買って破産しそうだったみたいです。それくらいのことがないと悲願はかなわないのでしょうか?
本を読んで記録しておくべきことは2つ。
勝つための勉強ではなく強くなる勉強をする。自分で苦心して悩んで考え抜くこと。
味や含みがあるのが本来の将棋や囲碁
最初に読んだときは素直に感心していたのですが、その後の米長先生がふるいませんでした。囲碁はともかく将棋は解明されつつある気がします。論理思考の積み重ねによって。年を取ると盤面のイメージを頭の中で考えるのが難しくなってくるので、それをカバーする力をつけるべき、それが直感やそれに関係するものではないかと考えています。
1999年出版、米長先生と藤沢秀行(しゅうこう)先生の対談です。
この本が、というよりは秀行先生の生涯が面白すぎます。ぜひ読んでください。米長先生も遊び暮らした部分はありますが、秀行先生のほうが桁違いに破天荒です。
将棋は終盤になるほど複雑になるので(といっても収束してしまうのが不思議ですが)、読みの力がものをいいます。囲碁はだんだん手の可能性が少なくなっていく、序中盤の手の可能性が大きいので、感覚のほうがものを言います。というのは子供のころ囲碁のルールを覚えただけの私が言うので的がずれているかもしれません。でもそういうものでしょう。男女のレベルの差が少ないのと詰碁の世界が詰め将棋より狭いこと、年配になっても活躍できるのはそういうことかと。昔の棋士のほうがレベルが高かったという話も聞きます。
まあそれはともかく66歳で囲碁のタイトルを取った秀行先生に50歳名人の米長先生が話を聞き、まだまだ修行だというのですから、楽しいのです。
筋とは関係ないのですが、米長先生の名人を取ったころ、NTT株を安値と思って買って破産しそうだったみたいです。それくらいのことがないと悲願はかなわないのでしょうか?
本を読んで記録しておくべきことは2つ。
勝つための勉強ではなく強くなる勉強をする。自分で苦心して悩んで考え抜くこと。
味や含みがあるのが本来の将棋や囲碁
最初に読んだときは素直に感心していたのですが、その後の米長先生がふるいませんでした。囲碁はともかく将棋は解明されつつある気がします。論理思考の積み重ねによって。年を取ると盤面のイメージを頭の中で考えるのが難しくなってくるので、それをカバーする力をつけるべき、それが直感やそれに関係するものではないかと考えています。