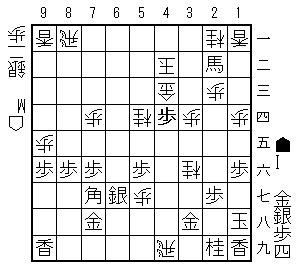大局を観る―米長流・将棋と人生 (NHK人間講座)
2004年10~11月に放送されたNHKの人間講座のテキストです。
TV放送は1回くらい見て、見逃したのでテキストを買って安心して、積読になっていました。
他の本で読んだ話は何度読んでも面白いのですが、引退してからは老人臭くなったなあと思います。残念。
直感や第一感がどこからくるのかうまく説明できない、とあるのですが、
これは記憶の中から似たような局面あるいは部分図を検索してくる能力です。経験を積めばストックが増えて強化されます。上達法則のシリーズで何度も書いていますね。
デジタルとアナログ(の比喩的な)話。コンピュータはデジタルで序盤終盤が強く、アナログな中盤の力で対抗する。アナログな教育をすべきである。
これについては先生とは別の考えを持っています。
将棋を符号で考えるのがデジタル、局面のイメージで考えるのがアナログ。人間の脳はアナログで考えられるけれど、コンピュータはデジタルで考える。
論理思考というか、詰将棋ならデジタル処理のほうが速い。序盤のデータはコンピュータに覚えさせて検索することもできる。人間の脳の力も素晴らしく、思い出す時にエラーがあるかもしれないがイメージ検索の能力はすごい。
コンピュータ将棋はアナログ的な局面の評価をプログラマーが改善することで進歩してきたが、駒の位置関係について、プロの棋譜から自動学習する仕組みをができて飛躍的につよくなった。総合力で多くのプロを上回るようになってきた。アナログ的な分析ができるようになってきたということ。
人間にしかできないのは、創造分野。少しあいまいな検索でいろいろ出てきた結果を組み合わせたり(足し算)、余計なところを削ったり入れ替えたり(引き算)、部分的に増やしてみたり強化したり(掛け算)、別の機能をやらせてみるとか(割り算)、あるいは思いもかけない変化をさせてみるとか、単純な検索だけでないアイデアも生み出せる。
まとまってないけれどそんなことを考えています。どうやったら将棋が強くなれるか、なんて考えるのはとてもいいことなんだ、と感じています。
2004年10~11月に放送されたNHKの人間講座のテキストです。
TV放送は1回くらい見て、見逃したのでテキストを買って安心して、積読になっていました。
他の本で読んだ話は何度読んでも面白いのですが、引退してからは老人臭くなったなあと思います。残念。
直感や第一感がどこからくるのかうまく説明できない、とあるのですが、
これは記憶の中から似たような局面あるいは部分図を検索してくる能力です。経験を積めばストックが増えて強化されます。上達法則のシリーズで何度も書いていますね。
デジタルとアナログ(の比喩的な)話。コンピュータはデジタルで序盤終盤が強く、アナログな中盤の力で対抗する。アナログな教育をすべきである。
これについては先生とは別の考えを持っています。
将棋を符号で考えるのがデジタル、局面のイメージで考えるのがアナログ。人間の脳はアナログで考えられるけれど、コンピュータはデジタルで考える。
論理思考というか、詰将棋ならデジタル処理のほうが速い。序盤のデータはコンピュータに覚えさせて検索することもできる。人間の脳の力も素晴らしく、思い出す時にエラーがあるかもしれないがイメージ検索の能力はすごい。
コンピュータ将棋はアナログ的な局面の評価をプログラマーが改善することで進歩してきたが、駒の位置関係について、プロの棋譜から自動学習する仕組みをができて飛躍的につよくなった。総合力で多くのプロを上回るようになってきた。アナログ的な分析ができるようになってきたということ。
人間にしかできないのは、創造分野。少しあいまいな検索でいろいろ出てきた結果を組み合わせたり(足し算)、余計なところを削ったり入れ替えたり(引き算)、部分的に増やしてみたり強化したり(掛け算)、別の機能をやらせてみるとか(割り算)、あるいは思いもかけない変化をさせてみるとか、単純な検索だけでないアイデアも生み出せる。
まとまってないけれどそんなことを考えています。どうやったら将棋が強くなれるか、なんて考えるのはとてもいいことなんだ、と感じています。