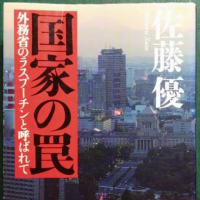友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」より
いくつかかいつまんで、紹介させていただきます。
カテゴリー: WAVE MY FREAK FLAG HIGH
ギターの歴史を変えたジミ・ヘンドリクス作曲の“If 6 was 9”の歌詞の中に出てくる言葉をヒントにしています。
(中略)
この曲は、そういう「違う生き方」を象徴する曲とされています。「異者の旗を振ろう」という意味ですね。
このタイトルのもとで、繁栄のなかの息苦しさを突破する「違う生き方」の可能性、また3.11以降の社会のありようを考える哲学的、宗教的なエセーを綴ろうと思っています。
2018年3月15日投稿
友岡雅弥
日本は、精神病院大国です。
誤解なきように。
「精神病大国」ではなく、「精神病院大国」です。
世界の精神科病床は185万床、
日本の精神科病床は、35万(精神科病院数:1700)
世界の精神科病床の、約5~6分の1が日本にあります。
日本では、精神病院からの治癒退院は一ヶ月で200人。
対して、死亡退院は、一ヶ月で1200人。
治って退院する人よりも、死んで退院する人が6倍多いのです。
先進国(この言葉いやですが)、在院日数は20日前後、
日本では1年以上入院者が20万人以上(10年以上が9万人、20年以上が5万人)。
イタリアでは、精神病院自体を廃止しました。地域で普通に暮らしています。
日本では、身体を拘束されている患者数は、約5000人とも言われています。
「わが邦十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この邦に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」(呉秀三 「精神病者私宅監置の実況」)
という、精神医療黎明期の状況は、日本には、今でも残ってます。
「異常」「普通じゃない」という言葉は、精神疾患のかたに対してではなく、私たちの社会に対して、使われることばではないでしょうか?
さて、ふるい京都の言い回しに「岩倉に行く」というのがありまして、それは、精神を病んで、岩倉の里に行くということでした。
今でも、岩倉には、複数の精神病院があり、しかも開放病棟などもあり、日本の閉鎖的な精神病院のなかでは、先進的な試みをしています。
もともとは、眼病に霊験あたらかな観音があり、眼病を始めとする病者が、そこに送られた。
今でも「目なし橋」というのがあります。観光地として有名な岩倉実相院の手前数百メートルのところにある、
小さな赤い橋です。
「目なし橋」。すごい差別的な名前ですね。
もちろん、これには諸説あり、ここより西に、目の不自由なかたがたが打ち捨てられ、東にはもう戻れなかったという意味。
また、そういうかたがたを救うために、地蔵菩薩が現れて、自分の目をあげたという由来もあります。
どちらにしても、共通するのは、身体的な障がいのある人々が、この橋辺りにいたということです。
精神的な障がいや身体的な障がい、そしておそらくハンセン病の人々も、この橋の「向う」に、あるいは自主的に向い、もしくは「棄て」られました。
さて、岩倉ですが、すべてがすべて非道な打ち捨てであったかというと、そうではありません。
ここに、かつて大雲寺という寺があり、万病に効くというわき水があり、その霊験をたのんで、精神的な病にかかった貴族や皇族が、療養を行ったという例もあります。
そして、その水の霊験をたのんで、全国から精神障がい、身体障がい者がここに移り住んだ、または、病み棄てられたのです。
また、滝にうたれるということが、「精神病にいい」と言われていて、岩倉には、その滝がいまでも、ある精神病院の裏にあります。
今でも全国に残る精神科の病院のいくつかは、身体的修法をかなり重視した修験道や日蓮系にその源流をもっています。
大阪の泉州地域のある精神病院も、その滝療法をルーツとしています。
ちなみに、大阪泉州で有名な七山病院も、浄土真宗の僧医・本多左内が、宗教的な慈悲心による看護をおこなった爽神堂が元です。
岡崎市の有名な羽栗病院も、光明山順因寺が起源です。東京の慈雲堂病院は、日蓮系の田辺日草が起こした石神井慈療院から始まってます。
さて、江戸時代には、病気平癒を願い多くの人々が岩倉にやってきました。その人たちは、大雲寺で、「参籠」、つまり宿泊しつつ祈願をしていたわけですが、やがて、周囲に、「茶屋」と呼ばれる宿泊施設が出来ています。当然、心身の不自由な人たちの宿泊の世話は、身体のケアも必要とするわけですから、介護・保養も行っていくわけです。
日本で最初の公立の精神病院である、京都癲狂病院ができたのは、1875年(明治8年)。
公的施設ができたから、と、何度も、茶屋の廃止令がでますが、何度も復活します。
なぜならば、岩倉の茶屋は、茶屋の従業員もですが、「公人」と呼ばれる地域の人たちも、病者のケアをしてくれ、「隔離された病院」ではなく、地域社会のなかで、暮らすことができたからです。今の言葉でいうと「共助」です。
もちろん、茶屋はただではないので、商売と言えば商売なのですが、一緒に農作業をしたり、かなり家族的な雰囲気の共同体ができていったのです。
いまでいうグループホームに類似しています。
上に述べたように、1884年(明治17年)岩倉癩狂院(後に、岩倉精神病院、岩倉病院、いわくら病院)という病院ができ、1901年(明治34年)、京都府立医学校(現・京都府立医科大学)の土屋榮吉が院長に就任し、ここを中核医療機関として、周辺の宿屋が、家庭的なサービスや作業療法を提供するという、画期的なコロニー方式の「精神医療村」ができたのです。
この「岩倉コロニー」は、第二次大戦の終戦と共に無くなりました。
だいたい、宿屋では2~4人の患者に対して、1人の看護人がいたそうですから、これは今の精神医療現場と比べて、医学的には未熟であったにせよ、手厚いケアができたと推定されます。
明治の当初は、当時の排仏毀釈の流れのなかで、運営主体が寺であることだけで、神道国家を支持する人たちからの、心ない非難もありました。
また、現代的な目でみれば、体(てい)のいい隔離ではないか、とかいろいろな批判もあります。が、きめ細かいケアを行っていたことは、間違いないでしょう。近隣の人と庭仕事や畑仕事をするという、作業療法的なものもありました。
ちなみに、今、いわくら病院は、「開放病棟の病院」として知られています。つまり、患者さんが、自由に病棟を出入りできるのです。90%近い開放割合を誇ります。
社会が遺棄した、ハンセン病患者や各種の障がい者。
しかし、その人たちが遺棄された場所で暮らしていく時、そこには、その場所でそれからも続く人生と、ともに生きた人たちがいたということを忘れてはいけないと思います。
社会から遺棄されながらも、必死に生きる人たちの作り上げた場所は、きっと、他の人にとっても生きやすい場所であると、思えるのです。
【解説】
今、いわくら病院は、「開放病棟の病院」として知られています。つまり、患者さんが、自由に病棟を出入りできるのです。90%近い開放割合を誇ります。
社会が遺棄した、ハンセン病患者や各種の障がい者。
しかし、その人たちが遺棄された場所で暮らしていく時、そこには、その場所でそれからも続く人生と、ともに生きた人たちがいたということを忘れてはいけないと思います。
社会から遺棄されながらも、必死に生きる人たちの作り上げた場所は、きっと、他の人にとっても生きやすい場所であると、思えるのです。
勉強になります。
友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」はお勧めです。
獅子風蓮