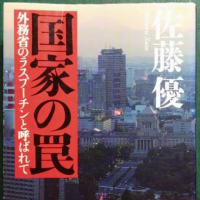友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」より
いくつかかいつまんで、紹介させていただきます。
カテゴリー: WAVE MY FREAK FLAG HIGH
ギターの歴史を変えたジミ・ヘンドリクス作曲の“If 6 was 9”の歌詞の中に出てくる言葉をヒントにしています。
(中略)
この曲は、そういう「違う生き方」を象徴する曲とされています。「異者の旗を振ろう」という意味ですね。
このタイトルのもとで、繁栄のなかの息苦しさを突破する「違う生き方」の可能性、また3.11以降の社会のありようを考える哲学的、宗教的なエセーを綴ろうと思っています。
2018年3月22日投稿
友岡雅弥

大阪市・浪速区稲荷町三丁目に赤手拭稲荷があります。大阪市内の代表的稲荷で、落語のマクラによく出てきて、江戸落語の「ぞろぞろ」のルーツにあたる上方落語(演者はほとんどいない)の舞台がここです。観光名所とかではないので、京都の伏見稲荷みたいに、初詣客でにぎわう、という類いのいなりさんではありません。
ちなみに、「稲荷」はキツネではありません。キツネは稲荷大明神の「お遣わし」、つまり従者です。
ただし、この赤手拭稲荷、稲荷といっても、稲荷明神が祭られているわけでなく、豊受大神、宇受売神、大山祗命、猿田彦大神、倉稲魂命など、漁業や、芸能などの、差別された職業、「賤業」とされた仕事の神様が祭られています。
『浪速区史』に「伝によれば、慶長年間中堤の中央に一大老松があって浪除松といわれ、その樹下に祀られた神祠であるところから松の稲荷と称したが、不思議の霊験を蒙ったものが、ここに集り神社を建て、紅染めの手拭を祠前に献じたのが恒例になって赤手拭稲荷というようになった」とあります。
でも、実は、それは俗説であり、定説は違うみたいなのです。
ここは、昔々、中世以来世界に開かれていた堺の港からの船の船着き場で、三本の松が目印として立っており、その下に、祠(ほこら)がありました。港の、人足さん、 仲仕さんたちは、汗で汚れた手拭いを、松にかけていた(干していたのでしょう)。
だから、「汚れた手拭い」=「垢手拭い」、働く人たちのしるし。いつしか、その労働をとうとび、その手拭いが、「難を除ける」ちからがあるもの、と考えられるようになったのです。
それが、いつしか、労働=「垢の手拭い」を“とうとぶ”のではなく、霊験あらたかな神様に、「赤い手拭い」を奉納するというように、変化したわけです。
ご存知のように、例えば、「えびす」は、「戎」「胡」「夷」「蛭子」などと書くように(後の時代に、「恵美須」や「恵比寿」と当て字で書かれるようになった)、「異国の人」「障がい者」を示す言葉です。
上方落語で、「えべっさんは、足が悪いから、えべっさんに詣るときは、正面からやのうて、裏から」とあるように、障がいのある人を、神のような存在として、大切にしたのです。
その歴史が、いつの間にか、商売繁盛の神となってしまったわけです。
苛酷な労働をする人、外国人、障がい者を、大切にする文化を、取り戻さねばなりませんね。
タゴールの詩の一節を思いだしますね。
そのような詠唱を讃歌を数珠のつまぐりをやめるのだ。
扉をすっかり閉ざした寺院のこんな寂しい暗い片隅で、おまえは誰を拝んでいるのか?
おまえの目を開けるのだ、そして見るがよい。
おまえの前に神様がいまさぬのを。
農夫が固い土を耕しているところ、道路人夫が石を砕いているところ、そこに神はいたもう。
神は照る日も雨の日も働く者とともにいて、その衣は塵にまみれている。おまえの法衣を脱ぎ捨て、あのかたにならって埃っぽい大地の上に降りて来るのだ!
タゴール『ギータンジャリ』(森本達雄訳)
画像は、赤手拭稲荷境内の奉納幟。この地域にゆかりのある会社がずらり
働く人の祈りの場なんですね。
(稲のしるしは、稲荷の象徴です)
【解説】
冒頭の赤手拭稲荷の写真は、友岡さんの記事の冒頭の写真そのままです。
創価学会に身を置いたことのある人がこういう写真を見るとぎょっとしますね。
友岡さんは、開明的な人なので平気なのでしょう。
私は、鳥居や神社仏閣を拝むことはしませんが、その歴史的な物語は尊重します。
ですから、このエッセイも大丈夫です。
友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」はお勧めです。
獅子風蓮