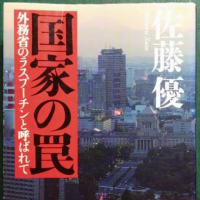友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」より
いくつかかいつまんで、紹介させていただきます。
カテゴリー: WAVE MY FREAK FLAG HIGH
ギターの歴史を変えたジミ・ヘンドリクス作曲の“If 6 was 9”の歌詞の中に出てくる言葉をヒントにしています。
(中略)
この曲は、そういう「違う生き方」を象徴する曲とされています。「異者の旗を振ろう」という意味ですね。
このタイトルのもとで、繁栄のなかの息苦しさを突破する「違う生き方」の可能性、また3.11以降の社会のありようを考える哲学的、宗教的なエセーを綴ろうと思っています。
freak13 - 安楽行品にまつわる問題/如説修行抄 1/2
2018年4月1日投稿
友岡雅弥
『法華経』安楽行品第十四は、その再説(もう一度重ねて説くこと)ともされる普賢菩薩勧発品(普賢品)第二十八とともに、『法華経』のなかでは、若干異質で注意を要する章です。
安楽行品には、他の宗教を説くものに近づいてはならない、文章家や詩人に近づいてならない、放浪の芸人たちに近づいてはならない、格闘家には近づいてはならない、 身に化粧をしいろいろな芸をする人には近づいてはならない、チャンダーラやマウシュティカなど低いカーストのものには近づいてはならない、豚や羊や鳥や犬を飼うもの、漁師など、悪業を積むものには近づいてならない、トランスジェンダーの人には近づいてはならない、と述べられます。
普賢品には、『法華経』を受持するものは、屠殺を仕事とするもの、豚や羊や鳥や犬を飼うもの、猟師(漁師も含む)売春業者に近づいてはいけない、と述べられます。
そして、『法華経』を過去世に誹謗したものは、ハンセン病となり、障がい者として、病人として生まれるとまで述べられ、仏教経典では、他に類例を見ないほどの差別的な言葉が並びます。
そして、そのような人を避けて、「立派な座」をしつらえて、おごそかに法を説いたら、現世も後世も、仏に守られて、ハッピー&ラッキーと説くわけです。
安楽行品の「修行者」の行うべきこと、行ってはならないことについては、いわゆる「小乗仏教」――
*今、「小乗仏教」という言葉は差別語なので、使ってはならない言葉となっています。
実際、ビルマなどは、軍事独裁政権に対して、先頭に立って、虐殺・拷問に負けずにリーダーとして闘ったのは、いわゆる「小乗仏教」の僧侶たち。
また、英語で、エンゲージド・ブディズム(社会活動を行う仏教)の代表として挙げられる世界の諸宗派の多くが、東南アジア、南アジアのいわゆる「小乗仏教」です。
逆に、東アジアのいわゆる「大乗仏教」が、仏に祈って、個人の現世利益を得ることを目的とすることが多いという、現実の逆転状態、つまり、いわゆる「小乗仏教」が大乗的で、いわゆる「大乗仏教」が小乗的になっている現状から考えて、「小乗」「大乗」の区別の無効さが、言われています。
さて、話を戻しますと、
安楽行品の「修行者」の行うべきこと、行ってはならないことのリストはいわゆる「小乗仏教」の、「清浄道論」「分別論」などと、そっくりです。
また、Śikṣāsamuccayaなどの経典集のなかに引用されている『法華経』の該当部分との比較を通じて、どうも、この安楽行品の、「近づいてはならない」の下りは、後世の付加であるということが、明らかになりつつあります。
そのうえ、チャンダーラやマウシュティカなど低いカーストのものには近づいてはならない、という下りは、そこにすらないものであり、仏教自体の存立基盤を犯すほどの差別的なものです。
また、日本において、他国に類例を見ない、ハンセン病差別が行われた根拠の一つが、『法華経』普賢品であり、この1節を携えて、禅宗や浄土真宗など、多くの宗派が、各療養所を回り、「君たちがここにいるのは、過去世に悪いことをしたからだ」と訓戒して回ったことは、よく知られています。
そして、「らい予防法」が約20年前に廃止になったとき、多くの宗派は、そのことについての、正式謝罪文を出しております。
でも、仏教経典が日本に入ってきたとき、また日蓮大聖人の時代には、今のような文献学的な考察も、また各地の写本の比較研究もできかったわけですから、全体を仏の説法として考えざるを得なかった。
だから、日蓮大聖人は、「摂受・折伏」という概念で、安楽行品の、「説かんでもいい人には説かんでええよ」というイージーゴーイングな思想を拒否するわけです。
「物怪なり」という強い言葉が、単に「摂受・折伏」という修行法の違いではなく、大聖人にとって、安楽行品がいかに、違和感があったかの証左と言えます。
【解説】
安楽行品には、他の宗教を説くものに近づいてはならない、文章家や詩人に近づいてならない、放浪の芸人たちに近づいてはならない、格闘家には近づいてはならない、 身に化粧をしいろいろな芸をする人には近づいてはならない、チャンダーラやマウシュティカなど低いカーストのものには近づいてはならない、豚や羊や鳥や犬を飼うもの、漁師など、悪業を積むものには近づいてならない、トランスジェンダーの人には近づいてはならない、と述べられます。
普賢品には、『法華経』を受持するものは、屠殺を仕事とするもの、豚や羊や鳥や犬を飼うもの、猟師(漁師も含む)売春業者に近づいてはいけない、と述べられます。
そして、『法華経』を過去世に誹謗したものは、ハンセン病となり、障がい者として、病人として生まれるとまで述べられ、仏教経典では、他に類例を見ないほどの差別的な言葉が並びます。
確かに、全ての人間の中に仏性を認める法華経の本質からはかけ離れた内容ですね。
法華経の成立に関しては、以前この本で勉強しました。
植木雅俊『法華経とは何か その思想と背景』(中央公論新社、2020.11)
獅子風蓮の夏空ブログで、言及しています。
気楽非活さんの言うことは全て正しいか? その7)後に加えられた第三類(2024-01-25)
差別的な箇所があるということで友岡さんが嫌っていた「普賢菩薩勧発品」は、後に加えられた第三類に属するのですね。
もう「普賢菩薩勧発品」は法華経から排除したいですね。
安楽行品の、「近づいてはならない」の下りは、後世の付加であるということが、明らかになりつつあります。
なあんだ、この部分も後世の付加なんだ。
まとめて、法華経から排除しちゃいましょう。
ただ安楽行品の全般の内容についての理解は、私にはまだできていません。
日蓮大聖人が安楽行品の内容に批判的であったかどうかも、不勉強なので知りませんでした。
勉強してみたいと思います。
友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」はお勧めです。
獅子風蓮