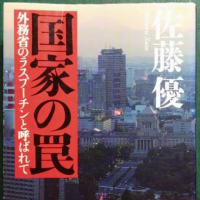友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」より
いくつかかいつまんで、紹介させていただきます。
カテゴリー: WAVE MY FREAK FLAG HIGH
ギターの歴史を変えたジミ・ヘンドリクス作曲の“If 6 was 9”の歌詞の中に出てくる言葉をヒントにしています。
(中略)
この曲は、そういう「違う生き方」を象徴する曲とされています。「異者の旗を振ろう」という意味ですね。
このタイトルのもとで、繁栄のなかの息苦しさを突破する「違う生き方」の可能性、また3.11以降の社会のありようを考える哲学的、宗教的なエセーを綴ろうと思っています。
2018年4月5日投稿
友岡雅弥
宗教的典籍の言葉は、作られたとき、どのような意味を持っていたかをしることは、とても大事です。
宗教的言葉でなくても、例えば、「影」。これは、「暗いところ」という意味ではなく、「光」という意味ですね。「月影さやかに」というのは、「月の光がくっきりと」という意味です。
日蓮が使う「主師親」ということば。
あれも、日蓮の言葉ではなくて、当時、確立期にあった封建道徳で、
「主」――世俗的権力者(家来とは、ご恩と奉公の関係で結ばれた)、
「師」――世俗的権力者が任命した宗教的権威者、
そして、
「親」――土地相続を媒介とし、一族郎党では、絶対的権力を持っていた家父長。
という、ごっつい権威的な存在だったわけです。
日蓮は、膨大な行数を通じて、それを脱構築していくわけです。つまり、みんなは、こんな権力やそのお友達ばかり尊敬しているけど、ほんとに、尊敬すべきものなのか、と問うていくわけです。
「主師親」は、日蓮の「主張」ではなく、日蓮の「疑問」なのです。
日蓮は「主師親」という言葉を使いながら、「主師親」を否定したわけです。
それで、「私は世間には見捨てられたぼろぼろの地位も名誉もまったくない、存在だけど、人を救おうという誓いに生きてきた」
――と言われるわけです。
俺は偉いぞ、主師親の三徳を持ってるんだ、という自己中心言説ではなく、誰を尊敬すべきか、常に問うて生きていこうという、ラディカルな問いなわけです。
さて、大事なのは、その言葉は、当時、どんな響きを持っていたかです。
たとえば、聖書を例にとります。
「マリアの子イエス」 という表現は、「聖母と神の子の神聖な関係」を表すなどと、伝統的な解釈はなされるのですが、もともとは違います。
「不貞の女から生まれた子は、生涯、(当時、ユダヤ教の伝統であった)父の名ではなく、母の名を以て呼ばれる」ということ。
つまり、「マリアの子イエス」という表現は、「不倫の父無し子イエス!」 という、
生まれながらの宗教的罪、差別的表現であったのです。
他にたとえば、「神は高みより人間の世界を見わたされた」などと、聖書にしょっちゅうでてくる「高み」(ヘブライ語で、???、ギリシャ語訳では、υψόμετροだったか?)
当時、金持ちや普通の市民は、低いところ(簡単にいえば、オアシス)に住んでいて、高いところは、ハンセン病の人、異民族、難民、町を追放になった罪人、ホームレスが住んでいたのです。
だから、???というのは、「立派な天国の御殿から」という意味ではなく、「ホームレスのいるところ、ハンセン病の人たちが追放されたところ、難民キャンプから」という意味なわけです。
立派な神様、立派なイエス様、立派な日蓮大聖人様ではないのです。
ぼろぼろの神、ぼろぼろのイエス、ぼろぼろの日蓮。
だから、立派なのです。
【解説】
「主師親」は、日蓮の「主張」ではなく、日蓮の「疑問」なのです。
日蓮は「主師親」という言葉を使いながら、「主師親」を否定したわけです。
私のこれまでの「主師親」の理解と違っているので、戸惑ってしまいます。
勉強していきたいと思います。
立派な神様、立派なイエス様、立派な日蓮大聖人様ではないのです。
ぼろぼろの神、ぼろぼろのイエス、ぼろぼろの日蓮。
だから、立派なのです。
ここは、賛同します。
友岡雅弥さんのエッセイが読める「すたぽ」はお勧めです。
獅子風蓮