
過去のブログから西部氏関連の二つを改めてアップさせてもらった。古い記事で申し訳ないが、保守政党を今一度考えていただくためのことであり、私自身の戒めの意味も込めてでもある。

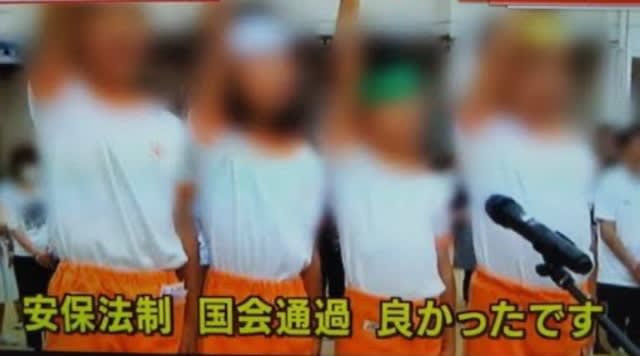

百田尚樹氏は書籍で日本の現状に警鐘を鳴らし徐々に保守層の注目を浴びるようになる。


西部氏の言葉をもう一度引用する。
『主権とは「何ものによっても制限されることのない最高権力」のことであり、そんな凄い権力は、天皇という個人においてであれ、特権階級という少数者においてであれ、国民という多数者においてであれ、所有されてはいけないものだ』
『国民とは、実は、歴史上の総国民のことであったのだ。したがって「国民の意志」なるものはそれら総国民の残した「歴史の知恵」のことである』
『このような存在をさして国民というなら国民主権を謳って一向に構わないし、またこの存在を象徴するものをさして天皇というのなら、天皇主権を憲法に謳ってもよいわけだ。それゆえ、わが憲法の第一条における「天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」という文章は、正しくは次のように読まれるべきなのだ。つまり「天皇の地位は、主権の存する日本的伝統精神に基く」というふうにである。』
『国民とは、実は、歴史上の総国民のことであったのだ。したがって「国民の意志」なるものはそれら総国民の残した「歴史の知恵」のことである』
『このような存在をさして国民というなら国民主権を謳って一向に構わないし、またこの存在を象徴するものをさして天皇というのなら、天皇主権を憲法に謳ってもよいわけだ。それゆえ、わが憲法の第一条における「天皇の地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」という文章は、正しくは次のように読まれるべきなのだ。つまり「天皇の地位は、主権の存する日本的伝統精神に基く」というふうにである。』
天皇は憲法上、大日本帝国憲法から日本国憲法へとトリック的手法で継承されていると判断出来るのである。
紛れもなく総国民の象徴である主権者が天皇なのである。
2008年航空幕僚長であった田母神俊夫氏が「日本は侵略国家だったのか」との政府見解とは真逆の論文を掲載したことで幕僚長を更迭された。

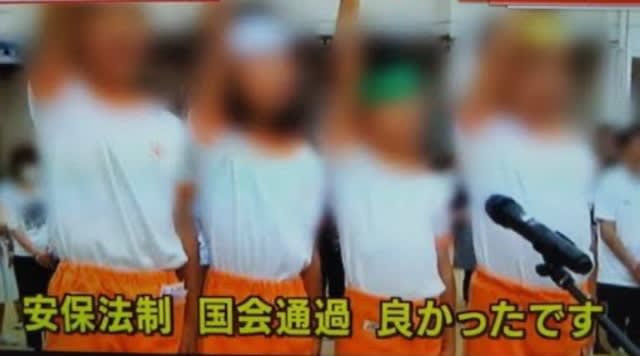
籠池氏の塚本幼稚園は園児に教育勅語や五箇条の御誓文を朗読させ注目を浴びるようになっていく

百田尚樹氏は書籍で日本の現状に警鐘を鳴らし徐々に保守層の注目を浴びるようになる。
昭和天皇が崩御され元号が平成になった頃から左派によるひそかな変革が始まったようにも思える。しかしながらそれは以前からの戦後民主主義、所謂戦後レジームとして捉えるならばその総仕上げでもあるといえる。
それに抗う形で上記三者が登場、注目を浴びたことは歴史の必然とも思える。故安倍氏が掲げた戦後レジームからの脱却ブームを利用して人気を得た所謂"ビジネス保守"である。
この"ビジネス保守"を揶揄して"エセ保守"と呼ぶ風潮があるが、コレを見抜くことは至難の業であってブームの渦中では決して容易ではない。
籠池氏は2億近い学園建設費の詐取、田母神氏は選挙資金横領、百田氏は問題発言と注目と共に失速していく。
特に百田氏は安倍氏が暗殺されてからの絶望感を拭う形と反自民の動きとを連動させたことがその勢いの根幹にあったように思える。
それだけに今回の問題発言は跳ね返りも大きいのであろう。
では取り残された保守に期待する国民は何を思えば良いのだろうか。
戦争という国家存亡の危機を乗り越えた日本人がいったい何を保守すべきかが重要なテーマとなってくる。
そこで一旦俯瞰して靖国神社の歴史を見ていただきたい


靖国神社は当初、国家の為に殉難した人を祀る為に創建された。つまり、彼等の犠牲の上に我々日本人が存在出来ている訳だ。しかも圧倒的多数の殉難者が太平洋戦争である。この事実はたとえ戦後から100年経ようが200年経ようが過去の遺物となろうが、変わらない。
靖国神社は昭和50年代からその存立について横槍が入り始める。首相の参拝、天皇陛下の御親拝、昭和57年閣議決定の平成18年に初回という意味で歴史は浅い全国戦没者追悼式。
加えてこちらに天皇陛下がご臨席となる。昭和61年には中曽根首相が戦犯合祀を理由に参拝を取りやめた。しかし、合祀は昭和53年とその理由としては不可解である。
このように、靖国神社は本来の目的である殉難者の追悼から戦争の象徴として政治問題化してしまった。
戦争への憎悪と国家への嫌悪が靖国神社を本来の目的から問題の対象物へと錯覚させられたままとなっている。
つまり、靖国神社を日本国民は保守し得たのか、ということに甚だ疑問が残る。
陛下の勅使派遣も言い訳の余地の感が否めない。
天皇陛下におかれても、女性宮家創設、女性天皇、はたまた女系天皇までもが議論の課題となっている。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
我々が保守すべきは皇統なのである。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます