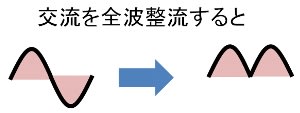2011.2.16 4回目車検 走行距離 33029km (年間2588km)
|
項 目 |
部品代(円) |
技術料(円) |
| 法定24ヶ月点検料金 |
22680 |
|
| 車検1ヶ月前予約 |
-1,050 |
|
| 引き取り納車不要のため割引 |
-2,100 |
|
| 保安基準適合検査 |
8,820 |
|
| ショートパーツ 1 |
1,050 |
|
| 発煙筒(期限切れ交換) 1 |
829 |
|
| ブレーキフルード交換 |
1,365 |
3,307 |
| フロントスタビ(ブーツ切)交換 ロッド、コントロール 2 |
5,418 |
4,200 |
| リヤスタビ(ブーツ切)交換 リンク、スタビコントロール 2 |
8,400 |
3,360 |
| エンジン・マウントラバーNo.2 (亀裂大)交換 |
3,129 |
4,788 |
| Vベルト(ひび割れ小) |
5,774 |
2,362 |
|
|
|
|
| 自賠責 |
24,950 |
|
| 重量税 |
30,000 |
|
| 印紙代 |
1,100 |
|
| 代行料 |
9,345 |
|
| 消費税 |
3,889 |
|
|
|
||
| トータル費用 |
137,727 |
|
このほかに任意保険がかかり、自動車税がかかり、ガソリン代もかかる。
年間3140km走っているメリダ(自転車)と比べて非常に金のかかる乗り物だ。
トンサンは「もう車は手放して、タクシーでもレンタカーでもすれば良い」と言っているのだが。