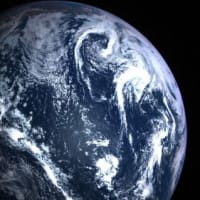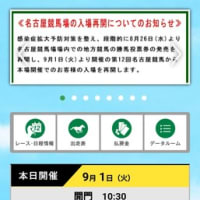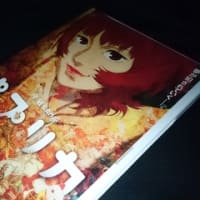追い込み。。。
ああ、この甘美で華麗な美しいこの言葉の響き。。。
馬券を買った馬が後方からただ一頭、前の馬をまとめてぶっこ抜いていくこの快感。
あのディープインパクトをはじめ、中央の芝レースではよく見られるこの光景も、なぜか地方競馬ではなかなか見られません。
これは当たり前といえば当たり前、地方競馬ファンならば常識であります。



競馬の戦法というのは、大まかに分けて4つ。
一般的に考えれば、逃げ、先行、差し、追い込み。
そして、実際の競馬の決まり手といえば、逃げ切り、先行抜け出し、好位差し、まくり差し、追い込みなどがあります。
騎手は、その馬の脚質にあった最適の戦法で勝利に向かってレースに生かします。

ただ、簡単に脚質といっても、馬によって特徴はさまざま。
絶対的なスピード能力が基本となることは間違いないですが、心肺機能の違いなどによるその速い脚が使える時間(距離)の違いや持っている脚力(パワー)の違いによっても脚質は変わってきます。
また、レースの距離や馬場状態などでも騎手の仕掛けどころは違ってくるでしょう。
はたまた、同じ速さの能力を持つ馬でも、瞬発力の優れた馬とそうでない馬では当然戦い方も違いますね。
スタートダッシュが利いてテンに速い先行馬もいれば、終いに切れるスピードがないがために騎手が無理やりでも先行させる馬もいます。
逆に瞬発力がなくても、スピードに乗れば最後まで長く良い脚を使えるので、あえて後ろからの競馬をする馬もいるようです。
また、脚質を考える上で一番厄介なのは、その馬の性格によるもの。。。
行ける脚はあるのに行けない、力は残っているのに我慢できない、など馬の脚質に一番影響しているのは、もしかしたらこの部分なのかも知れません。
騎手が思い通りに乗れないのは、その馬の性格によるところが大きいでしょう。
いかにその馬の性格やその日の気分、また調子などを把握してレースに臨むかも、結果には大きく影響すると言えます。
その馬の良い部分を生かすのも騎手次第ですが、またその馬の足りない部分を補うのも騎手の技量のうちなのでしょう。

しかしながら、レースに勝つための戦法というのは、このような馬の脚質だけで決まるものではありません。
それはレースにはさまざまな展開がありえるからです。
その決められた出走馬におけるレースでの展開予想は、勝つことを考えたならば必須項目。
逃げたい馬が多くいれば、最後の直線は先行馬にとっては苦しくなってしまうような息の入らない流れになり、後ろで脚を溜めていた馬の伸び脚が生かされるレースになるでしょうし、またその逆のレース展開では、先行馬が楽をしていて最後まで我慢できるので、後ろからいくら速い脚を使っても届かないことになってしまいます。
騎手は、出走馬を見渡しながら、また自分の馬の脚質を考えながら、勝つために毎レース、さまざまな戦法を考えているのでしょう。
しかし稀に、超ハイペースでも出走馬全てが脚色がなくなってしまい前の馬が逃げ残ってしまったり、超スローペースでも逆に瞬発力に優れた馬が後ろから持ち味を存分に生かして差し切ってしまうこともあるので、そこが難しいところでもあり面白いところ。
馬券を買うファンもそうですが、騎手にとっても自分の馬の脚色を考えながらレース展開を読むのはなかなか難しいことなのでありましょう。


初めにも述べたように、一般的にダート競馬、特に地方競馬場のレースでは、先行有利と言われます。
これは、地方競馬場の馬場は、深くて力を必要とするダート(砂?)であること。
また、小回りコースで思い切り馬を追える直線が短いことなどが理由として挙げられます。
深い馬場は、確実に馬の最後の切れ味(瞬発力)を殺します。
名古屋競馬では、よほど脚を残して3コーナーに入っても、だいたい終い3ハロン、マイル戦ではA級の馬でもせいぜい37秒台が出ればいいところ。
よほど速いペースで先行した馬でも、勝ち負けするような馬は3ハロン40秒を切るようなタイムでまとめてくることを考えれば、よほど早い段階からまくり始めなければ届かない計算になります。
また、相手は逃げ馬ばかりではなく先行馬をマークする差し馬も虎視眈々と前を狙っていますので、追い込みはよほど展開に恵まれない限りは現実的に決まりにくい戦法と考えて間違いはないでしょう。
中央の芝レースのように、終い3ハロン33秒台。。。なんて脚を馬が使えるような馬場ならば、また違うのでしょうが。。。
また直線が短く、3コーナーから大外をまくっていかなければならないことも決まりにくい理由のひとつ。
距離も相当ロスを余儀なくされてしまいます。
ただ、名古屋競馬でも、下級条件に組み込まれた転入馬やオープンクラスの中央交流戦など、馬の能力があまりにも違う場合には、比較的ペースの振幅が大きい距離の長い1600m以上の距離のレースで追い込みが決まることもあります。
それでも、2コーナーを過ぎて向こう正面の直線を向いた早い段階ですでに仕掛け始めなければ、最後は届かないことになってしまいます。
騎手としては、いかに瞬時にレースの流れを読み、仕掛けどころを間違えないようにしなければならないでしょう。
そういった意味で、名古屋競馬場など地方の競馬場での追い込みは、たとえ流れが向いたレース展開であっても、経験や判断力を要求される非常に難しい戦法と言えるでしょう。
やはり前に行ける馬はなるべく前にいた方が、断然有利にレースが運べることはまず間違いありません。

そんな名古屋競馬で、”追い込みが好き”という面白いジョッキーがいます。
それは、”茜ちゃん”こと山本茜騎手。。。であります。
名古屋競馬のオフィシャルの彼女のプロフィールにも、好きな戦法は”追い込み”と堂々と書いてあります。(笑)
あれがまだ右も左もわからない新人の頃のものであるのだとしても、昨年~今年にかけて行われたレディースジョッキーズシリーズの自己紹介の中でも好きな戦法は”追い込み”と他を憚らず書いてあるからスゴイ。
他のジョッキーのほとんどが、”無難に?”逃げ、先行を選んでいるにもかかわらず、、、です。
少なくとも、すでに新人であれだけ多くの勝ち星を重ねているのですから、地方競馬で先行有利なことは当然理解しているはずです。
まあそれでも、”好き”であることと、実際に”勝つ”こととは違うでしょうし(実際レースでは先行して勝ち星を重ねています)、一概には言えませんが、それでもこだわりは十分に感じられます。
それで思い出すのが、かつて中央で活躍した吉永正人騎手。
あのミスターシービーを3冠に導いた、追い込み専門(ってわけでもないでしょうが(笑))の稀代の名物ジョッキーです。(私はまだ弱冠高校生でした。。。)
彼の競馬は、大体いつも離れた最後方から。
彼曰く、「強い馬に乗って先行したいのはやまやまだけれど、いつも少し足りない馬ばかりに乗っていたから、勝つためにはあの位置になってしまうんだ。。。」と。
深すぎて、いまだに私にはその意味がよくわかりませんが。(笑)
ただ思うのは、彼が騎手として馬のことを考え、ただ勝つことでけでなく、彼なりの騎手としての哲学のようなものが何かあったということなのでしょう。
しかしながら少なくとも、彼が時代のトップジョッキーで無かったことだけは、歴史が証明していますが。。。(笑)
それでも、彼が時代の役者であったことは確かです。
そんなこんなで山本茜騎手。
今回、厩舎を移籍するということです。
仕事なのか、そうでないのか?
何がどうなってそういうことになってしまったのかは、私には全く知る由もありません。
何となくそれがいい話ばかりとは感じられないのも実際のところなのですが。。。
ただ、これからのジョッキーとしての彼女がさらに一層楽しみであることも確かです。
一風変わった新しい思考と存在感を持った山本茜という騎手。
新しい環境の中、今後どんな騎乗を見せてくれるのか?
どこまで勝ちにこだわっていけるのか?
どこまで自分にこだわっていけるのか?
それは馬券以上に、ドンコシンドローマーの興味を惹くことなのであります。
そこだぁ!追い込め~!茜ちゃん!!
なんちって。。。(笑)

とはいえ、やっぱり地方競馬で追い込みの名手なんてあまり聞いたことないなぁ。
大井限定の的場文男騎手とか?
あれほどのジョッキーだけに、追い込みオンリーってわけじゃないけど。。。
やはり、まずちゃんと馬をしっかり追えないとね。
そういえば、笠松に期間限定で来ている花本騎手って上手いと思う。
ステッキはあまり入れないけれど、ちゃんと馬は伸びてくる。。。
あれもやはり、騎乗技術なんだろうなぁ・・・・・。
それでは、また。