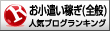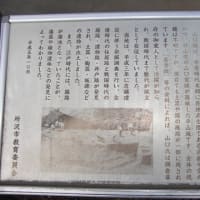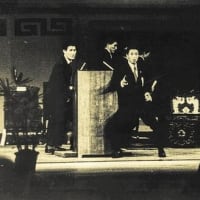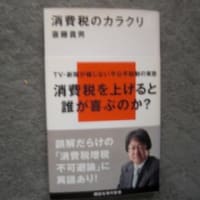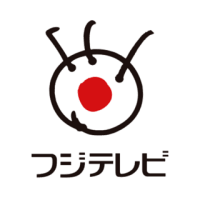<去年10月に書いた以下の記事を、一部修正して復刻します。>
安保法・戦争法への政治闘争を見ていると、日本では完全に“ガンジー的非暴力・不服従運動”が定着したと言えよう。何を今さらそんなことを言うのかと思われるだろうが、かつての60年安保(1960年)、70年安保(1970年)の闘争を体験してきた筆者にとっては、21世紀の日本の政治闘争が非暴力・不服従型になってきたと思えるのだ。
20世紀はレーニンや毛沢東らの「暴力革命論」が主流であった。日本でもその傾向が強かったが、70年安保闘争後に、一般市民や社会から嫌われ衰退していったと思う。日本共産党も戦後まもなく武装闘争方針を取ったことがあるが、今では完全に平和主義、議会主義である。
このように、過激な暴力的左翼運動は姿を消したのだろうか。多分そうだと思う。60年安保や70年安保の時のような、全学連の過激な闘争や全共闘運動は影を潜めている。代わりに平和的な秩序正しいデモ行進、集会などがほとんどだ。全学連の過激派はかつてこれを「お焼香デモ」などと皮肉ったが、今では暴力は“テロ”だけになったのだろう。
暴力革命は19世紀から20世紀にかけて全盛を誇った。しかし、社会が発達し文明が高度化すると、それは廃れたきたのだと思う。かつて、ガンジー的な非暴力運動はごく一部だったが、アメリカの公民権運動でもマルコム・Xの過激な闘争から、キング牧師の非暴力主義が主流になるなど変化していったのだ。
21世紀に入ると、その傾向はさらに強まる。暴動は相変わらず多くテロもよく起きるが、それらは主に発展途上国や紛争地帯で見られるもので、先進国では組織立ったデモやストライキが多い。ということは、暴力的手段を使わずに平和的、道理的な手法に移ってきたということだ。また、その方が一般の支持を受けやすいことになる。
それと同時に、国家権力側の対応も柔軟で利口になってきたと思う。残酷な血だらけの弾圧は、かえって憎悪と敵意を煽るだけだ。こうなると、権力側も抵抗する民衆側も“我慢比べ”のような形になり、忍耐強い方が勝利を収めるケースが増えてきたのではないか。これを言葉を変えれば、民主主義が成熟してきたとも言えよう。
つまり、高度な民主主義国家では革命や暴動、テロといったものは廃れ、代わりに非暴力的な手法が定着したのである。こういう国はもちろん「法治国家」だから、法廷闘争が盛んになる。また「違憲訴訟」も活発になる。一方、権力側は法治国家を逆手に取って、憲法解釈を勝手に変更することがあるのだ。
昨年7月、集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことなどはその好例だ。これは国家権力が一方的に決めたもので、目に見える暴力ではないものの、目に見えない“暴力的措置”だったと言えよう。目に見えないから、一般には平和的な手段による変更と受け取られた。しかし、これは暴力以上の大変な劇的措置だったのだ。
つまり、21世紀の今日(文明国家に限る)では、暴力の使用は極めて拙劣な手段だと受け取られ、「非暴力」が最上の手段と見られるようになったのだ。これは権力側にも抵抗する民衆側にも言えることだ。したがって単純な暴力ではなく、策略や陰謀、戦略などが重視される。つまり、知的な闘争が主流になったのだ。
私は安保法・戦争法の成立に際し、その反対闘争の手段として何度も野党議員の「総辞職」を訴えた。これはもちろん暴力的手段ではない。あくまでも非暴力で平和的、合法的な抵抗手段だ。ガンジーの非暴力・不服従の精神に通じるものがあると信じる。その代わり粘り強く、忍耐強く戦わなければならない。
以上、極めて理屈っぽい文章になってしまった。その点はお詫びするが、私の意図する趣旨は分かってもらえたと信じる。重ねてお詫びしたい。