
喉が詰まるほどでまず話を持ち出すのも苦しかった。<o:p></o:p>
「子供は?」<o:p></o:p>
「あ、息子が一人、娘が一人。」<o:p></o:p>
「僕と別れて直ぐに結婚したようだね?」<o:p></o:p>
「そうなの。あなたは?」<o:p></o:p>
「あ・・・息子が一人。」<o:p></o:p>
「そうなの・・・」<o:p></o:p>
彼と彼女はお互いの空っぽの杯に酒を注ぎ合って一緒に飲んだ。<o:p></o:p>
「家の中にだけいたから久しぶりに出てきて気分がいいわ。ここはちょうど果樹園にある番小屋みたい。私、足をちょっと伸ばそう。」<o:p></o:p>
彼女は膝を曲げた足が窮屈なのかテーブルの下に伸ばして、スカートで太ももをきちんと覆った。隣のバンガローの花札をする音を聞きながら、彼は膝の前でゆっくり動く彼女の小さく上品な足の指を盗み見た。歳月が経ったけれども相変わらず愛らしかった。<o:p></o:p>
「私、とても老けた?」<o:p></o:p>
知ってか知らずか親指を左右に動かしながら彼女が尋ねた。<o:p></o:p>
「いや、変わらないよ。」<o:p></o:p>
「あなたも変わらないわ。私達、先週別れて会ったみたい。8年過ぎた・・・」<o:p></o:p>
「そうだね、8年・・・」<o:p></o:p>
彼はうなずいた。彼女の言葉のとおり8年はまるで1週間のように早く過ぎた感じだった。煙草の煙と水炊きの匂いが抜ける小窓の外で蝉が鳴いた。栗の花の匂いもかすかに漂った。遠くからコノハズクかカッコウか区別できない鳴き声も聞こえてきた。<o:p></o:p>
「あっそうだわ。何をしているの?」<o:p></o:p>
「故郷で家内と小さい塾をしている。」<o:p></o:p>
「うまくいっているの?」<o:p></o:p>
「食べていくくらい。」<o:p></o:p>
「君はいつソウルを出たの?」<o:p></o:p>
「結婚してすぐ。夫が支店長に昇進したんで。あなたのワイフは私より可愛い?」<o:p></o:p>
「いや、ただ性格がいい。」<o:p></o:p>
彼女の足指は彼の膝の前に少し近づいていた。彼はチリ紙を取りながら彼女が近づいた分だけ後ろに退いた。<o:p></o:p>
彼と彼女が8年ぶりに再会し、鶏肉をむしって焼酎を飲んでいる、名ばかりの小さい渡し場の近所の栗林はお互いの住んでいる場所から、だいたい中間点にあった。もの寂しく落ち着いていて他の人々の視線からも比較的自由だった。彼は食べ残した鶏肉と鶏粥、空の焼酎瓶、ふちに口紅と脂が付いている空の杯、細いのやら太いのやらの鶏の骨を眺めた。それは世紀が変わったあの晩、彼女と別れた明洞の夜空を彩っていた花火の残骸のように感じた。その残骸が新しく会った栗の渓谷の密室のようなバンガローでどんな姿に変化するのか、彼はまだわからなかった。扇風機が回っていたけれど、彼女は暑いらしく上にかけていた薄い上着を脱いだ。彼は彼女の肩にかかっているスリップとブラジャーのひもから視線を外した。<o:p></o:p>
「どうして・・・私をさがしたの?」<o:p></o:p>
もう一度視線を戻させる彼女の酔ったような言葉だった。彼は彼女の首から下がって胸の谷間に輝いている首飾りに困惑した視線を向けた。口の開いている水の瓶に向かって突き出した彼女の手と一緒にテーブルの下の足指も動いた。わずかに彼の膝に8年前の風が刃のようにすっと過ぎて行った。<o:p></o:p>
「会いたかった。」<o:p></o:p>
「私も。」<o:p></o:p>
そして彼女と彼は狭いバンガローでお互いの視線を合わせないように努めながら、しばらくおろおろした。垢がついた壁紙と窓の横にかかっているカーテン、部屋の片隅に置かれている畳んだ軍用毛布と花札、そして用途のわからない敷布団、内側から鍵がかかる取っ手まですべて眺めた後、彼は食べ残した鶏肉にしつこく群がるハエを追いながら口を開いた。<o:p></o:p>
<o:p></o:p>



















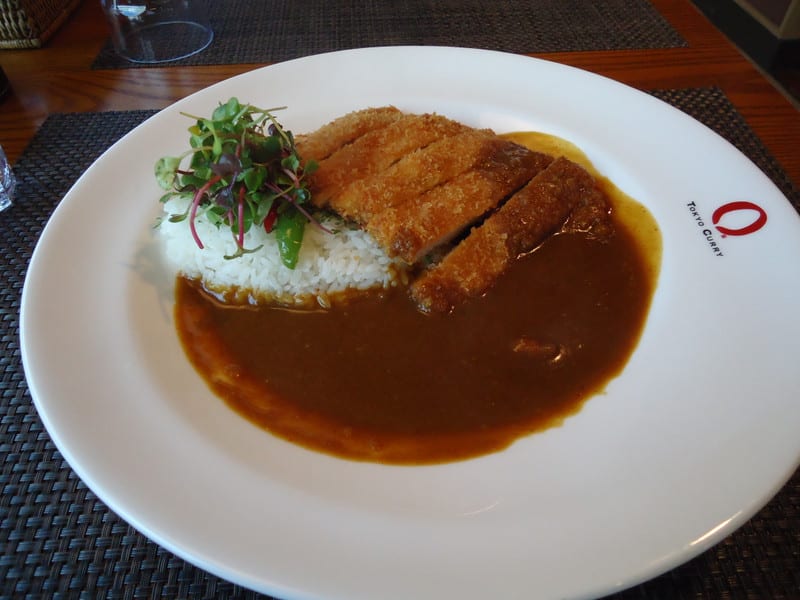





 感想
感想
 わがまま評価
わがまま評価 <o:p></o:p>
<o:p></o:p>