
★★趣味の韓国語サークルで勉強した教材を翻訳したものです。営利目的はありません★★
著者 : キム・エラン
帰り道のチャンソンの顔が暗かった。バスの窓の外で8月の無慈悲な草色が平然と揺れるのが見えた。日の光も風もそのままなのに突然別の世界に来た気分だった。数十分の間に同じ風景がすっかり変ることがあるという事実が驚嘆に値した。
「お父ちゃんもそうだったのだろうか?」
チャンソンがうつむいてエバンを見た。エバンはチャンソンの膝に座ってかすかなバスの振動を感じながらこっくりまどろんでいた。チャンソンは医者から聞いた話を一つ一つ反芻した。手術をしてもいいし、しなくてもいいということが何を意味するのかじっくり考えた。こんな時に自分が何をすればいいのかわからなかった。チャンソンがふと冷たく湿っぽい気配を感じて下をうかがった。自分のベージュ色の半ズボンにテニスボールほどの赤褐色の染みが見えた。染みは不完全な円模様を描いて段々大きく広がった。
「どうして、エバン。お前、そんなことしなかったじゃないか。」
チャンソンがエバンの耳に囁いた。エバンを叱るより周囲に説明したわけだ。夏なのでバスの中に少し生臭い小便の臭いがすぐに広がった。少しだけ我慢しようかと思って、チャンソンは目的地までバス停二つを残してバスから降りた。チャンソンが畦道にエバンを下して優しく言った。
「エバン、少しだけ歩いてみて。ね?」
エバンは地面にぴたっと腹ばいになったまま、動かなかった。チャンソンは仕方なくエバンを胸に抱いて黄昏に沈む薄暗い畦道を歩いた。真夏の暑さに犬を抱いて歩いてみると数分でTシャツがびっしょり濡れた。
「着いた。少しだけ我慢して。」
病院でエバンの聴力が弱っているという話を聞いたのでいつもより声を上げた。そこらじゅうで頭をよくぶつけるなんて、視力も明らかに悪くなったのだろうと思った。ふいに痛々しい気持ちになってチャンソンがエバンの頭をそっと撫でた。エバンの口元がかすかに上がった。反対に目じりは柔らかく下がって、人が笑うように見えた。チャンソンが頭を上げて残りの距離を見極めた。ぬるい水田の上にカゲロウの群れが丸く一つにまとまって飛んでいた。あたかも、空間に時間の水しぶきができるようだった。もうエバンにご飯を食べさせる時間なのでチャンソンが足を速めた。
その晩、祖母は夜中の12時過ぎに帰ってきた。祖母は板の間に上がるとポケットからラップで包んだバター焼きのスルメイカを取り出してチャンソンに差し出した。
「シロにやらずにお前だけ食べなさい。やろうとするなら頭だけ取り除いてやるんだよ。」
「お祖母ちゃん、お酒飲んだの?」
チャンソンは祖母から酒気とともに香水の匂いがするのを感じた。祖母は返事の代わりにナイロン素材の鞄から煙草の箱を取り出した。そうして一本残った煙草をつまんで火を付けてから、ため息をつくように小さく呟いた。
「主よ、私を許したまえ・・・・」
チャンソンはエバンを連れて一人で病院に行ってきた話を祖母にしようかしまいかためらった。
「明日日曜日なのにお酒を飲んだらどうするの?教会に行かない?」
「うん。」
「どうして?」
「ただ行かない。」
「お酒を誰と飲んだの?」
「前の牧師さまと。」
チャンソンは前の牧師さまがどんなに良い方かを祖母から何回も聞いて知っていた。父の葬儀を手伝ってくれたのも、保険会社が保険金支給を拒否した時に、訴訟を調べてくれたのも、祖母が通っている教会の前の牧師さまだった。印紙番号や送料という難しい言葉の前で戦々恐々とした祖母に、一番大きい力になってくれたのも牧師様だと言った。例え、保険料請求訴訟は棄却されたけれど、「それでもそれほど争うことができたのは牧師さまのおかげ」だと祖母はしきりに言った。チャンソンは祖母がする話を半分も理解できなかった。
「今牧師さまがお祖母ちゃんと会いたくないそうだ。」
「それはどういうことなの?」
「なんだって。何でもないよ。あっ、そしてこれ。」
祖母が話題を転じて財布から何かを取り出した。
「お前、前からほしいと言っていただろう?」
「何?」
「休憩所の所長が携帯電話を換えたの。液晶がちょっと壊れているけれど、通話はできるだろうって。欲しければ持っていけというので、家の子犬にやろうと持ってきたよ。何か芯かチップかそれだけ入れるといいと言っていたけれど?」
チャンソンが目を輝かせて旧型のスマートフォンを受け取った。祖母の言葉とおり、左側の角に蜘蛛の巣模様の小さいひびがあるけれど、それくらいなら大丈夫だった。
「米櫃にご飯が残っているかい?」
チャンソンがスマートフォンから目を離さないまま答えた。
「うん。」
「じゃ、お祖母ちゃんは先に寝るつもりだから、少し遊んで寝なさい。シロのご飯の入れ物からすえたにおいがしたけど、ちょっと洗っておいて。」
祖母が空の煙草箱につばを吐いてから煙草をもんで消した。そうしてよろよろ暗い部屋へ入って行った。
チャンソンは小部屋に横たわって電源も入らないスマートフォンをしばらくなでまわした。そして休み時間ごとに携帯電話のゲームに熱中していたクラスの子供達を思い浮かべた。四角いモニターの中で機械か生物かわからない小さいものが、ぶくぶくしながら砕ける姿を友達の肩越しにしばらく盗みみたりしたのだ。チャンソンはその世界がいつも気にかかっていた。友達達が互いに文字だけで対話し、チャンソンが勇気を出して話しかけても、液晶から目を離さず、返事をする時は特にそうだった。チャンソンは友達の間でコミュニケーションが動き出す原理と語彙から疎外されていた。ところが、突然嘘のようにそれが生まれたのだ。まだ通信会社と契約して電話番号が通じるようにしたのではないけれど、機器があるのでいつでも自分が望む世界とつながることができるようだった。チャンソンがふいに静けさを感じて周囲を見回した。一日中うんうん言って後ろ足をなめていたエバンがチャンソンの横でぐっすり寝ていた。チャンソンの顔に薄い影がかかった。動物病院の医者はエバンが手術をしなければ危険だと言った。しかし、老犬なので「手術しても良くなるはずもない」と言った。チャンソンはその簡単な言葉がよく理解できなくて何回も目をぱちぱちさせた。
「そうすればできることが何もないのですか?」
医者が呼吸を静めた後落ち着いて答えた。
「最後の方法として・・・・めったにないですが安楽死を選ぶ方がいて・・・・」
「それ、何ですか?」
「苦しむペットをぐっすり眠らせてから、心臓を止める注射を打ってやるので、安らかになって。」
医者は「それをしてから、後悔したり、苦しがる人も多いので、慎重に決めること」だという言葉を忘れなかった。ひとまず、エバンに良くしてやれと、持ちこたえて生きている間とても苦しいはずなので、横でよく慰めてやりなさいと言った。しかし、チャンソンはどうすれば良くできるのか、エバンが本当に望むことが何かわからなかった。折よく向かいの部屋で祖母がため息を吐くように「ああ、死ねばすべての苦しみが消えるだろう。死ねば憂いがないだろう。神よ、私を静かに連れて行ってください」と言う声が聞こえてきた。チャンソンが体を回してエバンを穴が開くほどじっと眺めた。互いに鼻が触れるほどの近い距離だった。
「お前がお前の顔を見た時間より僕がお前の顔を見た時間が長い・・・わかるかい?」
エバンの濡れた睫毛がかすかにぶるぶる震えた。チャンソンがエバンの口の形、髭、小鼻、眉、一つ一つ心を込めて眺めた。そうすると、その上に生きて、とても、持ちこたえる、苦しみのような言葉が慌ただしく重なった。
「ねえねえ、エバン。僕はいつも気にかけていた。死ぬことが治るほど苦しいというのは一体全体どれぐらい苦しいのだろうか?」
「・・・・」
「エバン、とても苦しいのかい?僕がよくわからなくて御免。」
「・・・・」
「ねえねえ、エバン。もしも耐えられなかったら・・・後で、とてもとても苦しかったら、お兄ちゃんに必ず言って。わかったね?」
エバンがううと声を出した。チャンソンは体を回してまっすぐ横たわってから、暗闇の中で空っぽの壁をしばらく眺めた。
チャンソンはアパートの外廊下それぞれの玄関にA4の大きさの紙を貼った。40枚単位で小分けして角ごとに前もってセロテープを張って置いたのだった。「高等部 国語 課外」「課外より強大な1台3システム、少数精鋭グループ」「内申 準備 特別 教材、期末成績表がさっと変わります。」その他にピアノとテコンドー学院を始めとして美容院とフィトネスジム、チキン、ピザ配達業界の広告も多かった。チラシ配布アルバイト面接の時に、チャンソンは自分の年を少し多めにした。幸い、生徒証を見せるという所はなかった。背が届かない所にある郵便箱は支えるものを使ったり、自分の位置から飛ぶことで解決した。共同玄関の暗証番号が必要な新築アパートはなるべく避けたけれど、時たま知らないふりをして入居者の後について入って行った。幼く見える顔に生徒鞄を背負ったチャンソンを疑う人はほとんどいなかった。それでも、他人の家の玄関にチラシを入れるうちに、誰かが突然ドアを開けて出てくれば胸がどきどきした。
割当量は考えるほど速く減らなかった。エレベーターがない高級テラスハウスのワンルームも多く、人々は行き来に防御的だったり、無視したり、神経質だったりした。アルバイトを始めてから、一日だけチャンソンは自分がチラシ配布をあまりに簡単に見ていたことに気づいた。生れてからこんなに体を使うことで、無理をしたことがなかった。初日から足に弾丸が詰まったように階段を上り下りすることは、体を侮辱するものだった。辞めたくなる度にチャンソンは呪文のように「1枚20ウォン。千枚配れば2万ウォン・・・。」
という言葉をつぶやいた。そうすれば少し耐える力が出た。何日間も休憩所にも立ち寄らず、夕暮になれば失神したように眠っているチャンソンを、祖母は別に怪しみもしなかった。ただ1回「お前、顔がどうしてそんなに日焼けしたんだい?」と言っただけだった。
作業は一人でする時もあり、多数がグループを組んで動く時も多かった。一度は同じグループで働く中学生の先輩がアパートの階段に座って青いイオン飲料をあおりながら尋ねた。
「おい、お前、どうしてこれをしているんだい?」
チャンソンが当惑したそぶりを隠しながら言葉を転じた。
「先輩は?」
「俺は何、ただ煙草代を稼ごうとしているのだよ。」
「そう・・・」
「お前は? 小学生がお金を手に入れて使うのかい?」
チャンソンが躊躇してから率直に答えた。
「・・・ちょっと具合が悪いのがいて。」
「あ・・・」
中学生が今更のように善良な口調で尋ねた。
「ところでこれで大丈夫?」
チャンソンが目を伏せて憂鬱げに答えた。
「うちの犬は小さくて10万ウォンぐらいかかるそうです。」
「えっ?何?犬?」
中学生はしばらく混乱して世間の世情に明るい大人のふりをして「最近は動物病院代もとても高い」と不平を言った。
「いいえ、そうじゃないです。犬の安楽死代がそれぐらいかかるので、僕にお金がなくて・・・」
中学生が何かじっくり考えてから、たちまちチャンソンを面と向かって責めた。
「何言っているのだ。こいつ、完全におかしい。」
決まった区域を全部回ると、チャンソンはアパート団地の中の遊び場で時々休んだ。セロテープとはさみ、チラシ、さらにタオルと水筒が入った生徒鞄を背負ったまま木陰に座って町の子供達が遊ぶのを見た。三々五々ベンチに集まる母親達が育児を共有し、歓談を交わして、心配や関心、愛情がこもった目で自分の子供を眺める姿を観察した。「ああ、母親達は子供をあのように見るんだな」「あんな目つきで接するのだね」ちらっと見た。その度にチャンソンは不思議にも生まれて一度も顔を見ることができなかった母の代わりにエバンを思い浮かべた。「エバンもこんな所で散歩したら良いはずなのに」「エバンもあんなおやつをやったら興奮するはずなのに」と惜しんだ。エバンは最近チャンソンが出かける時も見上げなかった。ぼんやりした目でぼんやりと虚空を凝視した。チャンソンがご飯に生卵を割って、祖母に隠れてマグロの缶詰を載せてやっても、首を回す日が多くなかった。「近頃、僕がしょっちゅう家を留守にするからすねたのかな?」すまない気持ちになったけれど、最大のお金を早く集めようとすれば仕方なかった。
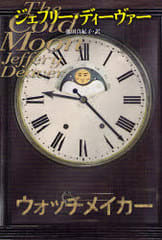
ウォッチメイカー
THE COLD MOON (原題)
著者 : ジェフリー・ディーヴァー
生年 : 1950年
出身地 : USA ミシガン州シカゴ市
出版年 : 2006年
邦訳出版年 : 2007年
邦訳出版社 : (株)文藝春秋
訳者 : 池田真紀子
★★感想☆☆
リンカーン・ライム・シリーズの第7作。リンカーン・ライムは元ニューヨーク市警科学捜査部長。現場鑑識中の事故で脊髄を損傷し、四肢麻痺の体になり、首から下を動かすことができない。現在は市警の捜査顧問として自宅の居間を科学捜査研究室に改造して難事件の指揮を執っている。アメリア・サックスはニューヨーク市警の新米刑事で、ライムに代わって現場の鑑識に出かける。ライムの足と目となっている。彼女抜きではライムの捜査はできない。トムはライムの虐待に6週間以上耐えた最初の介護士。彼なしにはライムの生活は成り立たない。さらに今回から、尋問のエキスパートのカリフォルニア州捜査局捜査官キャサリン・ダンスが加わる。
最初の殺人事件はハドソン川にかかる桟橋に凍った血だまりと血だらけの爪で引っかいた痕がついていたのを発見したことから始まった。死体は川に落ちたのか見当たらないが、黒い箱が置いてあった。中に古風な置時計が入っていた。第2の殺人事件はブロードウエイの近くの路地で4キロの金属バーで喉をつぶされた遺体が発見された。ハドソン川の事件と同じく古風な時計が見つかった。時計の販売元から、同一人物が同じ時計を10個購入したことが判明する。犯人2人組、ウォッチメイカ―(時計師)のジェラルド・ダンカンと相棒のヴィンセント・レノルズは廃屋と化した教会を根城にしている。
「ひもじい・・・
飢え・・・・
女性に性的暴行を働きたいという衝動は一種の飢えであるーヴィンセント・レノルズにそんなことを自分で考えつく頭はない。その理屈を教えてくれたのは、セラピストのドクター・ジェンキンスだった。」
「並んで1階に下り、教会の裏手の路地に出る。
ダンカンが南京錠をかけた。『ああそうだ、忘れるところだった。明日の予定だが、次も女だ。二人連続ってことになる。』」
いくつもの網が絡み合って最後まで引っ張って行く。
☆☆趣味の韓国語サークルで取り上げた韓国語の小説です。営利目的はありません☆☆
 著者 : キム・エラン
著者 : キム・エラン
「エバン」
チャンソンはその犬をそう呼んだ。
「どうしたの、エバン。どこか痛いの?」
人間の年で見積もれば既に70歳を超える老犬にチャンソンは兄の役を務めた。チャンソンはどういうわけかエバンが自分より長く生きている弟、生きて既に沢山のことを経験した弟のように感じた。チャンソンが初めて「エバン」と呼んだ時、エバンは別の所を見た。当然だった。それは自分の名前ではなかったから。チャンソンは何となく寂しくエバンを撫でた。エバンに自分が知らない生活と歴史があるということを認めようと努めた。それでも、ある時エバンの過去がとても気になった。前はどんな名前で呼ばれていたのだろうか? 主人は良い人だったのだろうか? 今まで生きていてどこまで行ってみたのだろうか? 僕よりは遠くに行ったのだろうか? 素晴らしい映画やドラマに出てくるように主人と海辺も懸命に走ったのだろうか? その時のことを覚えているのだろうか? その時のことをわかるということは良いことだろうか? そうだとしたら今はどこへ行きたいのだろうか?
祖母はエバンを見るや否や嫌がった。犬1匹育てるのは、人一人育てることと同じく手間がかかると首を激しく振った。
「そういうことは、人を育てたからこそわかるのよ。」
祖母が軽く嫌悪の目でエバンを眺めた。
「そのうえ、とても年を取っているじゃないかい?」
「この子が年を取っている?」
「そうだよ、あの歯を見なさい。人でも生き物でも毛が抜けて歯が抜ければ終わったのよ。お前はそんなことも知らないで犬を育てようというのかい?」
チャンソンが「そうかな?」という表情でエバンの背を撫でた。短くごわごわして本当に毛に艶が一つもなかった。
「言うまでもないけれど、明日道路に置いてきて。」
チャンソンの顔に失望の色がよぎった。
「そうしなければ駄目?」
祖母はチャンソンと目も合わせず、床に積もった犬の毛をセロテープではがした。
「家に犬がいれば泥棒が入らないよ、お祖母ちゃん。」
「うるさい。孫のご飯も充分に用意できないのに。この年で犬の世話を・・・・ああ、うんこやおしっこはどうするの。」
柔らかい頬ときれいなよだれを持ったチャンソンと違って、祖母は年を取ることがどういうことか知っていた。年を取るということは、肉体が徐々に液体化するということを意味した。弾力を失いぐにゃぐにゃした体の外に汗や膿、よだれと涙、血がしきりに漏れ出すことを意味した。祖母は家に年老いた犬を入れてその過程を日々実感したくなかった。
「ご飯はそのまま僕たちの食べ残しをやればいいじゃない、ね?」
祖母が床にセロテープを乱暴にくっつけながら「このくそったれの毛、きりがないね!」小言を言った。祖母が意志を曲げず、追い詰められたチャンソンは結局ある言葉を吐き出したのだが、その言葉を言って本人もぎょっと驚いた。だからエバンを・・・・自分が「責任」をもつと言ったのだ。生れて初めて言った言葉だった。
その頃、チャンソンはしょっちゅう悪夢に苦しめられていた。祖母がチャンソンに「今は大きくなったから、一人で大丈夫だ」と父が使っていた部屋に出してくれてからだった。チャンソンは度々同じ夢を見た。小型冷蔵トラックが自分に飛びかかる夢だった。トラックの中には食料の毛をむしった鶏の生肉がいっぱい積まれていた。トラックは真っ暗な道路を疾走して中央線の上でチャンソンを発見してカーブした。そしてすぐに、中心を失って路肩の下の崖に転倒した。絶壁の下から爆発音とともに巨大な火の手が上がった。チャンソンは路肩の周辺を苛立ってうろついた。あそこ、まだ人がいるので。僕が知っている人のようで。周囲に集まってきた見物人は「どこかでしきりに美味しい匂いがする」と言った。チャンソンが大人達に向かって「助けてくれ」と叫んだ。そうするとどこからか祖母が現れて唇に手を当てて「しっ」と声を出した。優しい声で「泣かないで、泣かないで、坊や」とチャンソンを慰めた。
「お前が泣けば」
「・・・・」
「お客様が目を覚ますじゃない。」
エバンを家に入れた日、チャンソンは久しぶりに何の夢も見ず深く眠った。チャンソンはエバンが眠りを守ってくれたと考えた。いつかエバンに何かあれば、自分もエバンを必ず保護してやらなければならないと誓った。その後、チャンソンとエバンはいつも一緒に眠った。チャンソンは誰かをしっかり抱きかかえて寝る気分がどんなものか初めて知った。エバンの温かく小さい胴体が、呼吸するにつれて穏やかに上がったり下がったりするのを見るだけでも、平和な気分になった。チャンソンはエバンのふわふわした足の裏をしきりにいじりながら、しょっちゅう独り言を言った。
「ねえ。エバン。これを見ろ。たくさん集めただろう? 3万ウォン以上。どこで使おうかな? ううん、後で大きくなっていつかここを離れる時に、その時僕も休憩所に立ち寄って珈琲でも一杯飲むよ。」
エバンは自分の足に顎を当てて横たわり、瞼をゆっくり開けたり閉めたりして先に寝ついた。それでもチャンソンのおしゃべりは夜中ずっと続いた。
「お前、骨肉腫が何か知っている? 何かサボテンの名前と同じだろう? そんなのがあるそうだ。お父ちゃんがその病気にかからなかったら僕も知らなかったのさ。」
一日また一日が過ぎた。人間の時計で2年、犬の時間で10年が流れた。チャンソンとエバンはいつのまにか互いに一番頼りにする存在になった。例え、動きが鈍く耳が遠くても、エバンは普通の犬のようにボール遊びと散歩が好きだった。チャンソンが毛羽立ったテニスボールを遠くに投げれば、エバンはチャンソンの目の前から消えて必ずボールと一緒に再び現れた。何か自分の場所に元どおりに持ってくるのはエバンが得意なことの一つだった。チャンソンはエバンが自分にくわえてくるものが、別にボールではない違うもののように感じた。そしてボールと同時にボールではない、その何かが自分を変えたようだった。
ところがエバンが最近少し異常だった。
祖母は夜10時過ぎに帰宅した。片腕に黒いビニール袋を持っていた。
「電子レンジで温めて食べなさい。」
チャンソンが袋を覗いた。アルミフォイルの間に砂糖をかけたじゃがいもが見えた。チャンソンが仕事を終えた祖母の後ろをちょろちょろ追いかけた。
「お祖母ちゃん、エバンがちょっとおかしい。」
「今食べないなら冷蔵庫に入れておくとかして。」
祖母がいつも携帯電話を入れて行く手提げ鞄を大きい部屋に投げるように下した。
「お祖母ちゃん、エバンがご飯を食べない。」
「年取ったからだよ。年取ったから。」
「そうだよ。僕がボールを投げても動かない。歩いてしょっちゅう座り込む。」
「年取ったからだ。」
祖母は全てのことが煩わしいように腕を振り回した。そうしてううんと言って床に布団を広げた。
「あそこを見て、あんなに自分の足をしょっちゅうなめる。一日中あんな状態で。さっきは僕が足を触ったら急に噛もうとした。」
祖母が敷布団の上に横たわろうとしたが、上体をおこしてチャンソンを見た。
「ううん、本当に噛んだのではなく、噛むしぐさだけ。」
祖母は目を瞑って額に腕を載せた。
「お祖母ちゃん、エバンを連れて病院に行かなければならないじゃない?」
「無駄口は止めて寝なさい。あちこち灯を点けておかないで。」
祖母の半袖にかすかにキムチ汁がくっついていた。チャンソンが祖母の横に座りも立ちもせずにためらった。
「お祖母ちゃん、エバンを病院に連れて行かなければと思うの。」
祖母がかっと怒鳴った。
「なんで犬を病院に連れて行くの。人も行けないのに。だから私が犬っころを道に置いておけと言ったね、言わなかった? お祖母ちゃんの火病が出る前にすぐに行って寝なさい。犬買いにシロを売ってしまう前に。急いで!」
「シロじゃないよ。」
チャンソンが以前にない大きな声を出した。
「何?」
そうしてすぐ言葉尻を濁しておどおど答えた。
「エバンだよ。」
祖母がため息をついてチャンソンにさっさと出ていけと手を振った。チャンソンもこれ以上言えずに自分の部屋へ戻った。チャンソンは暗い部屋で横たわり天井を眺めた。そうして、しばらくしてプラスチックのパトカーの中に隠しておいた3万ウォンを取り出し財布に入れた。
「どこか具合が悪くて来たのかい?」
動物病院の医者が訊ねた。
「エバンが悪いようなのです。」
「こいつの名前がエバンかい?」
「はい、〈トニンメカド〉に出てくるメカニモルの名前です。
「そう?」
医者が職業的な微笑を浮かべた。地方新都市アパート商圏では何よりも評判と噂が重要だった。
「はい! 僕が一番好きなキャラクターです。エバンは元々トニンカーで、メカドに向かってシュートしてメカニモルで変わります。」
医者はチャンソンの言葉がほとんどわからなかったけれど、問診票を見て老練に話題を転じた。
「それで君は・・ノ・チャンソン?」
「はい? はい。」
チャンソンが消え入りそうな声で答えた。姓と名前が一緒に呼ばれる時、良いことが起きた場合はほとんどなかった。職員室でも、父親が入院した総合病院でもそうだった。
「それで結局、賛成(チャンソン)するの、反対するの?」
チャンソンはそんな話はしょっちゅう聞いているうえに、今は本当に食傷して答えるのが面倒だというように肩を上下に揺らした。
「先生の冗談がつまらないという意見は賛成です。」
医者が再び作り笑いを浮かべた。
「うう、ところで、犬の持ち主がノ・チャンソンとなっているね?
君一人で来たの? ご両親は?」
エバンは緊張した様子がはっきり見えた。病院特有の消毒薬の臭いとひやっとした感じがエバンの具合を悪くしているようだった。医者はエバンの足を見るやちょっと驚いて「ああ、とても痛かっただろう?」と言った。これほどなら他の場所に腫瘍が広がった確率が高いと。
「腫瘍ですか?」
「そう。癌。」
「癌ですか? 犬も癌にかかりますか?」
「そうだよ。」
チャンソンは癌が何か知っていた。癌と関連する臭いか悲鳴、そして吹き出物で欠けた顔を。
「詳しいことは検査結果を見てわかるはずだけど、状況が良くないのは事実だよ。」
「検査ですか?」
「うん。血も取って写真も撮って。」
「それが・・・全部するといくらなんですか?」
「そう、検査次第なので。きちんとすればお金がたくさんかかるよ。明日ご両親と一緒にもう一度来るかい?」
チャンソンがズボンのポケットの中の財布を出さずいじりまわした。
「それなら、先生の思うとおりにどんな検査をして、どんなことはしなくても大丈夫ですか?」
「まあ、言ってみれば。」
「じゃ、あの・・・・3万ウォン、じゃなくて2万5千ウォン分だけ検査してください。」

































