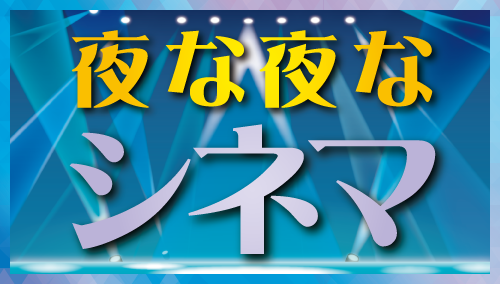『白雪姫と鏡の女王』(原題:Mirror, Mirror)
監督:ターセム・シン・ダンドワール
出演:ジュリア・ロバーツ,リリー・コリンズ,アーミー・ハマー,
ネイサン・レイン,メア・ウィニンガム,ショーン・ビーン他
TOHOシネマズ西宮でハシゴ、さらに遡って1本目に観たのがこれ。
まずは世界的なデザイナーで、同監督作品の『ザ・セル』(2006)や『落下の王国』(2006)、
本作の衣装デザインも担当された故石岡瑛子さんのご冥福をお祈りします。
みんながよく知るグリム童話『白雪姫』。
こんなふうに料理しちゃうのもありですね。
母親を亡くし、国王である父親に溺愛されて育った白雪姫。
年頃になった白雪姫には新しい母親が必要だと思ったか、国王は再婚する。
しかし、怪物が住むと言われる森に出かけた国王が行方不明に。
継母の女王は白雪姫を城のてっぺんに幽閉、好き勝手しはじめる。
国王がいた頃は栄えていた町。人びとは幸せに暮らしていた。
女王の散在のせいで今や町は見る影もなく衰退。
働けども働けども収入はすべて女王に吸い取られ、
女王は贅沢三昧、人びとの生活は貧困を極めている。
けれどももう搾り取るものすらなくなり、王国の財政は破綻寸前。
そこで女王は金持ちの王子を見つけて結婚することを思いつく。
ちょうどその折り、森で盗賊に身ぐるみ剥がれ、
女王のもとへ助けを求めて駆け込んできたのが隣国の若いイケメン王子。
女王は自分の年齢もかえりみず、さっそく王子を落とす作戦に出る。
一方、こっそり部屋を抜け出した白雪姫は、町の状態を見て悲嘆に暮れる。
かつて国王が築きあげた温かい国を取り戻したい。
そう考えた白雪姫は、森の盗賊=7人の小人に師事し、
女王に立ち向かう決意を固めるのだが……。
白雪姫を演じるリリー・コリンズの凜々しい眉毛と
王子を演じるアーミー・ハマーの野太い声が、
なんとも言えずこの古典童話に合っています。
『J・エドガー』(2011)でアーミー・ハマーを見たときには、
こんなコメディもバッチリこなせる人だとは想像もしませんでした。
女王役のジュリア・ロバーツは今までのイメージを一新。
よくもこんな役を引き受けたもんだなと思いますが、
意外に楽しかったのか快演。
アメリカでは美人の代名詞のような彼女の顔は、本作に限ってはコワイ。
全開のデコ、眉と目の間の深い彫り、高い頬骨、大きな口、
どこをとっても意地悪な魔女にしか見えません。
「鏡よ鏡」と唱えれば、鏡の向こうの世界に入るというのも新しいアイデア。
いつも色鮮やかな世界が美しい監督、
鏡の向こうの世界の描き方も不気味ながら美しい。
また、インド出身の監督だけあって、エンディングの踊りが愉快&唖然。
まさか白雪姫にマハラジャ風を持ってくるとは。
ハシゴした3本のうち、「DVDでも良かったかしらん度」はいちばん強いです。
でも、ま、楽しかったけど。
『スノーホワイト』(2012)では小人が8人いたかもとの噂だったので、
本作では思わずいちいち数えちまいましたよ。
監督:ターセム・シン・ダンドワール
出演:ジュリア・ロバーツ,リリー・コリンズ,アーミー・ハマー,
ネイサン・レイン,メア・ウィニンガム,ショーン・ビーン他
TOHOシネマズ西宮でハシゴ、さらに遡って1本目に観たのがこれ。
まずは世界的なデザイナーで、同監督作品の『ザ・セル』(2006)や『落下の王国』(2006)、
本作の衣装デザインも担当された故石岡瑛子さんのご冥福をお祈りします。
みんながよく知るグリム童話『白雪姫』。
こんなふうに料理しちゃうのもありですね。
母親を亡くし、国王である父親に溺愛されて育った白雪姫。
年頃になった白雪姫には新しい母親が必要だと思ったか、国王は再婚する。
しかし、怪物が住むと言われる森に出かけた国王が行方不明に。
継母の女王は白雪姫を城のてっぺんに幽閉、好き勝手しはじめる。
国王がいた頃は栄えていた町。人びとは幸せに暮らしていた。
女王の散在のせいで今や町は見る影もなく衰退。
働けども働けども収入はすべて女王に吸い取られ、
女王は贅沢三昧、人びとの生活は貧困を極めている。
けれどももう搾り取るものすらなくなり、王国の財政は破綻寸前。
そこで女王は金持ちの王子を見つけて結婚することを思いつく。
ちょうどその折り、森で盗賊に身ぐるみ剥がれ、
女王のもとへ助けを求めて駆け込んできたのが隣国の若いイケメン王子。
女王は自分の年齢もかえりみず、さっそく王子を落とす作戦に出る。
一方、こっそり部屋を抜け出した白雪姫は、町の状態を見て悲嘆に暮れる。
かつて国王が築きあげた温かい国を取り戻したい。
そう考えた白雪姫は、森の盗賊=7人の小人に師事し、
女王に立ち向かう決意を固めるのだが……。
白雪姫を演じるリリー・コリンズの凜々しい眉毛と
王子を演じるアーミー・ハマーの野太い声が、
なんとも言えずこの古典童話に合っています。
『J・エドガー』(2011)でアーミー・ハマーを見たときには、
こんなコメディもバッチリこなせる人だとは想像もしませんでした。
女王役のジュリア・ロバーツは今までのイメージを一新。
よくもこんな役を引き受けたもんだなと思いますが、
意外に楽しかったのか快演。
アメリカでは美人の代名詞のような彼女の顔は、本作に限ってはコワイ。
全開のデコ、眉と目の間の深い彫り、高い頬骨、大きな口、
どこをとっても意地悪な魔女にしか見えません。
「鏡よ鏡」と唱えれば、鏡の向こうの世界に入るというのも新しいアイデア。
いつも色鮮やかな世界が美しい監督、
鏡の向こうの世界の描き方も不気味ながら美しい。
また、インド出身の監督だけあって、エンディングの踊りが愉快&唖然。
まさか白雪姫にマハラジャ風を持ってくるとは。
ハシゴした3本のうち、「DVDでも良かったかしらん度」はいちばん強いです。
でも、ま、楽しかったけど。
『スノーホワイト』(2012)では小人が8人いたかもとの噂だったので、
本作では思わずいちいち数えちまいましたよ。