私は東京の調布市の片隅みに住む73歳の身であり、
今住んでいる近くで、農家の児として生を受けて、
やがて中小業のサラリーマンを35年近く勤めた後、多々の理由で年金生活の14年生となっている。
こうした中で、古びた一戸建てに住み、小庭の雑木、草花を眺めたり、
周辺の遊歩道、公園を散策をしたりして、日々季節のうつろいを教示されている。
ときおり、家内との共通趣味の国内旅行などをして、
各地の四季折々の限りない美に心を留め、齢を重ねるたび愛惜が深まっている。
このように感じ受けとめながら日々を過ごしたりしているが、
つたない無知な私は何かと書物で、改めて日本の歳時などを多々教示されている。

例えば、藤野邦夫・著の『幸せ暮らしの歳時記』(講談社文庫)、
飯倉春武・著の『日本人のしきたり』(青春出版社)、
朝日新聞社・編の『色の彩時記~目で遊ぶ日本の色』(朝日新聞社)、
講談社・編の『茶花歳時記』(講談社)、
野呂希一、荒井和生・共著の『言葉の風景』(青菁社)、
長谷川 櫂・著の『四季のうた』(中公新書)、
松田 修・著の『古今・新古今集の花』(国際情報社)、
道行めく・著の『美しい日本語帳』(永岡書店)、
山下景子・著の『美人の日本語』(幻冬舎文庫)
などが私の机の横にある小さな本箱にあり、
定年後に幾たびか読み返したり、或いは初めて精読した本もある。
そして齢ばかり重ねた無学な私は、ときおり国語の辞書を置き、
そおっと開く時もある。
久松潜一・監修の『新潮国語辞典 ~現代語・古語~』(新潮社)であるが、
二十歳以来から何かと教示を受け、私の秘かな言霊(ことだま)の恩師となっている。
私は齢ばかり重ねた高齢者の身であるが、何よりも季節感を大切に日常生活を過ごしているので、
この机の端にある程度の書物を置いたりしている。
こうした中で、私にとっては本棚の片隅みには異例とも思える一冊の本があり、
恥ずかしながら記載するが、弘田 茂(ひきた・しげる)・著作の『花ことば』(保育社)がある。
この本は確か1974年(昭和49年)の頃、私は20代の後半であったが、
季節感を深めたくて、店頭で偶然に買い求めた一冊である。
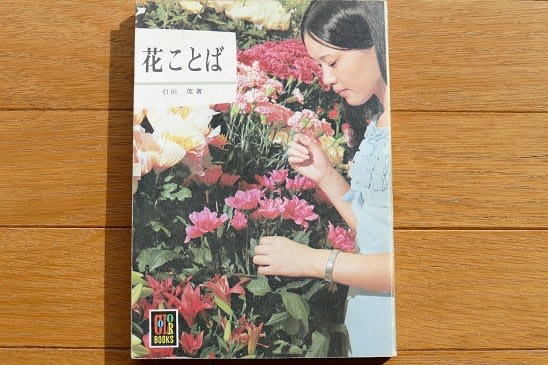
こうした根底には、特に西洋花が苦手であるので、拙(つたな)いなりに少し勉強をしょうと、
通勤の満員電車の中で読み耽ることが多かった。
チューリップは『博愛・名声』
ヒアシンスは『競技・遊技』
アモネスは『薄れゆく希望』
クロッカスは『焦燥』
デージー(ひなぎく)は『無邪気・平和・希望』
水仙は『うぬぼれ・我欲』
スノードロップは『慰め・希望』
フランス菊は『忍耐』
ガーベラは『神秘』
矢車草は『繊細さ・優雅』
・・このような『花ことば』と丁重な解説を学び、若き独身の私は、ときには女性とデートを重ね、
日比谷公園、新宿御苑を散策した時に、こうした花を見たりし、この『花ことば』を重ねたりしていた。
もとより『花ことば』は、人々の日常生活の中で、それぞれの人々の思いが凝縮され、
託された名言と思ったりしている。

そして何かと無知な私が、ヨーロッパの諸国の文化を学ぶ時、キリスト教、石の建物と同様に、
歴史書、文学、音楽、絵画などの世界は、その地に描かれた地域を理解する上で、
少なくとも幾つかの花のうつろいの情景、そして情緒は欠かせないと思ったりしている。
☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪![]() にほんブログ村
にほんブログ村![]()

















