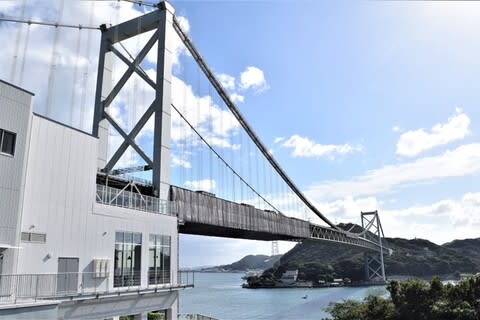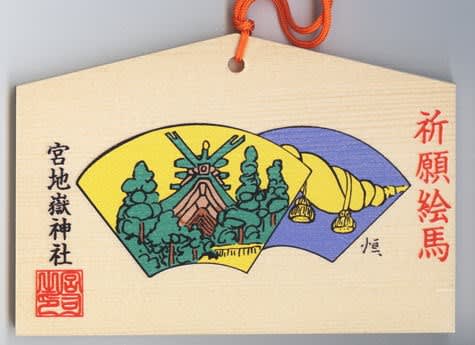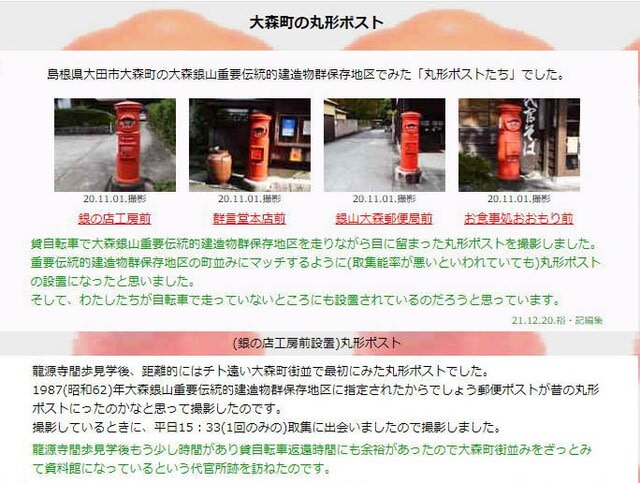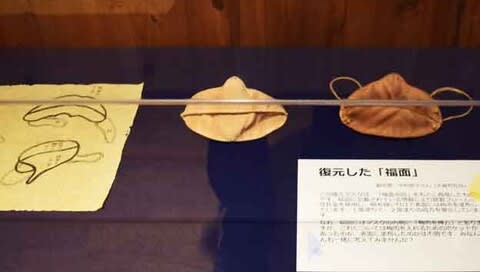福岡市東区志賀島字古戸(の金印公園)に建立されている「漢委奴国王金印発光之処・碑」です。
※当初金印発光推定地点に1922年3月漢委奴国王金印発光之処・碑が建立されています。
※題の揮毫者は黒田長成で、武谷水城撰によるものです。

金印出土場所は、
金印発光之処・碑の右斜め前(いまは海の中)の所と考えられています
2002年リニュアルされる前の金印公園の頁を編集する時、わたしは漠然とここ金印公園の何処から金印が出土したのだろうかと考えていました。
2008年更新した時やはり、発光之処・碑が建立されているところなのだろうと考えていました。
今(2022年)回、金印出土の場所を福岡市博物館資料やWikipediaを参照して考えてみました。
今回頁を編集しながら、金印公園に整備される前のこの場所のことなど(公園前の道路海側にも田圃や畑があったということなど)
この近くで育った妻に、色々と尋ねてみたいことが在ったな~といまになって思いながら尋ねることができないもどかしさで、頁を編集していったのです。
(裕編集の)漢委奴國王金印發光之處・碑
※当初金印発光推定地点に1922年3月漢委奴国王金印発光之処・碑が建立されています。
※題の揮毫者は黒田長成で、武谷水城撰によるものです。

金印出土場所は、
金印発光之処・碑の右斜め前(いまは海の中)の所と考えられています
2002年リニュアルされる前の金印公園の頁を編集する時、わたしは漠然とここ金印公園の何処から金印が出土したのだろうかと考えていました。
2008年更新した時やはり、発光之処・碑が建立されているところなのだろうと考えていました。
今(2022年)回、金印出土の場所を福岡市博物館資料やWikipediaを参照して考えてみました。
今回頁を編集しながら、金印公園に整備される前のこの場所のことなど(公園前の道路海側にも田圃や畑があったということなど)
この近くで育った妻に、色々と尋ねてみたいことが在ったな~といまになって思いながら尋ねることができないもどかしさで、頁を編集していったのです。
(裕編集の)漢委奴國王金印發光之處・碑
11月23日(安芸区のわが家付近)天候:あめ
17.0℃、61%