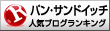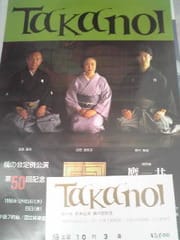大津の姉・大伯をめぐって・・・。
斉明天皇七年、百済救援の西征の途中、備前の大伯の海上で生まれたので大伯と名づけられた。
大伯と大津は幼い時に母を亡くしたが、壬申の乱が起こるまでは淋しさはあったと思うが比較的平穏に過ごせたのではないかと思う。
壬申の乱が終わり、天武天皇が誕生すると、大伯は伊勢神宮に奉仕する斎宮として伊勢に下る事になる。
これは壬申の乱の折の伊勢の神の加護に対する感謝を示すためだ。
彼女についての記録はあまり残っておらず、はっきりしているのは26歳まで斎宮を務めたこと、41歳で死去したことぐらいだ。
実はこの斎宮決定は讃良の画策だという説がある。

大伯が成長し、いずれかの皇子と婚姻すれば、草壁にとっての脅威が増えてしまうという理由だ。
なるほど、考えられる事だと思う。でも、斎宮決定が讃良主導で行われたとしたら、天武天皇ってかなりの恐妻家という感じになってしまうけど・・・。

それはせておき、伊勢の彼女の元を訪ねた人物が三人。ひとりは弟の大津だが、もう一組は十市皇女と阿閉皇女。
大津の事は後に譲るとして、十市の事に触れてみたいと思う。
十市は、大友皇子の后だった。
つまり壬申の乱は彼女の父親と夫の戦いだったわけで、どちらが勝っても彼女には辛い思いしか残らないものだったと思う。
結果として夫を失った彼女の浄御原宮での生活がどのようなものであったかは全くわからない。
歌さえ残されていない。額田を母に持っているのにかなり意外な感じだ。

だが、彼女を思って歌を残した人物がいる。高市皇子だ。

十市皇女の薨りましし時、高市皇子尊の作りませる歌三首
三諸の神の神杉 巳具耳矣自得見監乍共 寝ねぬ夜ぞ多き
三輪山の山辺真麻木綿短木綿 かくのみゆゑに長しと思ひき
山吹の立ちよそひたる山清水 汲みに行かめど道の知らなく
この歌は詞書にもあるように十市皇女が亡くなった時に歌われたもの。
十市が亡くなったのは天武七年四月七日で、天皇が天神地祀を祭るために、多武峰・音羽山に発する倉梯川のほとりに設けた禊のための斎宮に行幸する予定の日だった。
十市の死について書記は
十市皇女、にはか病おこりて、宮の内に薨せぬ
と記すだけだが、自殺だとする見方が強い。ではその背景は何か。
様々な見方がある中で、比較的多い見方のひとつが十市を斎宮にしようとしたとの説である。
ここには大伯の時と同じように讃良の思惑があると・・・。つまり、十市と高市の仲を警戒したのだという。
もし、斎宮に選任されてしまったら、高市との婚姻はできないどころか会う事もままならなくなる。これを悲観して自殺したというのだ。
高市皇子は天武の第一皇子。母親(尼子娘)の身分が低いため皇位継承の面から見ると大津や草壁には後れを取るが壬申の乱での功績は皇子中ナンバーワンだった。
実は高市皇子の歌は上の三首しか万葉集には残されていないし、十市の死に関する歌もこの三首以外にはない。
この事から考えてもふたりは親密な関係にあったのではないかと見方が強い。もちろん、反対意見もある。
十市はともかく、高市は十市に想いを寄せていたのではないかと私は感じる。
三首のうち最初の歌は、いまだに読み方が確定されていないために、読み込まれた意味を解する事は難しいのだが、二首目は短かった命を惜しんでいる。

三首目の「山吹の~」の歌が個人的にはかなり好きで、哀しみの言葉は使われていないのに「道の知らなく」という言葉には心に響く淋しさが表現されていると感じられて、万葉の中でも特に印象的な歌の一つとなっている。

それにしても斎宮って、伊勢の神様に感謝して遣わすはずなのに、息子の地位の安泰のために送られていたとしたら、なんだか虚しい。

そんな伊勢の地に大津がやって来る・・・。