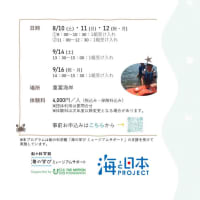雨、雨、雨、雨・・・・・・。
よく降ります。
早朝職場の同僚で、
「雨の日大好き。ああ、なにしよう ってわくわくする」という方がいらっしゃいます。
ってわくわくする」という方がいらっしゃいます。
雨の日は、私はほぼ、ダメ人間と化しています。
暑い日射しで、買い物にも出たくない!と文句をたれる自分を容易に想像できるのですが、
来い!盛夏って気分です。
本、その中でも小説を読むというのは、
自由で豊かで、楽しい時間を私に与えてくれます。
作者が書いた、ストーリーにのって、どこに行き着くかは読み手次第。
読み終わった後、とても前向きな気持ちになったり、世の中が新鮮に見えたり、
自分の中で続きのストーリーが始まったり、
それは誰にも迷惑もかけない自由な空間が脳内に広るものだったりします。
それに比べて、評論、研究論文的なものは、
私の解釈無用で、そこに書いてある作者が掴んだ事実をなるべく正確にこちらも読み取ろうとするので、
単語ひとつの意味も私がとらえている意味だと、こうだけど、
それじゃあ、なんか、よく意味が分からない…と立ち止まりながら読むので骨が折れます。
今、読んでいる本も難しくはないのですが、時々立ち止まってしまいます。

この本で書かれている状況は、リハビリ現場でのセラピストと子どもとの関わりですが、
私が子どもたちと一緒に学ぶときに、頭に置いておくべき示唆に富んでいます。
例えば、子どもとのリハビリが成立しないため、その子が拒否せずに参加できる課題を行ったとき。
それは、一時的には課題が成立したように見えても、
自分ができなさそうなことは拒否する自己防衛的な振舞いを強化させることになっていることがある、ということ。
例えば、集中して課題に向かうようになり、
本人が参加できる形で課題を続け、少しずつ難易度もあげて、本人も楽しんでいるように見えるとき。
実は、本人ができるだけ集中できる課題を繰り返した結果、
その子は、その時間を機械的にやり過ごす、という自己防衛的な振舞いを強化していたに過ぎなかった。
などなど。
私の日頃の関わり方によっては、
子どもの自己防衛的な振舞いの強化につながるかもしれない、
あまり、私の視点にはなかったことがこの本には書かれていました。
一見、できていると見せかけての、自己防衛強化。
これでは、子どもの中に何も入らないし、残りません。
やり過ごし方を学ぶだけ、ということにもなりかねませんから、厄介なことですね。
こうやって仕入れた知識が、私の中で消化されて生きるのか、
忘却の沼の澱となって、沈んでいくのかはわかりません。
それにしても、世の中、当たり前ですが、
知らないことだらけですね
よく降ります。
早朝職場の同僚で、
「雨の日大好き。ああ、なにしよう
 ってわくわくする」という方がいらっしゃいます。
ってわくわくする」という方がいらっしゃいます。雨の日は、私はほぼ、ダメ人間と化しています。
暑い日射しで、買い物にも出たくない!と文句をたれる自分を容易に想像できるのですが、
来い!盛夏って気分です。
本、その中でも小説を読むというのは、
自由で豊かで、楽しい時間を私に与えてくれます。
作者が書いた、ストーリーにのって、どこに行き着くかは読み手次第。
読み終わった後、とても前向きな気持ちになったり、世の中が新鮮に見えたり、
自分の中で続きのストーリーが始まったり、
それは誰にも迷惑もかけない自由な空間が脳内に広るものだったりします。
それに比べて、評論、研究論文的なものは、
私の解釈無用で、そこに書いてある作者が掴んだ事実をなるべく正確にこちらも読み取ろうとするので、
単語ひとつの意味も私がとらえている意味だと、こうだけど、
それじゃあ、なんか、よく意味が分からない…と立ち止まりながら読むので骨が折れます。
今、読んでいる本も難しくはないのですが、時々立ち止まってしまいます。

この本で書かれている状況は、リハビリ現場でのセラピストと子どもとの関わりですが、
私が子どもたちと一緒に学ぶときに、頭に置いておくべき示唆に富んでいます。
例えば、子どもとのリハビリが成立しないため、その子が拒否せずに参加できる課題を行ったとき。
それは、一時的には課題が成立したように見えても、
自分ができなさそうなことは拒否する自己防衛的な振舞いを強化させることになっていることがある、ということ。
例えば、集中して課題に向かうようになり、
本人が参加できる形で課題を続け、少しずつ難易度もあげて、本人も楽しんでいるように見えるとき。
実は、本人ができるだけ集中できる課題を繰り返した結果、
その子は、その時間を機械的にやり過ごす、という自己防衛的な振舞いを強化していたに過ぎなかった。
などなど。
私の日頃の関わり方によっては、
子どもの自己防衛的な振舞いの強化につながるかもしれない、
あまり、私の視点にはなかったことがこの本には書かれていました。
一見、できていると見せかけての、自己防衛強化。
これでは、子どもの中に何も入らないし、残りません。
やり過ごし方を学ぶだけ、ということにもなりかねませんから、厄介なことですね。
こうやって仕入れた知識が、私の中で消化されて生きるのか、
忘却の沼の澱となって、沈んでいくのかはわかりません。
それにしても、世の中、当たり前ですが、
知らないことだらけですね