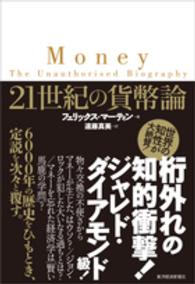
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784492654651
みなさん、太平洋にうかぶ南の島で、石でできた巨大なお金を使う(もしくは使っていた?)人々がいるのを聞いたことがあるだろうか?
わたしはこの話を中学校のどっかで聞いたことがある。
そこでは教員は
「その南の島の人たちは、石でできたとっても重たいお金を毎日転がしてお買い物に出かけていたから、とっても大変だったんですよ」
なんて言っていた。
当時わたしは
「そんな非効率なことを毎日やってるわけないだろ。バカかこいつは。どうせこういうのは100万円くらいの超高額貨幣だったんじゃないの?」
などと思っていた。
実際のところどうなのかまでは当時わからなかった。
ただ、少なくともその教員が言っていることが額面通り正しいことは絶対ないということだけは当時確信をもっていた。
むしろ発展途上国の人たちはそれが非効率であることに気づきもしないほど脳ミソが足りないヤツらなんだとでも言いたげな不遜な口調にイラッとしたもんだ。
では。
正解はどうなんだろうか?
それは実はこの本の冒頭20ページくらいのところにある。
日常の決済のほとんどは信用取引になっていて、債務は相殺、相殺しきれなかった分は次期持越し、石のお金を動かす決済はまれだった、そのように書いてある。
これを読んでどう思うか?
「だから何? そんなのどーでもよくない? それが俺たちにどう関係するわけ?」
そう思った人へは話はこれでおしまい。
「マジか! 非文明国でそんな高度な決済が日常的に使われているなんて…こいつはすげえ!」
少なくともわたしはそう思った。
この本はそういうところから始まる。
原初の文明からはじまり、貨幣を用いた決済システムや為替がいったいどういう紆余曲折を経て進化してきたか。
世界史や経済史に詳しい人でもほとんど誰も知らないような進化の歴史がこの本のあらゆるところに書いてある。
基本的にわたしは学校教育における日本史や世界史というものが嫌いである。
それは、全体の進化の系譜という流れについて軽視しており、ただ起きた事実の暗記だけが重要なのだという、日教組の教育論を軽蔑しているからであるところが大きい。
「鎌倉幕府ができた年はいつですか?」
なんて問い、100歩譲ってもこれに意味があるとは到底思えないからだ。
(なお東大卒のヤツは「これは暗記力を試すものであって意味なんてない!」と言っていた。したがって1万歩くらいゆずれば意味があるような気はする)
だが。
そんなわたしでも、この本のような話はとてもおもしろいと感じている。
世の中にあるしくみの動作原理を理解すること。
これは、学校教育における日本史や世界史が得意で物理が嫌いなヤツらが持つ興味より、我々のような理系の人間の知的好奇心を満たすものだ。
魂の源泉からあふれ出る知的好奇心を抑えがたい人。
あなたはこの本を買うといい。
きっと驚きをもって読めるはずだ。
しかし。
暗記が得意だから日本史や世界史が好きだという人。
あなたは買わないほうがいい。
きっとこの本のおもしろさを理解できない。









