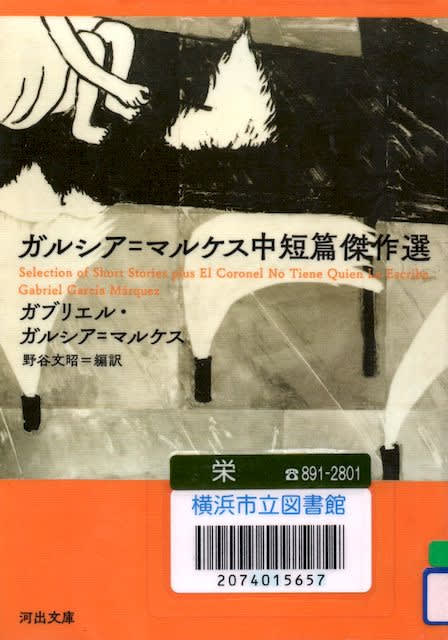
『百年の孤独』を起点に、それにインスパイアされた作品を読み進めるうち、昔によく読んだ安部公房を再読するに至っているのですが、ここらへんで一度ガルシア=マルケスに戻ってみよう、と図書館で2冊借りてきました。
長編の『族長の秋』から読み始めたのですが、これがかなりの難書です。ガルシア=マルケス慣れしないと読みにくい一冊なので、『族長の秋』はのんびり読むことにして、並行してこちらの短編集を読むことにしました。

こちら内容紹介。

目次はこちら。
ガルシア=マルケスの作品は『百年の孤独』しか読んでいなくて、そこでは頻出する同名人物や奇想天外な展開に戸惑ったのですが、中短篇は読みやすい作品ばかりでした。安部公房が上智大学の講演の最後に「でもガルシア=マルケスの短編くらいは、右脳のためにもね(読んでおくといい)」と締めたほどで、この作者は短篇から入るのがよいのかもしれません。
『大佐に手紙はこない(1961年)』1990年にガルシア=マルケスが来日した際、女性記者からのインタビューで「自作では何が好きか?」の問いに挙げたのが、この作品だそうです。退役大佐が、いつまで待っても届かない年金を待つやるせなさが漂う作品です。筒井康隆がガルシア=マルケスの文学を、「やるせなさの文学」と呼んだそうですが、まさに言い得て妙だなと思いました。
『火曜日のシェスタ(1962年)』泥棒と間違えられ射殺された息子の弔いに町を訪ねる母子の話です。これは最初から最後までやるせなさに浸る短篇です。『百年の孤独』にリンクするようですが、わたしはそこまで『百年の孤独』を読み込んでないので真の面白さは味わえていないのかもしれません。マルケスの作品は、このように他作品にリンクするものも多いようで、バルザック的な構成を感じます。それを他の棲むためには相当に気合を入れて読む必要がありそうです。
『ついにその日が(1962年)』歯を抜くことをモチーフにした復讐譚。これも読みこんだ人だから理解できる面白さがあるのかもしれません。
『この町に泥棒はいない(1962年)』行きがけの駄賃でビリヤードボールを盗んだ主人公、過大に被害を申請するずる賢い被害者、冤罪をきせられる黒人が織りなすストーリ、語彙が乏しいのは自覚しますが、やはりこれもやるせない。
『バルサタルの奇蹟の午後(1962年)』この世のものではないような鳥かごを作った職人の気質を裏切る金持ちの狡猾さ、職人の悲嘆と自暴自棄、これまでの作品のすべてはハッピーエンドではありません。これまた読後感がやるせない。
『巨大な翼をもつひどく年老いた男(1968年)』みじめな天使の物語、マジックリアリズムの作品といってよいでしょうか。幻想的ではありますが、美しさよりも切なさを感じます。
『この世で一番美しい水死者(1968年)』死してなお美しい巨大な青年、エスコバンとは何者?調べてみたけどよくわかりません。こちらは美しくかつ幻想的な短編。
『純粋なエレンデラと邪悪な祖母の信じがたくも痛ましい物語(1972年)』長いタイトルの通りの作品、孫を少女売春させる鬼婆が、マジックリアリズムの手法を駆使して描かれています。不可思議なラストシーンも象徴的。本書の中でいちばん印象的な作品でした。
『聖女』正者のままの状態を維持する娘の死体をもつ父親が、ローマ教皇に謁見を求めるもかなわず時間の流れの中にとどまり続ける話。これまで読んだマルケス作品の舞台は南米の架空の社会(マコンドとか)でしたが、この作品の舞台はローマ、マルケスならではの皮肉がこもっている作品のようですが、それを完全に理解するには至りませんでした。
『光は水に似る』途中までは明るいファンタジー作品かなと読み進めていましたが、ラストはやはりダーク。ストーリーの類似性はありませんが、どういうわけかハーメルンの笛吹き男のラストの怖さと重なりました。
そんなこんなで、手軽に面白く読めた一冊です。ガルシア=マルケスの他作品をもっと読み込むと、それらとの関連性からさらに楽しめるような気がします。わたしはそこまで達していませんが。

著者と訳者のプロフィール。

書誌事項。
p.s. 正月料理で体重が不安だったが、なんとかDWクリア。2500引いて残りなし。
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます