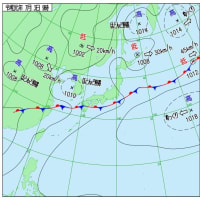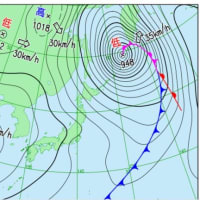最近、いわゆるイジメを受けたということが原因で自殺する子供のことが報じられることが目につく。筆者の子供の頃にもイジメらしいことはしばしばあった。イジメという言葉はその頃にはなかったが、現象としては同じであった。しかし、どんなに激しいイジメにあっても死ぬと言う考えには至らなかった。周囲の子達から疎外されて共有時間を持てなくとも、その時間を読書に当てたり、植物や星、丁度礼文島で皆既日食があったので日食はどうして起きるのだろうかなどいろんなことを考えることに使って過ごすことが出来た。そういうことは先生や親などが教えてくれたことではない。そしてその結果、沢山の知識を得ることが出来た。もちろん筆者は特別な才能の持ち主ではないし、毎日が生きることで精一杯の生活状態であったことは日本中の同世代の子供達と何ら変わらないと思う。筆者は、いつの間にか年を重ねるごとに自分のことは自分の力で周辺の状態を変えて行かなくてはならないと思うようになった。しかし、今の子供達は何かが起こっても、いつも親や周囲の人たちが何らかの援助の手を差しのべてくれると思うような育ち方をしてしまったのかもしれない。そして自分では何も出来ないのだと思い込んでいるのかもしれない。もしそうだとしたら、そういう状況を作ってしまった大人である筆者達の責任は重い。これは本当の意味で社会状況を改善しなければならないことであろう。例えば教育について考えると、社会の変化によってころころ変わる教育行政を筋の通ったものにしなければならないであろう。
ここで教育について考える。もちろん筆者個人の考えであるから、筆者と異なる意見を持っている人がいてもおかしくないし、そんな人がいることの方が当然ともいえる。
はじめに、「教育とは過去に蓄積されてきた知的財産を配分することである。知的財産を配分する所を学校という。」と定義する。
知的財産の配分であるから、すべての人に均等に行きわたらなければならない。これは日本国民については、日本国憲法で保障されている。もちろん現在知られているすべての知的財産を配分すると言っているのではない。それは義務教育9年間で、個人が生活していくために必要な知識、技術、芸術などの基本的な部分について学校で教育という形で実施されている。
より高度の知的財産の配分に預かるためには、配分を受けるものがそれ相当の努力をして上級の教育機関に進まなければならない。上級の教育機関では教えられるということはなく、自ら学習し研究していくことになる。したがって、上級の教育機関に進むためには、かなりの努力とある程度の資質が必要になる。現在の日本の状況は、大学への進学率はかなり高い割合である。しかし、昨今話題になっているように大学卒業後就職して社会貢献をする機会が得られない人たちが多数いるという。そのために、大学3年生になると早くも就職活動をするようになる。いちばん学習に目的を持って望む時期にそれ以外のことに全力を注がなければならないのは学生にとって不幸であるとともに日本という国にとっても大きな損失になるのではないだろうか。
しかし、もし筆者が企業人であったとしたら、まともに勉強をしてこなかった学生を自分の会社へ入れることには少なからず疑問をもつであろう。2005年くらいまでは、4年生になってから就職活動をして、遅くも7月中にはゼミ所属の学生の全員が内定を手にしていた。その理由を考えると、3年生のゼミではある事象に関してそれが起こった原因、当時の時代背景、それが社会にどんな影響を与えたかなどについて調査し、分析し得られた結果についてまとめ、全員の前でコンピュータを使って報告をする。報告は約1時間ほどに及ぶが、紙に書いた原稿を読むことなく(国会討論をTVで見ると首相を初め多くの大臣が原稿を読んでいるように見えるけれども少し情けないと思う)、画面上で説明をする。報告の後で全員で議論をする。議論ではどんなに過激なことも中傷でない限り許される。質問に答えられないときはみんなで回答を探す。発表者は回答が見つからなかった場合は、次回までに調査をして報告する。このような発表は、年間5~6回行うチャンスがある。こうして、調査法、発表技術、議論の仕方そして挨拶の仕方について学ぶことになる。その付随する効果は、言葉遣い、国語力、EXCEL、WORD、POWER POINTなどのコンピュータ使用スキルの向上、などにつながる。さらに筆者のゼミでは、パソコンを組み立てる実習、ホームページ作成、アルバム作りなども行った。学園祭には、お客さんの写真を写して、額縁付けやカレンダーに取り込む、その他PhotoShopを使った加工も行い大変喜ばれた。
大学3年生は、このように自分を磨く非常に大切な時期である。筆者が企業人であれば、このような経験をしてきた学生を優先的に入社させるであろう。
報道によると政府は、大学卒業後3年間を新卒扱いにするなどの案を考えているようであるが、その意味はどこにあるのだろうか。筆者は、そんなことをすることに疑問がある。日本の将来を考えるならば、就職活動は大学4年生になるまで禁止し、3年生までは勉学に励むようにする方が良いと考える。学生も大学3年間は、自分の将来を考えて自分の付加価値を増加させる。企業も3年生までの学生の就職活動に応じないことにする。以上筆者の独断と偏見に基づいた意見を述べた。