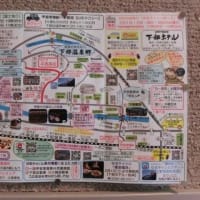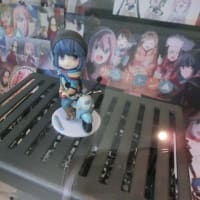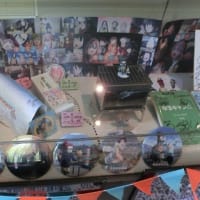丸太町通との交差点より長辻通をさらに北上しました。この道は平安期には「朱雀大路」と呼ばれて当時の嵯峨地区の南北の主軸路でありましたが、その第一の機能は大井津からの材木の運送路でした。なので、現在のように清凉寺門前まで繋がっていたかどうかは分かりません。
ですが、清凉寺の位置には九世紀の時点で嵯峨天皇の皇子にして臣籍降下した左大臣源融の別荘「栖霞観(せいかかん)」がありました。源融の一周忌に当たる寛平八年(896)に子息が阿弥陀三尊像を造立して「栖霞観」内に阿弥陀堂を起こし棲霞寺と号しました。いま清凉寺霊宝館に収蔵される国宝の阿弥陀三尊像が、その棲霞寺草創時の本尊です。
さらにその後、天慶八年(945)に、醍醐天皇皇子重明親王の妃が新堂を建て、等身大の釈迦像を安置しました。いま清凉寺を俗に「嵯峨釈迦堂」と呼びますが、その「釈迦堂」の名の起こりがこの時であったとする説があります。重明親王の妃が祀った等身大の釈迦像は、もちろん現在の本尊である「三国伝来の釈迦像」とは別です。
そのような「栖霞観」および棲霞寺が九世紀の段階で存在していましたから、「朱雀大路」はたぶんその門前まで繋がっていた筈です。中世に「三国伝来の釈迦像」への信仰が盛んになってから、「朱雀大路」は「出釈迦大路」とも呼ばれて「嵯峨釈迦堂」への参詣路となりました。いまでもこの道を俗に「すさか道」と呼ぶ場合があるそうですが、「すさか」とは「出釈迦(しゅつしゃか)」の訛りです。

途中の道端にある道標です。右は鳥居本、左は嵐山、とあります。嵯峨街道のルートを端的に示しています。嵯峨街道は中世戦国期の「出釈迦大路」から西へ延びる鳥居本への支道を江戸期に丹波国への往還路の一つとして再整備する形で成立したものとされています。
もちろん、嵯峨街道のルーツは古代以来の山道であっただろうと思いますが、それよりも大堰川を経ての舟便による交通のほうが便利で時間もかからなかったからか、中世戦国期までは大堰川経由の水上ルートがよく使われたようです。戦国期に管領細川氏の家臣として山城国半国守護代も務めた香西元長が、嵯峨統治の拠点として嵐山に城を築いたのも、眼下に大堰川の水上交通を掌握出来る位置にあったからでしょう。

長辻通をさらに進むと、道の突き当りに建つ「嵯峨釈迦堂」こと清凉寺の仁王門が見えてまいりました。中世戦国期には清凉寺も含めたこの範囲も、都市地区に含まれて大路の両側には十数の寺院が甍を並べていました。

清凉寺仁王門を望遠モードで撮影しました。かつての「朱雀大路」、「出釈迦大路」である長辻通が右に幅を狭めていますが、これも中世戦国期の名残であるようです。室町期の応永三十三年(1426)に描かれた「山城国嵯峨諸寺応永釣命絵図」でもこの大路が釈迦堂の門前で幅を狭めて描かれるからです。

長辻通を嵯峨小学校の横まで進み、校門の鉄柵の間より中を見ました。上図のように、樹木の下に一本の石標が見えました。

デジカメの望遠モードで引き寄せて撮影しました。

御覧のように、「天龍寺塔中 招慶院旧址」と刻まれています。「山城国嵯峨諸寺応永釣命絵図」にも記載される天龍寺の塔頭の一つで、江戸期嘉永三年(1850)の「天龍寺文書」の「絵図目録」に42ヶ寺が列挙されるなかに含まれています。その位置は天龍寺境内地の外であったため、「処々散在塔頭分」とされています。
招慶院は、もとは霊松院といい、室町期の応永八年(1401)に夢窓国師の高弟の絶海中津が住したと伝えられますが、詳細は不明で、明治初年同じ塔頭の喜春院と合併して廃されました。四年後に喜春院も廃止されましたから、法灯は完全に絶えてしまったわけです。
そして招慶院の敷地と建物は、明治五年に創設された上嵯峨校へ転用されて教育施設として使用されました。上嵯峨校の後身が、現在の嵯峨小学校です。
時計を見ると既に16時を過ぎていました。気温も下がってきたかな、と思いましたので、今回の散策はここで切り上げて終わりにしました。もうこれ以上の見るべき史跡、場所も無かったからです。
かくして、近くの「嵯峨瀬戸川町」バス停から市バスに乗って帰りました。 (了)