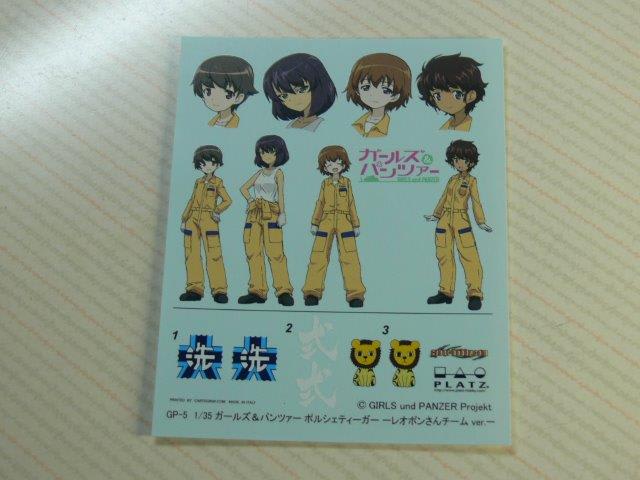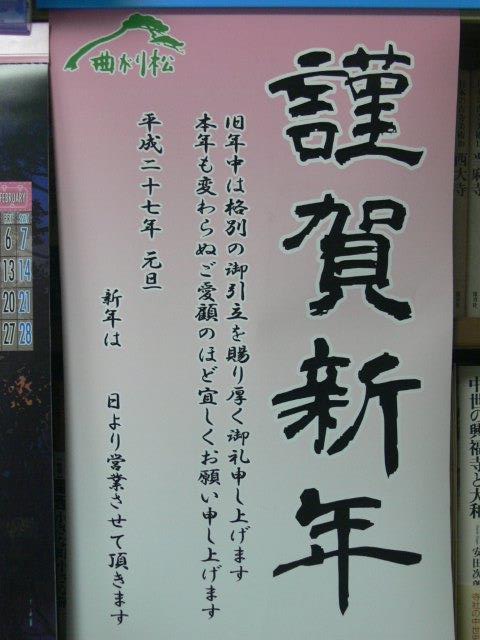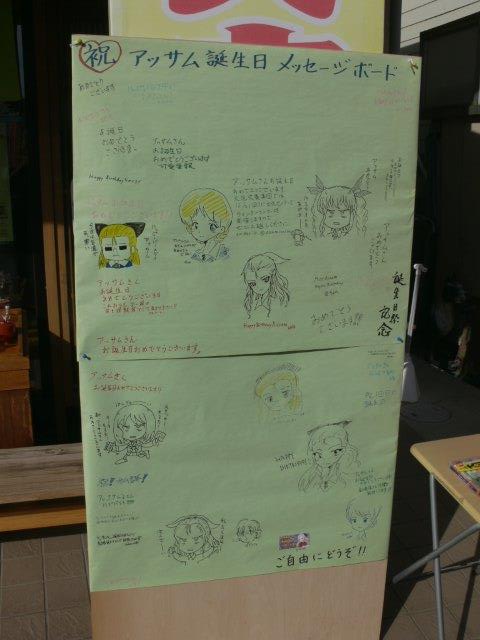この日の夕食は、水戸にて友人といつもの店でとる予定でしたが、早くも空腹感を覚えたので、大洗を出る前に少し食べておくことにし、お好み焼き道に立ち寄りました。来年春からの道路工事にてこのお店は立ち退きとなるため、新年1月末日をもっていったん閉店する、と聞いていたからです。最後の機会かもしれないので、入って焼きそばを軽くいただきながら、女将さんと色々話しました。
前回は水浜電車廃線跡の見学の折に立ち寄りましたが、その時のことを覚えておられて「来年早々に線路跡も工事で無くなるみたいですよ」と教えて下さいました。大貫停留所跡の駐車場も、向かいの大野屋レストランや金子屋薬局も立ち退きで無くなる、ということです。金子屋薬局はこれを機に店をたたむそうなので、劇中シーンにも「兼子屋薬局」の名で登場してカバさんチームⅢ号突撃砲の活躍の場になったお店が消えることになります。寂しいことですね。
お好み焼き道や大野屋レストランは、場所を変えてまた営業されるそうなので、新たなお店に行くのが楽しみです。
大洗駅を18時56分発の列車にて発ちました。ガルパンラッピング車輛2号車でした。水戸駅には19時13分に着き、友人夫婦と中央改札口にて合流しました。
「やあ、ござったな。どうだった」
「今回も色々と忙しく回ってた」
「だろうな、のんびりと過ごしているっていうイメージが全く無いからな」
「そんなに忙しい奴にみえるのかね」
「あははは」
横から奥さんが「今回もしゅんさいに行かれました?」と聞いてきました。いえ、と首を横に振ると、残念そうな表情になりました。完全にしゅんさいの大ファンのようです。
いつものお店、とは大洗栗崎屋の支店のひとつ「すし一番」でした。水戸駅から近い方のお店なので、これまでにも五回ほど入っています。もう一つの支店「海鮮どんどん」へも何度か行きましたが、メニューは全く同じなので、どちらに入っても栗崎屋の味が楽しめます。
寿司定食をいただきながら、今回の城跡探訪の成果などを報告しました。大館館遺跡、小館館遺跡については二人とも興味深々のようで、特に鉾田市出身の奥さんの方が色々と積極的に質問してきました。そういうあたりは、15年前に京都の芸大で同級生だった頃から変わっていませんでした。郷土の歴史文化にとても詳しく、大学での卒業論文のテーマも鉾田市の文化財に関する内容だったと聞いています。
それで、奥さんが問うには、大館館遺跡、小館館遺跡はいわゆる「南方三十三館」に含まれるのか、ということでした。これに対する明確な解答は、どう考えても出てきませんでした。
「まあ、可能性の問題ですね」
そう答えると、U氏が「三十三館っていうけどさ、いま残ってる城跡を合わせても三十ヵ所も無いんだろ?鹿島と行方の二郡合わせての数というなら、鹿島郡に含まれてる大洗の城も数えてるかもしれんぞ」と言いました。相槌をうちながら奥さんも「そうそう、大館館と小館館の城主も佐竹に滅ぼされたんですよ、きっと」と言いました。
「あのう、美和さんはやっぱり大館館と小館館の城主は常陸大掾氏の系譜に連なっていたと考えるわけですか」
「そうじゃないか、って思いますよ。いまじゃ伝承も記録も残っていないといいますからね、これは滅ぼされて全ての歴史を抹殺された結果じゃないかな、って考えるんです」
「でも、「和光院過去帳」に記載される十六人には、大館館と小館館の城主に該当するような人物は含まれていないみたいやけど・・・」
「それは、大田城で謀殺された人々のことですし、その後の佐竹の侵攻で滅ぼされた城主たちも居たはずですよ。常陸大掾氏の系譜筋は全て滅ぼされたということですから、そのなかに大館館と小館館の城主もいたんじゃないかと・・・」
U氏は笠間市の出身なので、中世戦国期の歴史に関しては国人領主笠間氏のほうに愛着があるようですが、奥さんは鉾田市の出なので、当地に歴史を刻んだ大掾氏系列の「南方三十三館」の歴史に相当な思い入れがあるようです。
その「南方三十三館」の城主たちを、戦国末期の天正十九年(1591)二月に佐竹義宣は居城の大田城に呼び寄せて謀殺し、直後に鹿島行方二郡に侵攻して「南方三十三館」の全てを攻め落としました。世にいう「南方三十三館仕置き」ですが、卑劣なだまし討ちの典型例として、現在でも地元の伝承などに深く根付いて語り伝えられています。だから、江戸期に秋田へ移封して名君といわれた佐竹氏も、鹿行地方においては残虐非道の極悪人として未だに悪く言われているようです。
それで奥さんも「佐竹氏」と言わずに「佐竹」と呼び捨てにしています。私なんぞは佐竹義宣を「伊予守」とか「右京大夫」と呼びますが、奥さんに一度「佐竹の官位なんて官位じゃないですよ」と不満げに言われたことがあります。奥さんの旧姓は鎌田(かまた)なので、「南方三十三館」の城主の一人として謀殺された烟田(かまた)氏の末裔なのかもしれません。実際に末裔だとしたら、先祖を謀殺した佐竹氏をこころよく思うはずがありません。
なので、私は大館館と小館館の城主が最終的には佐竹氏かその家臣であった可能性を、しまいまで言い出せずに終わりました。楽しい夕食での歴史談義を、気まずい方向へ持っていくのもどうかと思ったからです。奥さんは「大洗だって鹿島郡なんだから、佐竹に滅ぼされてしまった武士勢力があったに違いないよ、だから戦国期までの歴史が空白になっちゃったんだよ、きっと」と力説していました。
ですが、私自身としては、どう考えても奥さんの言うような歴史的イメージが湧きませんでした。大洗エリアでは佐竹氏の侵攻を受けた痕跡がなく、むしろ那珂湊と共に「大貫村」までが佐竹氏領となって代官職に根本氏が就いています。在地武士とみられる大貫氏に至っては一伝に「譜代之由」とあって佐竹氏に三代以上仕えていたとする認識が記されます。大洗エリアは早くから佐竹氏支配圏に含まれていたのではないか、と考えています。
現に、登城遺跡などは在地武士には似合わない規模と経済力を示しており、これと指呼の間にある龍貝館跡や字後新古屋遺跡の様相も、かなりの有力な勢力の関与を思わせますので、それらと尾根続きに位置する大館館と小館館にも同様なイメージを想定したほうが良さそうに思います。この場合、かなりの有力な勢力、とは佐竹氏以外に候補が思い当りません。
佐竹氏は長年にわたって鹿行二郡の掌握をひそかにもくろみ、在地の大掾氏系列「南方三十三館」の勢力の殲滅の機会をうかがっていたのですから、有事に備えて最前線にあたる大洗エリアの南部に何らかの備えを施していた、と考えるのが自然でしょう。「南方三十三館仕置」の直後に侵攻した軍勢は一万を超えたとも言い伝えられていますが、事実であれば、それほどの兵力をどこから動かしたかが問題になります。
「南方三十三館仕置」が成功すればただちに攻め込むという計画で、あらかじめ兵力が準備されていたのであれば、その軍勢は鹿行二郡にすぐに展開出来る場所に配置されていた筈です。その候補地として登城遺跡、字後新古屋遺跡、大館館遺跡などの、在地城館にしては広すぎる規模の遺跡群が注目出来ます。
それで、私の現時点での仮説として、登城遺跡、字後新古屋遺跡、大館館遺跡などの最終段階が、天正十九年(1591)二月時点の佐竹氏の兵力の駐屯地であった可能性を指摘しておきます。これらの遺跡に城主や由緒などの記録が残っていないのも、在地支配の拠点ではなく、佐竹氏による一時的な軍事作戦の駐屯地として使用されたため、と考えれば辻褄が合います。
もしそうであれば、城主は存在せず、佐竹氏家臣が代官もしくは城代として任じられるだけなので、登城遺跡のように代官職根本氏の名が記録されていても違和感はありません。
夕食後は水戸市内原の友人宅に泊めていただきました。まいわい市場で買ってきた干物や酒などを渡してささやかな二次会となり、今回貰った缶バッジなどを披露しました。
U氏は「なんでこう、次から次へとバッジを出すんだろうな」と不思議がっていましたが、奥さんは「大洗の商店街としてはこうでもしないとファンのリピーターや新たなファンに来て貰えなくなるからでしょうね」と核心を突いた見方をしていました。
「だって大洗って、昔からの海水浴場だったし観光地だったから、それなりに賑わっていたはずなんだよ。ガルパンのブームでそれ以上に儲かっていい思いをしたから、そういうのから離れられなくなったんでしょうし、ブームが去った後の元の状態には戻れない体質になっちゃったのと違うかな」
さすがに地元民の見方は冷めてるなあ、と思いました。ひょっとしたら、大洗で盛り上がっているのは一部の商店街と常連ファン達だけなのかもしれない、と考えてしまいました。
翌日は、朝からU氏と水戸市内を回りました。中世戦国期の歴史に関する資料とかを調べたい、と話してあったので、最初に水戸城跡内にある茨城県立図書館へ案内して貰いました。
何度見ても見事な、江戸期水戸城の空堀です。前回は下草がありましたが、今回は草刈り整備の後なので、遺構面が綺麗に見えました。
虎口跡を通り両脇の立派な土塁をみながら、旧城内に進みました。
茨城県立図書館です。その二階の郷土資料室で、U氏と手分けして大洗地域や周辺の中世戦国期に関する資料を検索しました。思った通り、大洗町の報告書類は数も少なく内容も簡素で、私たちが既に得ている情報以上の成果は得られませんでした。大洗町の埋蔵文化財調査報告書も三冊ほど閲覧しましたが、内容的には「茨城の城郭」のほうがしっかりしているので、そのコピーをとって貰いました。
続いてバスに乗って茨城県立歴史館へ行きました。他県の県立歴史博物館に相当する施設で、歴史関係の刊行物も充実しているそうです。ただし、中世戦国期に関する資料があるかどうかはU氏も知らないそうで、この機会にきちっと調べておこう、と話していました。
茨城歴史館の公式サイトは
こちらです。
敷地内にある旧水海道小学校本館を見学しました。明治十四年(1881)の建築で、明治初期の小学校建築の形態を伝える遺構として、昭和三十三年に茨城県文化財に指定されています。その紹介記事は
こちら。
敷地内の屋外展示品では、上写真の石幢が興味深かったです。室町期の遺品なので、まさに中世戦国期のものです。仏教の石塔の一種で、六角または八角の石柱の上に仏龕(ぶつがん)や笠、宝珠などを載せた意匠に造られます。外見上は灯籠に似ていますが、仏像を安置し祀る施設にあたるので、灯籠とは別です。源流は中国にあり、日本には中世期に伝来し、現存遺品は室町期からのものが多いです。
石幢の有名な遺品は、東京都立川市の普濟寺の延文六年(1361)銘のそれで、国宝に指定されています。普濟寺の公式サイトでの紹介記事は
こちら。
茨城県では、石幢を灯籠型に造ることが多かったとありますが、六地蔵を石幢や石灯籠の六面に配置する遺例は、近畿ではあまり見聞きしたことがありません。むしろ中部や九州に分布しています。
歴史館の建物は、城郭の石垣を思わせるようなデザインの外観でした。常設展示コーナーや刊行物コーナーで色々と探し、館員さんにも訊ねたのですが、中世戦国期に関する資料はあまりなく、研究も進んでいないとの事でした。常陸国の中世戦国期関連の研究は、地域的にばらつきがあり、鹿島神宮に多数の史料が伝わる鹿島郡の関係でもまとまったものが少ない、ということでした。
むしろ、城郭研究者や城郭ファンの方がそうした歴史の研究にも早くから着手している傾向があるので、その関係の刊行物やネット情報などを検索した方が良いように思いました。
調べ終わってから、館内の休憩スペースでコーヒーを飲みながらU氏と話しました。相手は、昨晩の夕食の際に私が最後まで何かを言い出せなかったことを察していたようでした。
「ここには美和はおらんから、話してくれよ。重要な事なんだろ?」
「そうやな、今の時点では単なる仮説に過ぎないんやけどな・・・」
「仮説でも、重ねれば史実や真実ヘの道しるべとなるんだ。違うか?」
「そうやな、つまりは大館、小館の城跡に関することや」
「ふむ?」
「あれは、たぶん最終的には、三十三館殲滅作戦の拠点として使われたんじゃないかと思う」
「だろうな、俺もその可能性を考えてるよ。でも言ったら美和が怒るからな」
「ちょっと聞きたいんだが、美和さんはやっぱり烟田城の釜田兄弟の末裔なのか?」
「俺も詳しくは知らんのだが、その本家にあたる家の長老さんが烟田城の西光院の檀家でな、いちど「烟田八館」の子孫たちを集めて慰霊の会とかを主催していたよ」
「それじゃ、完全に烟田城の末裔じゃないか・・・」
「まあ、そういうことなんだろうな」
それで、大館、小館の城跡に関することとは何か、と問われました。
「南方三十三館仕置の状況は詳しく分かってないそうやが、一万を超える軍勢が動いたという伝承もある。佐竹氏としても宿願の達成ということになるんで、佐竹氏は当主みずから大将に立ったんやろうかな」
「それは当然じゃないかね?石田三成の口利きで豊太閤の許可も得てるんだから、常陸介(佐竹義重)が自ら動いたに決まってるぜ」
「常陸介も出ただろうけど、主役はおそらく右京大夫(佐竹義宣)やな」
「ああそうか、右京大夫の方が三成と親しかったもんな・・・」
「やから、三十三館攻撃の実質的な大将は右京大夫。だが名目上の大将は親の常陸介がなってたはず」
「だろうな」
「この場合、当時の呼び方だと、当主を大殿、その後継者を若殿とかになるけど、古文献とかを見ると大館、小館と呼び分けるケースもあったらしいんでな・・・」
「なるほど、大館館と小館館の呼称がそこからきたというわけか。うん、それは有り得るな。ということは、大館館と小館館の二ヶ所は佐竹氏親子の陣場であった、三十三館攻撃の時の本陣であった、と、こういうわけだ」
「うん、そういう可能性を考えてみたんやけど、どうかな」
「いいんじゃないか。俺にもそういうふうに思えてくるし、遺跡そのものは戦国末期の状態になってるんだろ?」
「昨日見てきた限りでは、どうも南北朝期の城で終わったとは思えなかった」
「なら、その見解を大切にしろよ。もう一度行くんなら、それを再検証してみるんだ」
「その積りや。図面もその時にとってみるよ」
館外に出ました。庭に配置された埴輪のレプリカは、サンタの格好になっていました。
「あと二週間でクリスマスか」
「その一週間後には新年になってるんやな」
「年末年始はずっと仕事だと聞いたが、最初の休みはまとまって貰えるのか?」
「最低でも連休にはなる筈やけど」
「なら、また大洗に初詣に行ったらいいんじゃないか」
「うーん、そういう選択肢もあるか・・・」
そこで、なんとなく笑ってしまいました。私の干支の2014年は過ぎてゆきつつありますが、ガルパンや大洗との縁は、劇場版公開が予定される2015年までは確実に続きそうです。
「だからさ、また来いよ」
「ああ」
そう言って、水戸駅の改札口前にて握手を交わし、手を振って別れました。
以上にて「ガルパンの聖地・大洗を行く13」のレポートを終わります。