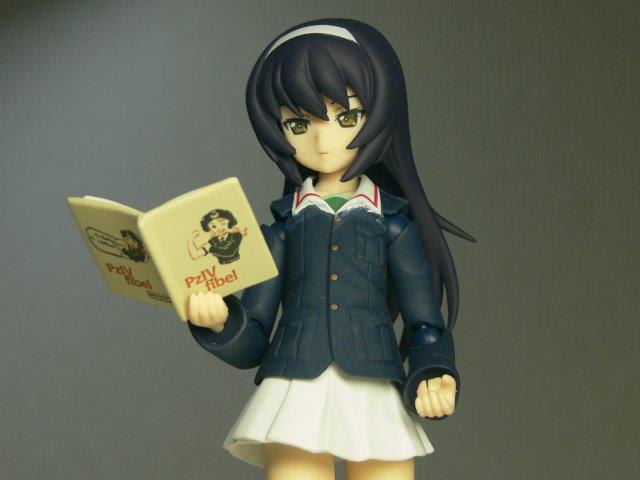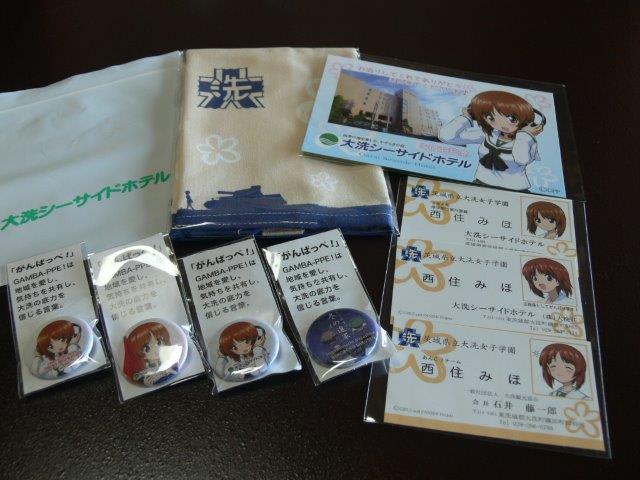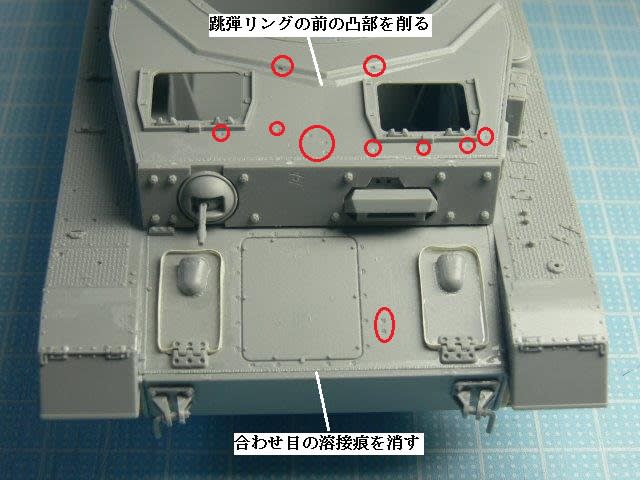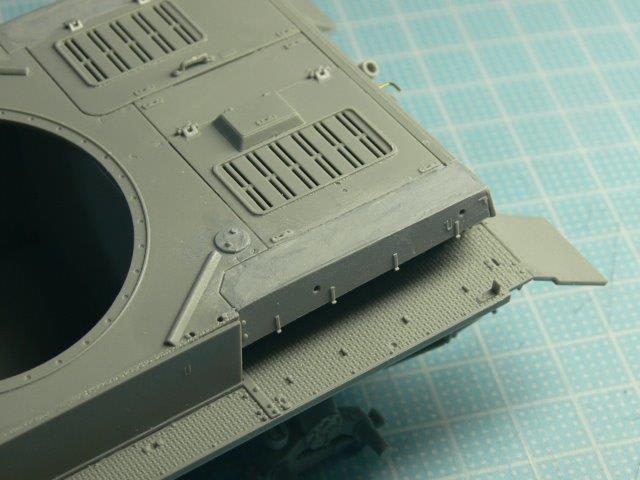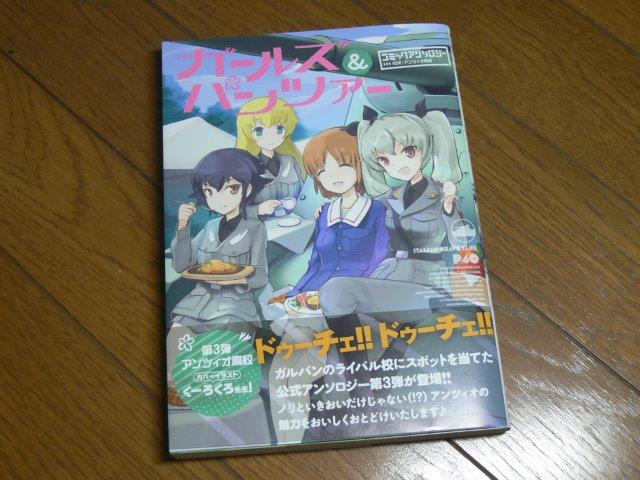山の辺の道を歩いた日から数日後、歴史散策仲間のMさんに「今度は吉野山に行きたい」と言われました。今の時期は天気が不安定なので、吉野山あたりだともっと天候は不安定ですが、と話したのですが、今度はKさんにも「今までにも行こう行こう言ってるけど全然行けてないから、思い切って行かないといつまでたっても行けない、天気が少し悪くたってかまわない、雨が降らなきゃいい」と言われました。
お二人がそこまで仰るのであれば、ということで案内役を務めることにしました。早朝の京都駅を近鉄の特急列車で出発しました。
京都から吉野へ近鉄で行く場合、橿原神宮駅で乗り換える必要があります。京都線は橿原神宮駅が終点なので、これに連絡する南大阪線にて吉野まで行きます。双方の特急列車は橿原神宮駅で乗り換えられるダイヤになっていて、地元では「吉野連絡特急」と呼ばれます。しかし、実は吉野線においては各駅停車となるので、普通列車に乗っているのとあまり変わりません。
吉野駅に着きました。記念写真におさまるMさんとKさん。車内は陽気でポカポカしていたので眠くなってウトウトしていた、とMさん。
今回は吉野山の奥千本から蔵王堂までのいわゆる奥駈道ルートを下る形での散策となりました。その方が楽ですが、ロープウェーと連絡バスの時間が限られているので乗り遅れないように注意しました。一気に奥千本の金峰神社境内地まで移動しました。
金峯神社(きんぽうじんじゃ)は、金峯山寺蔵王堂の奥宮にあたり、吉野山修験の重要な信仰拠点として多くの施設を有しましたが、明治の神仏分離にて荒廃し、現在は再整備された小さな境内地に再建の社殿がひっそりと建つのみです。付近には数多くの遺跡が草木に埋もれ、修験の石畳道と標識とが、大峰山系へのルートを示しているのみです。
散策ルートの起点は、金峰神社の裏手にある「義経隠塔」でした。源義経が、兄の頼朝に追われて吉野山入りして滞在しましたが、やがて追手が迫り、義経はいったんこの塔に隠れ、屋根を蹴抜けて、 下谷、宮滝の方へ落ち、西河へ敗走したといいます。塔はもともとは五重塔であったのが、一層目だけが残り、覆屋根を追加して現在に至っているということです。
現在の建物は、義経の時代のものではないとする説もあります。古址と言われるぐらいなので、当時の建物は建て替えられている可能性もあります。見た感じでも鎌倉時代の建物という感じがあまりしませんでした。
金峰神社に参拝して奥駈道ルートを歩きだしました。吉野杉の森の下の緩やかな下り道ですが、両側には幾つかのお堂や施設などの遺跡が点在しています。上図の牛頭天王社跡は、明治の神仏分離で廃絶した当地の高城山ツツジが城の鎮守での跡です。いまでは人家も無い山中にありますが、明治初年頃まで付近に人家もあり、境内では盆踊りなども行われていたそうです。
奥駈道ルートを歩きました。Mさんは時々スマホで現在位置を検索していましたが、吉野山の山中では電波も届かないのか、「全然動かん、何も出てこないねん」とボヤいていました。ガイドブックの地図を見た方がええんちゃうか、と言ったら「だよねえ」と笑ってその通りにしていました。
吉野水分神社(よしのみくまりじんじゃ)に参拝しました。この神社は、延喜式内社の一に数えられ、奈良では葛城水分神社、都祁水分神社、宇太水分神社とともに大和国四所水分社の一つとして古くから信仰されてきた古社です。祭神の一つ木造玉依姫命(たまよりひめのみこと)坐像は鎌倉期の佳品として国宝に指定され、上図の本殿を始めとする建築群六棟は豊臣秀頼による再興の遺構として国重要文化財に指定されています。こじんまりとした境内地に建物がぎっしりと並ぶので、実際以上の広がりと奥行きを感じさせます。
私が好きな大和の古社の一つで、吉野山に行く時はここに立ち寄らないと登った気がしません。
吉野水分神社から少し下っていくと、吉野山随一の眺望で知られる花矢倉(はなやぐら)に着きます。ここからは蔵王堂を中心とする金峰山寺の伽藍域と門前の街並みがよく見渡せます。
花矢倉は、吉野比曽寺の鐘楼があることからもとは比曽寺の境内地の一部だったようですが、源義経の潜伏期には防御陣地の一つとなり、義経の忠臣佐藤忠信がしんがりをひきうけて、攻め登る吉野の山僧と攻防戦を展開し、吉野一の悪僧とされた横川覚範を討ち取っています。また南北朝期にも南朝方の防御陣地として使われたようですが、詳しいことはわかっていません。
花矢倉展望台から、蔵王堂を中心とする金峰山寺の伽藍域を望遠モードで撮影しました。桜の時期には全山が桃色に彩られますが、初夏のあおあおとした新緑に包まれる景色もまた格別の味わいがあります。
ひたすら歩いて金峰山寺の門前エリアまで下り、街中の食事処「西澤屋」に入りました。今回の昼食休憩はこのお店でした。私は何度か入ったことがありますが、Kさんが事前にガイドブックで「このお店が評判みたい」と言って決めてあったものです。
今回いただいた「うどん定食」です。天麩羅うどんに、吉野の特産物である柿の葉寿司とデザートが付きます。私はいつもこれをいただいていますが、初めての来店だったお二人は柿の葉寿司が気に入ったようで、本場の味はやっぱり違うねえ、などと話していました。
市販の商品に比べると甘酢がよく効いており、その香りがスッと広がるのが、吉野山で食べる本場の柿の葉寿司の味です。
暑くなってきたこともあり、Kさんの提案で、隣のアイス屋でアイスを買いました。勝手神社の裏階段にて座って食べましたが、いつの間にかMさんが私ホシノのカメラで撮影していました。Kさんはカメラに気付いていましたが、ホシノは写真を見るまで知りませんでした。
中千本エリアの山道をたどりました。桜の時期には花見客で賑わい、混雑して前に進むのにも苦労しますが、新緑の時期には落ち着きを取り戻し、緑の絨毯の中に白い道がくねくねと巡る景色になります。
いつもながらの健脚ぶりを発揮するMさん(上図右のピンクのシャツ姿)。アップダウンの連続に息切れしつつあるKさんやホシノを後ろに引き離しつつ、如意輪寺への長い石段もサッサッと登って行くのでした。
如意輪寺(にょいりんじ)の本堂です。平安期開創の古刹で、もとは真言宗修験の拠点として栄え、南北朝期には後醍醐天皇が吉野に行宮を定めた際の勅願所とされました。寺の背後には後醍醐天皇の塔尾陵(とうのおのみささぎ)もあります。
南北朝期の正平二年(1346)冬、楠木正成の長男の楠木正行が四條畷への出陣に際し、一族郎党とともに当寺に詣で、辞世の歌「かへらじとかねて思へば梓弓なき数に入る名をぞとどむる」を詠みました。正行はその句を本堂の扉に鏃(やじり)で辞世の句を刻んだとされ、その扉とされるものが今も寺に伝わっています。南朝の哀史を伝える遺品の一つとされています。
寺の本尊である蔵王権現像は、鎌倉期の遊品で国重要文化財に指定されています。かつては秘仏扱いでしたが、文化財指定を受けて宝物館に祀られるようになってからは、いつでも拝観出来る状態になっています。
吉野山は役行者が開いた修行場の一つとされ、多くの寺院が蔵王権現を本尊としています。金峰山寺蔵王堂の本尊も同じですが、ここ如意輪寺の本尊像は姿形が最も美しいことで知られています。
如意輪寺から道を引き返して金峰山寺蔵王堂エリアへと向かいました。相変わらず足が速いMさんでした。山伏顔負けのスピードです。数分もすれば視界から消えてしまいますので、私よりも年上であるというのが未だに信じられません。
次に立ち寄った大日寺(だいにちじ)の門です。大海人皇子(後の天武天皇)ゆかりの歴史を伝え、吉野山では最古の寺院とされていますが、伽藍や建物は近年の再興です。ただ、本尊として祀られる五智如来像は、日本でも遺品が稀な藤原期の遺品で、国重要文化財に指定されています。
また、この寺は南北朝の抗争期に南朝の大塔宮の身代わりとなって戦死した村上義光、義隆親子の菩提所でもあり、そちらの方で参詣する方が多いです。
吉水神社(よしみずじんじゃ)に着きました。吉野山観光の主要スポットだけあって観光客で賑わっていました。この神社は、本来は金峯山寺の僧坊の一つ吉水院(きっすいいん)でしたが、明治期の神仏分離によって神社に変わりました。しかし、書院などの建物は僧坊時代の遺構をそのまま残しており、主要部分は国重要文化財に指定されています。
この神社は、歴史的には 源義経らの潜伏地、後醍醐天皇の行宮、豊臣秀吉の吉野花見の本陣、などの故事で知られています。書院内には後醍醐天皇の行宮だった時期の、天皇の玉間などが伝わっています。
学生時代、歴史研究サークルの活動で三回吉野山に行きましたが、吉水神社に行くといつも先輩たちが「君は南北朝のどっちを支持するんだ?」と質問するのが常でした。先輩の一人は典型的な南朝贔屓で、後醍醐天皇の陵墓の方角に向かって恭しく拝礼するような人でした。
そういう先輩方に向かって「私は室町幕府と北朝を評価します」としゃべったものですから、その後しばらくの間は睨まれて、話も出来ないような状態になりました。南北朝の争いじゃあるまいし、と思ったのを覚えています。
でも、奈良では古くから住んでいる方ほど、ウチは南朝方だ、俺んとこは北朝に組みした、などと言い合って喧嘩になる事例が多いそうなので、南北朝期の争いがいまだに尾をひいているのかもしれません。
吉水神社から金峰山寺へ行く途中、ちょっと休んで吉野の葛キリでも食べませんか、と提案し、上図の「八十吉」というお店に入りました。吉野山界隈ではかなり知られた老舗です。公式サイトは
こちら。
写真を撮り忘れましたが、こちらでは「吉野葛きりセット」をいただきました。
金峰山寺(きんぷせんじ)に着きました。本堂は蔵王権現を本尊とするので蔵王堂と呼ばれます。豊臣期の再建ながら日本では東大寺大仏殿に次ぐ大きさの木造建築遺構として国宝に指定されています。
外見上は二層のように見えますが、構造的には一重裳階(もこし)付きで、内部の柱には、原木の曲がりを残したツツジ、チャンチン、梨などの木柱が用いられています。付近の原生林の大木を使用したのでしょうか。
蔵王堂前にてMさんと記念撮影をしました。写真はKさんに撮っていただきました。本尊の蔵王権現は秘仏ですが、護摩法要のためか、厨子の扉は開かれていて、三体の巨像のうちの一体を拝むことが出来ました。
吉野山一帯は2004年に「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部に含まれて世界遺産に登録されており、それを契機としての秘仏開帳が二度ほどありました。なので、かつては拝見も出来なかった蔵王堂本尊像の姿は、いまではかなり知られているようです。
金峰山寺の山門にあたる仁王門です。室町期の康正二年(1456)の再興で、国宝に指定されています。本堂が南面するのに対して仁王門は北面しています。これは、熊野から吉野へ(南から北へ)向かう巡礼者と吉野から熊野へ(北から南へ)向かう巡礼者の双方に配慮したためといわれますが、もとの吉野山への入山ルートが北からつけられていたため、山門を北に向ける必要があったものと考えられます。
門の左右に安置する像高約5メートルの金剛力士像は延元四年(1339)、仏師康成の作で、仏像彫刻史上の重要遺品として国重要文化財に指定されています。
銅鳥居を経て黒門まで下りました。金峯山寺の総門で、黒塗りの高麗門なので黒門の俗称で親しまれています。現在の門は昭和60年の再興ですが、古式を踏襲して造られています。その下でKさんがなかなか来ないMさんを待っていました。
帰りの列車はあべの橋行きの急行でした。でも橿原神宮前駅までは各駅停車なので、特急でも急行でも変わりません。料金的にはこちらの方が安いです。
橿原神宮前駅で乗り換えましたが、京都行きの列車も急行でした。三人とも散策の疲れで寝ていて、京都駅に停車する直前までの一時間近くをその状態で過ごしたことでした。奈良からでも吉野山は遠いので、京都からだとかなりの遠路です。Kさんの言葉通り、思い切って行かないと、なかなか行けない所ですね・・・。
私にとっては、二年ぶりの吉野山でした。やっぱりああいう歴史豊かな地域は良いものです。
風はどこから、吹いてるのでしょうか・・・
青空の下、日差しを受け止めた、吉野山の木々が、誰かに手を振る・・・