今まで使っていた電話機は買ってから20年ほど経つものでした。親機が鳴っても子機が鳴らない。掛けてきた相手が表示されないなど、劣化が出てきました。
それで、電話機を新しくしました。
旧電話機です。
新しい電話機です。
おじさん達3人で一パイをやりました。場所は岐阜の街です
最初に入った店です。
岐阜市羽根町
迦具夜
まずは乾杯から。
冷奴。枝豆。
出し巻き玉子。大根サラダです。
いきなりの飛び込みの店でした。
夕暮れの羽根町。
アチコチ、灯がつき出しました。
次に入った店。
旭日昇天と言う店です。
店内。
若い人が多かったです。
ここでは冷酒にしました。
花串庵の枡。
花串庵のグループ店なのでしょう。
おでんを色々と注文しました。
手前はタマゴに筋肉。右は竹輪にジャガイモ。
奥はコンニャクです。
今日、ヒストリー各務野会が有りました。講師は岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の川上光洋さんです。タイトルは「村国座の建築構造と舞台機構」です。氏は村国座の解体修理に携わっておられました。その経験から、建築士の視点で村国座の解説でありました。
開講前。
談笑する講師。
講師の自己紹介です。
徳島県出身で村国座の大修理に携わられました。
今日の資料です。
1.村国座の優れた建築的特徴。
2.舞台転換機構。
3.農村舞台の祝祭性。 について講義されました。
村国座の優れた建築的特徴についてです。
1.舞台と客席が一つ屋根の下に収容する劇場型、全蓋式の農村舞台である。
2.大屋根を支える構造。10mを越える松を使い三重梁形式の小屋組みで15,000枚の瓦を支えている。
3.芝居小屋の古い姿を伝えている。
農村舞台だけのところは各所に有りますが、客席と舞台が一体化した全蓋式の農村舞台は珍しいです。
しかも、その全蓋式農村舞台は岐阜県に集中しています。
その中では、村国座が一番古い農村舞台です。
講師はこの後、上三原田の舞台(群馬県赤城村)。犬飼の舞台(徳島県徳島市)。祖谷の舞台(徳島県三好市)について話され、祖谷の舞台では襖カラクリの映像を交えて紹介されました。
八甲田山を見てきました。
この映画、エンドロールに1977年と出ていました。今から42年前の作品で、「午前10時の映画祭10」で上映されたものでした。この10時の映画祭。古い映画を上映しています。もう一度見たい人、初めてで古い映画を見たい人には打って付けです。
新田次郎の「八甲田山死の彷徨」を映画化したものです。明治34年に日露戦争の開戦を目前にして寒冷地耐寒訓練を実施した。高倉健の徳島大尉、弘前31連隊。北王子欣也の神田大尉、青森5連隊。雪中行軍を行い、八甲田山麓で両隊が擦れ違う筈であったが・・・・・。
高倉 健
三國 連太郎
大滝 秀治
丹波 哲郎
小林 圭樹
藤岡 琢也
神山 繁
緒形 拳
兵隊役ではないのは加藤 嘉や花沢 徳衛。
もう、40年以上前の作品で多くの俳優が亡くなっています。
ストーリーとして、トップが判断を誤ると・・・・。
全編を流れる芥川 也寸志のテーマ曲が良い。
それに木村大作のカメラも良い。雪原で岩木山をバックにした行軍。良いシーンでした。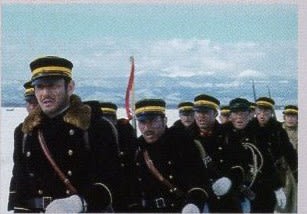
公開から40年を越えた作品ですが、見ごたえのある作品でした。
山の仲間同士の交流の場。ミツルのテントサイトです。
その会の夏の親睦会が名鉄岐阜駅前。白木ビルの8階の炙で開かれ、その会合に参加してきました。
炙の入口。
エレベーターで上がって来ると、直ぐに入口となりました。
久し振りに皆さんと顔を合わせました。
そして乾杯で始まりました。
近況報告。そして社会情勢や健康、年金etc。
中々、山の話にはなりません。
楽遊さんは、山の話しようよ~と言っていました。
トップバッターはサラダからでした。
続いて刺身の盛り合わせです。
こちらは天ぷら。
タマネギを大きく揚げたものや竹輪の天ぷらでした。
この後に厚焼きの玉子焼きが出ました。
最後は鍋です。
豚バラで、鍋は坦々麺のスープのように感じました。
仕上げはこの鍋に麺を入れて仕上げとなりました。
久し振りに皆さんと顔を合わせました。
12時に始まって15時。
15時を過ぎても話は尽きません。
店から、ソロソロと声を掛けられ切り上げました。
今日の参加者、3美女がブルガリアへ行くそうな。
楽しんで来て貰いたい。
気をつけて、行ってらっしゃい。
中央図書館の3階。展示室で写風会 の 第18回写真展が開かれていました。
彩美会の帰りに寄ってみました。
案内ハガキの表と裏です。
展示室の風景です。
日頃の写真の研鑽。
その発表の場として写真展取り組みでした。
1枚1枚に個性を感じました。
今日は第3金曜日で彩美会が有った日でした。
通常通り、絵の学習を行った後、廊下の絵を交換しました。
この廊下の絵。
各務原市西ライフデザインセンターの廊下なのです。
ここで受講している、各サークルの発表の場として活用されています。
6月と7月が私たちのサークルに展示を許された期間です。
絵の展示交換を行った後、8階のぶるーすかいで会食を執り行いました。
先生に加筆して貰っています。
実は、この絵。
5月10日に川島の河川環境楽園でスケッチ会を行った際のモノです。
河川環境楽園の中。木曽川水園の中の大滝をスケッチしました。
最後の仕上げを先生にやって貰っています。
作品が、ほぼ完成です。
この後、廊下の絵を交換しました。
絵の交換を終わって。
みなさんの新しい作品が並びました。
その後の会食です。
産文の8階。
ぶるーすかいで会食会を行いました。
2010年の春から夏にかけて、市の水彩画の成人講座を受講しました。10回の講座が終了した後にサークルとして活動をして行くこととなり、「彩美会」と言う会の名を付けて活動していて、今日に至っています。
絵を始めて丸9年が経ちました。
これからも続けていこうと思っています。
この夏。あいちトリエンナーレ 2019 が開かれます。
そのボランティアとして活動します。
第3回全体研修が開かれました。この研修、第3回ですが、ボランティア活動を行うのに、必ず受けなくては成らない研修です。
その研修を、今日。受けてきました。
会場は愛知県図書館でした。
愛知県図書館へ来ました。
これから館内に入ります。
5階の講堂が研修会場に成っていました。
ボランティア活動について話しをする会田大也キューレーター。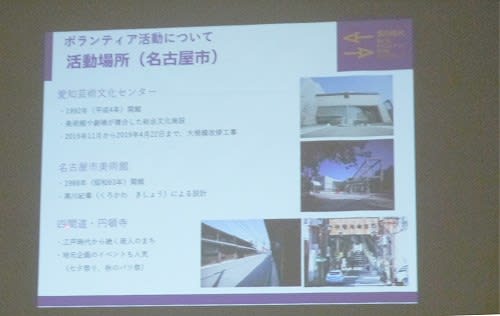
トリエンナーレの会場は名古屋市と豊田市です。
名古屋市は愛知芸術文化センターと名古屋市美術館。それに四間道、円頓寺となっています。
対話型鑑賞体験の研修です。
並んでいる椅子で、前の人と一緒になりグループを作ります。
私のグループは5人でした。
スクリーンに映し出された作品。それはFedexのダンボールと透明アクリルケースが映った写真で、クリード・べシュティの作品です。
この作品を見て、どう感じるかグループ内でディスカッションしました。
来年のNHKの大河ドラマは「麒麟がくる」で、明智光秀を主役としています。その明智光秀の妻が妻木広忠の娘だったと言う説が有ります。
妻木 広忠 (つまき ひろただ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。明智光秀の家臣。美濃国土岐郡妻木城主(第12代目)。旗本妻木氏の系譜では、光秀の叔父とされている。また、光秀の正室・熙子の父ともされるが、典拠となる史料は不明であり、俗説の域を出るものではない。Wikipediaより。
今日はそんな妻木城址と妻木氏の話でした。
講師は中日文化センターで講師を勤める中山さんです。東海古城研究会会員で古城の研究家です。
今日の講師。
中山さん。
会長から紹介を受けています。
妻木城の図を元に講義を進めています。
今回の資料です。
スライドを映してのお話です。
講師が妻木城址へ案内して行って来たときのモノで、城址から山麓を眺望したものだそうでした。
















