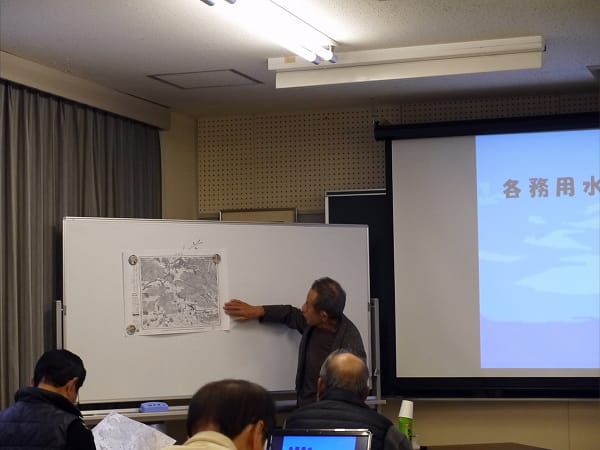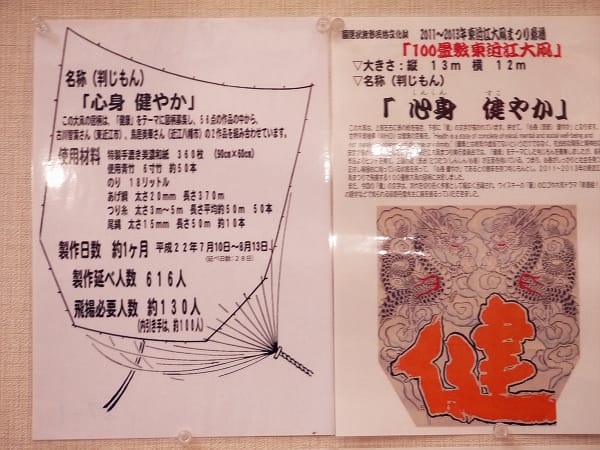「歴史街道を歩く会」の11月例会に参加しました。
今回はびわ湖大橋を渡り、道の駅米プラザに寄りました。その後、堅田の浮御堂へ。次に日吉大社に向かいました。日吉大社の境内へ入る前に穴太積みの坂本を散策して滋賀院門跡を前から拝観。慈眼堂に寄ってから日吉大社へ行き、そして西教寺へ行きました。最後は近江神宮に寄りました。
琵琶湖の西岸。大津市を歩きました。初冬の時期でしたが紅葉したモミジを見る事が出来ました。
浮御堂へ
バスから降りて堅田の街の中を通り、浮御堂に向かいます。
浮御堂に来ました。
竜宮門をぬけて境内に入ります。
浮御堂が見える位置です。
女性が何人か浮御堂をバックにして撮影していました。
どうも、日本の女性では無いようです。中国の人たちでしょう。
ミンナが同じようにサングラスを掛けていました。
ここ、浮御堂だけでなく浮御堂へ向かう道のお茶屋さんでも団体で入っていました。
浮御堂へ来ました。
風が強かったです。
浮御堂の前。
中高年の男性5名がボートを漕いでいます。
湖面に立つ石柱。
石柱に句が刻まれているようです。
ボートが直ぐ前に来ました。
対岸の近江富士が見えます。
風の強い湖面。
構築物が見えます。
穴太積みの坂本散策
坂本のマップです。
坂本観光協会作成。
広い道。日吉参道でバスから下車しました。
この辺り。道の両側に里坊が並んでいます。坂本には何箇所も延暦寺の里坊が立ち並んでいます。
左側の石垣。穴太(あのう)衆積みといわれる石垣です。
この時は穴太衆積みを知りませんでしたが、一つ勉強になりました。
前方に滋賀院門跡が見えます
滋賀院門跡に向かって歩きます。
石垣と滋賀院門跡。
坂本の町を歩いていますと、あちこちで穴太(あのう)衆積みといわれる石垣を見ることが出来ます。
趣の有る石垣が詰まれています。
この石垣。穴太(あのう)積みと呼ばれています。
穴太積みというのは、ここ坂本の穴太の石工集団が積んだ石垣の事を言います。基本的には自然石を積み上げる野面積みです。穴太でこうした石垣を積む技術を持った集団のことを「穴太衆」と呼んでいます。
坂道を登っています。
振り返ると後方に琵琶湖が見えます。
慈眼堂に向かっています。
紅葉も終わりの時期を迎えています。
慈眼堂に入りました。
古い墓石が並んでいます。
阿弥陀如来石造が並んでいます。
立派な墓石が並んでいます。
穴太積みの石垣の横を歩きます。
石に黒い線がマークして有ります。
石垣が崩れて補修したのでしょうか。
東北旅行に行った時、石積みに関係して、女性が「あのうしゅう」と言う言葉を喋った事が記憶に残っていました。その時は「あのうしゅう」ですから、伊勢自動車道に安濃サービスエリアが有り、安濃衆くらいに思っていました。今回、この坂本へ来て、あの時の言葉が「穴太衆」を指す言葉で、石工集団だと判りました。
変な風に思い込んでいた事柄が、ここに来てハッキリしました。
日吉大社
日吉大社の参拝マップです。
正面の鳥居から入り、西本宮。東本宮の順に参拝しました。
正面の朱色の鳥居が日吉大社への道です。
見上げると高い場所に社が見えます。
金大巌です。
日吉会館の中では大津絵展が開かれていました。
大津絵を見せて貰いに伺いました。
絵は撮影禁止となっていました。
私が絵を見終わった後に女性のグループが来ました。
西本宮の楼門です。
門を通り、先に進みます。
西本宮の本殿です。
ザックを背負った沢山の人。
私たちのグループ以外でも、ザックを背負った人が居ます。
歩いていて、お拝殿の先に紅葉した木が見えました。
神輿収蔵庫で神輿を見ました。
内部に立派なお御輿が安置して有りました。
山王神輿の説明と山王祭のポスターが入口に貼られていました。
日吉大社へ入ってくる時、鳥居の横の広告塔ににも書かれていましたが、山王祭は毎年4月12日~15日と決まっているようです。
東本宮へ歩いてきました。
右は東本宮楼門の前です。
お拝殿。
拝殿の内部。
山王祭の写真が展示して有りました。
作品の中には神輿を担ぐ勇壮なものも有りました。
元気な高齢者たち
楼門に居ましたら、3組の元気な高齢者が通過していきました。
私たちも高齢者ですが、何れの組も元気な人たちでした。
ボランティアガイドの説明を聞いている団体です。
ザックにSANYO BUSのバッヂが付いていました。
神戸方面から来た団体でしょう。

コチラも元気な団体で、旗を立てて階段を登って来ました。
旗に粉浜ウォークと書かれています。写真を撮らせてもらいました。
粉浜は大阪の学区です。
この人たちもウオーキングする元気な高齢者です。
東本宮の本殿です。
コチラでも沢山のザックを背負った人たちが居ます。元気な高齢者が沢山居ます。
日吉大社の「もみじ祭」パンフです。
11月30日で終りになります。
ライトアップしたモミジを見てみたいと思いました。
日吉大社を訪ねました。
私の住む地域に日吉神社と言うお宮さんが有ります。境内で宮司の姿をした人に聞きましたら、この日吉大社が総社だと教えてくれました。ここが本社で各地の日吉神社は支社のようなものです。身近なところに有る神社の総社がここだと知る事が出来ました。
日吉大社の西本宮から東本宮へと歩きました。
私たちも高齢者のグループなのですが、多くの高齢者グループを見かけました。何れも元気な中高年の人たちです。健康だからこのような場所へ来て歩く事が出来ます。
日吉大社を出てバスの駐車場まで歩きます。
当初の計画では日吉大社の境内で弁当を開く予定でしたが、境内での飲食が禁止となっていまして、断念しました。この道を歩き、先に有った大宮川緑地でランチタイムを取りました。
この道ではありませんが、日吉大社から八講堂千体地蔵を経由して西教寺へ通じる道で、山の辺の道が有りました。今回はこの山の辺の道を歩く事が出来ませんでしたが、琵琶湖の眺望がバッグの道のようです。機会を設けて歩いてみたいと思います。
バスの駐車場に向かいます。
途中道路を横断するときに琵琶湖が見えました。
そして、その先に近江富士が見えます。
右手にあずま屋が有ります。この一帯が大宮河緑地です。そこでお昼としました。
西教寺
バスが西教寺の駐車場に着きました。
車窓から青いジャンパー姿のグループが見えました。
青いジャンパー姿の人に聞きましたらボランティアガイドだと言っていました。
有償か、無償かかと聞いたら無償だと応えました。
西教寺の境内図です。
広い境内です。
西教寺の参道を歩きます。
参道の両側に大津絵の描かれた行灯タイプの照明が並んでいます。
暗くなると点灯するのでしょう。
表札に禅林坊と禅明坊と書かれています。
禅名坊には越前之国と有ります。福井の人が泊まるのでしょうか。
西教寺の境内図に有りましたが、このような宿坊が何箇所か有りました。
参道のもみじが紅葉しています。
宗祖大師殿へ来ました。
大師殿の前には琵琶湖が見えます。
宗祖大師殿へ入ります。
本堂の前に来ました。
明智光秀一族の墓とその説明です。
二十五菩薩群像とその説明です。
先ほど、駐車場で見かけたガイドボランティアの人たちが団体を案内していました。
私たちがバスに戻った時、この団体の人たちのバスも待機していました。フロントのステッカーには大和郡山市観光協会歴史講座と書かれていました。歴史の学習で各地へ出かけているのでしょう。
石段を下って行きます。
モミジが綺麗ですが、モミジが最後の時期を迎えています。
参道を下って行きます。
こちらのモミジも紅葉しています。
門の外まで下ってきました。
近江神宮
次に向かったのが近江神宮です。
近江神宮が、今回訪ねる場所の最後です。
門をくぐり、本殿に向かいます。
近江神宮は昭和15年に創祀された神宮です。歴史的にはそれ程古く有りません。
祭神は天智天皇です。天智天皇が日本で初めて水時計(漏刻)を設置した歴史にちなみ、境内には時計業者が寄進した日時計や漏刻などが設けてあり、時計館宝物館が有ります。
この日は28日でしたが、七五三で参拝する家族を見かけました。
最後に
今月の歴史街道を歩く会。
浮御堂。坂本の町を散策。そして日吉大社。西教寺。近江神宮に参拝しました。日吉大社や西教寺では、紅葉したモミジの最後の姿を見ました。何れも美しく紅葉していました。紅葉したモミジを見ていて思ったのは京都のモミジです。京都はこの坂本から近い場所です。今頃の京都は混雑しているだろうなと想像しました。京都市内でもモミジを鑑賞できますが、混雑する京都を避けて、坂本あたりでモミジを愛でた方が紅葉を楽しめます。多くの高齢者がこの場所に来ていましたが、坂本のモミジは穴場的な場所だと思います。それに、夜にライトアップするのも魅力です。
ライトアップしたモミジを見に、何時か訪れたいと思いました。
日吉大社が日吉神社の本宮だと知る事が出来たのも良かったです。また、穴太衆積みの坂本を訪ねる事が出来ました。石積みの多い坂本。積まれた石積みが穴太積みだと知り、勉強になりました。