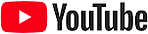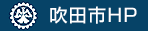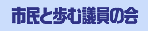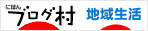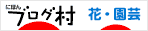未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
市民自治
今日、ドーンセンターで開かれた住基ネット差し止め訴訟・関西(私も入っています)主催の冬の講演会『上原公子さん(国立市長)講演会』に行ってきました。
<やろうと思えばできる>
国立市は国内の自治体の中で今現在、住基ネットと接続していない3自治体のうちのひとつです。(あとの二つは、矢祭町と杉並区)とくに国立市の場合は一度1999年8月に接続した後、同年12月26日に切断しました。一度接続してしまったら、なかなか切断できないといわれていますが、「やろうと思えばできる」ということを実践しています。
<市民自治の復権>
さて、上原さんの講演の中で何度も触れられたのは、「地方自治の本旨」「市民自治」という言葉でした。また、市長選に出たときのアピールは「市民自治の復権」だったそうです。徹底して「市民自治とは何か」「民主主義とは何か」ということを問い直さなければならないとのことでした。
<市民参画は最後まで>
私も今、一人会派でがんばっており、会派名を「すいた市民自治」としています。これは、市民が主体であることを忘れることなく、行政がするべきことは、市民がするべきことは、ということを考え、実践していきたいと思ったからです。
上原さんもおっしゃっていました。「市民参画は運営も市民が担っていくことであり、その参画の仕方、運営の担い方を常に考えている」とのことです。
たとえば、市民参加条例を作るときには、市民が自ら条例案を作ることを目標とし、そのために市民自治ゼミナールを開催して市民が学習し、視察に行くなどして市民自らが条例文案を考えたそうです。(ただし、これだけ市民とともにやってきても、条例案は議会ですげなく否決されてしまったと残念がっていました)
<高度な公共の福祉とは>
また、昨日、参院の委員会で可決された教育基本法の改正の中で特に重要なのは「公共の精神を尊び」という言葉だとのことでした。つまり、日本は敗戦国となり、これからは基本的人権を尊重する国になろうとしてきた。けれど、小泉首相が「高度な公共の福祉のためには基本的人権は侵害されることもある」という言葉が象徴しているように、今の政府がいうところの「高度な公共の福祉」とはおそらく「戦争」のことを意味し、戦争になれば国民の基本的人権は侵害されることもあるということである。とのことでした。
あわせて、そういう場合になったとき、政府は戦争にいける人を大事にし、戦争にいけない人、たとえば高齢者や障害者は軽んじられるだろうともおっしゃっていました。
<ペナルティよりも住民>
最後に「住基ネットを切断して国(政府)からペナルティはないですか?」との質問に対して、「表立ってはっきりしたペナルティはないけれど、どうも特別交付税額が最近の国の財政状況を反映して軒並み減ってきているが、その減り方が都内の他の自治体よりもさらに大きいようだ」と答えました。
そして、「たとえペナルティがあろうとも、住民を守るほうが大事」とはっきりと言われました。
上原さんは思ったよりも小柄な女性でしたが、心なしかずっと大きく見えたのは、その思いの大きさのゆえんだと思います。
<やろうと思えばできる>
国立市は国内の自治体の中で今現在、住基ネットと接続していない3自治体のうちのひとつです。(あとの二つは、矢祭町と杉並区)とくに国立市の場合は一度1999年8月に接続した後、同年12月26日に切断しました。一度接続してしまったら、なかなか切断できないといわれていますが、「やろうと思えばできる」ということを実践しています。
<市民自治の復権>
さて、上原さんの講演の中で何度も触れられたのは、「地方自治の本旨」「市民自治」という言葉でした。また、市長選に出たときのアピールは「市民自治の復権」だったそうです。徹底して「市民自治とは何か」「民主主義とは何か」ということを問い直さなければならないとのことでした。
<市民参画は最後まで>
私も今、一人会派でがんばっており、会派名を「すいた市民自治」としています。これは、市民が主体であることを忘れることなく、行政がするべきことは、市民がするべきことは、ということを考え、実践していきたいと思ったからです。
上原さんもおっしゃっていました。「市民参画は運営も市民が担っていくことであり、その参画の仕方、運営の担い方を常に考えている」とのことです。
たとえば、市民参加条例を作るときには、市民が自ら条例案を作ることを目標とし、そのために市民自治ゼミナールを開催して市民が学習し、視察に行くなどして市民自らが条例文案を考えたそうです。(ただし、これだけ市民とともにやってきても、条例案は議会ですげなく否決されてしまったと残念がっていました)
<高度な公共の福祉とは>
また、昨日、参院の委員会で可決された教育基本法の改正の中で特に重要なのは「公共の精神を尊び」という言葉だとのことでした。つまり、日本は敗戦国となり、これからは基本的人権を尊重する国になろうとしてきた。けれど、小泉首相が「高度な公共の福祉のためには基本的人権は侵害されることもある」という言葉が象徴しているように、今の政府がいうところの「高度な公共の福祉」とはおそらく「戦争」のことを意味し、戦争になれば国民の基本的人権は侵害されることもあるということである。とのことでした。
あわせて、そういう場合になったとき、政府は戦争にいける人を大事にし、戦争にいけない人、たとえば高齢者や障害者は軽んじられるだろうともおっしゃっていました。
<ペナルティよりも住民>
最後に「住基ネットを切断して国(政府)からペナルティはないですか?」との質問に対して、「表立ってはっきりしたペナルティはないけれど、どうも特別交付税額が最近の国の財政状況を反映して軒並み減ってきているが、その減り方が都内の他の自治体よりもさらに大きいようだ」と答えました。
そして、「たとえペナルティがあろうとも、住民を守るほうが大事」とはっきりと言われました。
上原さんは思ったよりも小柄な女性でしたが、心なしかずっと大きく見えたのは、その思いの大きさのゆえんだと思います。
コメント(0)|Trackback()
?