女性の読者から愚息のその後の容態について尋ねられることがあるけど、有難いことです。彼はいたって元気にしております。
週末の野球の練習には欠かさず参加していますし、前回からは量的に半分以下ですが、各練習メニューを何とかこなせるまでに回復しているみたいです。
こないだ久しぶりのシートバッティングでは全打席で安打を放ち、最初の打席では柵越えだったそうです。
「飛距離がかなり伸びてましたよ~」
夕刻になってグランドを訪れたボクに監督が話してくれました。
以前ドクターSに技術トレーニングは全くムダと言われ、以来、自主練習は全くのゼロにしたのだけれど、「ゼロトレーニング」=「休養」と「リハビリ」が功を奏しているのかもしれないですね。いや、ひょっとするとボクの知らないところで、コソコソとトレーニングをしているのかもしれないし・・・・。
ま、そんなこんなで愚息は元気です。
ところで、昨晩の夕食時、愚息が突然こんなことを語り始めました。
「あのね、棺桶にね、おばぁちゃんが座っとったけん、いつもみたいに、ニヤってしてコッチば見とったけん」
こないだこのブログで記録したナツエ祖母さんの葬儀のときの話しなのだけれど、そのナツエ祖母さん本人が自分の棺桶に腰掛けていたのをハッキリ見たというのです。
見えたときは、やっぱりなんとなく怖くって誰にも言えなかったということらしいです。
話しっぷりからして、ウソとも思えないし、その話しを聞いた娘たちは「いいなぁ~、いいなぁ~」を連発。愚息が共感覚を持っていた就学前の幼いころ、ボクらには見えないモノを見えると言っていたことを思い出して、「そうかぁ、オマエが見たと言うのなら、見たんだろうなぁ」とボクは答えたのでした。
しかし、愚息が見たナツエ祖母さんは、ナツエ祖母さんの「幽霊」という存在だったのでしょうか。
実は、我々、子供を含めた人間は、生物が「生きているのか」「死んでいるのか」を容易に見分けることができる能力があるらしいのです。これは進化の過程で獲得された能力のひとつで、つまり、動物が生きているか死んでいるかを瞬時に判断することは、自分の生命維持にとって極めて重要なことであるし、このことは誰でも簡単に理解できることと思います。
死んだ毒蛇には近づけるけど、生きた毒蛇には近づかないでしょう。
そういう意味において、愚息は、ナツエ祖母さんの遺体を見ているわけだからナツエ祖母さんの肉体的「死」をしっかり認知できていたと思います。
しかし、ナツエ祖母さんの「魂」や「精神」についてのはどうだったのでしょうか。
一般に、私たちは、死後における精神の継続性を考える傾向が強いイキモノであると言えそうです。こういった傾向を持つ理由の一つに、発達心理学における「人物の永続性」という概念が挙げられるそうです。
私たちはごく幼いときに、相手が自分の視界からいなくなっても、その人が存在しなくなったわけではないということを学習し、この考え方が、自分の知っている人が亡くなった後も、頭の中に頑固に居座っているからだというのです。
つまり、ボクは、愚息が見た棺桶に座っていたナツエ祖母さんというのは、愚息の頭の中に頑固に居座っていたナツエ祖母さんと言いたいのかもしれません。
しかし、このバカブログで記録しておきたいことは、ナゼ、「人物の永続性」を人間が考えるようになったかということです。
私はカワイイ兎ちゃん。
洞窟に身を潜めています。
岩陰から外を見ると、凶暴そうな虎が歩いています。
虎が視界から消えました。
私はすっかり安堵して洞窟から外に出ました。
外に出たとたん、虎が襲ってきました。
「虎は消えていたのに」と思う間もなく私は噛み殺されて、虎の餌食となりました。
死んだわが子を片時も離さずいつまでも抱き続ける「猿」の姿をTV番組などで見たことのある人は多いはずです。死んだわが子をおもんばかっているのでしょうか。
・・・・お猿さんです。
すでに高等な猿であるから「死」は十分に認知できていると考えられます。
猿には「猿の永続性」があるのかもしれません。
猿も「幽霊」を見ているかもしれませんね。
幽霊にビビッているお猿さんて最高ですね!
週末の野球の練習には欠かさず参加していますし、前回からは量的に半分以下ですが、各練習メニューを何とかこなせるまでに回復しているみたいです。
こないだ久しぶりのシートバッティングでは全打席で安打を放ち、最初の打席では柵越えだったそうです。
「飛距離がかなり伸びてましたよ~」
夕刻になってグランドを訪れたボクに監督が話してくれました。
以前ドクターSに技術トレーニングは全くムダと言われ、以来、自主練習は全くのゼロにしたのだけれど、「ゼロトレーニング」=「休養」と「リハビリ」が功を奏しているのかもしれないですね。いや、ひょっとするとボクの知らないところで、コソコソとトレーニングをしているのかもしれないし・・・・。
ま、そんなこんなで愚息は元気です。
ところで、昨晩の夕食時、愚息が突然こんなことを語り始めました。
「あのね、棺桶にね、おばぁちゃんが座っとったけん、いつもみたいに、ニヤってしてコッチば見とったけん」
こないだこのブログで記録したナツエ祖母さんの葬儀のときの話しなのだけれど、そのナツエ祖母さん本人が自分の棺桶に腰掛けていたのをハッキリ見たというのです。
見えたときは、やっぱりなんとなく怖くって誰にも言えなかったということらしいです。
話しっぷりからして、ウソとも思えないし、その話しを聞いた娘たちは「いいなぁ~、いいなぁ~」を連発。愚息が共感覚を持っていた就学前の幼いころ、ボクらには見えないモノを見えると言っていたことを思い出して、「そうかぁ、オマエが見たと言うのなら、見たんだろうなぁ」とボクは答えたのでした。
しかし、愚息が見たナツエ祖母さんは、ナツエ祖母さんの「幽霊」という存在だったのでしょうか。
実は、我々、子供を含めた人間は、生物が「生きているのか」「死んでいるのか」を容易に見分けることができる能力があるらしいのです。これは進化の過程で獲得された能力のひとつで、つまり、動物が生きているか死んでいるかを瞬時に判断することは、自分の生命維持にとって極めて重要なことであるし、このことは誰でも簡単に理解できることと思います。
死んだ毒蛇には近づけるけど、生きた毒蛇には近づかないでしょう。
そういう意味において、愚息は、ナツエ祖母さんの遺体を見ているわけだからナツエ祖母さんの肉体的「死」をしっかり認知できていたと思います。
しかし、ナツエ祖母さんの「魂」や「精神」についてのはどうだったのでしょうか。
一般に、私たちは、死後における精神の継続性を考える傾向が強いイキモノであると言えそうです。こういった傾向を持つ理由の一つに、発達心理学における「人物の永続性」という概念が挙げられるそうです。
私たちはごく幼いときに、相手が自分の視界からいなくなっても、その人が存在しなくなったわけではないということを学習し、この考え方が、自分の知っている人が亡くなった後も、頭の中に頑固に居座っているからだというのです。
つまり、ボクは、愚息が見た棺桶に座っていたナツエ祖母さんというのは、愚息の頭の中に頑固に居座っていたナツエ祖母さんと言いたいのかもしれません。
しかし、このバカブログで記録しておきたいことは、ナゼ、「人物の永続性」を人間が考えるようになったかということです。
私はカワイイ兎ちゃん。
洞窟に身を潜めています。
岩陰から外を見ると、凶暴そうな虎が歩いています。
虎が視界から消えました。
私はすっかり安堵して洞窟から外に出ました。
外に出たとたん、虎が襲ってきました。
「虎は消えていたのに」と思う間もなく私は噛み殺されて、虎の餌食となりました。
死んだわが子を片時も離さずいつまでも抱き続ける「猿」の姿をTV番組などで見たことのある人は多いはずです。死んだわが子をおもんばかっているのでしょうか。
・・・・お猿さんです。
すでに高等な猿であるから「死」は十分に認知できていると考えられます。
猿には「猿の永続性」があるのかもしれません。
猿も「幽霊」を見ているかもしれませんね。
幽霊にビビッているお猿さんて最高ですね!

















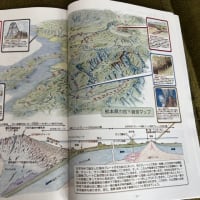









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます