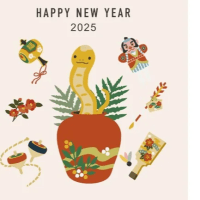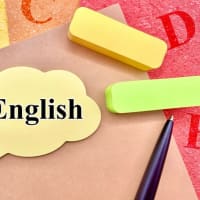近江商人の経営哲学を表す言葉としてよく使われるこの言葉。
ウィキペディアによると、
三方よし「売り手よし、買い手よし、世間よし」
売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献しなければならない。
三方良しの理念が確認できる最古の史料は、1754年に神崎郡石場寺村(現在の東近江市五個荘石馬寺町)の中村治兵衛が書き残した家訓であるとされる。ただし、「三方よし」は戦後の研究者が分かりやすく標語化したものであり、昭和以前に「三方よし」という用語は存在しなかった。
と書いてある。
つまり、自分の利益だけ考えて行動したのでは、長続きせず、大きくなれないということか?
同じくウィキペディアによると、大阪商人、伊勢商人、近江商人という言葉が使われ、
今の日本を支えているような大企業の名前がずらっとあがっていた。
例えば、住友とか高島屋とか。
企業の社会的責任(CSR)が言われて久しいが、こうした考えが個人としての人間関係や個人としての地域貢献にも必要だと思う。
それは、お互いが相手を尊重して助け合い、地域にまで輪を広げていくということなのだろう。
ウィキペディアによると、
三方よし「売り手よし、買い手よし、世間よし」
売り手の都合だけで商いをするのではなく、買い手が心の底から満足し、さらに商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献しなければならない。
三方良しの理念が確認できる最古の史料は、1754年に神崎郡石場寺村(現在の東近江市五個荘石馬寺町)の中村治兵衛が書き残した家訓であるとされる。ただし、「三方よし」は戦後の研究者が分かりやすく標語化したものであり、昭和以前に「三方よし」という用語は存在しなかった。
と書いてある。
つまり、自分の利益だけ考えて行動したのでは、長続きせず、大きくなれないということか?
同じくウィキペディアによると、大阪商人、伊勢商人、近江商人という言葉が使われ、
今の日本を支えているような大企業の名前がずらっとあがっていた。
例えば、住友とか高島屋とか。
企業の社会的責任(CSR)が言われて久しいが、こうした考えが個人としての人間関係や個人としての地域貢献にも必要だと思う。
それは、お互いが相手を尊重して助け合い、地域にまで輪を広げていくということなのだろう。