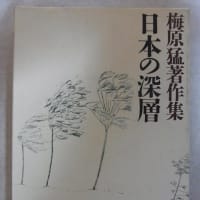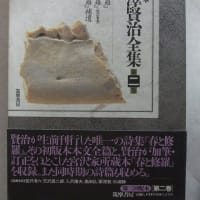The phenomenal modernization of Japan would probably not have been possible without the revivalist spirit of Japanese nationalism. It is perhaps also true that the rapid
modernization of some European countries [Germany in particular] was facilitated to some extent by the upsurge and thorough diffusion of nationalist fervor. Judged by
present indications, the renascence of Asia will be brought about through the instrumentality of nationalist movements rather than by other mediums. It was the rise of a
genuine nationalist movement which enabled Kemal Atatürk to modernize Turkey almost overnight. In Egypt, untouched by a mass movement, modernization is slow and faltering,
though its rulers, from the day of Mehmed Ali, have welcomed Western ideas, and its contacts with the West have been many and intimate. Zionism is an instrument for the
renovation of a backward country and the transformation of shopkeepers and brain workers into farmers, laborers and soldiers. Had Chiang Kai-shek known how to set in motion a genuine mass movement, or at least sustain the nationalist enthusiasm kindled by the Japanese invasion, he might have been acting now as the renovator of China. Since he
did not know how, he was easily shoved aside by the masters of the art of “religiofication” ― the art of turning practical purposes into holy causes.
〔附録1〕 [OKAI TAKASHI] A Tanka poet, an internist. He was born in 1928. He said Tanka is ultimately both a Song and a Tone.
肺尖にひとつ昼顔の花燃ゆと告げんとしつつたわむ言葉は
側面をさらしつつ退き(しりぞき)ながらたたかう其処の朱の肺臓は (そくめんを/さらしつつしり/ぞきながら たたかうそこの/しゅのはいぞうは)
手術室よりいま届きたる肺臓のくれないの葉が見えて飯(いい)はむ
“わたしの外来に通ってくる常連の一人にSさんという老人が居た。飄々とした瘦軀、どこか凡でない眼光がわたしを射るので、ひそかに敬愛して対って(むかって)いたのであるが、ある日、彼は診察室のベッドでわたしに血圧を測らせながら、「このあいだの短歌研究の歌はよかったですなあ、説をかえまた説をかうたのしさの、あれはいい。しかし、よくわからんのもありますな、管型の蔓状の思想なんていうのは、とてもわれわれには理解できません。」と言い出したので、わたしはいたく狼狽し、ひそかに顔を紅らめたのである。彼は若年のころ、右翼の文人政客と交わりそのパトロン格だったときいたが、そういえば、わたしが学生のころ会ったことのある追放中の安藤正純にどこか相通う風貌の持主であった。その後、Sさんは急性肺炎を患ってわたしの病室に入った。そして、クリーゼをすぎて尚少量の痰を喀出していたが、わたしのわずかな油断の隙に急死した。わたしは外科医ではないから「手術台上の死」を経験したことはないが、ほぼそれに匹敵する衝撃をうけて、長く苦しんだ。はなはだ私的な回想であるが、忘れがたいので附記しておく。”
説を替えまた説をかうたのしさのかぎりも知らに冬に入りゆく
真夏の死ちかき胃の腑の平(たいら)にはするどき水が群れて注ぎき
日本いまヴィジョンの沼地ここすぎて夏野わけ入る疾き(とき)風を見む
管型の思想を夢むなおいえば蔓状(まんじょう)の管型の鋭きを
もろもろの昨日をあつめ もろともの明日を紡がん手を想うのみ
対峙せる詩人と医師のめぐりには葉のみはげしくふかく騒(さや)げる
『現代歌人文庫 岡井隆集』(国文社)
〔附録2〕 寺田寅彦 「田丸先生の追憶」
“先生に三角を教わり力学を教わったために、始めて数学というものがおもしろいものだということが少しばかりわかって来た。中学で教わった数学は、三角でも代数でも、いったいどこがおもしろいのかちっともわからなかったが、田丸先生に教わってみると中学で習ったものとはまるでちがったもののように思われて来た。先生に言わせると、数学ほど簡単明瞭なものはなくて、だれでも正直に正当にやりさえすれば、必ずできるにきまっているものだというのである。教科書の問題を解くのでも、おみくじかなんかを引くように、できるもできないも運次第のものででもあるかのように思っていた自分のような生徒たちには、先生のこの説は実に驚くべき天啓であり福音であった。なるほど少なくも書物にあるほどの問題なら、その書物で教えられた筋道どおり正直にやれば必ずできるのであった。そういうことを発見して驚いたものである。” (昭和七年十二月 理学部会誌) 『寺田寅彦全集(S.36年版) 第六巻』
→ 『2013.7.9 東京新聞 発言欄』
〔附録3〕
paternalism 父親的温情主義〔干渉〕, パターナリズム.
『リーダーズ英和辞典 第3版』
パターナリズム 相手の利益のためには、本人の意向にかかわりなく、生活や行動に干渉し制限を加えるべきであるとする考え方。親と子、上司と部下、医者と患者との関係などに見られる。
『広辞苑 第六版』
→ 『2013.7.9 東京新聞 特報面』
modernization of some European countries [Germany in particular] was facilitated to some extent by the upsurge and thorough diffusion of nationalist fervor. Judged by
present indications, the renascence of Asia will be brought about through the instrumentality of nationalist movements rather than by other mediums. It was the rise of a
genuine nationalist movement which enabled Kemal Atatürk to modernize Turkey almost overnight. In Egypt, untouched by a mass movement, modernization is slow and faltering,
though its rulers, from the day of Mehmed Ali, have welcomed Western ideas, and its contacts with the West have been many and intimate. Zionism is an instrument for the
renovation of a backward country and the transformation of shopkeepers and brain workers into farmers, laborers and soldiers. Had Chiang Kai-shek known how to set in motion a genuine mass movement, or at least sustain the nationalist enthusiasm kindled by the Japanese invasion, he might have been acting now as the renovator of China. Since he
did not know how, he was easily shoved aside by the masters of the art of “religiofication” ― the art of turning practical purposes into holy causes.
〔附録1〕 [OKAI TAKASHI] A Tanka poet, an internist. He was born in 1928. He said Tanka is ultimately both a Song and a Tone.
肺尖にひとつ昼顔の花燃ゆと告げんとしつつたわむ言葉は
側面をさらしつつ退き(しりぞき)ながらたたかう其処の朱の肺臓は (そくめんを/さらしつつしり/ぞきながら たたかうそこの/しゅのはいぞうは)
手術室よりいま届きたる肺臓のくれないの葉が見えて飯(いい)はむ
“わたしの外来に通ってくる常連の一人にSさんという老人が居た。飄々とした瘦軀、どこか凡でない眼光がわたしを射るので、ひそかに敬愛して対って(むかって)いたのであるが、ある日、彼は診察室のベッドでわたしに血圧を測らせながら、「このあいだの短歌研究の歌はよかったですなあ、説をかえまた説をかうたのしさの、あれはいい。しかし、よくわからんのもありますな、管型の蔓状の思想なんていうのは、とてもわれわれには理解できません。」と言い出したので、わたしはいたく狼狽し、ひそかに顔を紅らめたのである。彼は若年のころ、右翼の文人政客と交わりそのパトロン格だったときいたが、そういえば、わたしが学生のころ会ったことのある追放中の安藤正純にどこか相通う風貌の持主であった。その後、Sさんは急性肺炎を患ってわたしの病室に入った。そして、クリーゼをすぎて尚少量の痰を喀出していたが、わたしのわずかな油断の隙に急死した。わたしは外科医ではないから「手術台上の死」を経験したことはないが、ほぼそれに匹敵する衝撃をうけて、長く苦しんだ。はなはだ私的な回想であるが、忘れがたいので附記しておく。”
説を替えまた説をかうたのしさのかぎりも知らに冬に入りゆく
真夏の死ちかき胃の腑の平(たいら)にはするどき水が群れて注ぎき
日本いまヴィジョンの沼地ここすぎて夏野わけ入る疾き(とき)風を見む
管型の思想を夢むなおいえば蔓状(まんじょう)の管型の鋭きを
もろもろの昨日をあつめ もろともの明日を紡がん手を想うのみ
対峙せる詩人と医師のめぐりには葉のみはげしくふかく騒(さや)げる
『現代歌人文庫 岡井隆集』(国文社)
〔附録2〕 寺田寅彦 「田丸先生の追憶」
“先生に三角を教わり力学を教わったために、始めて数学というものがおもしろいものだということが少しばかりわかって来た。中学で教わった数学は、三角でも代数でも、いったいどこがおもしろいのかちっともわからなかったが、田丸先生に教わってみると中学で習ったものとはまるでちがったもののように思われて来た。先生に言わせると、数学ほど簡単明瞭なものはなくて、だれでも正直に正当にやりさえすれば、必ずできるにきまっているものだというのである。教科書の問題を解くのでも、おみくじかなんかを引くように、できるもできないも運次第のものででもあるかのように思っていた自分のような生徒たちには、先生のこの説は実に驚くべき天啓であり福音であった。なるほど少なくも書物にあるほどの問題なら、その書物で教えられた筋道どおり正直にやれば必ずできるのであった。そういうことを発見して驚いたものである。” (昭和七年十二月 理学部会誌) 『寺田寅彦全集(S.36年版) 第六巻』
→ 『2013.7.9 東京新聞 発言欄』
〔附録3〕
paternalism 父親的温情主義〔干渉〕, パターナリズム.
『リーダーズ英和辞典 第3版』
パターナリズム 相手の利益のためには、本人の意向にかかわりなく、生活や行動に干渉し制限を加えるべきであるとする考え方。親と子、上司と部下、医者と患者との関係などに見られる。
『広辞苑 第六版』
→ 『2013.7.9 東京新聞 特報面』