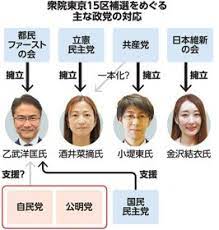人殺しはどれくらい難しいか? (2007年12月18日)
>どのように訓練されても、どのような大義名分があったとしても、直接的な怨みも何もない人間、自分と同じように親子・兄弟・友人に囲まれて生き、休日には家族そろって出かけ、いつかは年老いてこの世を去るであろう一人の人間を、われわれは心情的に殺せないのである

第二次世界大戦中、日本軍・ドイツ軍と戦った米兵のライフル銃兵のうち、実際に敵に向かって発砲したのは全体の15~20パーセントに過ぎなかった。残りの8割は引き金さえ引かなかったか、故意に目標をそらして発砲した。にわかには信じがたい事実だが、この数字が示す「戦わない兵士の多さ」は、ナポレオン戦争や南北戦争ほか古今東西の戦いを通じて観察される事象だという。
極端な例では兵士の練達度、銃の性能から推定される殺傷能力の100分の1程度しか軍隊としての能力が発揮されていない。射撃練習用の標的とは違い、生きて呼吸をしている敵に相対すると、ほとんどの兵士は相手に向けて発砲できないのである。デーブ・グロスマン著『戦争における「人殺し」の心理学』は、戦争の前線においてさえ、殺人という行為がわれわれにとっていかに困難なものであるか、また国や軍隊がいかにしてこれを可能にし効率的に行わせようとしているかを、過去の研究成果とインタビューの結果を元に説いている。
戦闘直後のイスラエル軍兵士に対する調査において「何が一番恐ろしかったか」という問いに対して、「死ぬこと」「負傷すること」よりも「ほかの人間を死なせること」という答えの比重が高かった。
これに対し戦闘体験のないスウェーデンの平和維持群の回答の多くは「死と負傷」だった。これは戦場が決して想像できない場所であることをわれわれに教えてくれる。アクション映画やサスペンスドラマでは(そこが戦場でなくとも)いとも簡単に人が殺したり殺されたりている。われわれ非戦闘体験者は、軍隊に入って訓練を積み前線に送られれば、敵に殺されるのが怖いし、またその怖さから敵に出会えば誰でも敵を殺傷できると思いがちだ。しかし実際はその逆である。兵士にとっては「殺される恐怖」より「殺す恐怖」「失敗する恐怖」の方が重荷なのである。
戦争における殺人に対する拒否反応を軽減する要素・方法はいくつかある。相手との物理的距離(遠いほど殺人が可能になりトラウマにもなりにくい)、集団との自己同一化(心理的つながりが強いほど殺人が行われやすい)、権威者の要求(同左)など。また、心理的なものには文化的・倫理的・社会的・機械的距離が関係する。
「あいつらは畜生以下だ」「これは復讐だ」という思い込みや刷り込み。画面モニターや暗視装置など人間をゲーム感覚で殺傷できる機器の発達など。
また、第二次世界大戦後「戦わない兵士」を戦わせるための訓練方法が確立したという。脱感作とオペラント条件付けだ。脱感作とはもともとアレルギーの原因物質を少量注射して過敏性をなくす治療法だ。たとえば訓練の過程で兵士たちは「殺せ、殺せ」と連呼しながら走らされる。他にもあの手この手で敵の痛みに対して慣れ、鈍感になるよう作り変えられる。オペラント条件付けは飴とムチによる矯正方法といえる。射撃演習において実際の人間そっくりの的を効率よく倒すと、報酬が与えられ、顕彰される。逆に失敗すると軽い刑罰が与えられるなど。
これらの現代的プログラムを導入した軍隊の殺傷能力は飛躍的に向上している。ベトナム戦争では兵士の発砲率は90パーセントを超えた。しかし、どのように訓練されても、どのような大義名分があったとしても、直接的な怨みも何もない人間、自分と同じように親子・兄弟・友人に囲まれて生き、休日には家族そろって出かけ、いつかは年老いてこの世を去るであろう一人の人間を、われわれは心情的に殺せないのである。そして、もし殺した場合にはその経験は深いトラウマとなり、その克服に残りの人生の多くの部分、あるいは全てを費やす事になる。
私は四五[口径]を持っていた。それをぶっ放したとき、相手の銃剣の切っ先はいまのあなたと私ほども離れていなかった。すべて片づいたあと、情報収集のためその兵士の遺体の調査を手伝いました。それで写真を見つけたんですよ。―中略― 細君と、ふたりのかわいい子供が写っていました。それ以来 ―中略― 頭について離れんのですよ。あのかわいい子供たちは父親なしで育ったんだ、それというのも私が殺してしまったからだと。私はもう若くはない。まもなく自分の所業について神に申し開きをせねばならんのです(第二次世界大戦中南太平洋で日本兵を撃ち殺した退役軍人の話より p.262)
この本は戦争反対を主張するものではないし、逆に軍事行為の正統性を主張するものではない。戦場という異常な環境に置かれた人間の心理を冷静に収集・分析することで、戦争がいかなる行為であるかをわれわれに考えさせる。ベトナム戦争後半から終結時にアメリカ世論が反戦一色になった際、帰還兵はパレードで歓迎されるどころか、人々に(実際に)唾を吐きかけられた。戦地のトラウマを引きずり自らの人間性を否定する泥沼の精神的状態にあった兵隊たちに対し、歓迎と受容と励ましで自己肯定を与え彼らを救う事ができたはずの国民。その国民のむごい仕打ちは彼らのその後の人生を破壊し、それにより少なくとも50万人のベトナム帰還兵がPTSDに苦しむことになった。著者はその責任を政府・国民に問うている。言葉は冷静だが糾弾と言っていいだろう。
私は崖を飛びおり、死にかかっている男に駆け寄った。助けたかったのか、とどめを刺すつもりだったのか、よくわからない。なぜかわからないが、見ておかなければならないという気がしたのだ。どんなやつで、どんなふうに死んでゆくのか。 ―中略― 聞こえるのは、死んだ男の血が泡立ちながら地面にしみこんで行くかすかな音だけだ。目は開いたままだった。まだ幼さの残る顔。何だかひどく穏やかな表情だった。こいつの戦争は終わったのだ。だが、私の戦争は始まったばかりだった。傷口からどくどくと流れ出る血が、死体のまわりに黒っぽく丸いしみを広げてゆく。こいつが生命を失くしたように、おれは永遠に無垢を失くしたんだと思った。こうして私ははるばるベトナムにやって来たのだった。立ち去る日が来るのかどうか分からなかった。いまもわからない。小隊の残りがその高台に到着したとき、私は焚き火の側面に茂みを見つけて、そこで激しく吐いた。(スティーブ・バンコ「駆け出し歩兵、無垢の喪失」より p.452)
この本は文庫本にして500ページある。過去の発表をまとめきれずに重複している記述も多いが、飛ばし読みをさせない情熱と勇気、冷静さと気迫に満ちており、真摯な態度には襟を正される思いがする。唯一、締めくくりの章で、現代アメリカの犯罪・社会的病巣とシューティングゲームや暴力的な映画を関連づける試みは科学的論拠に裏付けが乏しく、少々強引に感じさせた。それが残念だ。
デーブ・グロスマン/著 安原和見/訳 『戦争における「人殺し」の心理学』(筑摩書房 2004)[b Cg/Ku8/1] (原書 “On killing: the psychological cost of learning to kill in war and society.”)
追記(2008年5月17日)
先日、内村鑑三著『よろづ短言』の中に戦場の兵士に関する以下の一節を見つけたので追記しておく。
露國兵卒の述懐:露國兵卒の一人、曾て露土戦争に出て土國兵卒の一人を銃殺し、彼れ亦傷を負ふて其傍に仆る、幾干もなくして彼れ看護卒の發見する處となり、擔かれて味方の陣に歸り、終に聖彼得堡の病院に輸送さる、病床に在て彼れ感覺を回復するや、頻りに彼の殺せし土國の兵卒の事を思ふて歇まず、彼の傍に在りし人々に告げて曰く「余は余が銃劒を以て刺殺せしかの土國の靑年に對して何の怨恨をも抱かず、彼れ亦余に對して何の怨恨あるなし、然るに余は露國人にして彼は土耳古人なりしが故に、我等徴せられて戦場に出て、劒を以て相争ひ、彼は余を傷つけ、余は彼を殺したり、想へば何の理由ありて余はかの好個の靑年を殺せし乎を知らず、若し戦場以外に於て余彼れと遭遇せん乎、我等両人は最も好き友人となりしならん嗚呼忌むべきは戦争なるかな、余の傷平癒する後は余は終生戦争の廢止を唱へて歇まざるべし」と、知らず同一の感を懐く者は遼東の野に支那人を刺殺せし我が兵卒の中にも有るや無きや。(内村鑑三『よろづ短言』より p.396)