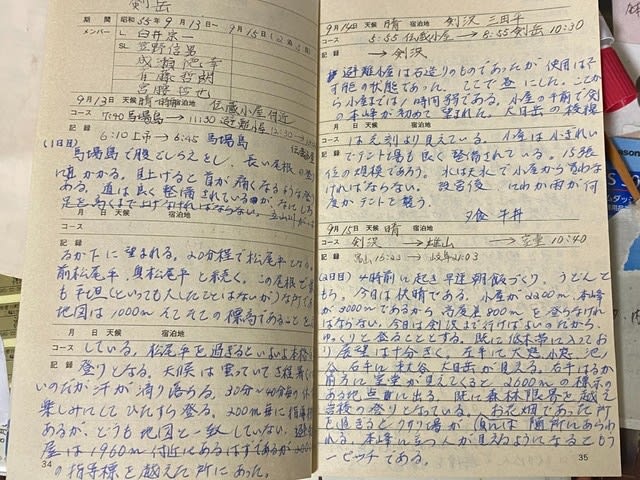オリンピックが終わったらと思ったら、いきなり秋雨前線の洗礼を受ける毎日。毎日が日曜日の身には、野外の活動ができないのがつらい。もちろん、その活動も昼時の暑いときは避けて、ほとんど午前中に行う。さて、いきなりここで皆さんに質問したい。今回のオリンピックのマラソン競技は、ケニアのキプチョゲ選手が優勝したのはかなりの人が知っているだろうが、1936年のベルリンオリンピックの同競技で優勝したのは誰か。これに答えることができるのは、余程のマラソン好きか歴史好きということになるだろうか。答えは、孫基禎で所属国は日本。しかし、その優勝者は朝鮮出身であったが、日本は1910年に朝鮮を併合しているので日本の選手ということになる。さらに、三着の南昇龍も同じく朝鮮出身であった。このベルリンオリンピックはヒトラーが国威発揚のために大いに利用したことで有名であり、その祭典の模様をお抱えの女性映画監督レニ・リーフェンシュタールが「オリンピア」として発表した。この二番煎じをしようとしたのが、日本でこの4年後1940年(この年は紀元2600年に当たる)に開催する予定だった東京オリンピックであった。ところが中国との戦争が膠着し、アメリカ等との関係も悪化していて、とてもオリンピックを開催できる状況になかったことから、中止となったのである。

夏のバラ
この幻のオリンピックマラソン競技に出場したかもしれない人物が今日の記事の中心人物である李雨哲(イ・ウチョル、日本名国本雨哲)であり、彼は作家の柳美里のお祖父さんである。そして彼を題材とした長大な小説が「8月の果て」である。この小説を紹介するのは後にして、まずおじさんが柳美里に興味を持ったわけから始める。そのきっかけは、7月に読んだ山折哲雄と柳美里が対談したのをまとめた「沈黙の作法」だった。柳美里の略歴をウィキペディアから抜粋して書いておく。
1968年に誕生
高校中退後、1984年東由多加率いる東京キッドブラザーズに最年少で入団 俳優を目指すも脚本等を担当 88年劇作家としてデビュー
1997年「家族シネマ」で芥川賞受賞
2000年長男誕生
2002年4月朝日新聞に「8月の果て」を連載開始、04年3月に連載打ち切り
2012年南相馬災害FMにて「ふたりとひとり」放送開始(多くの被災者の話を聞く)
2015年南相馬市に移住 2018年本屋「フルハウス」開店 同年「青春五月党」の復活公演を行う
この略歴を見ただけでも、何か凡人には窺うことも出来ないような人であることはわかるであろう。山折氏は彼女を見て京都広隆寺の弥勒菩薩に似ていると対談の中で述べている。確かに半島出身の典型的な顔をしている(もちろん彼女が在日韓国人であるからというのではない。日本人にも多い顔であることは間違いない。)。

広隆寺弥勒菩薩
この本をきっかけとして、揖斐川図書館で三冊の本を借りてきた。まず読んだのが「命」、そして「生」、これらの本は作家が妻ある男性と関係を結び、妊娠、そして出産それと同時並行で進むのが長年パートナーであった東氏の末期のがん闘病記である。この本を読んでいて驚いたのは、登場人物がほとんど実在する人であり、名前も実名であること(普段小説を読む習慣がないのでびっくりしているだけかもしれないとも思うが)である。おまけに表紙には篠山紀信撮影による子どもとツーショット、ここまで露出するのかとつい思ってしまった。

夏のバラ2
そして三冊目が「8月の果て」だ。揖斐川図書館の司書が書庫から出してきた800ページに及ぶ分厚い本、しかも字はページいっぱい、最後まで読み切れるかという不安が一瞬よぎった。主な舞台は韓国慶尚南道密陽市(ミリヤン)で釜山に近い。この小説には擬音が溢れる。最も多いのは李雨哲がマラソン練習時に発する呼吸の音「すっすっはっはっ」、他にも「トゥグントゥグン(心臓の音どきどき)」、風の音「フィンフィン」。そしてあたりまえだがハングル。日本人の産婆、稲森きわの出番は少ないが、当時朝鮮にいた日本人のうちでも良心的な考えを述べているのが特に印象的だった。戦争の影がどんどん濃くなって来ると読むのがだんだんと苦痛になってくる。日本語の強制、創氏改名、神社参拝、親友の反日グループへの参加あたりは序の口で、日本人の人買いの出現(福岡の軍需工場で働けば3年もすればお金を貯めて家に帰れるという甘言、実は中国の軍事基地に慰安婦として売られることになる)あたりで最高となる。李雨哲の弟雨根は兄同様、マラソンランナーで共産主義になびくのだが、日本の敗戦後始まる反共政策により、捕らえられ、拷問の後生き埋めにされる。朝鮮の不幸は日本の敗戦では終わらずに、反共の南とソビエトに支援された共産勢力の北、それは朝鮮戦争へとつながり、さらなる不幸となっていく。雨哲は戦後日本に渡り、パチンコ店を経営した。そこの釘師が柳美里の父親となる。雨哲は60歳台まで各地の大会に出場し、優秀な成績を収めたのだが、がんを患い最晩年故郷に帰った。

夏のバラ3
さきほど述べた擬音、さらに韓国の風俗が詳細に描かれている。儒教の教えによるものなのかはっきりしないが、当時の日本と比べても数段しきたりが多いように感じた。この作家はどれくらい勉強したのであろうかとつい思ってしまう。この作家はハングルは全くわからないのだから、家族内での経験を除き、ほとんど一から調べたはずである。朝日新聞が途中で連載を止めたのも非常に興味を惹かれる。朝日によると作者の構想が膨らみすぎて、中断となったと書いてあった(今だったら朝日といえどもこのような小説を連載することはできないだろう)。
最後に日本の責任について少し書いておくことにする。朝鮮を植民地とし、皇国化政策を行い、その過程で従軍慰安婦を作り出し、敗戦後は日本は分断を免れたものの、朝鮮は南北に分断され(日本の敗戦が朝鮮という力の空白地帯を作り出した)、挙げ句の果てに朝鮮戦争(この戦争にはアチソンラインというアメリカが朝鮮に勢力を及ぼさないという間違ったシグナルを北朝鮮に与えたというのが原因だと言われる)に巻き込まれた。日本は朝鮮戦争による特需によりこの後高度成長につながる発射台の基礎を作ることができた。歴史を学べば学ぶほど両国の関係修復は難しいことがわかる。柳美里の小説を読み、少しでも朝鮮の人々の声を聞くことできた(もちろん作家の想像によるところが多いだろうし、何より現代から見た姿であることも頭に置いておく必要があるだろう)。

夏のバラ
この幻のオリンピックマラソン競技に出場したかもしれない人物が今日の記事の中心人物である李雨哲(イ・ウチョル、日本名国本雨哲)であり、彼は作家の柳美里のお祖父さんである。そして彼を題材とした長大な小説が「8月の果て」である。この小説を紹介するのは後にして、まずおじさんが柳美里に興味を持ったわけから始める。そのきっかけは、7月に読んだ山折哲雄と柳美里が対談したのをまとめた「沈黙の作法」だった。柳美里の略歴をウィキペディアから抜粋して書いておく。
1968年に誕生
高校中退後、1984年東由多加率いる東京キッドブラザーズに最年少で入団 俳優を目指すも脚本等を担当 88年劇作家としてデビュー
1997年「家族シネマ」で芥川賞受賞
2000年長男誕生
2002年4月朝日新聞に「8月の果て」を連載開始、04年3月に連載打ち切り
2012年南相馬災害FMにて「ふたりとひとり」放送開始(多くの被災者の話を聞く)
2015年南相馬市に移住 2018年本屋「フルハウス」開店 同年「青春五月党」の復活公演を行う
この略歴を見ただけでも、何か凡人には窺うことも出来ないような人であることはわかるであろう。山折氏は彼女を見て京都広隆寺の弥勒菩薩に似ていると対談の中で述べている。確かに半島出身の典型的な顔をしている(もちろん彼女が在日韓国人であるからというのではない。日本人にも多い顔であることは間違いない。)。

広隆寺弥勒菩薩
この本をきっかけとして、揖斐川図書館で三冊の本を借りてきた。まず読んだのが「命」、そして「生」、これらの本は作家が妻ある男性と関係を結び、妊娠、そして出産それと同時並行で進むのが長年パートナーであった東氏の末期のがん闘病記である。この本を読んでいて驚いたのは、登場人物がほとんど実在する人であり、名前も実名であること(普段小説を読む習慣がないのでびっくりしているだけかもしれないとも思うが)である。おまけに表紙には篠山紀信撮影による子どもとツーショット、ここまで露出するのかとつい思ってしまった。

夏のバラ2
そして三冊目が「8月の果て」だ。揖斐川図書館の司書が書庫から出してきた800ページに及ぶ分厚い本、しかも字はページいっぱい、最後まで読み切れるかという不安が一瞬よぎった。主な舞台は韓国慶尚南道密陽市(ミリヤン)で釜山に近い。この小説には擬音が溢れる。最も多いのは李雨哲がマラソン練習時に発する呼吸の音「すっすっはっはっ」、他にも「トゥグントゥグン(心臓の音どきどき)」、風の音「フィンフィン」。そしてあたりまえだがハングル。日本人の産婆、稲森きわの出番は少ないが、当時朝鮮にいた日本人のうちでも良心的な考えを述べているのが特に印象的だった。戦争の影がどんどん濃くなって来ると読むのがだんだんと苦痛になってくる。日本語の強制、創氏改名、神社参拝、親友の反日グループへの参加あたりは序の口で、日本人の人買いの出現(福岡の軍需工場で働けば3年もすればお金を貯めて家に帰れるという甘言、実は中国の軍事基地に慰安婦として売られることになる)あたりで最高となる。李雨哲の弟雨根は兄同様、マラソンランナーで共産主義になびくのだが、日本の敗戦後始まる反共政策により、捕らえられ、拷問の後生き埋めにされる。朝鮮の不幸は日本の敗戦では終わらずに、反共の南とソビエトに支援された共産勢力の北、それは朝鮮戦争へとつながり、さらなる不幸となっていく。雨哲は戦後日本に渡り、パチンコ店を経営した。そこの釘師が柳美里の父親となる。雨哲は60歳台まで各地の大会に出場し、優秀な成績を収めたのだが、がんを患い最晩年故郷に帰った。

夏のバラ3
さきほど述べた擬音、さらに韓国の風俗が詳細に描かれている。儒教の教えによるものなのかはっきりしないが、当時の日本と比べても数段しきたりが多いように感じた。この作家はどれくらい勉強したのであろうかとつい思ってしまう。この作家はハングルは全くわからないのだから、家族内での経験を除き、ほとんど一から調べたはずである。朝日新聞が途中で連載を止めたのも非常に興味を惹かれる。朝日によると作者の構想が膨らみすぎて、中断となったと書いてあった(今だったら朝日といえどもこのような小説を連載することはできないだろう)。
最後に日本の責任について少し書いておくことにする。朝鮮を植民地とし、皇国化政策を行い、その過程で従軍慰安婦を作り出し、敗戦後は日本は分断を免れたものの、朝鮮は南北に分断され(日本の敗戦が朝鮮という力の空白地帯を作り出した)、挙げ句の果てに朝鮮戦争(この戦争にはアチソンラインというアメリカが朝鮮に勢力を及ぼさないという間違ったシグナルを北朝鮮に与えたというのが原因だと言われる)に巻き込まれた。日本は朝鮮戦争による特需によりこの後高度成長につながる発射台の基礎を作ることができた。歴史を学べば学ぶほど両国の関係修復は難しいことがわかる。柳美里の小説を読み、少しでも朝鮮の人々の声を聞くことできた(もちろん作家の想像によるところが多いだろうし、何より現代から見た姿であることも頭に置いておく必要があるだろう)。