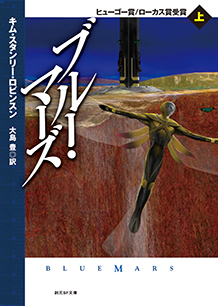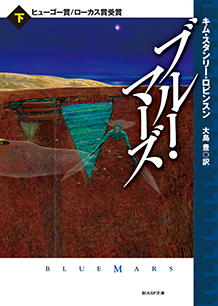『蠅の王〔新訳版〕』 ウィリアム・ゴールディング (ハヤカワepi文庫)
その昔、図書館で借りて読んだ気がするのだけれど、新訳版が出ていたので購入。これもディストピア・フェアだ。
記憶では、もっとどぎつい感じで救いが無かったようなイメージなんだけれど、そこまで酷い話ではなかった。きっと、これにインスパイアされたりされなかったりしたどぎつい奴を読み過ぎたせいだ。あれとか、それとか……。
読み返してみると、狡猾な狂人だと思っていたジャックはまるっきりの子供。主人公のラルフも絶望的なほどに子供。これって、全員小学生くらいだよね。そういう意味では、十代後半が入っているあれとか、それとかよりも、さらに絶望的と言えるかもしれない。
自らの中にある《獣》を畏れよというのが主題であろうかと思うが、個人的には最後に指摘された「全部で何人いるのかわからない」というので背筋がうすら寒くなった。
明確にジャックたちに殺されたふたりの他は、顔に痣があるせいで印象に残った少年の不在のみが示される。しかし、“おチビ”たちが何人生き残っていたのかは、ジャックどころかラルフも、ピギーですら把握できていない。心なしか、最初はうじゃうじゃといた“おチビ”たちが、最期には数人になっている描写があるようにも読める。
こういう小説を読むとき、自分だったら生き残れるかということを考えながら読んでいる。この小説の設定の場合、ジャックから離れて生き延びることは簡単かもしれない。しかし、読者としての自分が、“おチビ”たちをひとりも死なせずに救助を待てるかと考えもしなかったことに、改めて気づかされたのだ。なんというか、ものすごい自己嫌悪を感じた。
小説(もちろん映画やコミックでもそうだ)には読むのに最適な時期があると思っている。かつては規制図書にされたこともあるようだが、これはぜひ子供たちに読んでもらいたい小説だと思った。そして、自分だったらどうすべきだったのか、活発な子ならラルフの立場で、思慮深い子ならばピギーの立場で、それぞれ考えて欲しいものだ。