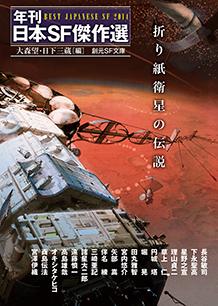『我もまたアルカディアにあり』 江波光則 (ハヤカワ文庫 JA)
なんだか、みょうちくりんな話だった。
働きたくない人たちを集めてマンションを作る。そこでは衣食住は保証され、何をやっていてもいい。ただし、いつか来る“終末”に備えること。これは現代社会批判なのか、果てしないスペキュレイティブ・フィクションなのか。
集団には必ず2割の怠け者がいるとか、会社は2割の働き者で動いているとか、そもそもがそういう話なのかもしれない。
働きたくなくて、餓死して死のうとまで思っていた主人公の前に、一緒に子供を作ろうと生き別れの妹が出てくるあたり、ラノベやエロゲーのパロディっぽくもあるのだけれど、そういった批判的パロディが主眼では無いのだろうとは思う。全編がこんな感じで何かのパロディだったり、ネタ的取り扱いだったりする。
餓死して死ぬはずの主人公がアルカディアマンションに入り、餓死するどころか暇をもてあまして働き始め、最後には大日本(そう、大日本政府なるものが出てくるのだが、これも昨今流行のネトウヨ批判ではなく、あくまでもネタ的取り扱いに見える)の未来に(間接的に!)関わっていくという皮肉な話になっている。つまり、主人公は怠け者の2割として隔離されたにも係わらず、その集団の中では働き者の8割になってしまう。
アルカディアマンションの管理者も、酔狂な金持ちや狂人的な宗教家ではなく、秘密の国家プロジェクトに係わる公務員だとか。つまり、アルカディアマンションは国家的な社会実験か、本当の意味でノアの箱舟として作られたものだ。その真相は思わせぶりに匂わされるだけで、明確には語られない。
それでも、幸か不幸か、大日本とアルカディアマンションを、前代未聞なテロと事故と天変地異が次々と襲う。それでも、終末は来ないと嘯いている主人公が可笑しい。それ、すでに終末じゃないか。
メインとなる主人公の一生を語る物語の合間に、彼の子孫と思われる人々のエピソードが挟まれ、アルカディアマンション、および、大日本の未来が語られていく。そして、その結末は、主人公と妹の(遺伝子の)世代を超えた邂逅であり、遠大なラブストーリーと読むこともできるようになっている。
しかし、“これ”はいったい何なんだろうか。
現代社会批判でもなく、未来社会予測でもなく、笑えるパロディでもなく……。ネタが詰め込まれている割に、それぞれの要素が弱いために、なんでもありで何にも無し。
しかし、こういうのが意外と著者の死後あたりに文学的に評価され、カルト的な人気を誇るようになるのかもしれないなと思った。