ブラインドサッカー世界選手権大会が終わったのにブログ更新しねーのかよ、と突っ込まれそうですが。
決勝や日本代表、その他の障害者サッカーに関して「パラフォト」さんに記事を書き、近日中にアップされます。
アップしたらお伝えします。
実はその記事に私とブラインドサッカーを初めて観た時のことなども書こうと思っていたのですが。決勝のインパクトが強すぎてうまく書き込めませんでした。
そいうことでこっちに書いておきます。だらだらと書いてます。
ブラインドサッカー(当時は視覚障害者サッカーという名称)を初めて観た時の感想は。「うるせーな」というもの。
時は2006年11月、世界大会(2大会前ですね)前の合宿最終日。
その時。私は「プライドinブルー」という知的障害者サッカー日本代表を追ったドキュメンタリー映画を撮っていまして、その一環で他の障害者サッカーも撮影したんです。映画のラストに日本A代表(現在のサムライブルー)も障害者サッカーも1点の重みは何ら変わらないという思いを込めて、各障害者サッカー日本代表のゴールを並べようと意図のもと。
ニューシネマパラダイスの最後で過去の映画のキスシーンが並べられていることからヒントを得たんですけどね。
でまあ一日ずつ撮影に行こうとまず最初に行ったのが電動車椅子サッカー。
その当時はまだ日本代表が立ち上がる直前で富山で開催されたクラブチームの全国大会に行きました。今と違ってボールも巨大でパスもつながらず「これをサッカーと言われてもなあ」というのが本当のところの感想。東京のクラブチーム「FINE」とかはバルセロナのユニフォーム着ていてサッカーを志向していることはわかるんですが。
ちなみに現在の電動車椅子サッカーは全然違います。特に国際ルールの場合は。自転車競技とF1くらい違います。少々大げさに言い過ぎました。
そして11月の3連休に脳性麻痺7人制サッカー(CPサッカー)、ろう者サッカー、視覚障害者サッカーの3団体がそれぞれ東京、淡路島、神戸で合宿することを知り、それぞれ行って来ました。
まずCPサッカー、印象的だったのは蹴り足の使い方は無茶苦茶うまいのに障害のあるほうの軸足がぶれてきれいにインパクトできない、といった光景。確か日本A代表と同じユニフォームを着ていて「試合の時は八咫烏の上にテープを張って見えないようにしてやることもある」と行った話を聞いたような気がします。
そして淡路島に飛んでいった翌日は、ろう者サッカー。手話であったり、ろう者特有の文化に魅入られてしまいます。しかも障害者サッカー唯一の女子チームがあり一目惚れし(被写体としてです)、その後映画「アイコンタクト」を撮ることに。
それで翌日がブラインドサッカー。なんせ前日ろう者サッカーで静かな時間を過ごしていたもんですから(もちろんしゃべる人もいますが)、ブラサカの合宿に行ったら「うるさいなあ」と思ったんです。風祭監督の関西弁のイントネーションが余計そう感じさせたのかもしれません。合宿をまわる順序が違ったら全く違う感想だったでしょう。
もちろんすぐに必要が故に音声言語化しているということはわかりました。
で、見えないのどうやってやるんだと疑問がわくわけで練習を観ていると徐々にわかってきて。そこで新鮮といか疑問というか、晴眼者がGKやっていることがなんだか不思議だなあと思い、そんな頓珍漢な質問を当時の風祭監督にしたところ、視覚障害者がGKをやるなんて「そりゃ無理でしょ」とあっさり返された次第。「そりゃそうですよね」と恐縮しましたわ。
その当時の自分としては、晴眼者(健常者)が言葉ではなくプレーそのものに関与することに違和感があったわけです。そういう疑問を持つ人はゴールボールに流れ、サッカーがやりたい人がブラサカをやったんでしょうか。でも晴眼者がGKやっているからハイレベルでスピーディーなサッカーになっているわけで、GKを晴眼者がやることがブラサカの大いなる特色だと脳裏に刻み込まれました。
今大会活躍した黒田選手は当時から目立っていて初見の私にも印象に残りました。少しだけ話を聞きましたが真摯に答えてくれる姿が印象的でした。おそらく頓珍漢な質問だったと思うんですが…、失礼しました。
合宿でもう一つ印象に残っているのはメディアの多さ。TVやラジオなどの取材がかなり多く入っていました。(もちろん今大会に比べれば圧倒的に少ないですけどね)
後々協会の方に話をしたところ「大会直前で特別です。普段はまったくいません」とのことでしたが、他の障害者サッカーでは大会直前でもそれほどのメディアが訪れることは一度も見たことがありません。
(2002年日本で開催された知的障害者サッカーの世界大会のことはよく知りません。ひょっとしたら多くのメディアが取材したのかもしれません)
もちろん釜本さんの存在や協会からの働きかけがベースにあったのは当然でしょうが、やはりブラサカは他の障害者サッカーに比べて視覚的に切り取りやすいという面があり、それが故にTVメディアが多いのだとも思います。
選手とのコミュニケーションの取りやすさもあると思います。
ろう者サッカーは言語の問題もありますし、知的障害者サッカーはコミュニケーションの問題もあります。
CPサッカーはむろんコミュニケーションに問題はありませんが、やはり見えないブラインドサッカーの選手の方が言葉にする術がたけている人が多いような気もします。
電動車椅子サッカーはその特殊性に興味を持つかどうかということになるんですが。
実際TVニュースで見かけることはその後も多かったですね。
一つ印象に残っているニュースがあります。ディレクターや元サッカー選手がアイマスクをしてブラサカの難しさを体験するという報道のパターンがありますが、その番組では元Jリーガーがアイマスクをしてボールを蹴っていました。で声の指示でどんどん修正できているんですが、わざと難しいというような演技がバレバレで。
まあいわゆるやらせです。ニュースの多くはそうなわけですが。
ある程度以上の選手になれば止まったボールを蹴ることに関しては、かなり早くに対応できるようになると思います。動いているボールはまったく別でしょうが。
で、その後は時々合宿や試合に行ったりしてました。
印象に残っているのはなんといっても宮城県で開催されたロンドンパラリンピックのアジア予選。
ブラサカ版“ドーハの悲劇”とでもいいましょうか。そのことは過去のブログに書いてますんで読んでみてください。
もうひとつ印象に残っているのは、(確か2009年だったでしょうか)東京味の素フィールドでの日本対中国の一戦。
中国は長身で身体能力の高いGKから壁パスで前線のプレーヤーへ、そしてひたすらドリブルで攻める。
選手間のパスは壁を使ったパスはあったと思いますが、とにかくドリブル、ドリブル、ドリブル。2人上がることもありますが、基本的には他の選手はブロックを作って守る。極めて合理的な戦術でした。
一方の日本はつながらないパスをつなげようとしている。みずからの理想のなかで逆にあえいでいるように見えました。「日本らしいサッカーをしたい。パスサッカーがしたい」その当時はそんな言葉を選手から聞いたような気がします。
「無理でしょ、ナイーブすぎるでしょ。パスつながってないし。まずは中国見習って守備から入った方がいいんじゃない。」とは思いましたが口には出せませんでした。
当時は壁にあてるパスも毛嫌いされている印象がありました。特にGKからのフィードなどは。
今は現実路線に舵を切っていると言えるんでしょうか。今大会の守備は完璧に機能しました。
しかし今後攻撃の厚みを加えることはかなり困難なミッション。
サムライブルーもなかなかうまくいかなかったですしね。
でもその困難なミッションをやりとげてほしい。

















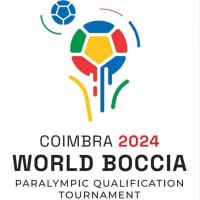

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます