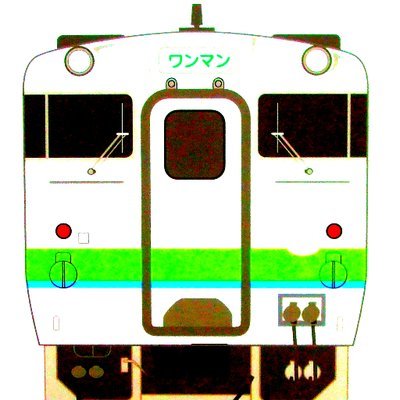先般のブログでは「北海道運輸交通審議会」には期待できないとの意見を投稿したところだ。
その理由の一つが、一部大学の先生の方々「だけ」によって結論が集約されていくことへの疑念だった。
さて、疑念を少しは払拭できるのか、さる12月17日に札幌で開かれた「
道民みんなで創る公共交通ネットワークシステム」と題したシンフォーラムに参加してみた
粉雪が舞う中、会場のホテルには約400人が集まり「各方面の識者の方々」のお話を伺うことができた。
本当の意味のフォーラムではなく、2時間足らずという限られた時間なので、会場の参加者と壇上のパネリストとの意見交換は無かったのが残念ではあったが、小生の脳みそにはちょうど良い分量で、今後の意見発信のための材料を得ることはできた。

コーディネーターと基調講演は北海道大学の岸准教授で、現在の北海道の交通問題にの状況を把握している唯一の研究者でもあり、北海道主催のシンポとしては、当然の選任あっただろう。
まずは話題提供者として長瀬道医師会会長・森道バス協会会長(函館バス)・今井道ハイヤー協会副会長(東邦交通)・中島札幌エアラインズアソシエーション副会長(日航・北海道地区支配人)が壇上に立ち、各業界の現状をお話になった。
特に、バス業界は運転手不足と高齢化についての懸念や、ヤマト運輸との貨客混載の実施。乗合バスの6割が赤字で国からの補助金を受けている実態などを話された。

さらに、高橋知事・菊谷北海道市長会長・堰八観光振興機構会長(道銀会長)・島田JR北海道社長がパネラーとして壇上に上がり、岸准教授がテーマを提供しながら、各自の主張を展開された。
正直なところ島田社長より西野副社長の方が、本音のお話が聞けたのではないかと思う。会場ですれ違ったが、きれいに整髪された社長と異なり、すっかり白くなった頭とお疲れの表情が印象的だった。
因みに観光関係の話題もかなり多く出されたが、中で記憶に残ったのが、北海道への観光客の入り込みは600万人弱で頭打ちになっている中で、その内訳をみるとインバウンド観光客が230万人を占めるという。さらにその半数は道内の移動にJRを利用しているそうだ。
因みに昨年度のJRのジャパンレールパスの販売枚数は10万枚近い。
先日のJR北・再生推進委員会の「有志」による声明に対して知事と菊谷市長が不満を露わにしていたのが印象的であった。
たしかに委員会からすれば一年は長く感じるのかもしれない。ただ、これだけの距離の鉄道路線について一気に議論を進めるには長い期間とは思えない。委員の皆さんには住民が見えていないのは確かだ。
両氏が反論を述べたのは理解できるし、各自治体は何もしていなかったわけではなかった。
ただ、この事態に及ぶまで沿線自治体はJRへの関心があまりに低かったと言うのは間違いないところではある。

翌18日に両氏は上京して、石井国交相に対し鉄道運輸機構の特例業務勘定を利用するという支援の要請をしたとのことだ。
フォーラムでは、その内容について知事が説明をしていたが、知事の無作為を批判する声に応えるように、懸命の説明ではあった。
おそらくは国交省の鉄道局や政府関係者・政権との根回しに時間を費やしていたのではないかと信じたい。
ただし、無条件で国の支援を仰ぐのではなく、本当に将来に渡って、私の孫、ひ孫の世代まで維持できるような交通体系を構築すべく議論を交わした上で支援を仰ぐべきであり、一時しのぎのようなことになってはいけない。
常識的に考えて、鉄道路線が今のままで残る、残すと言うのは非現実的である。設備、車両の更新と、鉄道の特性が生かせる再度の高速化への挑戦を前提にした上で、残すべき路線は残し、各地域においてはバスや乗合タクシーと融合した交通体系なども早急に構築すべきだろう。
駅を降りたらバスも何もないのでは、まさに元の木阿弥である。
当面は1月から3月に出るという道の総合交通政策検討会議の答申を基に議論を重ねて一定の方針を示し、国に支援を再度具体的に要請することになるかと思う。
最初に述べたこの答申についてであるが、やはり道内の有識者の意見が必ずしも反映していないのではないかという疑念は、今回のシンポジウムでも拭い去ることはできなかった。
ただ、道民の議論のたたき台にはなるのは間違いないが。
残念ながら、フォーラムというか講演会自体が、知事のアリバイ造りに利用された印象を持ったのは間違いない・・・・。
さて、むやみに国に支援を要請するのではなく、北海道民すべてが我が事として議論を重ねなければならない。次の知事選挙に向けた政争の具にするなどという呑気なことは言っている時間はない。

最後に、私としての路線合理化への考えだが、留萌線と札沼線はバス転換がベストであるのは間違いないし、日高線は大狩部の被災の際の地元自治体の対応からして、本音では必要とは考えていないのは明らかなので、DMVなどと夢を語る前にやはり別の交通機関を考えるべきだろう。
根室線の富良野・落合間のうち幾寅・落合間は今までの利用状況からしても、すでに必要性は失われていたものと考える。石勝線の迂回路と言う意見もあるが、現在の石勝線の防災と設備増強に資金を回す方が、よほど効率的かと考える。富良野・幾寅は通院、通学の生活路線であろうからできれば残したい。
さらに宗谷北線と花咲線は政治的な判断が望まれるうえに、存続するにしても設備の更新が必須である。
石北線の存続は言わずもがなである。日本の食糧問題にかかわるのだ。
設備・施設の更新、さらにJRFへの負担要請が求められる。

その理由の一つが、一部大学の先生の方々「だけ」によって結論が集約されていくことへの疑念だった。
さて、疑念を少しは払拭できるのか、さる12月17日に札幌で開かれた「
道民みんなで創る公共交通ネットワークシステム」と題したシンフォーラムに参加してみた
粉雪が舞う中、会場のホテルには約400人が集まり「各方面の識者の方々」のお話を伺うことができた。
本当の意味のフォーラムではなく、2時間足らずという限られた時間なので、会場の参加者と壇上のパネリストとの意見交換は無かったのが残念ではあったが、小生の脳みそにはちょうど良い分量で、今後の意見発信のための材料を得ることはできた。

コーディネーターと基調講演は北海道大学の岸准教授で、現在の北海道の交通問題にの状況を把握している唯一の研究者でもあり、北海道主催のシンポとしては、当然の選任あっただろう。
まずは話題提供者として長瀬道医師会会長・森道バス協会会長(函館バス)・今井道ハイヤー協会副会長(東邦交通)・中島札幌エアラインズアソシエーション副会長(日航・北海道地区支配人)が壇上に立ち、各業界の現状をお話になった。
特に、バス業界は運転手不足と高齢化についての懸念や、ヤマト運輸との貨客混載の実施。乗合バスの6割が赤字で国からの補助金を受けている実態などを話された。

さらに、高橋知事・菊谷北海道市長会長・堰八観光振興機構会長(道銀会長)・島田JR北海道社長がパネラーとして壇上に上がり、岸准教授がテーマを提供しながら、各自の主張を展開された。
正直なところ島田社長より西野副社長の方が、本音のお話が聞けたのではないかと思う。会場ですれ違ったが、きれいに整髪された社長と異なり、すっかり白くなった頭とお疲れの表情が印象的だった。
因みに観光関係の話題もかなり多く出されたが、中で記憶に残ったのが、北海道への観光客の入り込みは600万人弱で頭打ちになっている中で、その内訳をみるとインバウンド観光客が230万人を占めるという。さらにその半数は道内の移動にJRを利用しているそうだ。
因みに昨年度のJRのジャパンレールパスの販売枚数は10万枚近い。
先日のJR北・再生推進委員会の「有志」による声明に対して知事と菊谷市長が不満を露わにしていたのが印象的であった。
たしかに委員会からすれば一年は長く感じるのかもしれない。ただ、これだけの距離の鉄道路線について一気に議論を進めるには長い期間とは思えない。委員の皆さんには住民が見えていないのは確かだ。
両氏が反論を述べたのは理解できるし、各自治体は何もしていなかったわけではなかった。
ただ、この事態に及ぶまで沿線自治体はJRへの関心があまりに低かったと言うのは間違いないところではある。

翌18日に両氏は上京して、石井国交相に対し鉄道運輸機構の特例業務勘定を利用するという支援の要請をしたとのことだ。
フォーラムでは、その内容について知事が説明をしていたが、知事の無作為を批判する声に応えるように、懸命の説明ではあった。
おそらくは国交省の鉄道局や政府関係者・政権との根回しに時間を費やしていたのではないかと信じたい。
ただし、無条件で国の支援を仰ぐのではなく、本当に将来に渡って、私の孫、ひ孫の世代まで維持できるような交通体系を構築すべく議論を交わした上で支援を仰ぐべきであり、一時しのぎのようなことになってはいけない。
常識的に考えて、鉄道路線が今のままで残る、残すと言うのは非現実的である。設備、車両の更新と、鉄道の特性が生かせる再度の高速化への挑戦を前提にした上で、残すべき路線は残し、各地域においてはバスや乗合タクシーと融合した交通体系なども早急に構築すべきだろう。
駅を降りたらバスも何もないのでは、まさに元の木阿弥である。
当面は1月から3月に出るという道の総合交通政策検討会議の答申を基に議論を重ねて一定の方針を示し、国に支援を再度具体的に要請することになるかと思う。
最初に述べたこの答申についてであるが、やはり道内の有識者の意見が必ずしも反映していないのではないかという疑念は、今回のシンポジウムでも拭い去ることはできなかった。
ただ、道民の議論のたたき台にはなるのは間違いないが。
残念ながら、フォーラムというか講演会自体が、知事のアリバイ造りに利用された印象を持ったのは間違いない・・・・。
さて、むやみに国に支援を要請するのではなく、北海道民すべてが我が事として議論を重ねなければならない。次の知事選挙に向けた政争の具にするなどという呑気なことは言っている時間はない。

最後に、私としての路線合理化への考えだが、留萌線と札沼線はバス転換がベストであるのは間違いないし、日高線は大狩部の被災の際の地元自治体の対応からして、本音では必要とは考えていないのは明らかなので、DMVなどと夢を語る前にやはり別の交通機関を考えるべきだろう。
根室線の富良野・落合間のうち幾寅・落合間は今までの利用状況からしても、すでに必要性は失われていたものと考える。石勝線の迂回路と言う意見もあるが、現在の石勝線の防災と設備増強に資金を回す方が、よほど効率的かと考える。富良野・幾寅は通院、通学の生活路線であろうからできれば残したい。
さらに宗谷北線と花咲線は政治的な判断が望まれるうえに、存続するにしても設備の更新が必須である。
石北線の存続は言わずもがなである。日本の食糧問題にかかわるのだ。
設備・施設の更新、さらにJRFへの負担要請が求められる。